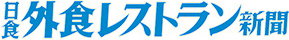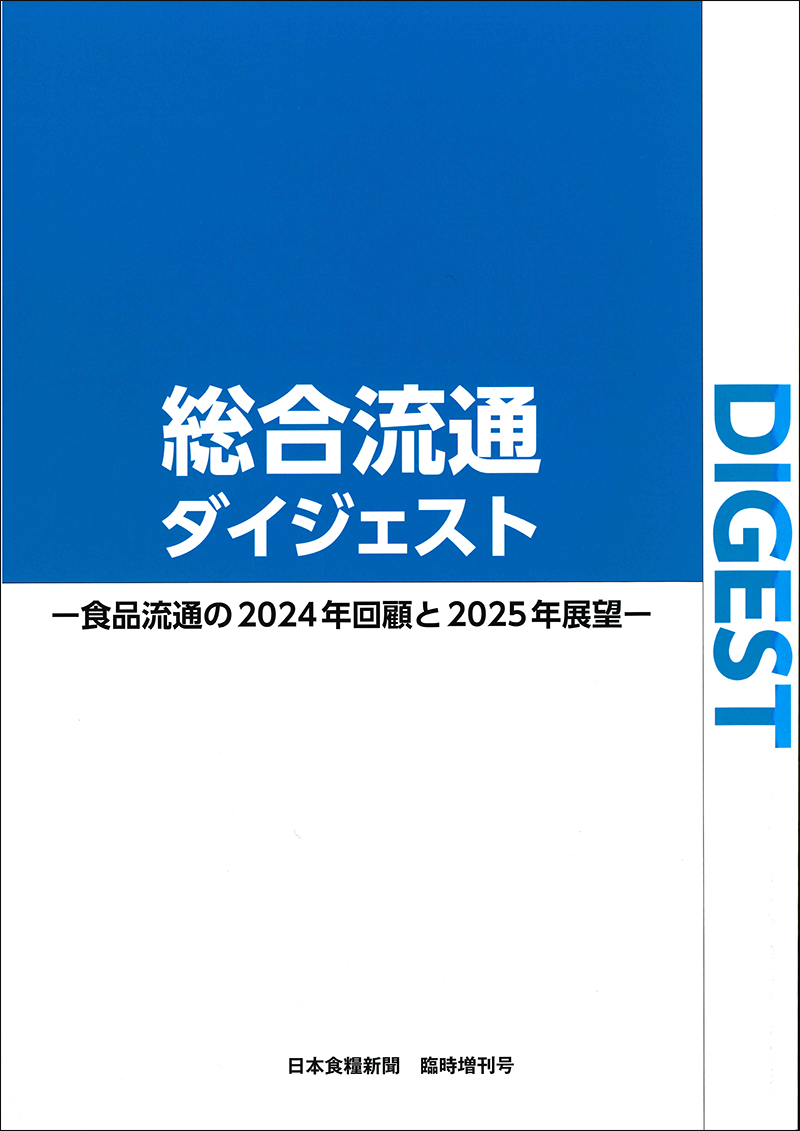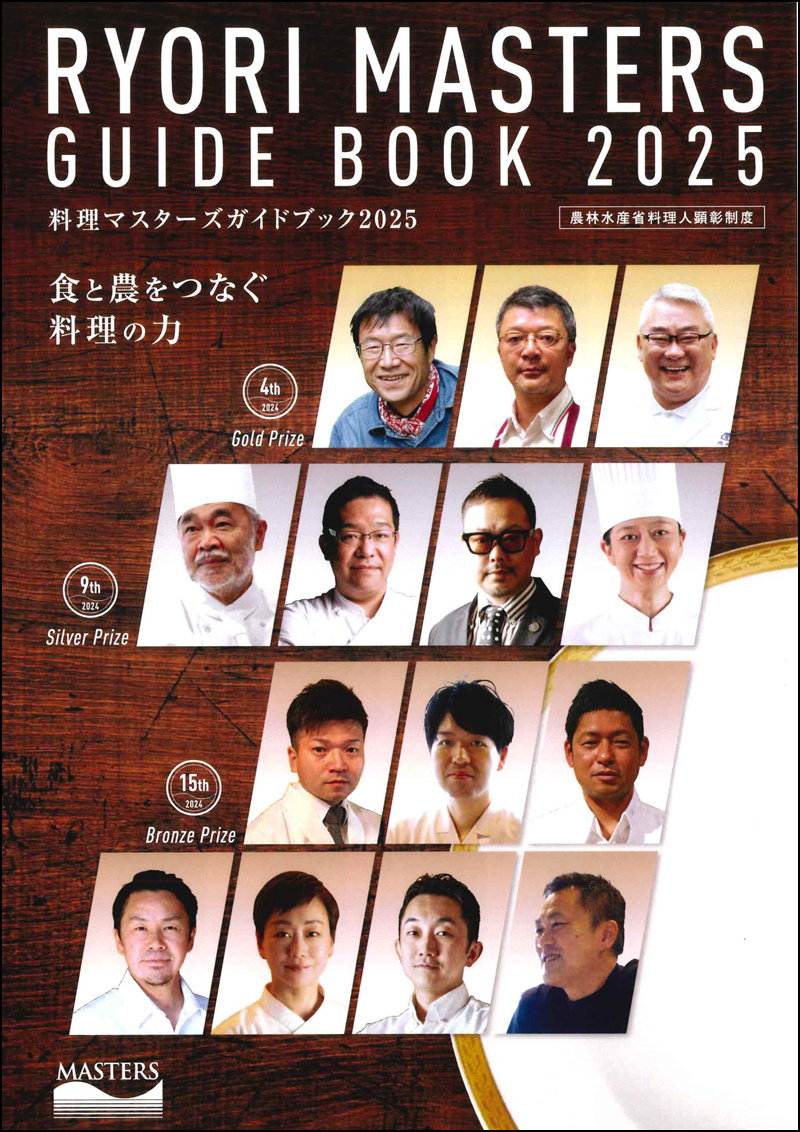シェフと60分:南部亭・高良康之料理長 血も内臓も全て自然の恵み
三〇歳という若さで南部亭を任された。若い感性とフランス料理のクラシックな部分が混ざり合ったシェフ。「国内外を問わず、野菜・肉・魚まで自分で納得いくまで追求し、仕入れる」というこだわりをもつ。特に野菜料理には思い入れがある。
「魚料理から肉料理に移るときにグラニテを出します。でも、ワインを飲まれる方や、料理の余韻を楽しみたい方もいます。そこで、私はグラニテという場所に季節感のある野菜料理を出して、次の料理へいっていただいています。付け合わせの野菜は、ジャガ芋やニンジンなど珍しくなくていいと思いますが、奇をてらったものをやっていきたいですね。もちろん季節感を忘れずにね」
「仕入れに関しては、直接畑に行って仕入れてくれる業者さんにお願いしています。どうしても食材には、ここにいるだけでは不透明な部分が出てきてしまいます。お客さんに出すものをつくる側としては、安心もいっしょに出していきたい気持ちがあります。もちろん、一〇〇%というわけにはいきませんけど、これからも追求していきたいですね」
工業高校に通っていた。物をつくることが好きで、将来は自動車の工場へ勤めようと考えていたが、なにげなく始めた喫茶店のアルバイトが料理界へ入るきっかけとなった。
「普通、喫茶店といえば、軽食なんかは業務用を使ったり、市販品に手を加えるくらいだろうと思っていたんです。ところが、アイスクリームまでつくっていた店で、ソースももちろん手づくりなんです。そこでベシャメルソースのつくり方を覚えたりして、一からつくるということに“奥が深い!”と感じました。そこで希望就職先を変えました。先生には『そんな前例はない』とびっくりされました。やっと就職課に紹介されたホテルの面接に行ってみるとボイラー室の募集だったりして」
前途多難だと思っていたところ、その年に開業した池袋のホテルメトロポリタンが求人を出し、なんとか料理の世界へ足を入れることができた。
洗い場がスタート地点。正直にいうと「チェッ」という気持ちもあった。
「同じ年で厨房に入っている人もいましたからね。なんだよ、とは思いました。でも、4月入社で6月がホテルのオープンだったんですが、二ヵ月の間に皿や鍋、グラスなんかを箱から出す作業もあったんです。そこで種類を覚えられましたね。新品をあんなにたくさん一度に見る機会ってそうないですよね。今思うと貴重な経験でした」
その後、厨房にも入り、基本を覚えたころ、歴史や文化にもふれたいとフランスに渡ることを決意。ブレス地方の鶏を見たい、サボアの湖でとれる魚や、生ハムを見たい、冬になるとジビエだと地方を転々と、二年ほど修業して歩いた。
「はじめはまったくフランス語が通じませんでしたけど、みんな親切に教えてくれたので、コミュニケーションはとれました。自分をスタッフの一員としてみてもらえるよう、安くても給料をもらえるところをさがしてよかったと思います」
フランスに渡った目的の一つは本場のジビエ料理を見るためだった。
「ジビエを見たくてランド地方に行ったわけですが、ジビエはフランス料理のクラシックな部分を持つ料理で、フランス料理の王道なんだな、と感じました。だって、言ってしまえば、自然のものを一羽ないし一頭殺してしまうわけです。でも、その殺すという行為に関して、すべてを使って料理をしようという精神がそこにあるんです。内臓を使って、血も使ってソースを仕上げてきちんと料理にする。ゴミ箱に捨てていくような仕事じゃなくて、一羽を自分たちでまっとうに皿にのせていく。これはすごい! だいご味のある仕事だ、と思いましたね。クラシックを踏んで、本線をはずさないで自分なりのアレンジを加えていっているのも魅力でした」
帰国後、フランスレストラン「ル・マエストロ」を経て、南部亭を前任のシェフに紹介された。秋に入るころ、南部亭を初めて見て、そのうっすらとした雰囲気のなかで、「ここでジビエをやりたい」と強く思い、今に至る。
毎年、年頭にはその年のテーマを決める。今年は「香り」にこだわることに。
「厨房で出来上がったときが、一番いいにおいではなく、お客さんの前に出されたときが一番いいにおいであってほしいんです。ですから、そのためにこれがバターの香り、といった素材本来の香りを追求したいですね。この一年で香りの表現をしていけるようになりたいです」
ジビエで、一羽(頭)を調理するときかなりにおいがきつい。そのにおいがどんどんおいしいものへ、視覚にも、嗅覚にも、味覚にも訴えるようになるのが、料理人としてうれしいという。
常に前向きに料理を考えている姿勢が、ジビエ料理からも伺えるようだ。
◆ 昭和42年1月生まれの三二歳。学生時代にアルバイトした喫茶店で、料理の楽しさにふれ、高校を卒業してホテルメトロポリタンに入社。四年ほど勤め、単身でフランスに修業へ。フランス語を習ってはいったが、言葉の壁には悩まされたという。
二年が過ぎたころ、日本の先輩から「店を出すから手伝ってくれ」と頼まれ帰国するが、開店の話は流れてしまう。しばらくして、知人の紹介で、ポールボキューズが顧問をしていた「ル・マエストロ」に入る。その後南部亭のシェフに後を任せたいと要請を受ける。「フレンチよりしし鍋を出したい」と思わせる雰囲気を持つ南部亭で、ジビエを中心にしたフレンチを提供している。
妻と二歳の男の子をもつ。休みは子どもにべったりのパパ。子どもに迷惑がられることもあるとか。
文 石原尚美
カメラ 岡安秀一