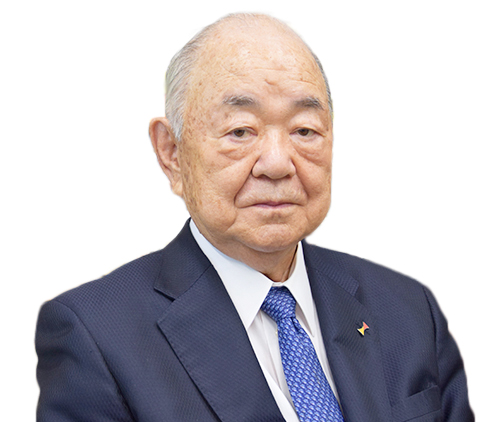食品企業におけるパーパス経営の先進事例:アークス・横山清代表取締役会長・CEOに聞く
◇株式会社アークス 代表取締役会長・CEO 横山清氏に聞く
聞き手:新井ゆたか(前消費者庁長官)、加藤孝治(日本大学教授)
* * *
新井:御社は北海道で事業を始め、東北から北関東へ「八ヶ岳連峰経営」(※注)を展開し、地域の中堅スーパーをうまく束ねることで多様な食文化を維持することに貢献されています。地元に密着したスーパーが残っていることで、食文化を残していく大きなパワーになっていると思います。地方に出張してみると、広い駐車場を持つ全国チェーンのコンビニかディスカウントストア、あとはドラッグストアがあるだけでした。地元スーパーの多くは閉店していました。昔から経営していた食品スーパーによって地元の食文化は支えられてきたと思います。御社が進める八ヶ岳連峰経営のスピードを早めないと、地元スーパーの体力が失われていってしまうのではないでしょうか。
※注 アークスグループを八ヶ岳連峰になぞらえ、富士山のように高くそびえる大きな一つの企業体ではなく、同じ高さの山々が連なる企業連合を目指した経営。
横山:私どもの経営は「八ヶ岳連峰経営」と言いますが、手を組んでいる相手は現時点の勝ち組企業です。要するに、財務的に黒字経営ができているところとしか手を組みません。これは大手企業が手を組む相手を見ても同じです。地方の食品スーパーで競争力のない企業が、実際には、どこも救済できない状況にあるといわざるを得ません。だから、生き残るためには力のあるうちに手を組むということが必要です。そういう意味では、私どもが手を組むことができる相手は、現実問題としてはあまり多くはありません。酒の販売が免許制だった頃は、地域大名みたいなもので、地域スーパーとして生き残ることができました。酒とタバコを取り扱うことができたら商売が成立しました。そういう企業にとっては、値段とか考えることなく、それを販売していればいいわけです。商売は成立するし、お客さんも離れなかったのですよね。それが、いつの間にか時代は変わってきました。
私が食品スーパーをはじめて2025年で64年目になります。もともと、北海道の田舎の出身で家業は芦別の鍛冶屋、仕事はあるのだけどなかなか儲からなかったです。それでも従業員は2人くらいいました。自分は長男なので、家業を手伝ううちに電気溶接やいろんなことができるようになりました。高校を出て2年間炭鉱で働いてから北大に入りました。
大学に入った後、あっという間に炭鉱業は斜陽産業になっていきました。終戦のとき、私は小学校の4年生で10歳でしたが、当時、芦別の町の人口は6千人ぐらいいました。昔はエネルギーが無くて、大正時代に炭鉱が始まったときは、少し掘れば採れたのです。最初にできた炭鉱は三井芦別炭鉱でした。そのあと、大正時代に三菱美唄炭鉱も開山しました。
戦後に北海道に戻ってきた人たちが石炭を掘るようになるとあっという間に貯蔵が無くなっていきます。私が高校を出たのは昭和29年なのですが、この10年間は石炭産業が活況を呈していて、人口がもう少しで8万人になるくらいまで増えていたのです。それが、北大に入った翌年の昭和32年に私の勤めた明治鉱業所が閉山されました。その後あっという間に残りの4つの炭鉱も閉鎖されました。その結果、7万人の人口が1万人切るか切らないかぐらいのところまで減少していきました。石炭産業もそうですが、同時に商売やマーケットというのが、時代の変化によって否応なしになくなってしまうということを体験しています。そういう面からいくと、今、地方のスーパーマーケットがどんどんなくなっていくことも仕方ないと思っています。
オンラインへ独自に取り組む
横山:小売業界でみると、いま、オンラインとオフラインの比率が大きく変わっています。オフラインを店舗とすれば、オンラインの売上のウエイトがどんどん増えています。いまの変化を結果的に言うと、例えばアマゾンみたいに、オンラインで国境を越えて来ることもできます。日本の小売業界で見たら、知らないうちに日本のアマゾンは売上規模が小売業界第2位です。我が社も2024年からアマゾンと組んでビジネスを始めました。アマゾンと組んでみてわかったことがいくつもあります。この前も同社のオンラインショップ統括責任者のラッセル・ジョーンズ取締役が我が社に来て、いろいろな話をしていきました。彼らにとっては、アマゾンが食品販売で組むことができるところが増えれば、お互いにプラスの効果があると考えています。
一方、我々にしてみればアマゾンみたいな大手と組むと、強い販売力があるのでお客さんを持っていかれるのではないかという恐怖感があるのですが、彼らにしてみれば、組むことでその分だけ売上が増えるし、お互いにハッピーになるねということで提携を持ち込まれていました。現在、アマゾンの食品売上は、店舗がなくてもどんどん増えていて、さらに、アメリカでいわゆるリアルな店舗を買収しています。そういうことを考えて、私は、今の時代の流れで言えば、方向性からいけば店舗だけでは飯は食えないかもしれないけど、オンラインとオフライン半々ぐらいにしてもいいと思っています。
また、物流センターを作って配送するより、近隣の店舗から持っていくというようなオンライン活用のタイプに変わっていくだろうと考えています。そういう方針の下で、我々は独自にオンラインへの取組みを行っています。この取組みは、まずはラルズで展開しています。要するに、小さく生んで大きく育てろという進め方ですね。集積してコストを下げてやれば一気にいけるだろうということで、宅配センターや工場を作るみたいなことをやっている企業もあります。だいぶ前の話にはなりますが、大手商社もそれをやろうとして失敗しました。
北海道でも、多くの企業が取り組んでいました。我々もスモールスタートで始めていますが、実際に、最近はオンラインの売上は増えています。生協も宅配をやっていますが、最近は店舗の販売だけだと伸びてないようですが、宅配事業の売上が増えているから大丈夫と言っています。確かに、生協は最初から宅配形式のビジネススタイルでやっていたので、それで成功していると言われています。
今は、逆に我々と一緒にやっているAmazonネットスーパーアークスの売上も増えていますから、オンラインは全体に拡大しています。生協の商売の方法は、例えば1週間のサイクルでオーダーしてもらって計画的に届けるという方式でやっているのに対して、Amazonネットスーパーアークスは代金を支払えば30分で届けてもらえるわけです。我々も利益が出るように、無理をしなくてもいい範囲で考えたら、オーダーを受けて2時間以内で届けようということになります。採算の合わないような仕事の仕方をしたら続かないのです。だから、小さく生んで大きく育てようと言う考えで取り組んでいて、ぼちぼちとはじめながら拡大させていき、このあと100億円くらいの売上になるまでにどれくらいの時間がかかるかということを考えています。
ところで、先ほど、私がこの商売を始めて64年になると言いましたが、最初は専門商社に入社したのですが、その後スーパーに派遣されることになりました。今は無いのですが、現本社のすぐ近くに75坪のスペースでダイマルスーパーという店が開店しました。私は、商社入社後沿岸バイヤーとして飼料にするためのサンマとかイワシを仕入れておりました。その飼料を使って、養豚業を専門商社がやっていたのですが、それが失敗しました。そこで2千頭の豚を販売しなくちゃいけないということで、昭和36年11月7日にスーパーを開業し販売することとなりました。そこに私は出向することとなり、大学を卒業して2年目に営業部長の名刺をもらうことになりました。レジを3台並べて札幌で2番目のセルフサービスの店ということでした。大学を出たばかりで1年間出向ということだったのですが、その後2年経っても3年経っても出向が解けず今に至ります。
加藤:先ほどお話のあったAmazonとの提携の件ですが、本日、お伺いする前にお店を見せてもらったのですが、その際にお店の入口にAmazonを扱っているというシールが貼ってありました。今、御社の他に組んでいるのは、ライフコーポレーション、バローHD、リテールパートナーズ、成城石井さんですね。これらの企業はみなさん充分に利益を確保できていて、オンラインとオフラインを組み合わせているということですよね。それぞれ売上を確保できる顧客地盤を持っていて、その基盤に対してオンラインとオフラインを組み合わせていますよね。消費者ニーズに対して企業側が合わせていくことができているということですね。
そう考えると、食品スーパーの中で生き残っていく企業というのは、今の時点で黒字を確保できている企業ということですね。逆に、今、利益を確保できていない企業に対しては、どの企業から見ても手を出せない状況になっているということですね。最初に新井長官からお尋ねのあった地方都市で、食品スーパーが撤退しているような地域というのは、ディスカウントストアとコンビニとドラッグストアしか生き残れないということになりますね。
Amazonのビジネスで言うと、日本では先ほどあげた5社が出店しているような地域なら提携するが、それ以外の地域は衰退していってしまうということですね。そんな地元の食品スーパーが生き残れないような地域が増えていってしまうのでしょうか。
横山:そうですね。今後は、おそらく何か新しい仕組みを作った上で出てくると思います。ただしそれができる企業は、大手かあるいは別の産業から入ってくると言うことになるでしょう。
生き残るための方策として、食品スーパーの中では物流の共同化の話もあります。当社にも全国展開する競合小売から相談がありました。お店では競い合うけど、物流は一緒に積んで走った方がいいという提案です。物流費用が安くなった分を商品価格の引き下げに使うということです。話はわかるけど、同じ商品を企業ごとに違う価格にできるかという問題です、また、どこかのセンターで小分けするとしたら、その費用が発生する。企業ごとに手の内がみんなわかってしまう。実際に、我々の業態では共同物流によるコストの引き下げ効果は小さいと考えています。やはり競い合っていくことに意味があると考えています。
合理化できない商売に挑む
2024年の年頭所感で書いたのですが、「競合は成長の粮」だと考えています。また、店頭でお客様が見るのは価格です。そこで「納得価格」という造語を作りました。今、食品価格はどんどん上がっています。我々はインフレと戦うインフレファイターです。いいものを安く売ることが大事です。原価を割ってでも安く売るということはしてはいけません。北海道でも地元スーパーが頑張っているところに大手が入ってきて、休みを減らし営業時間も増やして安売りしたが、働いている人たちが続かなかったこともあり、最終的には撤退していきました。
これから金利の上昇する時代になると、多額の負債がある企業はますます厳しくなる。だから、食品スーパーも潰すものは潰さないとダメになる言うことです。北海道でも、大手はイオンさん以外全部撤退しました。そういう中で、我々は64年生き残ってきて、プライム市場で頑張っています。
加藤:今、北海道では、イトーヨーカ堂が撤退してロピアが出てくるのが話題になっていますね。
横山:ロピアさんはマスコミを上手に使って宣伝していますね。これから先の展開はどうなるかわかりませんね。
加藤:今は食品の値段がどんどん変わっています。北海道の店舗を見て、お米は東京よりも随分安いなと思いました。東京(2025年5月時点)では、コメの棚もガラガラです。今それほど給料が上がっているわけでもないのに、モノの値段がずいぶん上がっています。実質的な購買力が下がっていると思います。この先、御社が八ヶ岳連峰経営に参画を促そうとする企業を考えても、なかなか各社とも経営が厳しいかもしれませんね。改めてお尋ねしたいのですが、御社は八ヶ岳連峰経営の他、三社連合(アークス、バローホールディングス(HD)、リテールパートナーズからなる「新日本スーパーマーケット同盟」)にも取り組んでいますね。また、横山会長は、CGCジャパンの副会長や全国スーパーマーケット協会の会長でもあります。業界全体の方向性をどう考えていらっしゃいますか。
横山:実際のところ、食品スーパーは全部足しても20兆円くらいです。そのうち、CGCは全部入れて5兆円を超したぐらいです。そのうち、我々の今の売上高は6千億円でCGCの1割程度です。
加藤:今のお話で、現在の売上が6千億円と仰いましたが、以前にライフコーポレーションの清水会長とお話しされているときに、1兆円を視野に入れるようなお話がありました。とはいえ、そこまで届く企業はかなり限られますね。逆に、勝ち組グループに入れない企業がたくさんある中で、業界再編はどのくらいのスピード感で進むのでしょうか。
横山:業界として、早くやっていかないと我々の売上は増えないだろうと言うお話ですが、今の食品スーパーの市場は縮小しています。1兆円規模の会社が10社集まると10兆円です。日本の食品スーパー業界の半分はそう言う構造になるでしょう。どんどん拡大し続けるということはないでしょう。さらに、GMSについて言えば、大手は全社北海道に来ましたが、どんどん撤退していった。どう考えても採算は合わないのです。食品では競合があって儲からない。我々は、その儲からないところに専念しようとしているのですが、それが儲からないと言っても消費者ニーズはあります。それに応えなくてはいけないということになると、結局はコスト競争になるのです。生き残るには、どんなにコストを下げても、最後に利益がでるようにしなくてはいけない。一時的なマイナスでも他社が撤退すれば儲かるようになるという考え方ではダメです。これが、私が64年やってきた体験からの結論です。
加藤:地場に密着した経営が強いということですね。
横山:働く方法論からいくと、合理化できないで人手がいる商売ほど大変なのです。だけど、生き残るには、それこそ人がいて、お金もいるわけであり、それをどうやってやるかということです。大手の場合は儲からないから止めるということがありますが、我々はそうはいかない。なんとか頑張ろうとする。その代わり、いろんな問題も出ます。
アメリカの小売業を視察したら、スーパーはこうでなければいかんと言われて、渥美俊一先生からも、僕なんかボロクソに言われました。そうは言っても理屈じゃないんです。能力のないものは時間で稼ぐしかない。これから人が減るということは消費者が減るということですよね。
そういう中で、例えば無人店舗でも、カメラが200台あればいいというわけにはいかない。Amazon Goもうまくいってないと言われています。だから、普通の店では採算が合わなくなるから、どんどん切っていかないといけない。アナリストは「もっと伸びるはずだ」と言います。連峰経営というのはグリップが弱いからダメだと。グリップをもっときつくすれば、もっと利益出るはずだと言うのです。でも実際には、そんなことは理屈だけの話です。何もせずに安く買って高く売るなんていう商売はできません。かっこいいことばかり言って、客のためにどうすればいいとか言うけど、実際には、永遠の成長なんかありえないのですよ。
そういう面では今の状況と物価水準の中での商売を考えないといけない。今は、以前と同じように広い敷地で今までと同じ店舗を建てても採算に合いません。店を出そうとしても、どう考えてもコストが高いので、今、出店している店が黒字になるとは思えないです。
加藤:出店コストが上がるだけでなく、商品の仕入れ価格も上がっていますよね。消費者はもう価格を上げないでという悲鳴みたいな状態になっていますが、企業サイドも新店の不動産コストを考えたら、確かに儲からないですよね。
横山:儲かっている風に見えていてもそれは不動産収入とかであって、本当に惣菜1パック、ホウレンソウ1把で稼げているわけではないのです。先ほどお話ししたトライアルさんも小売収益だけが上がっているわけではない。自社開発したシステムを西友さんに導入することで収益をあげるという話もありますが、いつまでに決着できるかわかりません。新たに北海道に進出するロピアさんも、従業員確保などこれからいろいろな問題に直面すると思います。また、小売企業で上場維持するのも結構大変です。だから、最近、上場をやめようという企業も多いですよね。
アリの目で見る
加藤:八ヶ岳連峰に加わる企業のイメージはありますか。また、グループ企業も含めて、御社の場合は、社員の定着率は高いのですか。
横山:参加したいと申し込んでいる企業も複数いますが、条件に合わないので話を進めていません。必要な条件としては黒字経営しているということです。たとえ、一時的な赤字があっても、来年は黒字につながるような投資をしている場合は問題ないですよね。あとは労働組合のないところは難しいです。労働組合はないといけません。労働組合があることは経営者にとっては邪魔かもしれませんが、働く人たちの気持ちをくみ取ることができるようになっていないといけない。
自分のこれまでの体験として、例えば炭鉱などは労働組合が活発だった。組合は経営者から見て邪魔かもしれないけど、これを受け入れられる会社でないと、私たちとは一緒に共働はできません。アークスの仕組みに入ってくるということは、中小の地方スーパーからするとシステムが大きくなっていくわけですから、それを受け入れてもらわなくてはいけない。アークスはAG労連という労働組合連合会があり、その上にUAゼンセンがあります。北海道のUAゼンセン内でAG労連は約1万人います。組合は経営者に反対の意見を言うから嫌だという考えがあるが、みんなが仲間になるためには、組合という形になっている方がお互いに良いと考えます。また、経営サイドで気がつかないことも現場の声が入って深掘りできるようになります。
加藤:アリの目ということですね。現場の声をちゃんと発信してくれるということですね。
横山:経営者は鳥の目として全部見えていますが、アリの目として陸上で見えている必要がある、あと、魚の目として、海の中で流れを見るように、時代の潮目を読むことも大事です。鳥の目だと上から広く見えるけれども、アリの目の場合、下からしか見えないところが見える。そういう目線が大事だということなのですよ。
加藤:企業の中には「うちは組合ができるような経営をしていません」と言う経営者もいますが、それは組合と言えば反発するものだという前提で、社員が一致団結しているから必要無いという意味で言っているのでしょうが、会長にとっては、逆にそう言う経営者ほど現場が見えてないということですね。
横山:私みたいな体験をしている経営者はあまりいないのかもしれないので、自慢するわけではないですが、反省をこめて本当に見えないものはいかにたくさんあるのだと思うべきです。
地方の小売企業で大手の傘下に入ることには善し悪しがあります。当地でも地元で同時期に創業したスーパーがある大手から30%以上株式を持つことはないから一緒にやろうという話を持ちかけられ、提携をしました。その後、お店の名前を変えました。当時の社長は会長になり、息子が社長として後を継いだのですが外されました。地元優先といいながら、そういうことになるのは、何かおかしいと思います。私どもを地元連結型というのであれば、地域買収型とでも言うのでしょうか。
開発商品を共通化
新井:「競合は成長の粮」ということですが、相手を潰すという意味での競合ではなく、いろんな形で成長することですね。ところで、これからのスーパーというのはある面、惣菜とかready to eat、すぐ食べられるもののウエイトが増えていかざるを得ないと思います。そうなると商品開発力が重要になると思います。そういう面の展開を考えると、今後、八ヶ岳連峰の方々でいろんなものを共同化するとか、知恵を貸し合うというのは増えていきますか。
横山:どんどん増えるでしょう。例えば、我々1社でできないことは、2社あるいは複数でやればいいと思います。今、スーパーは人口の高齢化とともに、巨大惣菜販売店になりつつある。ただ、そういう惣菜屋になったその先はどうなるのかということです。惣菜屋になるのはネットでもできるわけだし、Amazonでも百貨店でもできます。コンビニエンスストアも配達しています。
私は、大事なことは商品開発だと思います。私たちは、10社のスーパーで開発商品を共通化しています。情報共有やセンターの共有も進めています。地域単位でいえば、北海道のラルズと東光ストアは物流センターを統一しており、東北のユニバースとベルジョイスでも統一を予定しています。企業同士が合意すれば、グループ内で合併してもいいと考えています。
スーパーが巨大な惣菜屋になる傾向はあっても、それが終わりではないと思います。極端な話をすれば、確かに人間が食事を作らなくてもいいような時代になることもあり得ると思っています。ただ、惣菜で美味しいものはいろいろあるけれど、自分で作ってみるという楽しみは残ると思います。でき上がったものは、すぐ食べられるもので利便性だけが追求されています。
店で売って採算が合わなくても、オンラインとオフラインを組み合わせて採算を合わせることができる。また、店に来て、いろいろな素材があって、それを組み合わせて料理するというちょっとした工夫を楽しむこともある。方向性として、小売店舗が商品開発された惣菜を買うという場所と、楽しみのための料理の素材を買う場所の組み合わせになるということです。店舗でものを売るときには、原価と別に付加価値で売る商品もある一方で、我々の場合やっぱり最終的にはコスト競争です。今後も価格は上がっていくでしょうが、そういう中で、消費者が納得して買ってもらえる価格である「納得価格」が大事になると考えたのです。
私たちの八ヶ岳連峰経営は、店舗ごとに考え方を変えなくてはいけません。独自性と共同性の両方を組み合わせます。また、三社同盟でいけば、東はアークスから西はリテールパートナーズであり、真ん中に岐阜のバローHDがあります。この三社の同盟のメリットは、一部はCGCで扱う商品とバッティングするものもありますが、棲み分けもできます。
例えば、CGCの加盟企業は208社ありますが、そのうち売上が100億円以下の企業が6割を占めます。我が社のCGC商品の扱いだけで、総量の約15%です。今後、CGCのメンバーでも生き残れない企業もあるかもしれません。一つのパターンとして、CGC加盟社の中で、我が社のように連峰経営を目指す企業も出てくるかもしれません。ただ、私たちのグループに入ってくると言うわけではありません。とはいえ、規模の小さい企業同士だけが集まっても生き残りは難しいでしょう。これからが正念場です。
三社同盟は日本の端から端までやっていて、食品売上ではアークス、トータルの売上はバローHDの方が多い(8千億円)。バローHDは、東北の水産会社を経営しています。自社だけの販売ではなく、我が社でも引き受けますよという話になります。東北から岐阜へ持っていくより、北海道に持ってきた方がコストも安いのもあり、東北の水産会社にとっても都合がいい。また、例えば、惣菜工場を作るには、最低10億円かかるとして、それを償却できるだけの売上を確保できなければ採算が合わなくなる。こういう場合には買収しなくても、業者同士で提携すればいいと考えます。とは言っても、商品のレシピ開発は重要であり、そこは独自性を出す必要があります。
加藤:確かに商品の組み合わせを考える必要があり、食品スーパーの将来像は決め打ちしてはいけないということなのでしょうね。
時代に合わせて商売の仕方を変える
横山:私は、今後、GMSの生き残りは厳しいとは思いますが、食品スーパーもかなり淘汰されると思います。これからの時代、儲からないものは、無理して残すことなく、やめていくべきだと思います。ただ、儲からない店はやめようと「社長」が言っても、「会長」が反対するからやめられないというケースも多い。スーパーがなくなるとコンビニしか残らなくなる。
少人数で回す店や無人の店も増えていますが、そういうことを続けていくと、企業の人件費は下がるでしょうが、地元の人たちが知り合いと話をする場所がなくなる。また、配達の帰りに一緒に車に乗せてもらうとか、人と人とのつながりが希薄になるということです。私のところにも店員さん大変だろうけど、これ以上店舗を減らさないでくれと言う声はあります。仮に一つの店舗が赤字でも、周りの店で補っていくことを考えることこそがサステナビリティではないかと思います。これが経営の一つの売りにもなる時代ですから、それができるところだけが残るのではないでしょうか。そういう面はいわゆる経済の原則とは別の社会的な意義ですね。
新井:場合によっては、ドラックストアとかでも、全く買う場所がなくなってしまうよりはいいということですね。
横山:ドラッグストアについては、薬の販売の他に、最初は雑貨を扱っていたのが、食品も扱うようになっている。原価割れで食品を売っても、収益性の高い薬で儲けることができるという時代もありました。上場して売上維持が必要になって、取り扱う食品の種類を広げ生鮮も扱うようになっているが、薬が儲からない時代になると、今のやり方は続かないかもしれません。
これからの5年~10年の間でいろいろ変わっていくでしょう。自分は会長になって1年経ったが、あと2年のうちに、今、考えていることを実行していきたいと考えています。表面的には見えないかもしれないけど、大きな流れが動いています。その動きの背景には銀行業界の変化も関係してくるのではないでしょうか。
加藤:企業グループを一つの大きな塊にするのではなく、小さな塊を組み合わせていく方が最終的には強くなっていくという考えが印象的です。大きな所帯にしてしまうのではなく、ある程度の規模の所帯でやることで緊張感があるというのが八ヶ岳連峰経営の持つ意味ですね。
新井:スーパーの合従連衡みたいな動きとして、昔は魚屋とか肉屋だったところが時代とともに変わっていくのだというお話ですね。まさに、時代が変われば商売の仕方も変わってくる。時代の先を見て、時代とともに求めているものが変わればそれにあわせて商売の仕方も変わってくるということですね。これまでいろいろな企業の資料を見てきましたが、公表資料はきれいにまとまっているものの、今ひとつ幹部・社員に定着していないケースが多いのですが、御社の場合、会長が書いた新年の所感を皆さんが読んで、自分のものとして仕事に活かしています。そういうことができる社内の土壌が素晴らしいと思います。
横山:年頭所感は、持ち歩けるような小さなカードでお渡ししたり、関係会社などの社長室にも掲げてあります。現場がイメージしていることを、例えば「納得価格」のように、うまく年頭所感で示すことができていると思います。
新井:まさに、「納得」というのはすごく重要だと思います。私は消費者庁で消費者からの要望を受付けるところですが、よく聞くと契約内容をしっかり理解していないために生じたトラブルが多いです。納得するとクレームにはなりません。納得していないとどんなに安くても無駄遣いをしたと思うし、逆に、どんなに高くても納得していたら、それでいいわけです。納得のプロセスをどうやって作っていくのかというのが重要だと思います。物の価値は人が評価するものであり、コストの積算で決まるものではないですよね。
横山:今のインフレ問題についても、新価格体系へと変わっていると考えるべきかと思っています。本当の意味でのインフレというのはあるべきではないと思いますが、世界と比較して日本はいろいろなものの価格が安すぎます。今は新価格体系に移行しているところだと言う意識に変わっていく必要があるのではないでしょうか。同時に給料をどう上げていくのかという問題もありますね。両方が代わるがわる前に出ていかないといけないわけで、そうなってくると価値判断も変わってくる。原材料などが上がって行く中で、企業がどのくらいの時間で転嫁できるかということです。今はまだ転嫁できていません。
横山:商品価格の値上げについて、食品メーカーの社長が「もう謝らない」と発言したことがありました。確かに値上げに対する消費者の不満もあるでしょうが、良い物は高く売っても構わないと思うのです。たまたまCGCの取引先の会合のときに、ご本人がいらっしゃったので、私としては言葉の使い方だけ気をつけて欲しいとお伝えしたら、それじゃ私はここで謝りますと言われました。そういうことではないのですが、受け取る側の気持ちの問題はあると思います。
加藤:先ほど、CEOになってあと2年のうちに、今抱えている宿題を仕上げようとおっしゃっていたのは、八ヶ岳連峰経営をもう少し広げるという話ですよね。
横山:いろいろ話はありますが、飛び石にしないようにと考えています。
新井:会長は石炭産業の大きな変化を目の当たりにして、企業・産業の栄枯盛衰を肌身で感じたのが原点ですよね。その後の動きを見ていると、とても柔軟な発想で経営していると思います。若いときに達観されたのが、その後の企業経営に活きていると感じましたね。今、いくら栄えていても、おごってはいけないし、世の中の変化に応じていろんなものを変えていかなきゃいけないということですね。そのときの経験則から始まっていることを強く感じました。
横山:経験則だけでやると難しいのですけどね。
新井:本日は大変良いお話をお聞きすることができました。長い時間をいただき、誠にありがとうございました。