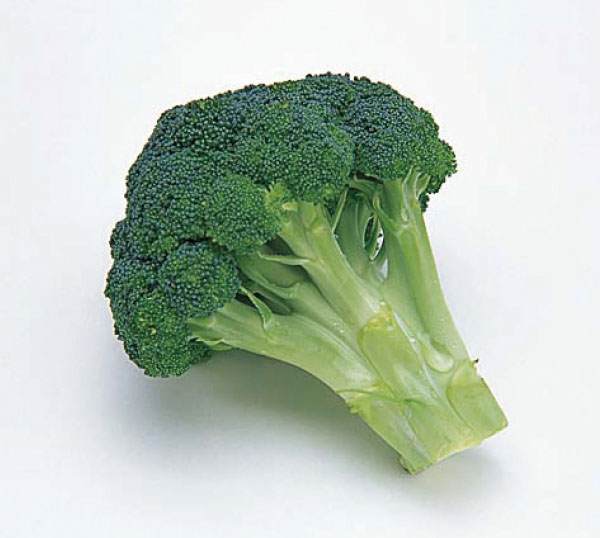百歳への招待「長寿の源」食材を追う:「酢」
サツマ芋と酢‐‐ともに最も庶民性に富む食材であるゆえ、長寿食品としてはいつもはあまり注目されないが、じつはなかなかの効能がある。ぜひ見直していただきたい食べ物だ。
(食品評論家・太木光一)
酢は人間のつくり出した調味料のうちで、最も古いものの一つ。クレオパトラ(前六九~前三〇)が一回の食事で全財産をなくすことができるかで、アントニオとの賭けで真珠を酢でとかしたのは有名な話。聖書にも、聖人は酢が好きだとも記され、古くから食生活になじんでいたともいえよう。
酢は清涼感あふれる酸性の調味料で、サワー食品の代表である。この酢の効用は昭和二八年にイギリスのクレブス博士とアメリカのリップマン博士がトリカルボン酸サイクル理論でノーベル賞を受賞したことで証明される。
激しい運動や労働、または精神的ストレスが長く続くと体内に乳酸が蓄積される。体液や血液を酸性にし、脳も刺激して不快感・けんたい感を深め、そのため肩こりが起こったりする。またコレステロール・けい酸などが沈着しやすくなって、動脈硬化の原因となる場合もある。
酢は乳酸がたまらないように、また発生した乳酸を素早く処理する機能を持っている。また新陳代謝をおう盛にして、体内にエネルギーを蓄積する役割を果たす。極めて有用な食品であるといえよう。
酢それ自身の味は酸っぱいが、体内に入るとアルカリ性食品と同じ働きをする。健康な人間の体液は弱アルカリ性である。食生活でコメ・パンや肉類は酸性食品であり、野菜・海藻類がアルカリ性食品である。現代は疲れやすい酸性食品に偏りがちであり、この点で酢をもっととる必要がある。
日本で酢はすし・酢の物をはじめ、酒・しょう油・みりん・砂糖などを適当に配合し、合わせ酢・二杯酢・三杯酢・七杯酢などいろいろ作られている。洋酢を中心にするとマヨネーズ・ドレッシング・マリネなどとなる。最近ではイタリアのバルサミック・ビネガー(芳香のする酢)がサラダに利用され、ブームをよんでいる。
酢は調味料として優れた特性を持っているが、これ以外の効用をみると
(1)酢を使うと結果的に塩分のとりすぎを防ぐ。酢を多く使用すると塩の使用量が減り、減塩効果が大きい。成人病や高血圧を防ぐ。
(2)酢には防腐効果がある。酢を使った料理は腐りにくいといわれる。酢は殺菌力が強く、短時間で菌は死滅する。関西では夏場に食酢を入れて炊いたり、炊きあげご飯に酢をまぜて保存面に注意している。
(3)酢は生臭みを消し、かくし味となる。魚料理に生臭みを消すため、小量のかくし味として酢を使う。そのほか褐色に変わるのを防ぐためレンコン・ごぼう・とろろ芋などに利用。
(4)食用以外にも用途は広く、湿布消炎剤をはじめ銀器や銅器のさび取りに、畳の汚れ取りや、花の水揚げなど多方面に使われる。
(5)酢の入ったものは食欲を増進し、胃液の分秘を促し、消化吸収を助ける。健康と美容面にも深い関係を持つ。百歳元気、そして美しさを保つため酢をもっと多く利用したい。