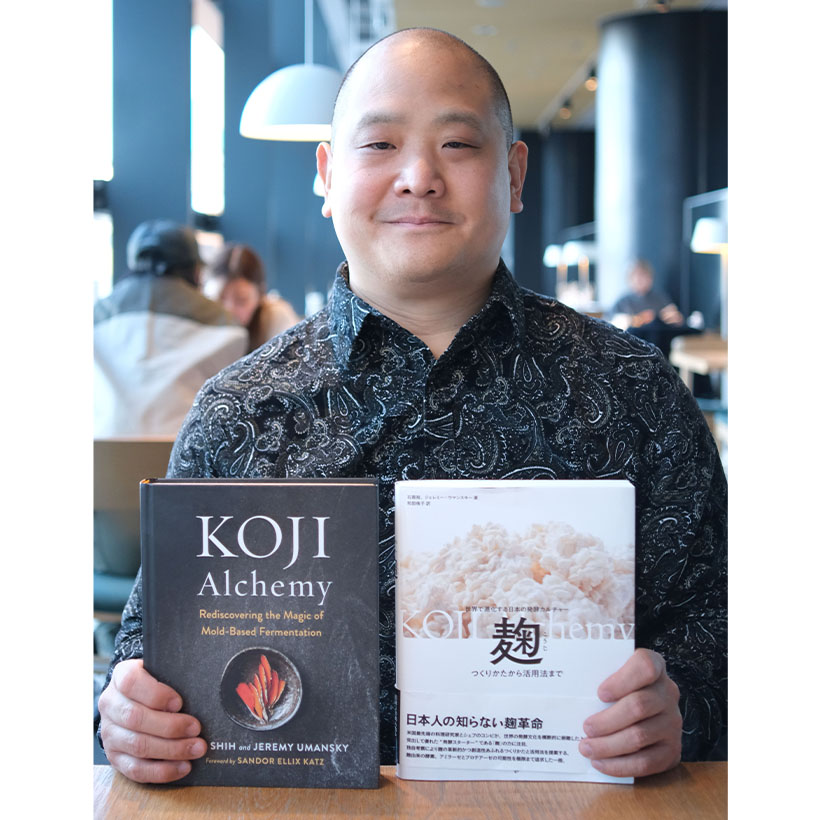食と健康「偽情報」の誤解払拭を 味の素社がリスクコミュニケーション構想
食と健康に関わる「偽情報」をテーマに正しい情報の浸透と誤解の払拭(ふっしょく)を目指す組織、市場、業界、個人の立場の枠を超えたリスクコミュニケーションの場を設けることを味の素社は提案する。
食の安全・安心財団の理事長を務める唐木英明東京大学名誉教授、日本生活協同組合連合会の嶋田裕之代表理事専務、東京大学大学院の林香里情報学環教授の3氏を招き開催した11月29日の「~現代に必要なリスクコミュニケーションとは?~うま味調味料(MSG)/食品添加物を事例として」と題した味の素社メディア懇談会で、同3氏によるパネルディスカッションのモデレーターを務めた味の素社の西井孝明社長が同ディスカッションの締めくくりで今後の同社のリスクコミュニケーションの実践に向けた行動を宣言し、構想を披露したもの。
同社が示した「当社が提案するリスクコミュニケーション・フレームワーク」の概念図からは、食品企業、流通・外食、食品関連協会・業界団体、食関連NPO(非営利団体)・NGO(非政府組織)・消費者団体、行政、栄養士・管理栄養士、料理研究家・料理系SNSインフルエンサー(ソーシャル・ネットワーキング・サービスで影響力のある著名人)などの料理インフルエンサー、メディアソートリーダー(メディアの第一人者)、関心の高い生活者、アカデミアKOL(学究キーオピニオンリーダー)に対し、味の素社が発起人兼事務局として参加を呼び掛ける意向がうかがわれる。

西井氏は「具体的な組織が出来上がっている訳ではない。唐木先生のご活躍によって、機運が食品業界に高まりつつあると認識しているので、そのメンバーとも手を取り合って、こういうことを仕掛けてまいりたいと思っている」と説明した。「MSGや化学調味料の問題は、リスクコミュニケーションという観点で非常に分かりやすいレビューができるいい題材だと思っている。これからこのようなフォーラムを提案していく中で、一つの題材として何回も何回も取り上げさせていただくことによって、理解が高まっていくことを期待している」とも語った。
同日明らかにした行動宣言は「当社は、組織・市場・業界・個人の立場を超えた新しいリスクコミュニケーションの『場』を立ち上げ、生活者と『食と健康』に関する正しい情報を分かち合い、真に健康で豊かな社会の創造に貢献していきます」というもの。
味の素社の考えるリスクコミュニケーションは「あらゆるステークホルダーに対する共感と信頼を得るコミュニケーションを通じ、正しい情報の浸透と誤解の払拭を図り、信念を持って真に豊かな社会づくりを目指すこと」とした。
パネルディスカッションでは、「リスクコミュニケーションを進める中で企業はどのような役割を果たすべきか」との問いを西井氏が唐木氏、嶋田氏の両氏に投げ掛けた。唐木氏は「食品企業の商品に対する消費者の質問は(1)添加物(2)残留農薬(3)遺伝子組み換え(4)表示――の四つ。表示の間違いや食中毒を起こさないためにどんなことを日ごろからやっているのかということを繰り返し繰り返し消費者に分かりやすく伝えるということが基本的だが大事なこと」と応じた。
嶋田氏は「何か起きた時に説明するではなく、消費者の関心事、さまざまな不安を受け止めながら、日常的に丁寧な情報提供なり、コミュニケーションをしていくとが非常に大事。1件1件の申し入れの対応にどう丁寧に向かい合っていけるのか」とした。
社会の中の一員として読者や視聴者と一緒に社会を作っていくジャーナリズムの一つの姿勢を「建設的ジャーナリズム」と名付け研究している林氏に対しては、西井氏は、風評を払拭する報道ですら、客観性を担保する手法として風評の立場も併記する両論併記が存在していることについて水を向けた。
林氏は「バランスをとらなければならないから、そのまま出すというのはやはり思考停止だ」とし、「生活者とのコミュニケーションとか、リスクコミュニケーションのきちんとした考えを先生方から聞くとかいうことによってしか解決できない。思考が停止してしまうのはジャーナリズムの考え方がすごく古くて更新されていないから。取材する記者だけでなくデスクや幹部もどういうジャーナリズムの形が現在求められているかということを価値多様性の時代だから考えなくてはならない」と応じた。