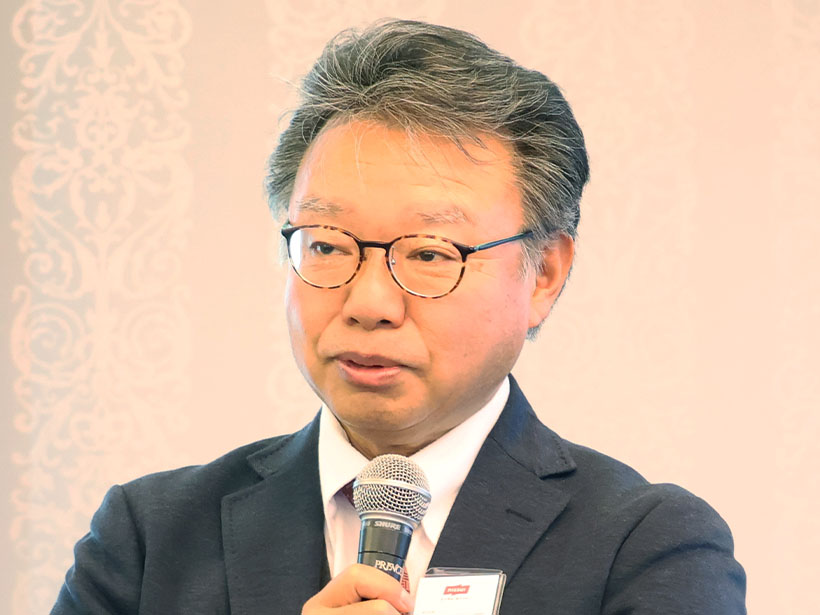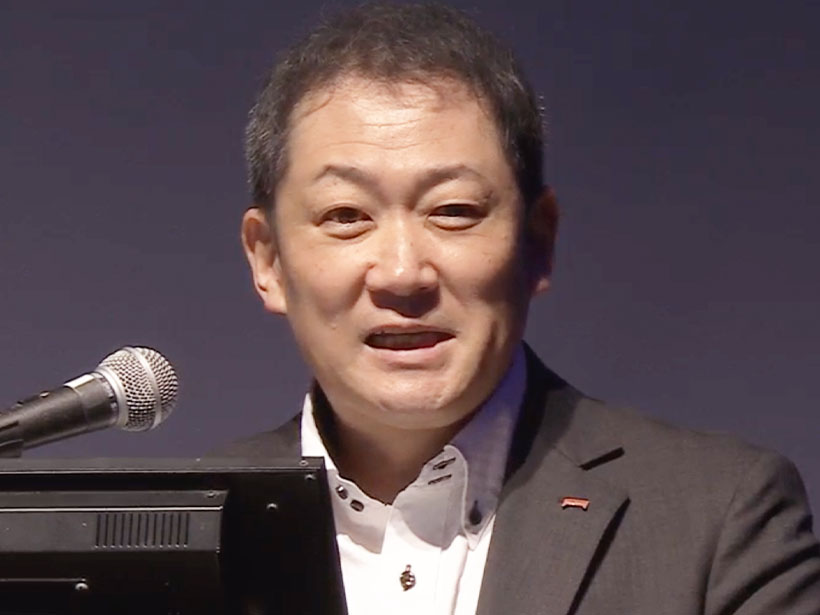食品企業におけるパーパス経営の先進事例:ニチレイ・大櫛顕也社長に聞く
◇株式会社ニチレイ 代表取締役社長 大櫛顕也氏
インタビュアー:新井ゆたか/加藤孝治
インタビュー日時:令和6年2月28日
インタビュー場所:株式会社ニチレイ本社(東京都中央区)
※社名・役職はインタビュー当時のものです。
* * *
長期ビジョンで目指す姿を示す
新井:水産会社は1970年代の200海里問題への対応に努力された歴史があると思います。その中で、御社は「冷力」に注力しコールドチェーンを構築された。そのほかにも、これまでの歴史の中でいくつかのターニングポイントを経ておられると思います。最初に、そのご苦心をお聞かせいただければと思います。また、2019年の時点で長期ビジョンとして「2030年の姿」を策定された経緯についてもお教えください。
大櫛社長(以下、敬称略):当社では、もともと中期経営計画を3年ごとに作るというマネジメントサイクルで運営されています。3年というのは長いようで短い期間です。先が見通せるので計画が積み上げで作成されます。前年とか2年前の実績を見ながら、数字を作っていくことになりますので、結果的に保守的で現実的な計画になりがちです。そういったこともあり、目指す姿をもう少し緩く柔らかく議論できるようにと、中期経営計画策定年度の1年前に組織プロフィールというものも策定しています。2017年に次の幹部候補生を含めたチームが編成され、様々な制約を設けず、5年先の目指す姿が描かれました。しかし、この5年先をターゲットにするという発想も、中期経営計画策定における3年先を見ていくことと、時間軸的には大きく変わらないじゃないかと感じていました。そこで、私が社長になった2019年には、ほぼ10年先の「2030年の姿」を示し、もう少し先からバックキャスティングして計画策定時の議論ができるようにしました。
私は、社長に就任したときに、これからは社員みんなで変わっていきましょうということを、最初のメッセージとして出すにあたり、どうしても、目指すところが必要になりました。それが、「2030年の姿」です。組織プロフィールも中期経営計画もありつつ、長期ビジョンを策定することとしたのです。なぜ2030年なのかと言われると、2019年から考えれば、ほぼ10年先ということでキリが良いということと、社会的にも2030年にはカーボンニュートラルの話も出ていましたから、そこに合わせる形で2030年をターゲットに置くことにしました。
ただ、役員の間でも賛否両論は出てきましたので、「これはコミットメントじゃなくて意思表示でいい」ということとしました。その時には従業員みんながわかりやすい数字の目標がないといけないと思い、売上高1兆円、海外売上高比率30%、営業利益率8%の数値目標を取締役会に諮って開示をしました。
加藤:2019年の最初に、それまでのマネジメントサイクルを残しつつ、長期ビジョンを作られたんですね。
大櫛:長期ビジョンは、どちらかというと事業成長数値目標に焦点があたりますが、われわれが目指す姿というものを定性的に考えることも同時に進めていました。それが、ミッション・ビジョンに関わる議論です。私が社長になる2年前の2017年ころからの取組みです。ミッション・ビジョンでは会社としての方向性は示されているけど、作ってからだいぶ時間も経っていることもあり、今のままでいいのかなという話が、役員の中で出てきました。そこで、先達が作ったものを一回見直してみようということで、役員の中で揉むことになりました。それがだいたい1年半ぐらいかかったかと思います。
その時にいろいろ議論がありましたが、ミッションというか存在意義みたいなところについては、変えなくていいよねという結論になり、一方、ビジョンについてはちょっと抽象的でわかりにくいかなということで、ビジョンをみんなで議論して作りなおすことにしました。今の自分たちが腹落ちできるビジョンを目指していこうという方向へと自然に議論はまとまっていきました。
新井:こうした議論を始める外的要因・内的要因としては、どのようなものがあったのでしょうか。
大櫛:2016~17年というのは、それまで、しばらく低迷が続いていたグループの業績が一気に良くなった時期です。タイに大型投資した生産工場の稼働が上がったり、国内の主力商品である「本格炒め炒飯®」の売上が急激に伸びたりと、様々な打ち手がほとんどうまくいったのです。ただあまりにも成功体験が続いたため、この好業績がこのまま続くわけがないと考え、一旦引いて見ていました。それはほとんどの大型投資が、計画よりも早期にリターンとして戻ってきただけで、次に私たちは何をしたらよいのかということが見えていなかったんです。次の手に向けて、具体的な施策を考えなくてはいけないということになりました。
また、ミッションとかビジョンを考え直そうとしたときに、ちょうど働き方改革への対応を考えていく課題に直面しており、そもそも会社が考えていることが、ちゃんと社員に伝わっているのかということも気になっていました。そういう一連の課題を俎上にのせて考えることとなりました。業績はいいけど、今まで引っ張ってきたものがそのまま使えるのかどうかということや、そもそも次の打ち手が不透明ななかで、社会の変化にどのように持続的に対応すべきなのかなど、私たちが議論を始めるきっかけとなりました。
新井:業績が好調だからこそ、次のステージに向けて余裕がある中で見直していこうと考えたということですね。当時は、SDGsに対する取組みが話題になり始めた頃ですよね。パーパスという言葉は出てくる前ですが、資本主義の限界みたいなことが言われるようになってきたころですね。
大櫛:2017年~18年は、私が持株会社の社長になる前のタイミングで、事業会社(ニチレイフーズ)の社長を務めていました。そこでは、旬のテーマを取り上げて、全国8か所でお取引様のトップの方々をお呼びして、フォーラムを長年にわたり年1回開催していました。その中では、これからの食のあり方についてや、持続的で良質なタンパク質摂取、人手不足などの社会問題への対応などを取り上げていました。2017年には言葉としてまだ定着していなかった「SDGs」を取り上げましたが、全体としては思ったほどの反応は得られませんでした。しかし、いくつかの大手企業のトップの方々は大変関心が高く、社内でも試行錯誤されているとお聞きしました。企業として、この社会的課題への対応に取り組む意義を再認識でき、それが社内でのマテリアリティ特定の検討へとつながっていきました。
加藤:2017年の組織プロフィールの作成から2019年までは、役員の間での議論だったのでしょうか。若手を含めたプロジェクトチームは組成されましたか。
大櫛:組織プロフィール作成のための議論には、30代の若手社員も入り、事業会社ごとにチームを組むので結構な人数での活動になります。組織プロフィール作成では、社員から意見を挙げていくボトムアップ型を取っています。
加藤:組織プロフィールで社員から意見を上げさせ、役員の議論を1年半かけて2019年に「2030年の姿」を作り上げていくというわけですね。
大櫛:はい、若手を含めた現場の議論では、制約をかけていないので、多様な意見が出てきます。それを、中期経営計画を作る段階で、役員が基本方針と数字を含めて現実的な施策へと合わせていくこととなります。
加藤:確かに売上高だとか、海外売上高比率とか営業利益率などの数値は、完全にコミットメントせずに方向性を示すだけでも、責任ある立場の人でないとなかなか提示できませんね。御社は「2030年の姿」という表現をして、社員全体に方向性を示そうとしている。「豊かな食生活」「健康に貢献」という方向性を出しつつ、数字に落としていくことの関係はどう考えたらよいでしょうか。
挑戦的な数字が選択肢を増やす
大櫛:パーパスやバリュー及びビジョンというものを作っていくときには、どうしても抽象的、定性的なものになりますが、もう少し事業活動を想起できるものが大切だと考えています。5年後とか10年後にこうなっているという定性的なことを社員はなんとなく分かるけど、その時の売上規模がどうなっているのか、どれくらいの利益を求められるのかということを会社が提示することで、現在とのギャップの大きさを感じることができると思います。従来の延長線上で考えるのでなく、新しい企画への取組みや、新たな事業開発、他社とコラボレーション、M&Aなどの可能性まで考えることができるようにすることが大切だと思います。例えば、海外事業を拡大していく場合も、日本での自前主義のやり方をそのまま持っていくだけでは、市場を獲得するのに何十年もかかってしまいますので、あえて挑戦的な数字を提示することで、様々な選択肢を考える機会が増えるのではないかと思います。
新井:既存の事業に今までにない新たな事業を積み上げていく可能性を示すということですね。検討を着手した経緯が、外部環境から迫られたからということではなく、御社内部の事情として、業績が好調であったからこそ、もう一回足元を見直そうと考えたというのが、長期経営目標を策定するきっかけになったということですね。
自分たちで作り上げたものに責任を持つ
大櫛:中期経営計画を作るときや、今回の長期ビジョン「2030年の姿」を考えるにあたり、様々なバイアスを取り除くために外部コンサルタントにお願いすることも考えましたが、まずは、自分たちで徹底的に議論し作り上げたものに責任を持つということを大事にしました。
新井:御社のアプローチは、パーパスとミッションの掛け合わせみたいなものと考えられますね。社長がよく考えて作り上げていると思います。
大櫛:そもそも、社内の議論の過程で、パーパスの定義は何かという話がありました。また、ミッションやビジョンを作る時も、同じような議論がありました。従業員の中でも現在のビジョンは、わかりやすいと思っている方もいますし、もっと明確にしたほうがいいと考えている方もいます。私個人の意見では、今の形のままでも改めてパーパスを作らなくてもいいのではないかと思っていますが、一定の時間が経てば見直していくということは自然だと考えます。こういったことを自由に提案していく風土は大切にしたいですし、その時は、もう一回ゼロベースでの議論から始めることになるかと思います。
新井:社員の方々も数字を見た方がついてきやすいというのはとてもよくわかります。社員が、自分の仕事をイメージする時に、例えば、単に独創力を発揮しましょうとか書いてあっても、どうやって独創力を発揮したらいいの、独創力を発揮してどうするの、というのはわからないと思います。また、健康と食生活と豊かさということを考えたときに、「健康」というのをキーワードにして、そこに数字がついてくることによって皆さんが行動しやすくなるということでしょう。社員の方々が自分の生産の現場、あるいは営業の現場で、何をすればいいか考えやすくなる。社員の行動変容と言っても、従業員の方々が次に何をすればいいかと、ステップが分かりやすくなるということは効果的ですね。
加藤:御社の企業風土を考えたときに、社員の方々はある程度方向性を示してもらうと動きやすいタイプか、自分から積極的にイノベーションを起こしていこうというタイプか、どちらの感じだと思いますか。
大櫛:社員には怒られるかもしれませんが、どちらかというと指示されて動くというタイプではないかと思います。それは、当社の場合、事業特性や時代背景もあったかと思います。事業が人の口に入る食に携わっていることもあり、安全なものを作り続ける責任があります。また、それを実現していくために、カリスマ的な経営者が求められたということもあるかと思います。私が社長になる頃には事業環境も大きく変化しており、先が見えない中、求められることも多様化してきました。何から何までトップが決めて進めなくてはいけないという感じではなくなったと感じます。
加藤:社長が長期ビジョンを出すことでカルチャーを変えようとしたということですね。経営陣についていけばいいという指示待ち的な感じでなければ、数字など具体的なものを示さずに頑張ろうと言うまでもなく、社員が自発的に頑張ることになるかもしれない。社長は、自社の社員はそうはいかないかなと考えられて、数字を示しながら自発性を出せるように工夫されたということかと思います。
好調の時に価値観を変えていく
大櫛:そうですね。2015年~17年のころは業績が良い時期だったのですが、それまでが大変厳しかったから、そこにあぐらをかいて変化しないことは大きなリスクだと感じていました。会社はよい時期がずっと続くわけではなく、どこかで止まります。その時のために、今この業績の良い時にいろいろチャレンジしておかないといけない、調子が悪くなってからやっても、失敗は許されず、後ろ向きな仕事が増えていくだけだと思っていました。だからこそ、業績の良い時期に、自分の会社に対するイメージや価値観を変えていく必要があると考えたのです。
加藤:ストレッチをかけた数字を出すことによって、社員のモチベーションを高める、やる気を出させるという意味が、この売上1兆円、営業利益率8%に込められているということですね。
大櫛:あとは、投資家向けのメッセージという意味もありました。長い間、食品企業は総じて利益率が低いと言われていましたから、これから変わるのだという決意表明でもありました。「本当に営業利益率が8%もいくのですか」や「どうやってそれを実現するのですか」という意見や質問もありましたが、社内外では賛否は分かれると思ったからこそ、議論する場づくりとして、あえて言う意味があると考えたのです。
新井:今でも中期経営計画は3年ごとに作成しているのですか。
大櫛:今でも3年ごとに作成しています。次の中期経営計画は2025年~27年になり、今年策定していくことになっています。
加藤:だんだん、「2030年の姿」が、間近になっていますね。そうなると、社員の方々は、気にし始めていますか。例えば、1兆円をどうやって達成するのか、という話は出ますか。
大櫛:社員はもちろん、投資家からも具体的なシナリオについて聞かれることは多くなっています。ただ、私も社長としての任期もありますので、さらにその先の2040年や2050年を見据えて、そろそろ考える必要があると思っています。未来はどうなっているのか、ニチレイはどこを目指したらいいのかなどの議論を社外取締役の方々も含めて一緒に始めたところです。
新井:そうすると、「2030年の姿」が変わるかもしれないということですね。ところで、御社が提示している8つの約束に分けている意味と効果についてお教えいただけますか。
大櫛:2001年にCSR基本方針を制定した時に「6つの責任」を定めました。その後、内外環境の変化にあわせて見直していく必要があり、2017年に「6つの責任」を「ニチレイの約束」に修正しました。この「ニチレイの約束」は、もともと私たちが大切にする価値観なのですが、さらに、これらの価値観を「サステナビリティ基本方針」として改訂することにしました。今の時代に求められる、循環型社会の実現や環境負荷の低減、気候変動への対応、人財の育成などに文言を直しました。
さらに、社会的要請に応えて、マテリアリティの特定に向けた議論が始まりました。2019年9月からプロジェクトをスタートさせ、2020年6月にマテリアリティを特定しました。マテリアリティを議論していくなかで、その重要性や緊急性を挙げては潰して、全体を組み立てるというプロセスを踏んだ結果、現在の5つのマテリアリティの形になりました。この過程で、「ニチレイの約束」は意識していませんでしたが、特定されたものが、「ニチレイの約束」に近いものであることを改めて認識しました。
「ニチレイの約束」は8つあるのに対し、マテリアリティは5つになっています。ただ「ニチレイの約束」では定性的な文言になっていますが、具体的に何をやるんだということは示されていません。これをマテリアリティとして整理したことで、はじめて具体的なアクションプランへとつながるということに気が付いたのです。「ニチレイの約束」を守ることは、特定した5つのマテリアリティをやることとイコールなのです。
加藤:マテリアリティに落としていくことで、KPIとしての評価ができるようになるというお話でしょうか。
大櫛:そうです。マテリアリティで設定したKPIを達成していくことは、「ニチレイの約束」を実現することと一緒なんです。ただ、ニチレイの約束に入っていて、マテリアリティに入っていない項目は、コンプライアンスやガバナンスの項目です。これらの項目は、会社の対応として当然のことでありますので、マテリアリティから外しました。
加藤:お話を伺うと、現在、社会や市場から期待されていることを議論していくうちに、気がつくと御社が、かねてから経営のベースとして考えていたことに収れんしていくことになったのですね。出し方が違うだけで、結局同じようになっていくということが面白いですね。
大櫛:私も一連の議論を振り返りますと、先輩たちが策定した「ニチレイの約束」もおそらく同じようなアプローチを踏んだのではないかと思います。私たちがゼロベースから策定したのが、結果的に「ニチレイの約束」に似てきたということは大変興味深く感じます。もし最初から「ニチレイの約束」を前提にマテリアリティを特定していたら、もう少し時間は短かったかもしれませんが、白紙の状態から経営メンバーで議論したことはとても有意義だったと思います。もし、マテリアリティの議論プロセスを踏まなくても、「ニチレイの約束」から、どうやって実際に行動変化を起こすかを議論していくことは避けられなかったと思いますので、遠回りしたかもしれませんが、とても意味がある議論をしてきたと総括しています。
新井:「ニチレイの約束」の中で示している事業活動に対して長期目標や中期目標が作成されているということですが、私には、うまくつながっていきません。もう少し教えて頂けますか。
大櫛:会社が特定した5つのマテリアティで行動の方向性を示し、それぞれに施策やKPIを設定してきました。もちろん、2030年からバックキャスティングしていきますので、詳細は各部門との調整が必要になりますが、結果的にマテリアティを遂行していくことが、「ニチレイの約束」を実行することになると位置づけています。
加藤:結果的に寄り添っていくような形になるということが、御社の先輩たちが作ったものと、今、自分たちの考え方に基づいて作成したものが、気がついたら同じ方向に向かっていた、より現代的に分かりやすいように作成されたことになっているということですね。そして、そうすることが、社員が行動原理として分かるような形に落とすことにつながっているということですね。繰り返しですが、結果的にそうなったというのが面白いです。ニチレイさんとして一つの軸が連綿と続いていて、そこに意識せずに近づいているということですね。
大櫛:お恥ずかしい話ですが、初めは、社会や投資家からの要請もあり、マテリアティを作成することが、一種の流行りみたいなところもあって、当社も作らなくてはいけないということがきっかけでした。先ほど申しました通り、社内ディスカッションを経て、5つのマテリアティへと絞り込んでいったのですが、最初にあがった課題は30から40個もありました。後半で5から10個くらいまで絞り込んでいく過程では、コミットメントできるできないなどに意識がいくことが多く、議論が高まりました。
KPIを設定していく際にも、目指している時間軸は単なる2030年ではなく、そもそも自分たちが議論して設定した課題に対して、明確な活動の先に2030年があるという意識の方が大切なのだと思います。
新井:なるほど、そういうことですね。先ほどのお話に戻りますが、多くの会社は日本人独特の「危機になってから検討を始める」という感じがありますが、御社の場合、好調な時に検討を開始してマテリアリティを1年程度かけて議論しています。また、みんなで議論して作ろうという御社の土壌に社長が変えてこられたところもあると思います。かつては、トップダウンで落としながら議論するという土壌があったというのは、日本企業としてはすごいことだと思っています。しかも、マテリアリティを1年近い時間をかけて議論するという時間軸に感心しました。
制度導入後も議論を継続
大櫛:当社の社風については、何事も石橋をたたいて渡ると言われてきましたが、その一方で、取組みに着手するのは時代の流れより早いことが多いのです。さまざまな仕組みや制度を、ロールモデルがない中、先んじて導入することになるので、十分でないことも多く、導入後でも継続して議論していくことが必要になってきます。そういうことを過去の先輩たちはやられてきたのだと再認識できました。
新井:社内で議論を、時間をかけて行うことができる土壌というのは素晴らしいと思います。また、先ほどコンサルタントに頼らないとおっしゃったように、御社の社風として議論する会社であるということはよくわかりました。
大櫛:2005年の分社化後は、トップダウンでないとグループ経営ができなかったのではと思います。グループ業績も厳しい中で、それぞれの事業ポートフォリオが、それぞれの事業領域で自ら成長するという遠心力を働かせて振りきる経営をされていたと思います。国内外の冷凍食品事業、低温物流事業、素材軸の水産・畜産事業などグループ会社に対して、主体的なチャレンジに経営資源を振り向けていました。
加藤:各事業部門にとにかく頑張れという感じの経営を2016年まで続けてきたということですね。業績が厳しい頃は各部門に発破を掛けてきたという経営スタイルですね。
分社化して各部の損益を可視化
大櫛:もともとは一つの事業体ですが、分社化前に、それぞれの領域で業績を可視化しました。それぞれの数字の推移を見てみると、いつも、どこかが助けてくれるという意識があるように見えたようです。分社化することで、そのことが明白となり、自立して採算をとるというグループ経営スタイルに転換したのです。
加藤:部門ごとの業績などを可視化して部門ごとの損益が把握できるようにすることを通じて、自分たちがやるというカルチャーも作られたということでしょうか。
大櫛:2005年の分社化前までは、各事業部門は一定の規模になっており、業績の良いところと悪いところが混在していました。分社化後は、それぞれが自分たちの顧客に向かって最適なビジネスを構築するために、商品やサービスを磨き上げろと発破を掛けながら、そのやり方は任せるという感じでした。そのために資金が必要であれば基本的に配分されたので、各事業会社は、それぞれの目標に向かって走り出したのです。しかし、当時の事業環境下では、うまくいくところといかないところがありました。一番、環境的に厳しかったのは低温物流事業です。もちろん素材の水産とか畜産事業も芳しくなかったのですが、最初に分社化したのは低温物流事業からでした。当社の祖業にあたる事業ですが、価格競争下で収益構造は大きく棄損していたこともあり、聖域を設けずに採算性を明らかにすることで退路を断った決断だったと思います。
新井:物流に求められる役割も昔と今ではだいぶ変化していますね。当時は、御社の低温物流は収益事業になっていなかったということでしょうか。
大櫛:そうですね。当時は儲かっていませんでした。サービスの差別化ができずに競合と価格競争に入っていたのでしょう。各エリアで競争優位性をだしながらも、国内全体を見渡して、効率的な物流を再構築する必要がありました。分社化することで議論がスタートしたのですが、はじめは大変だったと聞いています。
収益が厳しいとき、全体の中にいるとよく分かりませんが、分社化したことで、よく見えてきます。当時の低温物流部門のトップは、社員の処遇から抜本的に見直すなど、大胆に様々な仕組みを変えていきました。
新井:「2030年の姿」において御社が目指すポートフォリオの形を確認させてください。「豊かな」とか「健康」をテーマに社員皆さんがやることですが、長期ビジョンで示すときにポートフォリオの入れ替えも一緒に行うことになるのでしょうか。事業を組み換えて収益基盤を移行させるとなると、自分の部門は縮小することになるなと感じる人や、自分の部門がメインになるなと感じる人もいると思います。事業の方向性を打ち出すと、社員がポートフォリオの入れ替えもイメージするということです。ただ、御社の「2030年の姿」を見るだけでは、ポートフォリオの入れ替えの将来の姿があまり見えません。
大櫛:そこは、中期経営計画や決算発表で明確に示しています。その提示の仕方の社内的な評価はわかりませんが、当社は経営資源の多くを加工食品事業と低温物流事業に配分していくことを開示しています。この2つの事業部門以外にも多くの従業員が在籍しています。どうして自分の部門に経営資源が配分されないのかという不満があると思います。センシティブなことであるので、従来までは、どうしても総花的な発信になりがちでしたが、持続的な成長のためにグループ視点での資産効率や資源配分を明示していますので、一定の理解は得られていると思っています。
加藤:なるほど。ポートフォリオの入れ替え方針も出しているんですね。「2030年の姿」はパーパスという表現ではありませんが、社会貢献や従業員満足あるいは顧客に対するアプローチなどに関わる方向性として経営陣が作成していますが、社内への浸透に関して、どのような取組みをしていますか。
ミッション・ビジョン策定はスピード感を重視
大櫛:これまでと違うことを何かやろうとするとき、大事なことは社員それぞれの腹落ち感だと思います。目指す姿を役員が作っても腹落ちしない人は、必ず出てきますし、ボトムアップで選ばれた社員が作っても同じです。私はむしろ、スピード感の方が大事だと考えています。今までと違うミッション・ビジョンの方向性を出すにあたり、そのスピード感を重視し、役員メンバーを主体に策定しました。もちろん、そのあとの社員に腹落ち感をもってもらうための取組みも話し合いましたが、継続的な理解を得るためには、事業計画や施策に結び付いていることを明確にしていくことが重要だとなりました。中期経営計画や予算などの事業計画を立てるときは、各施策において、グループが策定した数値目標やマテリアリティKPIにどうつながっているのかを整理します。
マテリアリティにおける社会的課題も掘り下げていけば様々あります。お客様に近い課題もありますし、社会や地域全体につながるような課題もあります。難しいのは社会全体につながる課題の方です。近いところの課題はお客様と話していくことで明確になっていきますので、その打ち手も講じやすいです。一方、事業全体を見通しての課題は、実際は社会とこんな関係になっていて、こんな影響を及ぼしているのだということは中々気づかず、全体を俯瞰して見ることができないと難しいものです。つまり、改めて意識して勉強しないとわからないものだと思います。
当社としては、そういった感度を磨くために、ここ数年にわたって、研修や勉強会を開催しています。会社として、サステナビリティ経営を標榜してから、特に社内外の役員や部長においては、例えばサステナビリティに関する様々なテーマについて十数回の勉強会に参加しました。現在のオンライン技術のおかげで、関係部署の社員だけでなく、希望者にもリアルで傍聴できるようにしています。毎回、100人以上の社員が参加していますが、アンケート調査結果からも好評です。また、ある一部の情報共有に留まらないよう、その録画もポータルサイトで見ることができるようにしています。
これからの議論を広く行っていくには、多くの社員含めて、社会課題について感度を上げていくことが必要であると思います。また、組織編成を通じて経営サイドからメッセージを出すこともしています。新しい取組みを実施するときは、これまでの組織に付加していくのではなく、新たな組織編成にすることで、その重要性を社員に伝えることができると考えています。例えば、取締役会の下に諮問された委員会が多く構成されていましたが、それもゼロベースで見直しました。ガバナンス体制や組織の見直しを行うことで、当社は変わろうとしているというメッセージを社員に伝えることを意識しています。
加藤:社会との共生というと環境問題や健康問題、少子高齢化への対応などいろいろな社会課題があります。そういう分野への具体的なアプローチも教えて頂けますか。
大櫛:マテリアリティの最初に、「食と健康における新たな価値の創造」を掲げています。この関連で具体的には2030年度の目標として売上1,400億円を掲げています。国内ではすでに単身世帯が多数を占めており、この傾向は加速していきます。人々のライフスタイルは変化し、それに伴い食生活も多様化しています。料理時間やゴミの問題、栄養問題などへの対応が重要になってきています。具体的には家庭用冷凍食品の冷やし中華をはじめとするパーソナルユース商品や、脂肪酸バランスの健康価値に着目した「亜麻仁の恵み®」シリーズといった畜産品なども、このマテリアリティに係る取組みとなっています。
あえて大きな目標を立てる
新井:日本では大きな目標を掲げることが難しく、変に大きな目標を掲げるとそれが企業の成長の足を引っ張りがちだといわれます。日本のスタートアップ企業を見ても、国内上場を目的にするなど希望が小さい。もっと大きく捉えて世界に向けた成長を追求するのがグローバルなスタートアップ企業には多いのにといわれます。日本企業は伝統的に足元を固めていくという経営をしがちですよね。戦前には、中国への投資も早い段階で行いましたが、戦後は国内に留まりがちでした。
このような傾向がある日本の企業社会において、パーパスを唱えるときに、あまりに遠い目標を立てると、「何言ってるの、この人」みたいな感じになってしまいます。それは市場の受け止め方もあるのかもしれませんが、「そんな遠い目標をパーパスにしてもね」という感じです。しかし、今の時代に、あえて遠い目標としてのパーパスを掲げることに意味があるのではないでしょうか。
今の多くの日本企業の事例を見ると、パーパスとミッションの中間ぐらいの位置づけの目標を立てることで、社員の皆さんを引っ張っていく力と、その目標を社内の各部分へと落とし込んでいくという両方を取りに行くイメージが多いように思います。これが、現在の日本型パーパスではないでしょうか。日本の会社の求心力を考えると、企業が実際に行っているビジネスの中で、ミッションよりちょっと上のあたりをイメージして、もしかしたら手が届きそうな感じみたいなところにパーパスを持って行くという、より現実的なスタイルで作られており、それが会社の成長にも結びついてくものではないかと考えています。
加藤:パーパスについて、投資家へのアピールを目的とする企業もあると思いますが、御社の「2030年の姿」は、社員に対してのメッセージと社長は位置付けている部分も多分にあると思いますがいかがでしょうか。
大櫛:おっしゃる通り、インナーブランディングとしての位置づけとしても大きな役割を担っています。以前からインナーブランディングの様々な取組みは行っています。例えば、ニチレイフーズの「ハミダス活動」です。2011年からスタートし、すべての事業所に経営のトップが回り対話をします。また、ニチレイロジグループも2007年度から「選ばれつづける仕事賞」を表彰しています。顧客を見つめ、今までにない新しい仕事ができている人を表彰するのです。
社会貢献の一環ではスポーツ支援への取組みもあり、日本スケート連盟のオフィシャルパートナーのほか、日本水泳連盟の泳力検定もサポートしています。女子プロゴルフトーナメントのサポートは1984年から続けています。スポーツ協賛は、食に携わっている会社として、健康を目指す上では食と運動の両方が大事であると考えているからです。
加えて、子供に向けた食育にも力を入れています。寄付や食品支援の他、食に関する授業が主な活動です。
新井:社会に対して、いろいろ発信しているのですね。御社のこれまでのお話を聞くと、議論していくことが大切であることや、トップが引っ張っていくための苦労が伝わってきました。大きな方針を作る中で議論をして中味ををまとめていき、それが、順次、バージョンアップされていくイメージですね。
大櫛:「ニチレイの約束」という言葉は、対外的にも社内的にもわかりやすいメッセージだと思います。「ニチレイの約束」のメッセージに描かれているデザインには5色の線が相互に絡まりあっています。これは持株会社と4つの事業会社を表した色です。グループ社員に対し、どの事業でも目指すものは一緒だということを伝えています。ちなみに、グレーが持株会社、赤がニチレイフーズ、青はニチレイロジグループ、青緑はニチレイフレッシュ、緑はニチレイバイオサイエンスです。
マテリアリティが行動をしやすくする
新井:社会との共存を考える上で、企業は方針とか約束をどう作り上げ、社員にどう落とし込んでいくのかというところに苦労があります。御社とのお話を通じて、これまでの歴史の中で培われてきたものと、新たに作り上げるものの関係を整理するのに苦心されたことがわかりました。御社が取り組まれた歴史を見ることで、後からついてくる企業に対して、「こういうステップで自分たちの社内をまとめていくことができるかな」という手引きになるとよいなと思います。
大櫛:少しでもお役に立てれば幸いです。苦心ということであれば、一番大変だったのはマテリアリティの特定ですね。経営メンバーを一つにしていくことは、すごく時間がかかりました。実際に策定されたものは、シンプルなのですが、議論の拡散と収束の繰り返しに時間がかかるのですね。このマテリアリティの性格として、外部へのメッセージでもあると同時に、社員への思いにつながっていくものでもあります。「ニチレイの約束」とマテリアリティを比べると、マテリアリティの方が、社員には行動に結びつきやすいのではないかと思います。
健康というテーマについても、具体的に何をするのかわからなくなる時、マテリアリティに書いてあることで従業員がアクションを起こしやすくなっています。目標や施策が可視化されることが大事であると思います。他社のビジョンのなかには、いつまでに具体的にこうするのだというものを明確にしているものもあります。それらと比較すると、当社のビジョンメッセージは定性的な色合いが高いです。私たちは2030年の主な財務目標とこの数字を達成していくために必要な行動指針を示すものとしてマテリアリティが作られています。
加藤:マテリアリティが市場からの要請に基づき作成したのが、結局それをうまく活用することで社員とのよい会話ツールになっているということですね。
大櫛:中期経営計画を策定するときも、このマテリアリティに掲げた数字が、どういうところにつながるのかというのを意識しながら作っていくことができます。
新井:なるほど。その時に先にお示しいただいた御社作成の図が生きているということですね。
大櫛:ニチレイとして独自性をどう出すのかを議論しています。社員からは、自分の会社の強みとして挙げられるのは「冷力」だというものが多く出てきます。「凍らす」という技術をベースに、他社との違いを創り出したうえで食品も物流もビジネスをやってきたからです。
加藤:商品開発を通じて冷凍食品の種類を増やし、食卓を豊かにしたのも「冷力」に通じるんですね。
大櫛:そうですね。会社として「冷力」を使って、という言葉は、いろいろなところでアピールしています。最新のコーポレートブランディングのための企業広告においても、その一つに「冷力」を入れました。「冷力」という言葉は、昭和25年くらいから使われていたようです。これは、当社の造語ではありますが、これまで何十年も使われ続け、当社では「冷力」をもとにビジネスをしています。
新井:戦後間もなくのころに、モノをちゃんと冷やすというのは、すごい能力だったと思います。当時の社会環境で言えば、まずは魚の保存ということで御社がスタートし、それを継いで現在に至っているということがよくわかりました。本日はありがとうございました。
◆略歴
おおくし・けんや 1988年当社入社。2011年、株式会社ニチレイフーズ事業統括部長。2013年、経営企画部長。2014年、執行役員 経営企画部長。2015年、株式会社ニチレイフーズ取締役常務執行役員。ブランド推進部・人事部・管理部・事業推進部・海外調達部・国際事業部管掌、経営企画部長。2017年、株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長。2017年、株式会社ニチレイ取締役執行役員。2018年、取締役執行役員 経営企画部管掌。2019年、代表取締役社長(現職)。