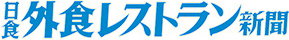シェフと60分 リストランテ「西班牙市場」オーナーシェフ・村田 禮三氏
当初スペイン料理を料理と思っていなかったと言う。
たまたま勤務先の社長が明大マンドリンクラブの初代マネージャーであったことから、「アルハンブラの思い出」に惹かれスペインへ行き、帰国後、突然日本で一番のスペイン料理をやれとの命令を下す。
命令を受けた氏は当時二三歳。老け顔のため三五歳くらいに見られ、社長は「三五歳で通せ、給料もそれに見合ったものを払う。ただし、その歳の男が何をやったら良いか考えて行動しろ」と応援ともつかないひとことで、日本一のスペイン料理店を目指しスタートを切る。
生来のこだわり癖が高じ、ついには本場スペインに乗り込み料理コンクールに出場する。ただし、外国人のため正式に受け入れられたのではなく、場所の提供だけに過ぎなかった。
たまたま現地新聞が日本から来たムラタについて記したり、日本のテレビが取材をするようになって、今までの一地方の行事に過ぎなかったものが、一挙に脚光を浴びるようになった。
こだわりはこれだけではない。ベネンシアドールの称号を現地で獲得しようと挑戦、ついに日本人では初めての栄誉を勝ち取る。
スペイン人があんなに格好良くやるなら、日本人の自分も負けないでやろう、向こうがグラスを見るなら、自分は見ないで入れようと、毎日、最低一時間、休日は二~三時間の練習をする。
軸足がけいれんを起こし、動かなくなるほどの練習量だ。「野球の選手と同じで、反復と数をこなした結果」というが、負けじ魂に裏打ちされた努力がうかがい知れる。
スペイン料理は、フランス料理が栄華を極めた時代には没落していた国の料理。さほど贅の豊かさを享受できなかった国の料理のため、素朴さが感じられる。
ヨーロッパ人でありながら、彼らが北を見ている目と違った目で日本人を迎えてくれるという。
「社交辞令、接待ではなく根っこの部分で迎えてくれるのが嬉しい」
ただ油断をすると、かつて世界を制覇した歴史の顔が見えかくれする。根底は頑としたヨーロッパ人であり、今日の繁栄の糸口を作ったのはコロンブスであり、作り上げたのはスペイン人と自負する誇り高き民族意識がある。
こうした関わり合うほどに好きになるスペインを、少しでも多くの人に知ってもらおうと、スペイン大使館その他から要請があれば、万難を排し「チンドン屋になり」、ベネンシアドールを披露しに出掛ける。
「スペインを題材に商売をやっている。何らかの形で気持ちを表したいだけ」と淡々と語る中に、熱いスペインへの思いが感じられる。
「われわれは食事を作り、さあ、お食べなさいと振る舞っているのではない。代金をもらい賄いをやっている」
マスコミなどで料理人がスポットを浴びているが、特別の世界にいるわけでない。お金をもらってものを作っていることに変わりはなく、「この姿勢は守るべき」と力説する。
そのため、自分の感性で作った村田流スペイン料理をひっさげ、第三者である本場スペインで認めさせ、それをお客に賞味してもらう。
また、「私のプランの推進役であるスタッフの生活も考えなければならない」。一部の人に村田の料理はうまいといわれても経営は成り立たない。不特定多数の人に受け入れられる味を提供し、「そこでみなさんが、村田の料理はおいしいとなればなお良いのです」。
食材へのこだわりがうんぬんされているが、今では物流も良くなり鮮度の良い物が食卓に運ばれている時代。
「われわれ料理人はこの物流に助けられていることを知り、おいしい物をさらにおいしく提供するにはどうすべきか、もっと真剣に取り組むべきだ」
また、大量生産する惣菜工場での厳しい衛生管理の実態を見ることも勧める。
「あそこまでやって、あの価格。われわれはもっと付加価値をつけて売る意識を持つべきだ」と、知らないままの甘えを戒める。
文 上田喜子
カメラ 岡安秀一
昭和23年、石川県羽咋郡生まれ。子供のころから絵がうまいと自他共に認め、将来は絵かきと決めていた。
上京後、学費もままならないなか、絵を志すが、基礎もできていない自分に、「村で神童、町で天才、東京でただの人」の現実を知らされる。
アルバイトで入ったレストランで、初めて知った料理の道。また、なにかと目を掛けてくれる経営者の命によりスペイン料理の道を歩む。
何ごとにも徹する性格からスペインに乗り込み、日本人初のベネンシアドールの称号をもらったり、国内では、自ら手掛けた手づくりの店「すぺいん亭」「西班牙市場」を展開、村田流スペイン料理を提供する。