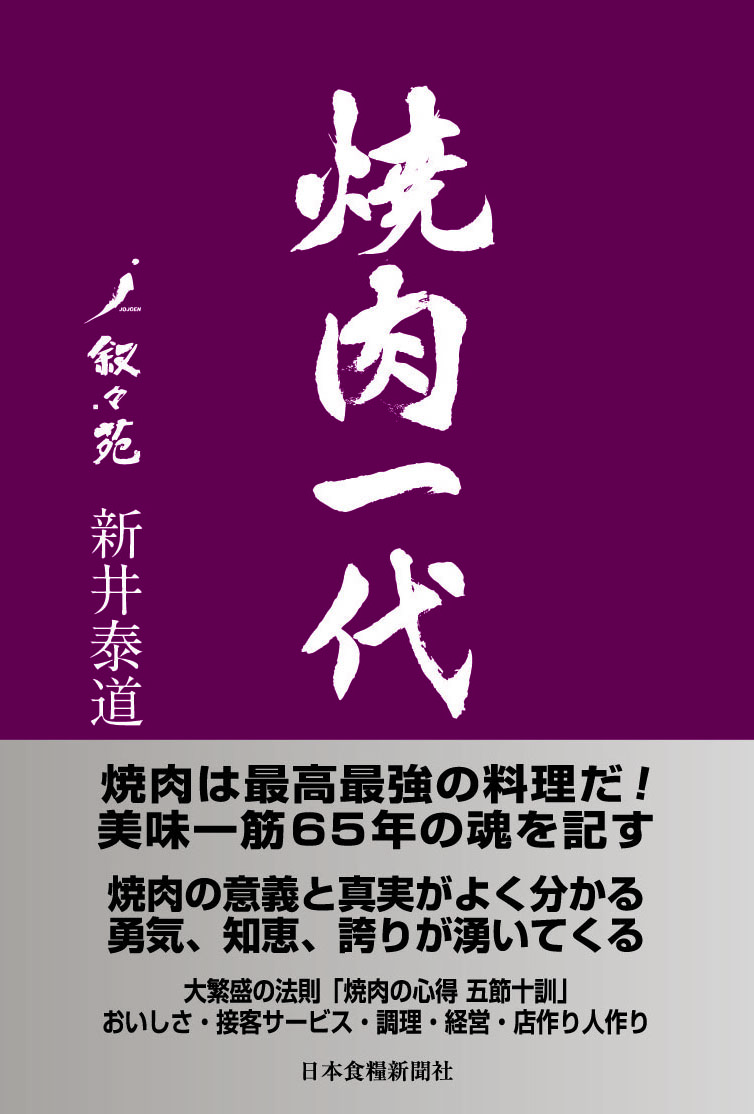忘れられぬ味(79) ヤグチ社長・萩原美明 スペインでの体験
遅い昼食のあと人々の陽気な喧騒で午睡からさめ、ふと目を向けると、ぬけるような青空からの白い透明な日差しは、白い土壁をより白く彩っている。日本の夏と違い気持ちの良い乾いた風に吹かれて、今まで全く経験したことのない心地で、窓越しの丘陵地帯に連なる緑の小高い丘の稜線に目を移した時、下階から民宿の肝っ玉お母さんの人なつっこい声でふと我にかえり、午後の仕事に向かう。
こういう人間本来の生き方を体験して一〇日目にもなると、自分がスペインのバレンシア地方の田舎町の缶詰工場に、果実缶の製造指導に来ているという非日常的生活であることさえ忘れてしまう。
私がこのコラムの寄稿依頼を受けた時、今から一八年前の夏の約二〇日間のスペイン滞在の体験が脳裏に鮮明に浮かんだのは、食事とは生活の一シーンだとの思いをその時強く感じたからだと思う。
仕事柄、外食をする機会も多く、料理や食事を楽しむというより職業意識が先に立ち、料理の材料や調理方法に気をとられ味わうことを忘れがちであった私にとって、スペインでの生活は全く異質なものであった。
生活習慣の違いで、工場の午後の操業は、3時から始まり終業の8時まで。一般家庭でも夕食は9時頃となるが、私の滞在時は、サマータイムのおかげで外にはまだ明るさが残り、薄暮というより日中の日差しが木々の間からこぼれ、夕食時にいつも通るカトリック教会の白い壁に、こずえの影が風できらきらとして輝いていた。この町で一番といういつも行きつけのレストランからは、男たちの談笑にまじって店のウエイトレスのオーダーを流す高い声が聞こえてきた。
店に入りオリーブ油の香りの中で、天井から下がった幾つものプロシュートハムを見ながらワインを傾けていると、五覚で食事をしているんだという感覚におちいった。何年も使っているメニューなのか、店の自慢料理が書かれた場所は手あかで黒ずんでいる。今日はこれと、私もメニューを指差しオーダーすると、気持ちもこの町の住人に一人となって、男たちの談笑に耳を傾けていた。
もちろんスペイン語なので、何を言っているかわからないが、胃袋で心地よさを感じ、出てくる料理に想像をふくらませながら待つ楽しみを感ずるのは私だけでないと思える。アペタイザーを体中で吸収しつくした時、私の所にパエーリヤ鍋が運ばれてきた。香りのつまった湯気を口と鼻から吸い込むと、地中海の魚貝類とサフランの香りとともに流浪の起源となった東洋の香りを感じ、料理の味わいの深さとともに最近の華美に流れがちな料理の原点を見たように思えた。
帰国し、何度かパエーリヤを食する機会があったが、あの時の感動にめぐり会うことはない。食事は生活の一シーンということを確信している。今度機会があったら、家族であのバレンシア地方の田舎町のレストランを訪れ、私が一八年前に感じたあの気持ちをパエーリヤ鍋を囲みながら皆で味わいたいと思っている。
((株)ヤグチ社長)

日本食糧新聞の第8433号(1998年10月2日付)の紙面
※法人用電子版ユーザーは1943年以降の新聞を紙面形式でご覧いただけます。