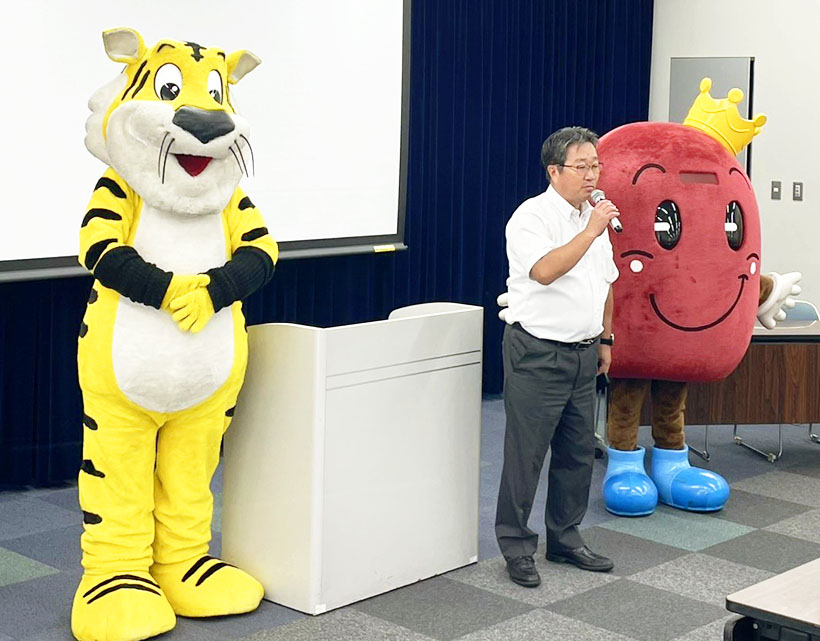10月18日は「冷食の日」販促など各種イベント展開
冷凍食品の新商品発売も一段落し、流通段階、小売段階での販売状況に関心が移ってきた。10月は「冷凍食品月間」で、全国的には日本冷凍食品協会が18日を「冷凍食品の日」として西村知美さんを起用して普及活動が行われている。また、業務用冷凍食品のイベントとして、9月にはセミナーが開催された。関東地区では首都圏市販冷食連絡協議会(市冷協)が、冷食流通企業と冷食メーカーの連携で慣例になった「冷食まつり」を量販店、CVSの協力を受けてフローズンガールも動員して行われる。市冷協は11月に入って、秋の新商品の中から選抜したおすすめ商品について、第二弾の冷食キャンペーンを計画している。
近年、新商品のサイクルが短くなる傾向にあり、メーカーもこれに対応して新商品の発売を四季折々と年四回に増加、成果を上げてきた。とはいえ、消費者の嗜好には保守的な一面もあって、売れ筋商品についてはリニューアルで対応することが多くなっている。とりわけコロッケ、メンチカツ、焼売、餃子、ピラフ、おにぎり、ピザ、唐揚げチキン、エビフライなどには固定的な顧客も少なくない。より積極的に購買してもらうため、売れ筋商品をより美味しく改善する傾向もみられる。他方で、素材的な冷凍食品が売れている。とりわけ、野菜類が目覚ましい伸長ぶりをみせている。枝豆、ソラ豆、ホウレン草、サトイモ、ポテト、インゲン、ミックスドベジタブルなどが家庭用として消費が定着、さらに増加している。冷凍野菜はポテトに代表されるように、業務用として大きな需要が形成されている。また、むきエビ、ホタテ貝柱、シーフードミックスなどの冷凍魚介類も需要が伸長している。
◇
冷凍食品は業務用が七五%、家庭用が二五%である。業務用は外食産業のレストラン、食堂などから、産業給食、学校給食、病院給食など、さらには中食分野、デパート、量販店などの惣菜売場の食材、冷食自動販売機のメニューとして幅広く利用されており、これらを総称して業務用といっている。家庭用も冷食売場から販売されるものの他、通信販売などでクール宅配便で届けられるものを含んでいる。これらの冷凍食品は業務用であれ家庭用であれ、いずれも消費者に賞味される食品であり、同じ胃袋に納まっていく。こう考えてみると、生活者は自分で冷凍食品を買って食べるより、外食や中食など他人に調理してもらって食べることが多いことを示している。日本人の家計消費支出で九七年の食料費は二三・五%、このうち加工食品が六一・九%と過半数を占めており、生鮮食品が三二・二%、穀物が六・二%といった状況である。このほかの家計費からも食料消費はあり、交際費での飲食支出、教育費での給食費や外食費用など、もっともっと国民は食料に支出している。
◇
食品産業の九六年総出荷額は二四兆四五六四億円、飲料などを含めると三五兆一一〇五億円の大きな数字になる。同じ工業統計で調理冷凍食品七九九〇億円、冷凍水産食品七〇六三億円、冷凍水産物五七二〇億円を含めると、広義の冷凍食品は二兆〇七七二億円に達する。二六七五事業所、従業者九万〇九三七人である。
◇
冷凍食品は国民生活になくてはならない食品の一つになったが、実際の販売面では価格競争が激しく、勢い、そのシワ寄せがメーカーにはね返って企業の採算悪化につながっている。良質の安全な原料を使って製品を製造し販売することで、冷凍食品は高い信頼を得てきた。技術的にも製造・品質管理面でも世界的な水準に引き上げて需要を形成してきた。ところが、厳しい販売環境では、製品水準の維持にも影響が出るのではないかとの危惧も生じる現状である。採算を度外視した製品販売は、業界にとってゆゆしきことといわなければならない。