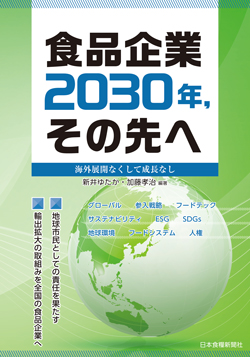食品企業におけるパーパス経営の先進事例:伊那食品工業・塚越英弘社長に聞く
◇伊那食品工業株式会社 代表取締役社長 塚越英弘氏
インタビュアー:新井ゆたか/加藤孝治
インタビュー日:令和5年12月8日
インタビュー場所:日本食糧新聞社本社(東京都中央区)
※社名・役職はインタビュー当時のものです。
* * *
創業者の考えの意味を引き継ぐ
新井:年輪経営を実践されていた塚越寛最高顧問(以下、顧問)を引き継いで社長になられた時、どうしていこうと思われましたか。ご自分としては何をバージョンアップというか、進化させていこうとお考えになったのか、そこを最初にお聞かせいただきたいです。
塚越社長(以下、敬称略):引き継いだ時点で経営スタイルを全く変えるつもりはなかったですね。顧問の考え方は私もそのとおりだと思ってましたから。顧問は創業者ではないけれども、創業者みたいなものなので、やはり創業者の人の考えはどんな会社にとってもすごいものだと思います。いろいろやってきたことの積み重ねから、多分感覚的というか直感でやっても成功している部分があると思います。一方、引き継いだものは、その能力はないので、きちんと勉強しないといけないと思います。創業者のやっていることの意味を自分なりに考えて、自分なりの捉え方で考えようと思いました。今、当社がやっていることには、どういう意味があって、一番のポイントは何か。顧問の場合は直感的に進めていたところもありましたが、それを自分なりに全部考えてみて、形として少し進化させていこうと考えて取り組んでいます。
新井:今まで直感で行われてきたものを社長が読み解いて、文章化するということはされなかったのですか。
塚越:文章化まではしてません。ただ、少し話はしています。その意味合いとか、なぜこういうことをやるんだという、背景を伝えるようにしています。顧問はそこも言わずに進めてきたところはありました。
顧問の発想でじっくりじっくり成長させていくこと、無理はしないで伸ばすことが大事なんだという発想でずっと経営してきたと思います。社会環境というか時代環境が激変してきている中で、じっくり伸ばしていこうというところ、年輪経営を変えないがための苦労があったと思います。一方で、今の時代はITがどうとか、AIがどうなるとか言っているので、苦労する部分がだいぶ変わってくると思います。ただ、取引先との関係や社員との関係みたいなものがしっかりしていれば、「これまでとこれから」みたいなことで変えなくてはいけない、ギアチェンジする必要があるとは思っていません。もちろん、やり方とか仕組みを少し整理するとか細かいところは変えてますが、基本的な考え方は変えてません。
加藤:企業経営のベースにある思想は変えなくても、70年代から90年代にできたことが、2020年~30年も同じままで続けられないことはあるように思いますがいかがでしょうか。
社員の給料を必ず増やす
塚越:私が変えたことといえば、社員の給料を必ず増やすと明言したことですね。もともと、それも目的そのものと捉えて努力を続けていました。物価連動で増やすほかにも社員が増え続けていますから、デフレの時代もずっと人件費は増え続けています。今は、業績が悪くても増やす方針ですので、今のような値上げが続くと、その分はさらに上乗せして増やしてます。その結果か、社員の定着率は高く、ほとんど辞めないです。
加藤:御社は年功序列の体制で、かつ賃金を上げ続けているということであれば、若者の感覚からすると、不公平感を感じて辞めていきそうな気もしますがいかがでしょうか。
塚越:当社は営業マンに対する評価も、営業成績で決めていません。営業成績の善し悪しはありますが、その影響は担当によって全然変わるので、そこに差をつけないという評価方法です。もしかしたら、それを不満に思っている社員はいるかもしれませんが、個人成績というよりは、もう自分が稼いで会社の全体の業績が良くなればいいと考えて働いてくれていると、私は思っています。したがって、同年齢の人の給与水準は、あまり変わりません。
役職が違えば多少は違いますが、その役職でやった分が違うだけで、基本給は一緒です。こういう話をすると若い人、頑張っている人は腐っちゃうんじゃないかとか、うちの会社はあの先輩は全然働いてないのに、なんで俺だけ安いんだって思う人が多いのではないかと言われますが、多分そんな風に考える人はあまりいないのではないかと思います。多少はあるかもしれませんが、別に個々人で競っているわけではなく、年功序列で給料は必ず上がっていくので、先輩の方がなんで俺より仕事ができないのに給料高いのって思う人もいるかもしれないけれど、いずれは自分も上がっていくと考えて、先輩と同じように処遇してもらえるんだと思い頑張れるのだと思います。
社員の幸せを軸にする
新井:一般的には、いろいろな人材がいるので、給与体系を変えたり、売り方を変えるなどしていくわけですよね。新しい分野の商品を開発したり、いろいろな分野で目先を変えて何とかしようとか、経営方式を直営店からフランチャイズに変えるとか、苦心しています。そのような中で、揺るぎないということはすごいと思います。変えなくてよいという自信はどこから来るでしょうか。
塚越:自信があるわけではないんですけど、まさに新井長官がお話されるパーパスが、企業にとっては一番大事だと思います。私たちの会社において、自分たちの軸になるもの、絶対ぶれないものは何かと考えると「社員の幸せ」です。全ての軸を社員の幸せという軸で判断すれば、そんなに難しい判断ではないと思います。
加藤:今の日本企業はどんどん人件費が上がっていって、コスト負担がすごく厳しくなってしまうので、苦しんで仕組みの見直しをしているところだと思いますが、御社では中高年になっても辞めないということですよね。
塚越:わが社には役職定年はないのですが、給与は60歳まで上がり、その後、65歳まではそのままの水準になります。
加藤:60歳で給与水準を引き下げる企業が多い中、65歳までステイさせると、従業員にとってはよいですが、企業経営としてはかなりコスト負担がきつくなるのではないかと思います。多くの日本企業はそこで苦しんでいます。
塚越:確かに、わが社も苦しむかもしれませんが、それをやることが会社の一番の目的だと考えているから、それをやり切らなきゃいけないということです。だから苦しんでもいいと思ってます。
加藤:従業員の方々の平均年齢はどうなっていますか。
塚越:若い人が増えているので、平均年齢は下がっています。年輪経営で少しずつ拡大するのにあわせて、緩やかに増えているということです。最近は、毎年の採用人数を変えずに30人ぐらいなので、30代~40代ぐらいから下は、大体同じ人数くらいいます。一方、当社は1958年に創業していますが、家庭用のヒット商品の「かんてんぱぱ」を売り出したのが1980年なので、最初の20年くらいはまだ会社の知名度も低く、50代の社員の新卒のころは、新入社員も少なかった。今、若い人が入るにつれて、徐々に平均年齢が下がっています。この30年の間に大きく変わったということです。また、中途採用も少なく、研究職も新卒で採用されてそのままであり、営業職や事務職もあまりローテーションはしません。
加藤:社長の経営に対する考え方は、自信をもって行うというより、それが自分達の使命だと考えていて、社員にもその姿を示し続けているということですね。
塚越:ぶれない姿勢を示すのが大事だと考えています。顧問の時もそうでした。顧問は、ある意味カリスマ性のある天才ですから、社員への姿勢について、直感的に捉えて感覚的に周囲に説明することなく、また、本人もあまり深く考えることなく経営を行うんです。感覚でもできてしまうということです。ところが、我々の場合はいきなりぱっとはできないです。いろいろと考えたうえで、顧問の行動を「こうした方がいい、こういう意味がある」と考えます。そう整理して、「だから逆に私はこういう風に言おう」と考えて、社員を意識して説明するようにしています。
新井:チーム力を意識しているということでしょうか。
部署の垣根を越えたつながり
塚越:これは元々顧問がやり出したことですが、社員みんなでやることを大事にしました。仕事ではなくてみんなでやる社員旅行などのイベントです。最近、私は、社員旅行は単なる福利厚生ではなく、当社にとって一番重要なイベントなんだと言ってます。この社員旅行について、社員が一生懸命計画を立てています。決して、会社がやらせているのではないということです。それぞれが工夫して、楽しんでいます。メンバーは、部署も別々の人で構成します。これはすごい大事なことで、旅行とはいえ、社内の行事でみんなが垣根を越えてどうしたら良くできるかを考えるのです。知らない人間と旅行して、会って話をしてコミュニケーションができるようになれば、業務にも活かされます。
加藤:そのほかにも、朝の掃除がありますよね。これも部署をまたいで全然関係ない人と一緒になって掃除をしていると聞きます。普段会わないような研究職の人たちと営業職の人たちが、掃除の場所で全く普通に会話をしていると聞きました。通常、会社の中で部門ごとに垣根を作りがちだと思われ、多くの会社はそれをローテーションで交流させるのですが、御社はローテーションさせないままで垣根を壊しているということなんでしょうか。
塚越:そうですね。最近、フラットな組織とか言われますが、私はフラットな組織は仕事を通じてだけではできないと思います。
新井:御社の経営の根本は年功序列ですね。また、人事ローテーションもしないですよね。下から考えると、フラットではない組織が出来上がっていて、不満を募らせてしまいそうですが、御社はそうならないように工夫しているということですね。
塚越:仕事以外の場所でフラットな状態になれるイベントを増やしているといえますね。他社の事例で、企業が部門を越えられるように、垣根を取って休む場所を今作っているという話を聞きますが、これと一緒ですね。部門は分かれてるんだけど、交流スペースを作って、みんなで楽しめるようにキャンプ道具が置いてあったりという話も聞いたことがあります。
加藤:掃除は何年前ぐらいからやってらっしゃるんですか。
塚越:私が入社する1997年よりも前から、ずっとやってます。社員も慣れてきて、だんだんやる内容がエスカレートしています。専門道具を使いながらやっています。掃除をやっている時には役職は関係ないです。同じ目的に向けて取り組んでいるので、上司部下関係ない状況となり、横のつながりが作られることになり、話もしやすくなります。立場を越えて、同じ立場でいろんな話もできたりします。その時には、顧問は指示する役になりますが、それ以外は私も含めてみんなフラットです。私になってからそういうイベントをさらに増やしています。
社員旅行も以前からやっています。今の形になったのは2000年前後です。昔はもう少しまとまったもので、そんなに班を分けるということもなかったです。みんなまとまって、ハワイとかにも行ってました。
加藤:その旅行費用も会社がそのコストを負担しているわけですか。
塚越:全額ではないですが、相当額を負担します。社員旅行だけで会社の負担は、数千万から6,000万ぐらい使います。それは経費で落としてます。
新井:年功序列で来年はこのポジションに就くというのがわかっているのは、社員にとって精神的な安定につながりますね。会社が社員を大切にしてくれているというのは安心感がありますが、それだけではなかなかイノベーションにつながるような一体感はできないように思います。それを、いろんなイベントをやることによって一体感を持たせようとするんですね。一連のイベントの中で、社員が自分で喜ぶという社員旅行もありますが、社会貢献イベントというのもありますよね。
塚越:経営者セミナーということで、たくさんの企業が来ます。わが社と比べて、他の会社はなぜそうなれないのかという話は出ます。同じような企業規模で、まさに地域の中堅企業としてやっている企業が同じような取組みができないのはなぜか、という話ですね。食品企業の中には、300年の伝統があるという企業もありますよね。小さな企業が社員との関係を作れないのはなぜか、私たちと給与体系は同じなんだけど、なかなか同じような取組みはできないようです。
加藤:御社の利益率はどのくらいになるのですか。
塚越:経常利益率で10%くらいです。
加藤:先ほどからお聞きしていると人件費やその他の経費を負担しながら、高い収益を維持していることを考えると、御社はすごい収益性の高い事業に取り組んでいるんですね。儲かりにくいBtoBの素材を扱いつつ独占的なマーケットシェアを押さえているという状況は素晴らしいと思います。
世の中にない商品で利益率を高く設定
塚越:当社は寒天のシェアは8割ぐらい押さえてますが、我々の売上の中で寒天が占めるシェアが30%ぐらいです。それ以外のイナゲル(洋菓子用寒天製剤)とか、かんてんぱぱの方が売上は大きいです。これらの商品分野では競争相手がいっぱいいます。我々は価格を下げないようにしています。価格競争に巻き込まれないようにするには、なるべく新しいものを取り扱うということです。世の中にないものを作るということです。新製品を開発して販売する時の価格設定の目標利益率を高い状態でスタートさせて、他社が参入してきて価格が下がってきたら、次の新しい商品にシフトしていきます。研究開発型の企業として収益性が高い状態を維持し続けているんです。
加藤:新規開発をして、他社の供給が追い付くと別の分野へシフトするのですね。普通の会社ではとてもそんな負担できないような経費を負担していては儲かっていないなら、資金を調達できなくなる恐れもありますが、誰も言わないし言えない状態になっているのは、すごいことだと思います。
塚越:今はそういう形で経営できているので、私は引き継いでからすごいやりやすい状況です。収益性も高く、内部留保も確保できています。自信を持って経営できる状態にあるからこそ、私は今の取組みが正しいと言えると思います。顧問の時代は、そこまでの蓄えは全くなく、スタートは大変だったと思います。顧問はここまで成長できたのは、運が良かったと言ってます。
加藤:他社との競争に陥らないように新しい分野に入っていって、収益性の高いビジネスを確保できているのは、ブルーオーシャン戦略とも言えますね。
塚越:顧問は、元々、そういう風にしようと言ってました。研究開発の投資は積極的に進めるべきだ、当社の行くべき方向はそちらだと最初から考えていたようです。
加藤:寒天というのは、製法も単純で差別化が難しい商品だと思いますが、研究開発型の企業として新しい領域に参入するという方向に舵を切り、それが成功して現在の高収益につながっていると思います。これは、みんなが必要とする企業へと発展してきたということだと思います。
新井:今、社員の1割以上が研究開発に携わっているということですが、どのような社員ですか?
塚越:わが社は、数十社くらいあった寒天企業のうち最後発だったんです。最後発ですから、最初は、既存の取引先は誰も相手にしてもらえなかったと聞いています。
長野県内だけでなく、全国に競争相手がいました。昔は昭和電工とかも、工業用というか細菌培地として寒天を作ってました。
寒天は、元々は日本にしかなく、戦前は輸出産業でした。日本から世界中に輸出していたこともあり、いろんな会社がやっていたのです。当社のスタートが1958年で業務用粉末寒天の製造事業を開始したということですから、かなり後発だったんです。そこで基礎研究開発でやっていかないと駄目なんだという風に考えたということです。寒天の商品分野は培地か菓子しかありません。当社が参入した当初は、和菓子が寒天の販売先の中心でした。そういうところは長い取引関係を重視するので、当社は相手にしてもらえなかったので、ほかの業種に「こういうものがあるけど使えませんか」と言って回ったんです。
利用者が求める価値を作る
新井:なるほど。でも、今となってはそれがよかったですね。和菓子に対しては寒天の代替物が出てきてますよね。また、和菓子自体もあまり伸びてないですよね。寒天と同じような機能のものがたくさん出てきたので、寒天が使われないようになってしまったわけですが、新しいお客さんを作ってそちらに買ってもらうようにしたのは正しい選択だったということでしょうね。和菓子の方だったら一緒に低迷することとなってしまったでしょうね。新しい分野で使ってもらえるように価値を作るということだったのでしょうね。
塚越:仰るとおりです。利用者に必要性を認めてもらうように価値を作るということをしていました。
加藤:御社はそれができたのですね。なぜ他の会社は同じようにできないと思われますか?
塚越:厳しい言い方をすると、やはりモノづくりに対する思いではないでしょうか。基本から外れてしまっているのではないかと思います。極端な言い方をすると、「いいものを作ろう」というこだわりが持てるかどうかです。「売れるものを作ろう」という風に流れていってしまうのではないでしょうか。
加藤:確かに、御社はたくさん売ろうというお考えではないですね。価格競争には行ってないですね。
塚越:小さい会社とか個人で事業をやっている間は、「いいものを作ろう」と考えて事業を行いますよね。それがなぜかある程度大きくなっていくと、「売れるものを作らなきゃいけない」という方向に変わっていくので、おかしくなっていくのではないでしょうか。本当は、企業が大きくても小さくても変わらないはずだと思います。
加藤:御社がこだわるというのもあるでしょうが、取引先のプレッシャーがありますよね。取引先から大ロットで売ってくれ、そうすれば安くしてやるという誘いですね。御社の製品を原材料として使う製造企業も商品として販売する小売企業も、まとめて作ってまとめて仕入れてやるから安くしろという交渉が始まると思います。その誘いに乗らないことの怖さはないですか。取引が切られてしまう怖さのようなものです。御社はお客さんからの要望に応えないというスタンスですよね。価格の引き下げもやっていない。
塚越:カップゼリーが売れていった時に、大口の取引を持ち込んだ大手スーパーがありました。最初は長野県だけで売れてるものを、一緒に全国展開しないかと言ってきたんです。当時、営業の現場だった人たちは是非やりたいと顧問に相談しました。それに対し、そんな取引をしたら、自分の会社のためにならないといって、顧問は断りました。大手スーパーと取引をしたら、販売額を追いかけることとなり身のほどを超えた成長になってしまい、社員が不幸になるかもしれないと言ってやめたということです。
考え方が合う企業とのみ取引
塚越:その時もどこに売ってくるかという基準が、たくさん買ってくれるところがいいお客さんだということではなく、きちんとした考えを持った会社で、当社の考え方と合うお客さんがいいお客さんだと考えたわけです。考えの合うところにきちんと物を販売することが大事だと考えたということです。営業担当が取引を相談する時に、たくさん売ってくれる小売企業でも、私たちの会社の考え方が合わないところには売りません。そういうところに売ってくると顧問から怒られるわけです。一時的にたくさん売ってくれるという契約しても、1年や2年でブツッと取引が切られるような企業より、10年以上の期間にわたって、長く細く取引をしてくれる会社のほうがいい会社で、そういう取引先をいかに見つけてくるかということが大事だと言われるわけです。
付き合うべきか迷った時には、相談して継続性はどうなんだということを考えさせられることとなります。もちろん、営業は取引を広げたかったと思います。かんてんぱぱは売り出したばかりですから、当然。商売ですから広げたくないなんて思ってないです。ただ、大事なことは考え方が合うかどうかです。結局、私たちに取引を持ち込んだ企業は破綻しました。やはり、考え方が合わない企業との取引はしなくて良かったという結果になったわけです。
加藤:スーパーみたいな大量仕入れ大量販売みたいな商売の仕方が、御社のビジネスモデルに合わないということでしょうか。
塚越:そうですね。当社のビジネスの仕方だと、基本一般的なスーパーとは合いません。顧問ほどではないですが、私もスーパーとの商売はあまり好きではありません。営業の人間も理解しているでしょうね。スーパーとの取引はあまり力を入れなくてもいいと言っていますから。
新井:確かに、長野県内でもかんてんぱぱは、スーパーでは売ってなかったですね。エーコープにはありましたが。大手スーパーだけでなく、地場のスーパーでもなかったと記憶しています。最初は農協で売ってました。
塚越:そうですね。今は、スーパーというか卸との取引を行っています。長野県内ではマルイチ産商さんを通じてスーパーでの販売がされています。
加藤:農協のほか、御社と同じ精神でやることができる会社にこだわって、マルイチ産商さんと取引をしているということですね。
塚越:我々も大きくなってきて、いろいろと要望を言うこともできるようになってきました。以前は、マルイチ産商さんは、我々が足元にも及ばない大きな会社でしたが、最近は対等にお話ができるようになり、こういう条件だったらやりますということが言えるようになってきました。最近は、そういった話を聞いてくれる卸売企業、スーパーさんも増えてきて、長野県外への販売も拡がっています。
加藤:非常に特徴的なビジネスモデルですが、研究開発型の企業だったら同じようなことができるかというとそういうわけにはいかないと思います。何が違うのでしょうか。
新井:やはり伊那食品工業といえば、「年輪経営」というのが取引先の皆さんに浸透しているという点がちがいますよね。新規開拓する時も、一時の売上よりは継続性で判断すると仰ってましたが、普通の営業ではできないですよね。
加藤:今となっては、伊那食品工業さんと商売するためには、自分たちもこういう思いでいかないといけないというのが、取引先企業にも浸透している状態にあるということですよね。
塚越:今はそうですね。おかげさまで当社のことを、みんな理解してくれてます。
新井:大手スーパーや卸売企業との取引を断った時には、変な会社だと思われたのではないですか。こんなに好条件を出しているのに、なんで取引をしないんだと不思議に思ったのではないでしょうか。それでも、貫いたというのは、その当時から御社の中で、身の丈にあった成長という思いがあったということでしょうね。
塚越:マルイチ産商さんとの取引は90年くらいからスタートしています。それまでは大手流通企業との取引は少なかったです。
加藤:90年くらいから御社の考え方、ここではパーパスというよりは企業理念みたいなものを理解してもらえる人としか商売しないといったとしても、取引先に受け入れられる状況になってきたということでしょうか。
塚越:そうですね。90年ぐらいから少しずつです。そのころ、よく営業マンが「今、〇〇君は、我々のお客さんみたいだけど、心の中では、本社見てるでしょう。」って悪口を言われたと言ってましたね。わが社の営業担当が、お客さんの言うことを聞かないからですね。特に、古い人にはよくそういうこと言われたって言ってました。
新井:すごい売り手市場ですね。
塚越:これは本社がそういう方針ですから、「本社を見てやってる」というのは、悪口ではありますが、当社の人間が考え方を変えないということをわかってくれているということだと思います。
新井:普通はお客様になびいて、お客さんが第一なんだよ、という風に見せますよね。
塚越:営業が「これだけ売れる」って、「売れるからこういう風に、こういう条件を出してくれ」とか、「こういう条件も付ければお客さんに買ってもらえる」って言ってきても、本社はダメだといいます。お客さんになびかないので、そういう風に言われることになります。
新井:顧客第一主義ではない会社ということですね。
塚越:確かに、そういう意味では顧客第一ではないですね。でも、お客さんの言うことのすべてに対応するわけではないということです。
加藤:最初の取引をスタートする交渉の時、取引の入り口のところでお客さんを選別しているというわけですね。ちゃんと自分の会社の理念とハーモナイズする人としか取引しないという強い姿勢がうかがわれます。
塚越:そういうことです。お客さんが大事でも自分たちが困ること、自分達の不利になるような話だったら、いくらお客さんが大事とはいえ、それを断るということですね。
加藤:なるほど。大事な順番でいえば、顧客第二主義ということで、社員が一番大事ということになりますか。
塚越:もちろん、社員ファーストで考えています。社員が困ることだったら、いくらたくさん売れることでもやらないということです。
加藤:顧問が経営しているころから、ずっと社員ファーストの考え方は続いているということですね。社員ファーストの意識は、社長の年始のお話とか、社内報などを通じて、社員に対し、繰り返し伝えることで定着していくのですか。
塚越:確かに繰り返し話はしています。社内報の新年の挨拶でも言ってますし、それ以外の時も話します。あと、本を通じて社員は理解していますね。新しい取組みでビデオなどでのメッセージもあります。
加藤:今は、最初から伊那食品工業がどういう会社か知っている人が面接に来るでしょうし、御社の考え方を分からないような人は採用されないこともあるでしょうね。
塚越:社員の意識に関して言えば、ある意味、洗脳されているところはあるように思います。現在のわが社の状況は、個人の夢の実現を求めるというだけでなく、個人の未来と会社の夢を一緒に考えて達成を目指しているという状態といえると思います。ただ、これは最初からそうだったかと言うと、決してそうではないと思います。人間は誰だって両方持っていると思います。いろんなことに挑戦してみたいという気持ちもあれば、やはり安定した安心できる状態の時も欲しいと考えるでしょう。
そうして考えると、わが社の場合、先輩を見ても、あまり働いてないなという人は少ないです。もちろん、個人差としての能力差はあり、年配の人は若い人と同じようにはできないところもあると思います。でも、その分、これまでの取引経緯や会社の歴史も知ってるし、経験もあります。だから、若い人は、困ったら誰に相談したらいいかということで、年配の方に頼ることはあります。だから、上の人があまり働いてないのに給料をもらっているという感覚はうちの社員にはないと思います。
決裁ルートは横一線
塚越:そもそも、うちの中で発生する作業として、書類作りという時に、営業書類としてお客さんに出す書類だけであり、社内内部のための書類作りの仕事というのは基本として少ないです。無駄な作業をさせないようにしています。口頭でやりとりをして、それで決まっていくことも多いですね。その内容を後から、社員がメールなどで確認のために報告書を出すことが多いです。そのやり取りは、個別のラインに限った話ではなく、全体的にそんな感じです。役職者を通してくる必要はありません。
加藤:縦のラインを年功序列で運営しているからといって、決裁ルートを順番に行くことがないというのは驚きました。
塚越:リーダーや支店長に相談したうえで、困ったら社長にというところもありますが、口頭が多いです。イメージとして、社長がいて、社員がある意味横一線に並んでいる感じです。いわば、全部家族というイメージです。
新井:今、社員が500人を超えていますが、500人単位の組織をその方法で回すのは、とても大変だと思います。自分の経験上、500人にそんな感じで相談を持ち込まれても、とてもやれないと思います。その意思決定の方法を信頼ある関係にできるように、日頃の交わりがあるということですね。社長の立場で500人以上の社員がいきなりやってきて電話がきて判断しろと言われたら、私は絶対できないです。
塚越:社員からのダイレクトでの相談は、私のところには毎日、メールや口頭を通じて、何10件と相談が来ますよ。社員と社長の関係や、社員同士の関係を考える材料は社員旅行とか、朝の掃除の作業や月例会、営業会議などの機会にトップからの話や、社員同士のコミュニケーションが行われることでフラットな関係ができているのではないでしょうか。
新井:無意識の意思疎通ができているということですね。とても面白いです。
塚越:営業会議とか役員会議とかの場で決めるのではなく、トップダウンで決めていきます。決裁を取ろうとしたら、トイレに行くために歩いている時でも「こういうことやっていいですか」と聞いてきて、「それやろう」と私が言えば決まっていくことは結構あります。私がやろうと言ったところで決裁は取れているということですから、あとは報告書みたいな社内書類だけを書いて提出されることで決定になります。時には、少し思い違いのような決定をしてしまう時もあります。それは、顧問の時にもあったようです。
新井:顧問が経営していたスタイルを、社長が引き継がれたということですね。顧問の経営スタイルを引き継ぐにあたり、組織として文書とかにしないと不安にはなりませんでしたか。顧問の経営スタイルを咀嚼しても、やはり心配にはなりませんか。
塚越:自信はないけれども、決めた以上はやるしかないということですね。この会社の形を残すとか、会社を大きくするということは大事じゃないわけです。それよりも、社員を一番大事にするという、この理念を貫くことが一番大事なことだと思ってます。
新井:それがやはりすごいと思うんですよ。創業者の時には天才でいいのですが、それを引き継いで従業員ファーストというのを維持されている、それで成長を続けている、これはなかなかできないことだと思います。
塚越:もう一つの当社の現状をお話すると、先代の時に、創業家(塚越家及び井上家)は株式を売却し、マジョリティを持っていないのです。今でも一部は所有していますが、所有株式の多くは社員持ち株会に売却していますので、当社株式のマジョリティを持っているのは社員です。
新井:むしろ、そのような状況であれば、逆に組織化をしたいと思います。
塚越:社員が自分たちの考えと異なる判断をするリスクがあると考えたら、社員に持ち株を渡すという判断はせずに、マジョリティを持ったままにしておきたいと思いますよね。
新井:創業家ファミリーが、マジョリティを持っていても持ってなくても、意思決定のプロセスを見える形にした方がリスクが分散されるように思います。そのほうが社長の肩の荷が降りるのではないですか。肩の荷が降りなくても、分かりやすい形になるメリットを考えて、私はそういう判断をするように思います。
社員と経営者がやりたいことだけをやる
塚越:説明が難しいのですが、顧問も私も同じ考えですが、自分の本当にやりたいことだけをやっているということです。会社を組織化するというのは、私たちにとってやりたくないことなんです。社員と経営者の間で、自分のやりたいことだけをやっているという感じなんです。それは、社員との関係をドライな関係にすると、関係性が壊れるのではないかという思いと、いろいろと面倒なことになるという感じです。
新井:お話を聞けば聞くほど、顧問も経営の天才ですが、社長も天才ですね。社長と社員の関係性について、「やりたいことをやっているんです」と言い切れる人は多くはないと思います。社長の言葉は裏付けだと思います。社長からお話いただいたビジネススタイルに似ていると思うような企業はありますか。
塚越:部分的には同じような考えで経営している企業はあると思います。家族的な経営を行っているとか、社員に共感を持つように考えさせるとか、そういうやり方の会社はいくつかあると思います。確かに、コンサルタントの方と話をしている時に言われたのは、ここまでの規模でやってる会社は他にはないと言われ、あるとしたら同様の経営ができるのは、20~30人規模の会社だと言われました。
新井:私も実現できるのは、社員100人までだと思います。小規模で実現できる家族経営を、この規模まで引っ張っていくことができているというのが、顧問と社長の経営が引き継いできたものですよね。「いい会社をつくりましょう」という御社の社是に基づき、社員の方々が、「みんなでいい会社をつくりましょう」という形で、その社是に乗っかっているということがすごいと思います。
社員の気持ちが一つになるのは、起業したばかりの企業や、イノベーション分野の企業の場合には、ある程度成り立つと思いますが、御社のように、普段からみんなが接している食品分野のように変化が少ない分野で実現しているのは、御社がニッチトップ企業だからできるということでしょうか。
お客さんからのアイデアを形にする
塚越:儲けなくてはいけないというのは、その通りですが、食品の場合は、「こういうものじゃなきゃいけない」「寒天じゃなきゃいけない」という形で、自社がこれまで生産してきたモノありきで考え、こだわっていてはいけないと思います。例えば、寒天はローカロリーな食材で栄養分が少ないという特徴がありますが、今はそれにこだわらず、寒天を素材として使いながら、高齢者ゼリーのように高カロリーの商品開発に取り組んでいます。我々がやるのは、お客さんのニーズに合わせることで、「寒天だからヘルシーでローカロリーのもの」ということではないのです。新しい利用方法も考えて研究開発を続けています。
こうした新たな分野への研究開発は、社内の研究者のアイディアもありますが、お客さんからのアイディアがきっかけになります。お客さんから「こういうのできないか」と相談されて対応するのが多いですね。商売の細かいやり方の部分でお金とかの交渉については、お客さんの声には振り回されませんが、商品開発はお客さんの声を踏まえて取り組みます。私からトップダウンで開発に落とすよりは、多くは現場であるBtoBの営業ではお客さんの声を聞き、それを研究部門に投げて、実現化していくということです。だから、こういうものを作らなくてはいけないという意識ではなく、お客さんの相談事にうまく応えていこうというところからスタートしています。
新井:そういうところは、顧客第一主義ですね。
塚越:こういうことをやるのであれば、この会社に相談しよう。この会社に言えば何か解決してくれるのではないかという存在になろうというのが、一つの目標です。
加藤:どこにでもあるような寒天という商品だけど、そこで開発をずっと続けていくところで、他との差別化を図って顧客との関係を作ってということを早い段階から取り組んでいるんですね。
塚越:そうですね。今はその寒天だけではなく、お客さんのほうで、「少し粘度をつけたいとか、とろみをつけたい、あるいはちょっと固める」ということを考えた場合に、寒天素材でなくても、ニーズに応えてくれる会社として伊那食品工業に相談してみようという風に思ってもらえるようになっていると思います。
加藤:これからの伊那食品工業を考えた時に、今の手法、モデルでまだまだいけるのでしょうか。持続性のある方法かということでは、今の研究開発型で進めた場合、食品分野だけでは限界があり、栄養とか医療とかの分野に広げる可能性はありますか? あるいは海外への展開を考える必要はあるとお考えですか?
塚越:まだまだ食品分野では研究開発型で市場開拓できると思っています。また、国内市場でも十分拡大の余地があり、慌てて海外展開しなくてもいいと思っています。
我々は販売する商品と、その商品開発力を活かして一つの商売にしています。むしろ、商品そのものより開発力を評価されて使っていこうと言っていただける企業だと思います。
加藤:なるほど。開発力を活かすことができる事業領域は、食品分野でもまだまだたくさんありそうだとお考えだということですね。
事業拡大は社員の幸せが前提
塚越:我々がこれまでに扱ってきた商品なんて、食品全体のごく一部の世界です。まだまだ食品の中で開発できる分野はあります。食品にはたくさんのジャンルがあるので、まだまだ市場は広げられるのではないでしょうか。
新しいニーズに応えた商品を開発していくと、企業規模も社員1,000人から2,000人くらいに拡大しなくてはいけなくなるかもしれません。
年輪経営の発想ですから、無理して拡大するということではないですが、市場からの要請にこたえるうちに、直近10年で事業が拡大することもあり得ると思います。今の会社の考え方は変えずに販売市場が日本からアジアに展開する可能性もあります。今、直ちにどうしようということで狙ってやっているわけではないのですが、自然にお客さんの需要が増えてくれば対応することとなります。ただ、そういう時でも今までのお客さんとの関係は変わりませんから、10年20年単位で取組みができるような会社との関係を考え、単に今だけ儲かる、売上が上がるということでは基本的にやりません。
加藤:御社の事業に関して、さらに商品開発が進んだり、市場拡大を進めると、今のように社員が同じように考えられるか難しいですね。扱い分野を広げることで、今のようなスタイルのままでは増やせなくなるような気がします。
塚越:そこは、ある意味で「洗脳」ですね。繰り返し声をかけるとか、行事に参加する中で共有していく必要があるでしょう。この時に、事業を拡大させるために買収するということはありません。
加藤:やはりそこは相変わらず成長を求めないわけですね。あくまで社員の幸せを追い求める、社員の幸せな状態が続くのであれば、その範囲内で新商品開発や新市場開拓をする、ということですね。何かをすることで社員が不幸せになりそうだったら、それはやらないということですね。
塚越:社員が一番大事です。社員の幸せが目的であり、全てはそこから考えます。また、年輪経営が基本ですから、短期的な事業課題ではなく、中長期的にじっくり取り組むことになります。
新井:今、パーパス経営に取り組んでいる企業の多くが、会社のパーパスを決めて、それから各社員にマイパーパスを作らせて、個人のマイパーパスと、会社のパーパスをすり合わせしていくということを組織的に進めるというパターンが多いです。社員の幸福というのは社長がイメージしているものがあるのでしょうが、それぞれ違うこともあります。御社では、「あなたにとっての幸福は何なんですか」という形で、社員の方々に尋ねるなど、いわゆるマイパーパスを表明させるようなことはやってますか。
塚越:そのようなことは行っていません。従業員満足調査も行っていませんね。ある意味、私の思い込みもあるかもしれませんが、社員はこうしたら幸せだと思うように経営を行っていますが、そうではない人もいるかもしれません。ただ、少なくとも、給料の面は、誰だって増えた方が良いに決まってると考えて思い込みでやってます。従業員満足度調査をやっていませんが、常に社員の幸せのことを考えていると伝えることが実は一番大事なのかもしれません。皆さんのことを考えてますよということが、こちらが言うだけでなく、受けとる方がそう思うように働きかけています。
新井:いわゆる心理的安定性を与えているということですね。
加藤:組織の仕組みとして年功序列で上がっていくことなどもありますが、インフォーマルな関係作りが出来上がっているという気がします。少し変だなと思っている人がいたら、周りが放っておかないような組織文化ができているように思います。
塚越:みんなでやっている社員旅行でも、行った先で飲みながら意見交換したり、同じ部署だけの親睦だとそこで止まってしまいますが、横串を刺して違う部署にも伝わることで、上に上がってくることもあります。
加藤:最初から仕組んでいたわけではないが、結果的に全社員が参加する朝の掃除や、社員旅行活動というのが、インフォーマルな横串の関係として結果的にすごく良いものが出来上がっていったということですね。
塚越:そうですね。だから、最初にお話したように、顧問は、それを直感的に実行していたんです。一つ一つはこういうコンテンツをすることが社員にとって正しいだろうと考えるだけです。だけど、やっていることが結果として、全て社員全体のつながり、社員の幸せにつながっているということです。私の場合、自分なりにそういうことを解読して、これからも続けるとしたら、こういう風にしたらどうだろうか、どういう方向にしたらいいかと考えながらやっているということですね。
加藤:トヨタ自動車の豊田章男さんが顧問のところに来て、「模範となる会社がここにあった」といって講演をお願いされたと聞きますが、どこに一番感銘をされたと思いますか。
塚越:章男さんがお話の中で引用しておられるのは、社員に対する思いの部分ですね。社員への思いというか、気持ちでしょうか。社員との関係性や社員ファーストで考えるというところもありますが、それだけではないと思います。要は、仕事に対する考えで、それぞれ思い込みがあるわけですよ。いわゆる「社会人で一般の会社はこうじゃなきゃいけない」「仕事の進め方がこうじゃなきゃいけない」という形で。どこの民間企業もそうでしょうし、行政機関も同じだと思いますが、目標数字を設定して、今の進捗状態をチェックしていくというやり方ですね。それが仕事だという思い込みがあるから、計画を作ってそれに沿ってやっていくとか、その手法ばかりに目がいってしまうと思います。
その結果、あるべき姿かたち、自分たちが何を目指すのかというところが薄れてしまう。目指すべきものを忘れてはいけない、ということを章男さんは、顧問の話の中から伝えたいのではないかと思います。企業経営に対する考えの入り口が違うということですね。方法じゃない、意思なんだと。新井長官も以前に「how to」じゃなくて「to be」が大事だと言っていましたよね。どうあるべきかがやはり一番基本だと思います。
新井:その考え方に沿って、御社の規模でできているということは、すごいことだということを、あらためて認識しました。
塚越:ちょっと厳しい言い方をすると、皆さん、パーパスとか社是とかいう言葉を使って、結構考えていらっしゃるように思いますが、みんな本気で思っているわけではないように思います。今の私たちの経営を考えてみると、パーパスという言葉を使うことは、少しなじまないように思っています。
加藤:パーパスとは違うのかもしれません。コーポレートガバナンスに基づいて考えようとか、KPIで評価しましょうということに縛られすぎて、そちらから考えてしまうことで少しおかしな方向に向かっているのではないかという気がします。豊田章男さんは、御社の経営に対する考え方を社内の方に見てもらうことによって、各自の仕事に対する考えをリセットして、ゼロベースで考え直そうよと伝えているのでしょうかね。
塚越:言葉でまとめるとそういうことになるかもしれません。ただ、簡単なことではないと思います。わが社の取組みは、収益重視ではなく、社員重視です。私としては、儲けたくないというわけではないですが、急激に伸ばしたくはないです。信念を崩してまで仕事を取りに行く必要はないということですね。自分の考えが大事だし、社員とどういう関係性を保つか、自分たちの家族が一番大事だから、それを曲げてまで取引を取りに行くということはしませんということですね。
新井:なかなか他社には真似できないことです。形から入って、皆さんも実践できますよとは言えない。皆さんが運動会とか社員旅行だけやっても意味がないでしょうから。
塚越:多分、豊田章男さん自身も、経営に対する確固たる思いがあると思います。自分なりのすごい信念ですね。本気で、形だけではないところです。それがないと結局どこかで変わってしまうこととなり、意味がなくなりますよね。経営の前に経営者自身の信念、やるべきことは何なのかというぶれないものがないといけないと思います。
新井:信念もあんまり固いと、時代の動きでポキッと折れてしまいます。信念がありながら、柔軟性と信念の耐久性のバランスだと思います。
塚越:信念というと、細かい部分ではなく、大きな意味で捉えたほうがいいと思います。当社がこうなった過程を考えると、やはり顧問には柔軟性があったと思います。あの年のわりには、考え方が若いのです。社員の幸せが大事というところは変わらずに、他のことに関してはすごい柔軟性があるんです。
新井:そこの組み合わせというか、価値の順番が大事ですね。今、お話を伺ったように、価値をおく順番が明確になっているから、その価値に共鳴する人がついてくる。それが社員の方にも共鳴するから、社員も会社のことを考えて仕事してくれるようになるのですね。
塚越:今の役員の方々は、長く会社にいて、それぞれが会社であり顧問の理念に沿っているということですが、役に就いているのは、年功序列で考えて一番年齢が上の人たちです。これは、当社の営業マンも含めて部長たちもみんな同じで、年齢が一番上の人が、役員をやっています。
「いい会社をつくりましょう」というのは絶対こうじゃなきゃいけないというものがないところなのです。普通の会社は、多分役員と部長クラスの意識の差とか処遇の差が結構あると思いますが、当社は社長も含めて、大きな差はないようにしています。
新井:役員が能力で抜擢されてないってことですね。逆に考えると、意思決定をフラットにしておかないと有意な知恵が死んでしまうのですね。
塚越:意思決定は、最初はそれぞれの役員がするのですが、最終的な意思決定は私です。ここは、もう家族ですよ。大きな家族です。当然として最終的に決めるのは一人になります。
加藤:社長は、この大家族を守るんだという意識でやっていらっしゃるんですね。
新井:だから、意思決定で自分の考えを進めていくにあたって、能力がない人が上にいると、自分の思いが通らないことになり不満が出ますが、御社の場合、自分の思いを社長を活かして通していけばいいんですね。
塚越:社内に権限を阻害する人はいません。
新井:自分のやりたいことを阻害する人がいないから、あの人あの年であの役職で働かないという不満は出てこないということなんですね。
加藤:俺に話通さずになんで社長にいきなり言うんだよっていう人がいないということですよね。部長と本部長とかがいないということでしょう。
塚越:上にいる人が自分を通さずに社長に話をしたから怒るということはないですね。
新井:大変、よくわかりました。本日はお忙しいところ、細かな部分までお話をお聴かせいただき、誠にありがとうございました。
◆略歴
つかこし・ひでひろ 平成2年3月、日本大学農獣医学部卒業。平成2年4月、CKD株式会社入社。平成9年3月、CKD株式会社退社。平成9年4月、伊那食品工業株式会社入社。平成13年2月、取締役購買部長就任。平成17年2月、専務取締役就任。平成28年2月、代表取締役副社長就任。平成31年2月、代表取締役社長就任。令和4年2月、米澤酒造株式会社代表取締役社長。現在に至る。