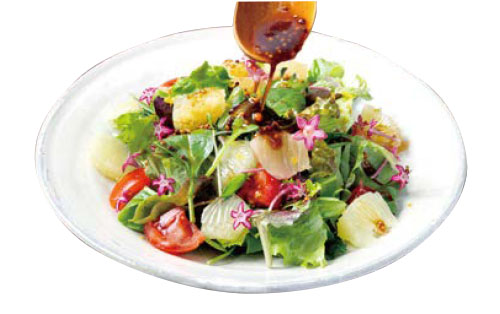10年後を見据えた飲食店の課題 お好み焼き=繁盛する郊外型店舗
外食産業界の市場は、既に二八・八兆円規模にまで拡大し、競争激化の様を一段と強めている。その中で、小売業界が「買い回り品店」から「専門品店」「最寄り品店」へと“二極分化”の現象を表しているように、外食業界においても二極分化の流れが起こっている。
つまり「○○屋と表現される店(例えばとんかつ屋、焼き肉屋、居酒屋などなどである)、言い換えれば、そこそこの商品があれこれそろっているFR(ファミリーレストラン)ではなく、より特化し高いQSCレベルを提供する専門店的な店」と、「FFS(ファスト・フード)のようなコンビニエンス性を重視した店」である。
そんな中で、今注目されつつあるのが「お好み焼き屋(店)」である。その根拠と取り組み方について、検証してみたい。
「お好み焼き」という呼称は、戦後確立されたようだが、「麩の焼き」→「一銭洋食」→「お好み焼き」と変化してきた。現在、「お好み焼き店」は、大阪、兵庫、広島の三府県が、店舗数、人口当たり店舗数の上位を占めており、幅広い支持を得ているものと考えられる。
半面、秋田、岩手の両県をはじめとし、東北地域では非常に少ない。事業として考える場合、頭に入れておく必要がある。
「お好み焼き」だけでなく、「たこ焼き」も含め“鉄板焼き”が好まれる要素として、売り手側(店)から見れば――
(1)客層を選ばない(お年寄りから子供まで幅広い顧客層がねらえる)。
(2)お客様が調理してくれるので、人手がかからない(人件費を抑えられる)。
(3)何といっても原価率が低い(従来の店ではせいぜい三〇%。あるいはそれ以下である)。
――などが挙げられる。
買い手側(お客様)から見ると――
(1)気軽に手軽に利用できる(気取らずに家族、グループ、カップルで行ける)。
(2)味つけや具(トッピング)が、好みに応じていろいろ選べる(好きに料理できる)。
(3)健康的である。
(4)価格が手ごろである。
――という“行きやすさ”がうれしい。
しかし、実状は店舗規模が一〇~二〇坪くらいの小規模店が多く、月商も一〇〇~三〇〇万円クラスが圧倒的である。市中・駅前商店街の立地で、個人営業のテナント店舗がイメージされ、多店化の事例は割と少ない。その「お好み焼き店」が注目されるようになったのは、モータリゼーションと“食の多様化”という大きな変化の中で、「郊外型お好み焼き店」に対するお客様の反応によるものである。
香川県高松市の郊外に「お寿美」(本社=坂出市)がある。平成7年11月にオープンし、八九坪・一二〇席で年商二億円超の大繁盛店である。
成功のポイントとして(1)QSCレベルの高さ(2)駐車場の広さ(3)店舗の雰囲気の良さ――を挙げたい。
(1)と(2)は立地に関係なく重要であるが、生活者としてのお客様が“楽しい食事”をしに行く時の足は「車」であることから、(2)の重要度は高い。
「お寿美本店(坂出店)」は、坂出市の住宅地の中に入り込んだ立地で、年商一・七億円を売っており、そこも駐車場は広い(四〇台以上駐車できる)。つまり駐車場の広さが、この店の繁盛を支えている要因の一つであることは否めない。学ぶことの多い店である。
効率面でクリアしたいのは、(1)坪売上高=月一五万円以上(2)一席当たり売上高=一日四五〇〇円以上(3)人時売上高=一時間四五〇〇円以上である。
もちろん「原料費三〇〇〇円+人件費率」≦六〇%、管理可能費率≦七二%も忘れてはならない。
以上のことから、これからの「お好み焼き店」成功のキーワードは――
(1)郊外型店舗(市中型を否定するものではない)(2)コンセプトが明確である(3)QSCレベルの高さ(必然的に客単価も高くなる)(4)オペレーションの高効率性
――であり、十分な準備で臨めば大変面白い業種である。