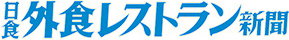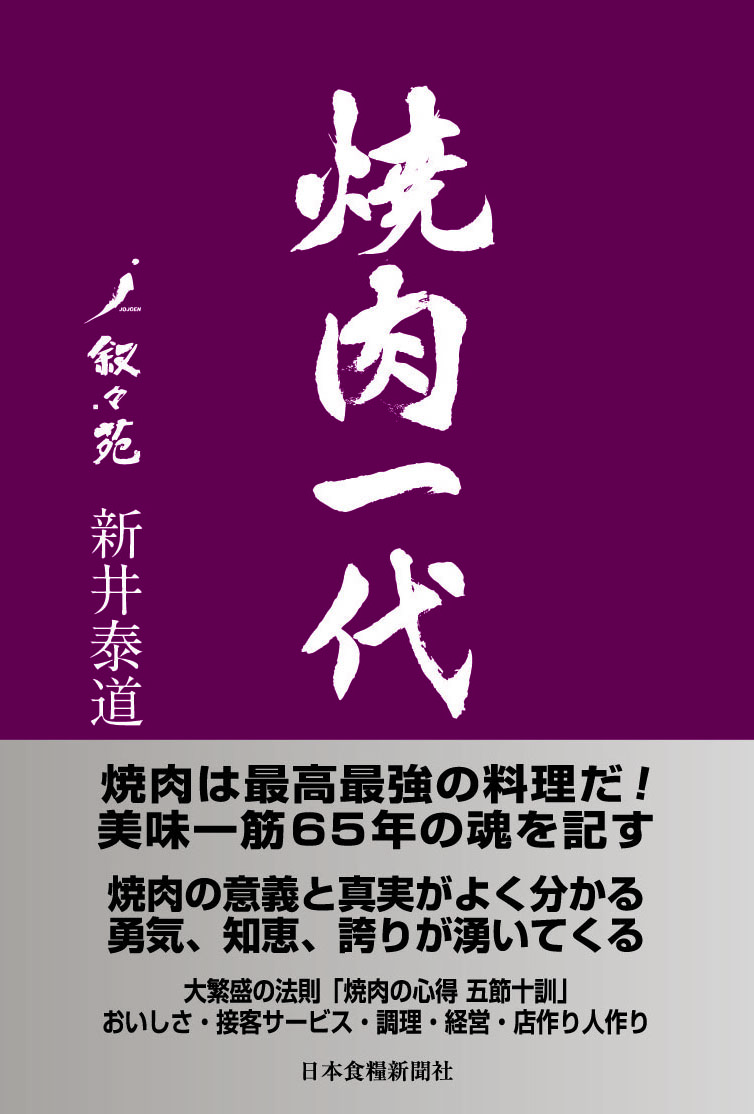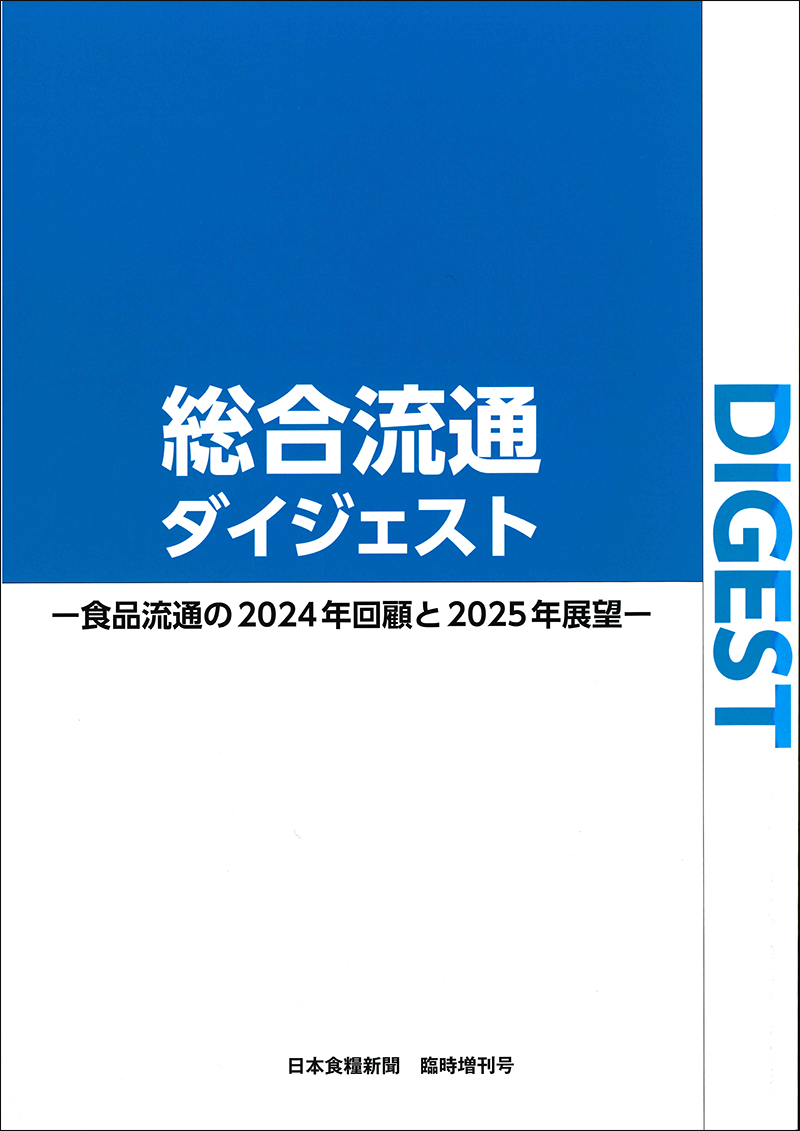シェフと60分 中国料理「香港苑」料理長・平野秀樹氏
新しい職場に移りまだ日が浅い。毎日の仕事の中で自らのやり方をバンバンぶつけ、「私がどういう気持ちで料理を作っているかを見せていきます」。受け入れてくれる者、拒否する者いろいろだが、仕事への取り組み方で本音が分かる。
「性格が内気だから声が小さいという者もいるが理由にならない。声が大きくなるのはその人の心が開いている表れ。責任を感じれば自然に気持ちが前に出ていき、今まで口に出さなかったこともハッキリ口に出すようになる」すべては本人次第。妙におべっかを使ったりはせず、怒鳴るのも褒めるのも皆平等だ。
新人には、学校で描いていた夢と現実の料理人の世界が違うことをハッキリ理解させるようにする。
「私の修業時代は、少しでも多くのことを覚えようと自分の時間作りに工夫をした。段取りを良くし一〇分でやるところを八分に。また時間外の朝早くに出勤したり、夜遅くまで居残って練習をした」
今はどうか。確かに時間内は教えられればやる。それ以上に積極的に学ぼうとする者は少ないという。
自らの修業経験を振り返りいささか不満をおぼえるが、どんな環境でもやる気のある者はしっかり取り組んでおり、それほどの危惧を抱くほどではなさそうだ。四川料理が柱の平野シェフと広東料理が柱のセカンド、「調理場をまとめるには同じ系統がやりやすいが、お互い刺激しあう関係でありたい」と安易な妥協を許さない。
お互い切磋琢磨すると同時に「たとえ私が風邪をひいて休んでも、店が回せる状況にしておきたいから」と笑う。今後の管理能力が問われるところだ。
今までのコースメニューは一卓で大皿にまとめて提供する方法であったが、新客層を取り込むため小人数、カップルでも楽しめる小皿料理に切り替えることにする。
四川料理はもともと小皿料理。なんら抵抗はない。ただ、こうした小皿料理を酒のつまみ的料理ととられるのにはいささか困惑する。特に、古くからの酒好きの常連客は二~三品で何時間も居座ることになるからだ。
料理人にとり一生懸命作った料理が手つかずで返されることほど悲しいことはない。
味が悪くて残されたのか、酒を飲むあまり料理にはしをつけなかったのか、生まじめな性格からデータをとる。一方で酒の席で冷めても大きく味の変わらないもの、また、味にメリハリをつけたり、ポーションを少な目にするなどの工夫をする。
「看板は中国料理店。居酒屋とは違いあくまでも食事がメーン。お酒は食事を楽しむために飲んでほしいですね」と本音をチラリ。
「川崎の土地柄に合わせ徹底してメニューを改定しました」
一ヵ月の予定が二ヵ月になったほど、新天地にかける意気込みは半端ではない。
駅ビル内に立地する店舗は歴史も古く、長年の固定客がついている。
「東京と違う神奈川独特のひと味半濃い味の好み、また、盛りの多さなど長年親しまれてきた地元の味わい」は、だんだんと支持者年齢を高くしてきている。
「ある宴会で『小柱が硬い』と言われたときにはビックリしました。辛い、薄いは調整できるが……」
予期せぬクレームを受けた後、宴会料理には細心の注意を払うようになった。
また、ピータンはネギ、ショウガ、香菜に酢醤油で食べるのがオーソドックスな食べ方。これをガリ、ネギ、ショウガで出したところ、「おまえは中国料理を知っとるのか」と怒鳴られたことがある。
「食べやすい味として人気商品となっているが、お客の中にはこの料理はこうして食べるんだという固定観念が強い人もいるんです」
自らおいしいと思ってもお客がおいしく感じなければ商品にならない時代。「個人差があり押しつけはしないが、これからもどんどん新しいことに挑戦していきますよ」と意気盛ん。
長い間、四川料理を手がけてきただけに、和食、洋食の世界の素晴らしさが見えてくる。
「中華の手法は崩せないけど、良いところはどんどん取り入れていきます」
手間ひまかけて作る洋食のソース。アイデアをいただき、玉ネギ、セロリなどの野菜にリーペリンソース、トマトケチャップなどをバターでのばし、中華らしく豆板醤、豆鼓、黒コショウを入れたソースでグラタン風メニューにする。
このほか和食の焼き物、前菜の色彩感覚、盛り付け、味のメリハリの付け具合いなど、参考になるエッセンスは数限りない。
「最終的にはお客の審判を受けなくてはいけない」ながら、形にとらわれることなく自由に素材を使い、アレンジできる今の時代に生きる幸せを素直に喜ぶ。
同じ料理人からおかしいんじゃないかと言われたり、お客の中には、俺は中華料理を食べに来たんだ、きれいに盛りつけ気を使ってくれるのはありがたいが、思っている中華のイメージとは違う、何故わざわざこんなものを出すんだと苦情を受けたこともある。
「古い客は昔からの食べ方に固執するが、新しく若い客層を増やしたいから新しい試みをやっているんです」
コースメニューの中に新しい味を入れることで、若いお客が入るきっかけになれば良し、古くからの客も味のレパートリーを広げてくれればと期待する。
◆ 昭和36年、神奈川県鶴見市生まれ。小さいころから大の食いしん坊、高じて自ら鍋を振る世界に入る。憧れの洋食店で一年余り修業するが、店が居酒屋に業態転換、これをきっかけに本格的中国料理への道を進む。
横浜・中華街「謝謝」、川崎「大沼飯店」、銀座「四川飯店」などを経て今年4月から現在の「香港苑」に勤務する。駅ビル内レストランとして長い間、固定客に支持されてきたこの店に、平野流四川の新風を吹かせ、新たな客層を広げようと奮闘する。
文・カメラ 上田喜子