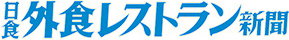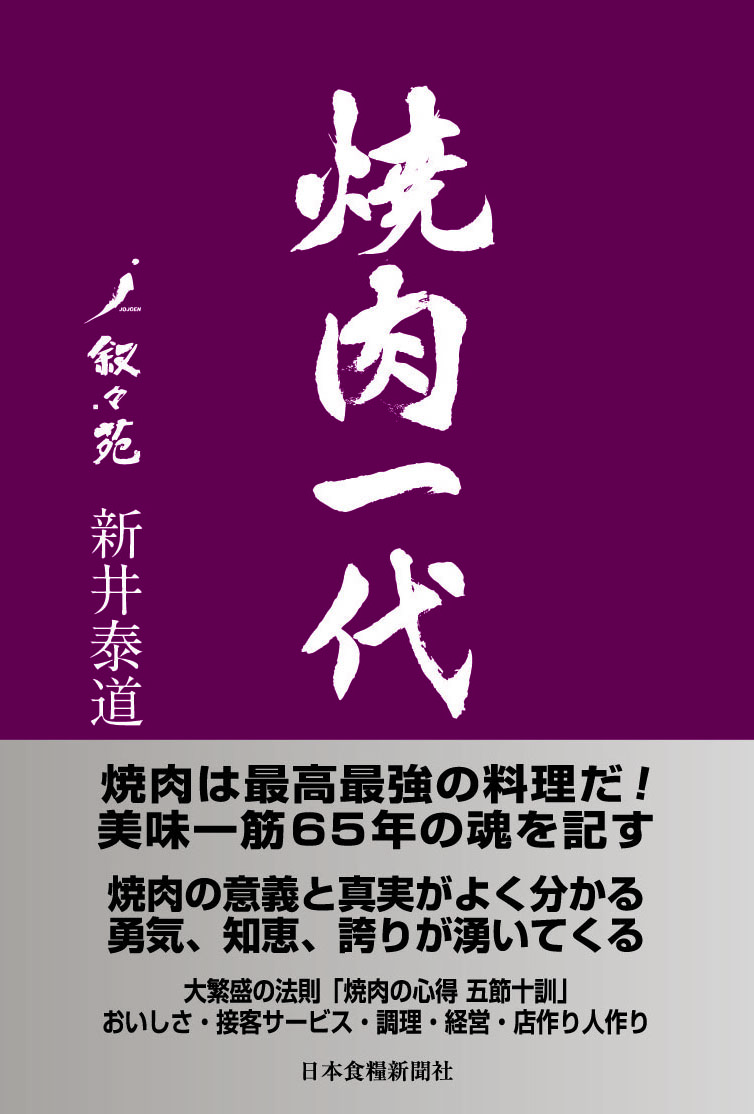そばレストランの事例研究 「満留賀」 結束強め独自のそば畑計画
都内の街中をはじめ埼玉、千葉、神奈川など関東近県でよく見かけるそば屋で、「のれん分」で約二八〇軒がこの屋号を名乗っている。創業は明治33年にさかのぼるが、「満留賀」としてののれんを組織的に一元化したのは大正5年、店舗が二〇店になってからのことで、すでに八〇年近くの歴史になる。
当時の本店格の店は四谷にあったが、現在も満留賀の総本店としての伝統を守り、グループの中心的役割を果している。しかし、中心的役割といっても親睦的な範囲にとどまっており、チェーン店のような求心的、あるいは、スケールメリットを追求したシステム的な機能を果しているわけではない。したがって、共同仕入れ、共同デリバリー、組織的な販促活動といったものはない。あくまでも同一屋号を掲げる親睦グループ的な存在なのである。
実は、満留賀の「のれん」は「満留賀会麺業協同組合」(理事長成瀬光男氏)で組織化しているのであるが、同組合は会の窓口的存在であり前述したようにチェーンシステムにみるような本部機能を果しているわけではない。
二八〇店舗の同一屋号の店があっても、店の運営はそれぞれが自由におこなっているということである。これがFCやVCなどのチェーンシステムであれば、共同仕入れや共同催事(販促)プランなどで、原価率を引き下げるほか、消費者により強くアピールするなど競争力をもつのであるが、ただののれん分グループであれば、力の発揮のしようがない。
いま、老舗のそば屋は大きな転換期にきているといわれている。一つにはそば職人の高齢化と若年層の求人不足、もう一つは店舗運営のマンネリ化と世代交代による技術の低下である。
このままでは厳しい競争社会に生き残れなくなる。老舗にあぐらをかいていては、消費者にもやがて飽きられることになる。時代の流れ、消費者ニーズを十分に把握して、新しいものを取り入れ、工夫していかないと、のれんを維持していくことも難しくなる。
前記の満留賀会理事長の成瀬氏は、神田小川町に二店、日本橋に一店、計三店のオーナーであるが、独自の生き方を展開している。
まず三店のメニュー構成については、そば、うどん、ご飯ものの三種目をラインアップし、そばにこだわらない営業方針を打ち出している。
といっても、そばの全体ウエイトは八、九割を占めており、そば屋としての特質は失っていない。
メニューは場所や客層によって多少変えている。小川町にある二店は、靖国通りを挟んで南北に分かれ、南を「そば処」、北を「釜めし・そば処」と称しているが、両店は例のスキーショップ街の真只中に位置しているので、客層はむしろこれら来街者や周辺の店、オフィスに勤めるサラリーマンやOLということになり、メニュー構成も一般的なものになり、そう気取ったものは置いていない。
小川町釜めし、そば処はお茶の水寄りに位置するが、通りから路地を入った形になり、目立たない存在にある。これは小川町そば処も同様の立地条件で、一見の客には即座には見つけにくい。このために、両店ともに固定客六割、フリー客四割のウエイトだという。
極めて結束力のないのれん分グループ(協同組合)であるが、しかし、ここにきてようやく結束力を強めて、スケールメリットを発揮していこうという動きが出てきた。
すなわち、そば粉、米、野菜、魚介類などの食材を共同仕入れしていこうという考えである。もちろん、一挙にというわけにはいかないが、価格的に競争力を維持し、おいしいものを提供していくとなると、グループとしてのバイイング機能をもたせることは急ぐべき課題だという。
「もう、それぞれがバラバラにやる時代ではないということですね。バブルがハジけて景気も悪く、消費者も節約ムードですから、高いものは売れなくなってきています。
現に百貨店なんかでは高価なものは敬遠されていますし、外食では一五〇円コーヒーとか、回転すし、立喰いそばなどが人気を呼んでいます。やはり値段が安いということは大きな武器であるわけです。そのためには、材料コストを引き下げる努力をするとか、経営の効率化を考えるとか、いろいろと改善すべきことは多いと思います」(満留賀会麺業協同組合成瀬光男理事長)。
近い将来の考え方として、満留賀はそば粉を安定確保していくために、グループ専用の畑をもつこと、また産地から直接契約で、質のよい食材を仕入れる計画だという。
とくに主力材料のそば粉については、畑で獲れたそばを製粉メーカーに委託して良質のそば粉を手当てする。同業他社との差別化を推進する意味でも、組合として是非とも具体化したい事業だという(成瀬理事長)。