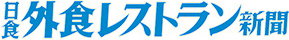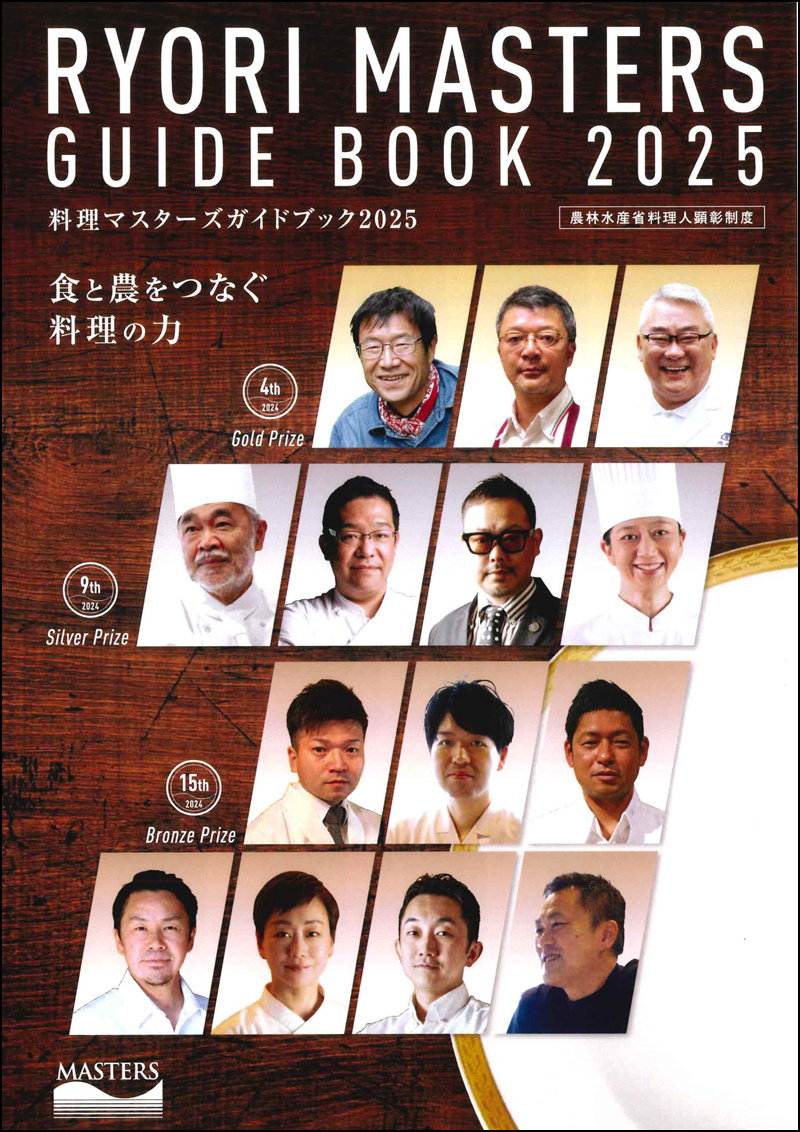シェフと60分:四川料理麻布十番中華楼料理長・鈴木恒行氏
この場所で中華料理店がオープンしてから、オーナーが三人代わった。
「私で三代目。初めはこのビルのオーナーで、次は私の知り合いのシェフがファミリーレストランっぽく中華をやっていたんですが、だめでね。私が始めた時は最悪。一日二〇人くらいしかお客が来ない。今は何とか、ランチで六〇~七〇人来てくれるようになりましたよ。まだ採算ベースにはのっていないんだけど。この辺りは地の利がよくて、ちょっと出れば白金、自由ヶ丘、広尾、新橋、銀座……なかなか難しいです」
「これまでは私のホームグラウンドは五反田で、サラリーマンが相手で、接待なんかに利用されていた店でした。でも、ここへ来ると主婦、女性客が多い。自腹を切って食べてもらうわけです。食べ方を知っている人たち、というか、シビアなんですよ、料理に対して。ちょっとしょっぱいだけでも、帰り際に言われます。商売やっててこんな怖いことはないですね。だから、一年たった今でも緊張の連続です」
ランチの値段は八〇〇~一〇〇〇円。「安すぎないか」と周りから忠告を受けることもあったという。
「あえて、この値段に設定したのは、今の時代、安くておいしいもの以外にはやるわけがないと思っているからです。高くてうまいは当たり前でしょう。安くてうまければ繁盛するに決まっていると考えてます」
宣伝しなかったが、結果として口コミでリピーターを増やしてきた。
子どものころからものを作る仕事に憧れた。勉強は嫌い、おちこぼれだった自分が再スタートを切ったのは、就職第一日だった。
「私は栄養士の専門学校を出ていますが、とにかく勉強することが多くて卒業するのも大変でした。その分調理の学校より知識があるんです。で、厨房では差別されました。先輩の言ったことを一度で、スッとやれる人って、そうはいなかったんですよ、そのころは。(厨房に)入って半年したら、客に出す料理とかも作ってて、手先が器用ということなんでしょうが、周りの人はおもしろくないでしょう。生意気に見えたでしょうね、上からは。でも、私はこの世界では一流になろうと決めてましたから、何を言われても礼儀正しくはしていました。でも、一年半してとうとう堪忍袋の緒が切れて、セコンドに缶詰ぶつけてやめました」
上達が早かったのは、「おいしいものを作れるようになりたい、という気持ちが人よりめちゃくちゃ強かったから」と振り返る。
「先輩の中でも、うまそうに見える皿を華麗につくる人がいます。その人を見て、ああなりたい! と強く思ってやってきました。とにかく早く上達したい、その一心でした」
そのすばらしい皿をつくる先輩の多くが四川料理だったため、自らの中華も四川料理に決め、その道を進んできた。
二七歳で五反田の東京酒樓のチーフに就き、三六歳で独立。早い出世は時折、「経験」という言葉に敏感になることがある。それは料理に対してだけでなく、新人教育の面でもしかり。
「一番のプレッシャーは新しい料理ができないとか、そんなことじゃなくて、私の所で修業した人間がここを辞めても無事に食っていけるようになるか、それに尽きます。経験のない私の下で働くんだから、かわいそうだと思いますよ。だから、私の知っている、これ、と思うことはすべて教えたいです」
「新人には厳しいですよ、めちゃめちゃ。できなかったら、お玉でなぐりました。病気をしても『とにかく店に来い』と言いました。『倒れるまでやって初めて限界なんだから、倒れるまでやれ』と。だって、自分がチーフになってから休んでいたんじゃどうにもなりませんから。厨房でも、一番大切にされる奴っていうのは、できる奴じゃなくて、いつもいる奴なんです。そう考えると厳しくせざるを得ないです」
ずっと面倒を見られる自分の子どもより、自分の下で働く子の将来の方が心配でさえある。そんなプレッシャーもあり「新人はとりたくない」と思うこともしばしばある。
よく「完全主義者だ」と人に言われる。しかしそれは「もっと上がある、もっとおいしいものが作れる」と思っているだけ。
「よい料理を作るっていうのが、どういうことか。コックって、自己満足の料理がたくさんあるんですよね。でも、それが必ずしもお客にとってよいとは限らないんです。自分のプライドとか、お客さんに食べさせる愛情とか、人に食べさせる喜びを感じながら、そのものに集中して料理をつくる。そうまでしてお客さんがおいしくないというなら、これはもう仕方のないことで、どうすることもできません」
「でも、これができていないとき、お客さんに何か文句を言われたらきっと、これはコックとして許せないでしょうね。情熱がなくなったら料理人なんてやってらんないですよ」
自分を奮い立たせるよう、力強く語った。
◆プロフィル
昭和30年生まれの四三歳。栄養士の専門学校を卒業して、池袋の地球飯店に入る。その後、新宿・東京大飯店を経て、五反田の東京酒樓に入店。二三歳の時、前菜を作らせると日本で三本指に入るといわれる鈴木潔氏に就き、最後の弟子を言われる。二五歳で再び東京酒樓に戻り、二七歳でチーフに。七年前ビルの建て替えを機に、看板を受け継いだ。昨年二店舗目として、麻布十番に店を構える。早い出世のため、チーフになってからその人の才能より、経験に怖さを感じることもあったという。
料理に自分のプライドを込めたり、手を抜かない気持ちが、最後には自分に帰ってくる。客においしく食べてもらうための努力は惜しまないと、常に情熱をもって仕事をする。
文 石原尚美
カメラ 岡安秀一