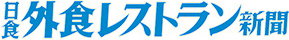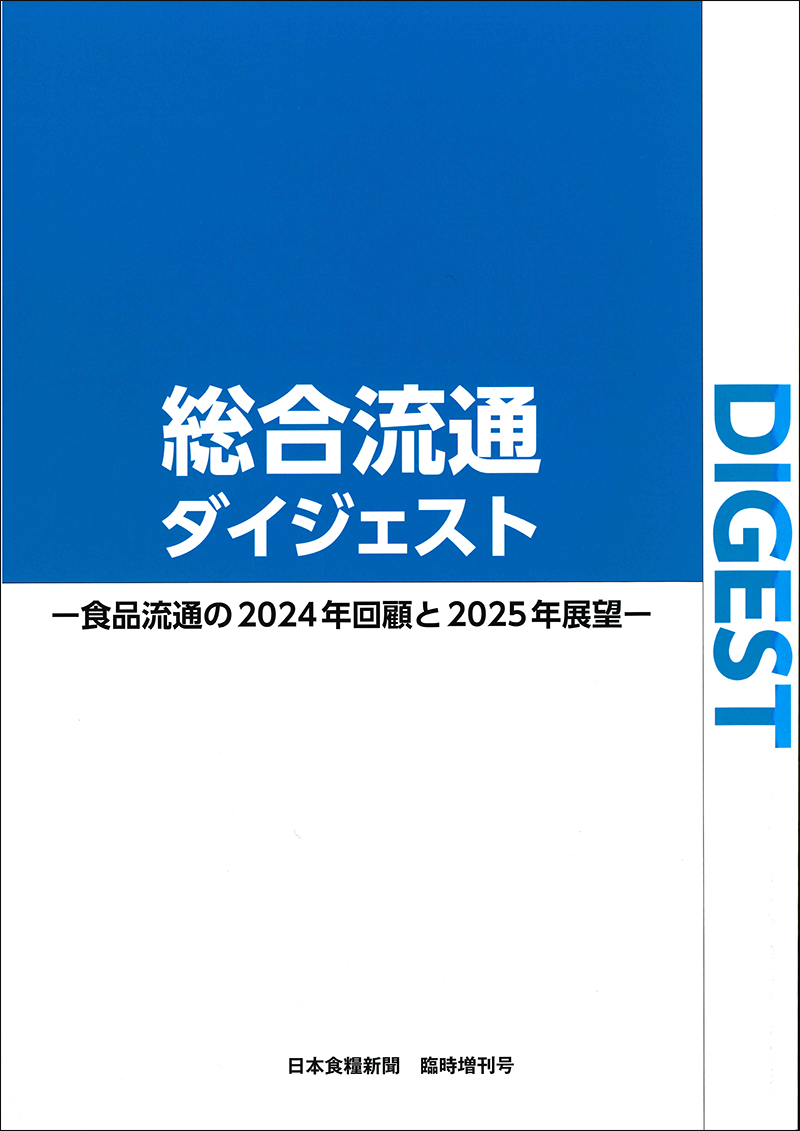シェフと60分 パレスホテル総料理長・山下敏宏氏 仏・古典料理を守る
「料理長になろうという野心はなかった。病気もせず健康に恵まれたので今日まで働かせてもらったのだろう。それに、田中徳三郎さんの下でずっと働いてこられたのが一番幸せだった」。
温厚な表情でさらりと語る。
田中徳三郎さんは山下さんが生まれた翌年の昭和3年に日本人として初めて渡仏して、本場のフランス料理を勉強したフランス料理界の巨匠
その巨匠のもとで料理の基本を身につけた。今でも、その基本は崩さない。新派料理に若いコックが目を向けても、ソースはデミグラスにこだわり続けている。
「いま、ソースはフォンドボーを使って軽い味に仕上げる傾向が強くなっているけれど、私は昔ながらの料理を作り続けている。古典的料理の信奉者かもしれない」と笑うが、気負いはない。
「“料理はおいしくなければいけない。しかし、しつこい味ではいけない”と田中さんに教えられた」という。
白雲楼ホテルに勤めていた二一歳の時、田中さんにひどくしかられたことがある。
「グリンピースをゆでるように指示されて、材料の缶詰入りのグリンピースを探したけれど在庫がなく、仕方なしに冷凍ものを使ってしまった。そしたら、これじゃだめだ、とストーブの前に立たされてしかられた」。山下さんがソシエの時代、燃えるストーブの前に立たされて脂汗を流した。「同じことを二度聞くとしかられたから、一生懸命メモをとった」。
《なべを洗いながら、 ソースの味を覚えた》 山下さんは盗んで覚えた世代。ナベを洗いながらソースをなめた。しかし、今はナベは機械が洗う。「職人気質の人が少なくなった。帝国ホテルの村上さんは料理の本に“田中さんが最後の職人”と書いている。今の若い人は、しかると辞めてしまう」と嘆く。「時代が違うから仕方がないのかもしれない。スピードの時代だから悠長に構えていられないのだろう。だから、早くいろいろなことを教えた方がよいようだ」という。
《恩師の墓参を欠 かさない篤実家》 昭和52年に田中さんが他界、今年で一七回忌を迎えるが、この間、毎年、山下さんは夫人とともに田中さんの墓参を欠かさない。名料理人であるとともに篤実家である。
「最近テレビなどで、“こだわりの料理人”がよく登場、お客さんがしかられながら食べているのをよく見るけれども、本来、料理人はお客さんに喜んでもらうように心掛けなければならないはず。威張って料理を提供するのはどうかと思う」と“世相”をチクリ。
山下さんはお客さんの料理のリクエストにできるだけこたえようと努力を惜しまない。「近く、あるパーティーの宴会料理にすいとんとぞうすいのメニューを要望された。めったにないリクエストだけれども、何とか要望にこたえられるよう、今、その材料選びに頭を使っている」。プロの料理人気質を残している。
《プロフィル》
昭和2年、石川県出身。旧制県立金沢二中を卒業後、一八歳の時に白雲楼ホテルに入社。そこで田中徳三郎さんに出会う。その後、昭和25年に東京会館に入社し、36年、パレスホテルの開館にともない、田中さんとともに入社。52年に調理部次長、57年に調理部長と歩み、60年、取締役調理部長、平成3年、常務取締役に就任する。現在、パレスホテルの料理人三五〇人を抱えるムッシュ・グラン ドシェフ。
文 ・富田 怜次
写真・新田みのる