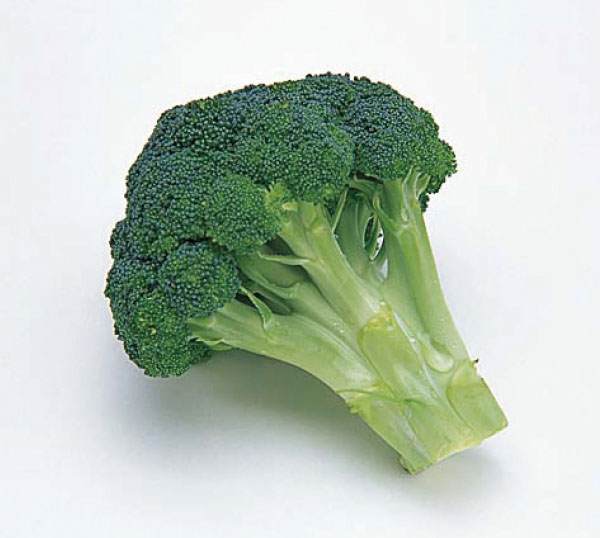中医ダイエット実践編(その2)湿熱太りタイプ 湿しんも実は体質が原因
「湿熱」とは、食生活の乱れなどによって余分な水分「湿」の邪気が身体に溜まって、熱を持つようになった状態。身体がほてったり、顔が赤くなりやすい。基本的にはエネルギーにあふれていて疲れ知らず、興奮しやすい人が多い。必要以上に食欲を感じ、満腹感
を得られにくい。
●来局のキッカケ
来局のキッカケは皮膚疾患から。皮膚科でアレルギーによる皮膚炎と診断され薬を服用していました。同時に最近太りだし、疲れやすく、皮膚もブヨブヨしている感じがする。中性脂肪もやや高い。一カ月の服薬中は皮膚症状が収まったものの、中止後再び発症し、半年間の継続服薬を指示されたとのことでした。
●症状
まず、ご本人に自覚症状を伺いました。
「両大腿部と前腕内側に三カ月前から指の頭くらいの大きさの淡紅色の同心円ができた。隆起して大きくなり、環状の紅斑になってしまった。かゆみもある。最初は入浴後だけだったのが、一日中出るようになった。以前にも季節の変わり目によく同じ症状が出た。今回はまた、下アゴから首、胸、背に前からあった紅くてウミをともなうコメ粒大の丘疹が悪化し、数が増えた。イライラするとかゆみが増す。皮膚症状以外には一日中、特に食後眠い。また刺身や肉、冷たいものを食べると下痢を起こすが、腹痛はなく排便後はサッパリする。便臭がやや強い。ベトっとした寝汗をかく。下肢が冷えている。夜間頻尿」ということでした。
舌を診せていただくと、薄くて紫紅色、苔は薄く歯型がついていました。
●診断
「脾虚痰湿、湿熱」(胃腸が弱く、余分な水分が溜まり熱がこもっている状態)であると判断しました。湿熱の人は熱のため冷たいものを好む傾向があるのですが、そうすると胃腸を冷やし消化機能を低下させてしまうのです。この方は、小さいころから冷たいもの、生ものを食べると必ずトイレに何回も行っていた。これが自分の体質と思いこんでいたため、大人になるまでこの悪循環を繰り返し、湿熱の状況を作っていたわけです。生活習慣から本来自分の体質にはない症状を作ってしまい、皮膚症状を出す結果になってしまったんですね。
状況を改善するには、「脾(消化器系統)の働きを助け、水分代謝を良くする」こと。食事指導としては、原則として生もの、冷たいものは控え、紅斑もあるので刺激物(唐辛子・キムチ・カレー・アルコール)は中止してもらいました。それから健脾利湿、つまり胃腸の働きを良くし水分代謝を改善する「勝湿顆粒」と、清熱利湿、つまり過剰な熱を冷まし水分代謝を改善する「瀉火利湿顆粒」の二つの漢方薬をそれぞれ二分の一包、食後に消化を助けるオリエンタルハーブティーの「晶三仙」一包を、すべて一日三回ずつ。本人の希望で脂肪を燃やす「三爽茶」を一日二包適宜服用としました。
オリエンタルハーブティーをとる習慣が気に入られたようなので、二週間後からはさらに清熱解毒する「板藍茶」を夕飯前に一日一回一包、清熱利湿する「五行草茶」を朝夕一日二回一包加えました。
病院の薬は中止していましたが、四カ月後、かゆみが出ることもなく、下アゴ、胸、背の丘疹もとれてきました。七カ月後にはすべての症状がとれ、気にしていた体重も四キロ減少、体脂肪・中性脂肪値も正常値となりました。皮膚の症状が好転し始めたころから、来局されるたびにアゴのラインがハッキリして小顔が強調され、高いウエスト位置がしまり、メリハリのあるきれいな身体の線が出来上がってきました。
【実例】
女性・35歳 身長154.0センチメートル
*体重と体脂肪率の推移
体重(キログラム) 体脂肪率(%) 除脂肪率(%)
来局時 53.0 34.0 ‐
7カ月後 49.0 24.2 37.1
14カ月後 49.0 22.4 38.0
◆食医・安川哲二の秘密のレシピ
湿熱太りタイプに効くメニュー「緑豆・ハトムギ・冬瓜入りスープ」
緑豆・小豆・ハトムギは水分代謝を良くする。スイカ・ニガウリなどウリ科の野菜も同じ効果があるので、手に入る季節には活用したい。
<材料・1人分>
・緑豆………………60グラム
・ハトムギ…………60グラム
・冬瓜……………100グラム
・コメ………………60グラム
・貝柱………………3個
・塩…………………適量
<作り方>
(1)冬瓜はサイの目切りにして、ボイルする。
(2)緑豆・ハトムギ・貝柱・コメ・水(分量外)を入れ、弱火でお粥を作り、塩・冬瓜も入れる。