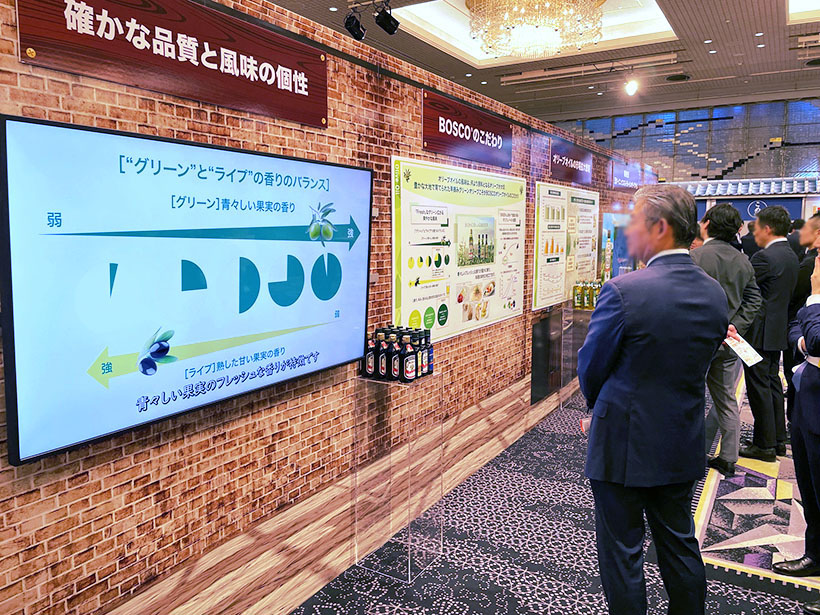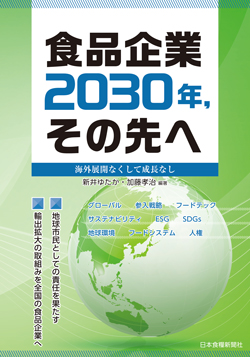忘れられぬ味(19)吉原製油・神田良樹社長「忘れてしまったイワシの味」
親しい友人にいわせると私は“味音痴”だそうである。「お前にはどこで何を食わしてやっても“うまい、うまい”としかいわず、一切れも残さず食ってしまう。あいそのない奴だ。そういう奴を“味音痴”というのだ」とその友人の言い分である。
実際私は好き嫌いがほとんどなく、何でも食べる。その上“育ち”が悪いせいか、終戦前後の極端に物のなかった時代に、育ち盛り食べ盛りの年頃を過ごしたせいか、いまだに何を食べてもおいしい。一流のレストランや格式高い料亭の料理はもちろんおいしい。ロードサイドのチェーン店のラーメンやギョウザもおいしい。女房の作る手料理もまたおいしい。最近のテークアウトのお惣菜などもおいしい。ただし、どちらがおいしいかと聞かれてもどちらもおいしいとしかいいようがない。こういう私に対して先ほどの友人は皮肉とやや羨望を交えて「お前は幸せな奴だなあ」と食事をするたびに言う。
「忘れられぬ味」とは“飛びぬけておいしかった”とか“他では味わえないおいしさ”をいうのだろうが、それは味わい分ける味覚を持っている人にできることであって、私のような何を食べても同じようにおいしい“味音痴”には「忘れられぬ味」の記憶がないというのが本当のところである。
私の生まれ育ったのは大阪湾沿岸の高師浜。今でこそ埋め立てられ工業地帯になってしまっているが私の小学生の頃は白浜の続く海岸で、漁師の家の友達も何人かおり、地引網でいろんな魚が獲れた。朝早く浜に行き網を引くのを手伝うと山のようにイワシが引き揚げられ大きなひしゃくですくって私のバケツにどさっと入れてくれる。
その場で周りの大人にならって頭をちぎり爪の先でしごいて背骨をはずし海水で洗って食べた。何となく子供ながら充実感、満足感に満たされたことは覚えている。懐かしい味、もう一度味わってみたい味、しかしそれがどんな味だったか正確には思い出せない。
それを思い出したくてその後もイワシの活造りを何回か食べているがどうもあの時のイワシの味とは違うように思えてならない。もうあの味は一生味わえないのかと思うと少し寂しい気がするが、想い出とはそういうものかもしれない。それでも活けのイワシを見ると「それを刺身で…」はこれからもやめないだろう。
(吉原製油(株)取締役社長)

日本食糧新聞の第8665号(2000年3月24日付)の紙面
※法人用電子版ユーザーは1943年以降の新聞を紙面形式でご覧いただけます。
紙面ビューアー – ご利用ガイド「日本食糧新聞電子版」