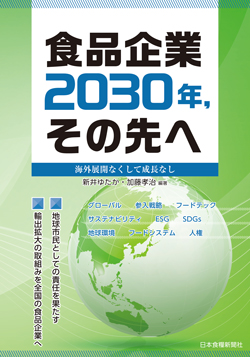忘れられぬ味(42)奥本製粉・奥本晋介社長「伊勢のブリ」
私は大阪市内に生まれたが、父は三重県の海辺の村の出身であった。今から五〇年も六〇年も前のことだが、父につれられて、家族みんなでその村に行く事は何よりの楽しみであった。
バスで宇治山田から宮川に沿って遡り、途中で宮川と別れて山を幾つか越え、最後に能見坂という峠のトンネルを抜けると、突然眼下に、太平洋に連なる輝く様な湾が現れる。その湾に沿った小さな村が父の故郷であった。村の前の浜には、広々とした砂浜があり、海は静かであった。お宮さんの前の砂浜の入り口に大きな一本松があって日影を作り、その下で、体の大きな老漁夫がいつも網を繕っていた。
私達が村へ着くと、祖父がポンプを押すと冷たい水が溢れ出る井戸端で、一m近いブリを捌いて刺身を造り、大きなお皿に山盛りにして、食卓に出してくれた。祖父は左利きの大変器用な人で、村では「あの人が魚を捌くと血がほとんど出ない」といわれるくらい上手な捌き手であったので、タマリといわれる濃い口の醤油をつけて食べたそのブリの味は、格別であった。
祖母は、俎板の上に小アジを乗せ、大きな包丁で、根気よくコトコトコトとアジを叩いて、身を骨も砕いた後に団子を作り、それを入れて澄まし汁を作ってくれた。その澄まし汁とアジの団子も、また忘れられぬ味である。
近所に住んでいた、祖母の妹にあたる人が、父が村に帰ると聞くと、必ず小豆の餡と黄名粉のおはぎを作り、お盆に山盛にして、持ってきてくれた。甘いものの少ないその当時のおはぎは、めったにない御馳走で、今でも二色のおはぎが目に浮かぶ。
もう一つの忘れられない味は、終戦後間もない頃のアメリカ進駐軍の真っ白な食パンの味である。私が小学校の五、六年の頃であった。ある午後、父が真っ白い食パンを一斤持って帰って来た。進駐軍のパンを人から貰ったということで、さっそく母が分けてみんなで食べた。真っ白いパンに、貴重品の砂糖をつけ、牛乳に浸して食べたが、こんなおいしいものをアメリカ人が食べているのかと思った。それから約五五年、私達の会社も、小麦粉とミックス類でパンの製造につながっている。
(奥本製粉(株)社長)

日本食糧新聞の第8800号(2001年1月31日付)の紙面
※法人用電子版ユーザーは1943年以降の新聞を紙面形式でご覧いただけます。
紙面ビューアー – ご利用ガイド「日本食糧新聞電子版」