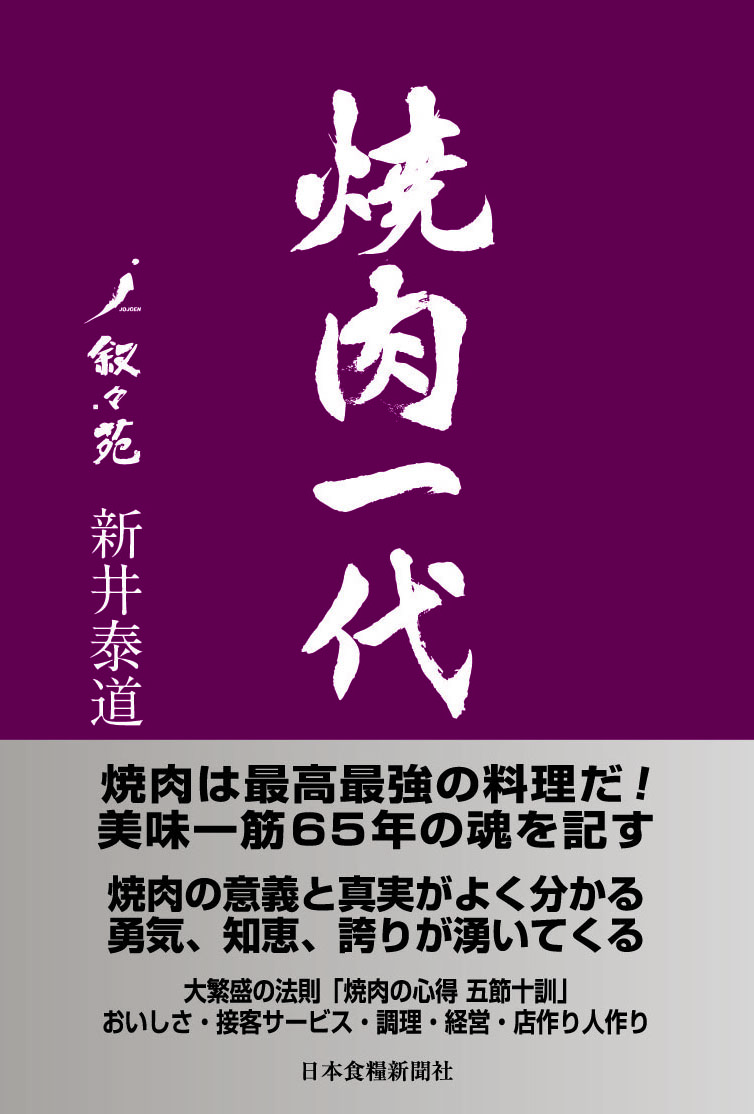忘れられぬ味(63)石光商事・石光輝男代表取締役会長「シュラスコ」
初めてブラジルを訪れたのは一九六一年の事であった。当時はブラジルだけでも世界のコーヒー消費の約一年分といわれる六〇〇〇万袋の在庫を抱え、世界のコーヒー相場を圧迫していて国内各地の倉庫も満杯であった。
マーケットに対するジェスチャーでもあったろうが、毎日一万袋のコーヒーを焼却、五〇万袋になるまで続けるという。事実、筆者はパラナ州ロンドリーナの近郊で、軍隊が倉庫からトラックに満載して運び出し原野に積み上げて焼却している現場を目撃し、八ミリメートルムービーカメラのシャッターを押し続けたものである。当時の日本の年間消費約三〇万袋弱であったから、これは筆者にとって想像を絶する出来事であった。
生産調整と価格維持のために国際コーヒー機構(ICO)が設立され、国際コーヒー協定が締結されたのは、その翌年の一九六二年であった。
その後何度ブラジルに行った事か。年齢も若かったせいか、行く度にこの国の大らかさ、こだわりのなさ、野性味たっぷりさ、無限の将来性(と当時は思った)に魅せられていった。そういう雰囲気にピッタリなのが「シュラスコ」である。
シュラスコを食べさせる店を“シュラスカリヤ”というが、要するに焼き肉屋であり、国内各地に数多くある。ただし、焼き肉といっても日本式、韓国式のものではない。牛、豚、羊の各部位ごとに直径一〇センチメートルのカタマリに切り分け、表面を岩塩で十分に揉み、長さ八〇センチメートルほどの剣のような串にそのいくつかを刺して焼き上げ、それをウエーターが切り分けるナイフを持って客席の間を回り、客が「もう結構」というまでサービスを続けるものだ。筆者は各部位の中でもコブ牛の瘤の部分“クッピン”と称するが、口の中に入れると油がジックリと滲み出てくるところに、えもいわれぬ美味を感じる。
それによく合う飲み物が“カイピリーニャ”という代物、砂糖きびから醸った無色透明の度の強いピンガという酒を水で割ってブラジル特有の青いレモンを搾ったもの‐‐これを屋内ではなくて、ひと仕事終えた夕暮れの広大なコーヒー園の片隅にしつらえた煉瓦の爐を囲んで、片手に肉、片手にカイピリーニャで大勢の仲間と歓談する時、人生の至福を実感するのである。
(石光商事(株)代表取締役会長)

日本食糧新聞の第8884号(2001年8月17日付)の紙面
※法人用電子版ユーザーは1943年以降の新聞を紙面形式でご覧いただけます。