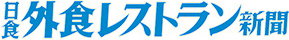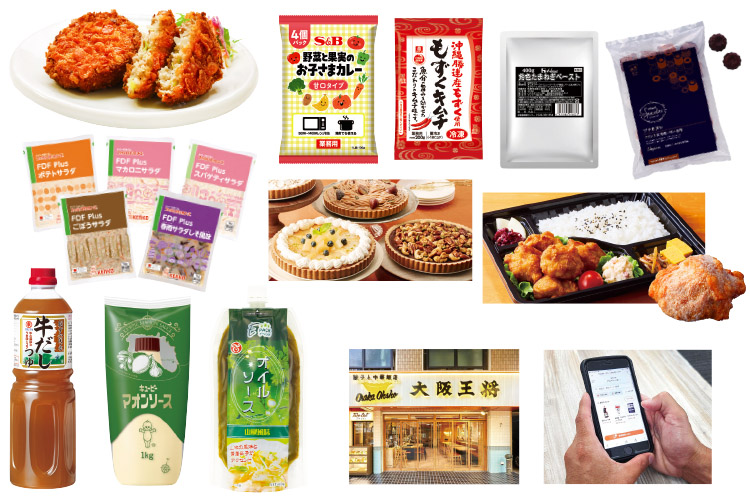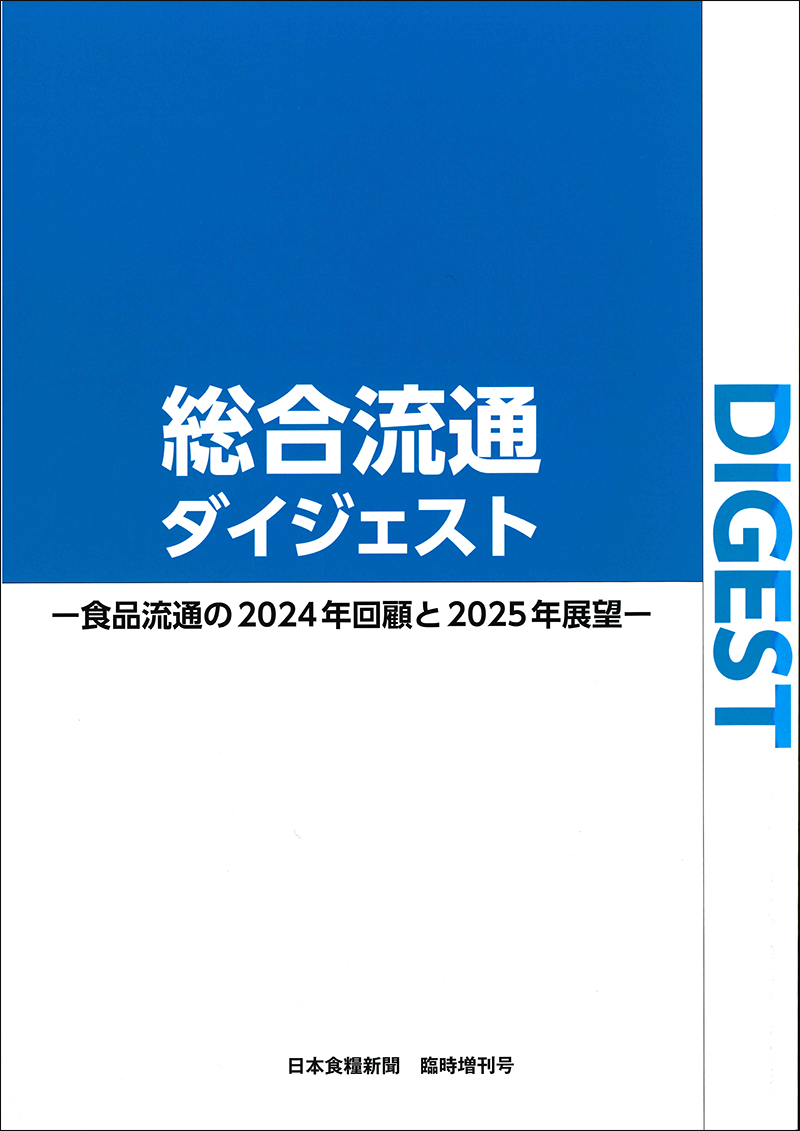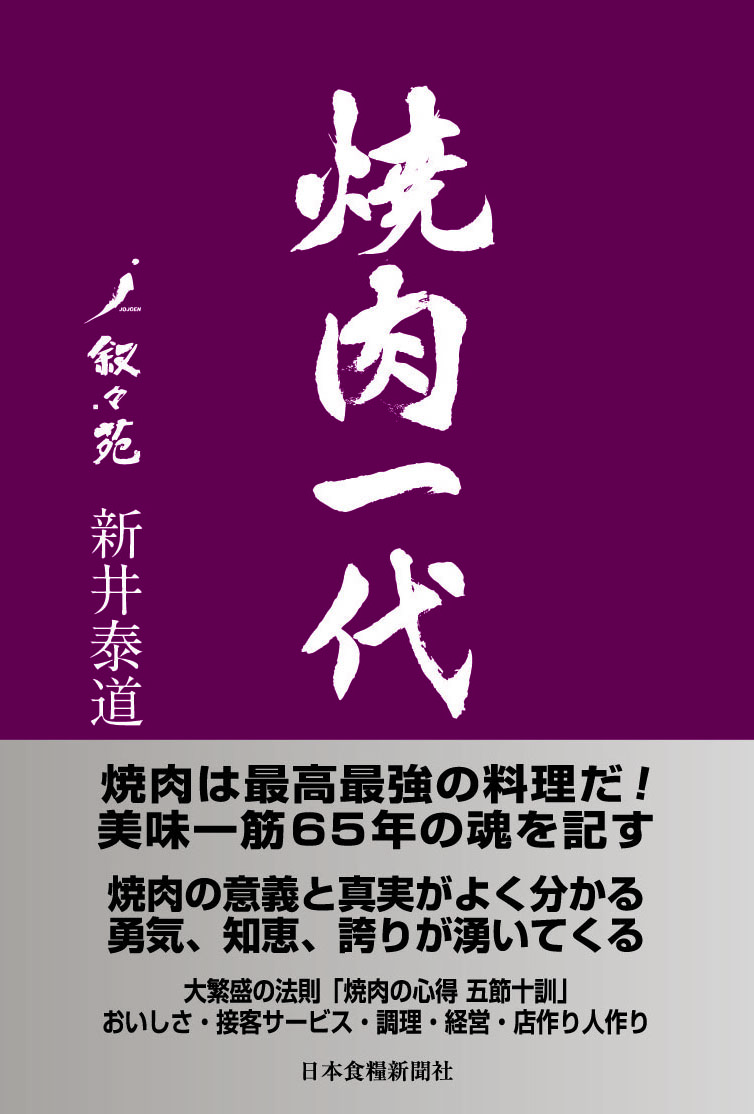カレーの昭和史 学校給食が戦後カレーを救う
家庭から集団給食やレストランまで、幅広く支持されているカレー。素人から玄人まで作って楽しく、食べて楽しいのもカレー。そんなカレーがどのようにして定着してきたのか、その歴史を日本食糧新聞社発行の「昭和の食品産業史」からカレーメーカーの動向を中心にかいつまんでみた。
カレー粉が日本に入ってきた時期は、ソースと同じ明治の文明開化期というのが定説。イギリスのリー&ペリン社のウスターソースと、クロス&ブラックウェル社のC&Bカレー粉がその代表である。
それ以後、西洋料理店の出現とともにライスカレーはコロッケ、ロールキャベツなどとともに急速に普及していった。
明治中期ごろになり、国内でも洋風調味料に目が向けられ、薬商筋でソース、カレー粉の企業化に取り組む人々が現れた。しかし、カレー粉は輸入品のC&Bカレー粉が国内市場を席巻、実需筋のホテル、西洋料理店などのコックたちのかたくななまでの舶来崇拝の風潮と、「東洋の神秘的な味」とだけしか定義されていないカレー粉に手を付ける術はなかったという。
それでも、輸入品のカレー粉に唐辛子、陳皮(ミカンの皮)などを増量剤として混ぜ合わせたものが、徐々に散見されるようになった。
大正12年、日賀志屋(現エスビー食品)はカレー粉の分析製造方法の研究の結果、「カレー粉には熟成が必要なこと」を見出し、念願の国産カレー粉第一号を生み出した。
そして、カレー粉製造工程の一つである焙煎釜の工夫に取り組み、焙煎機を二重構造にして焙煎中に全く香気を失わず前後左右上下に回転しつつ、均一に焙煎され、カレー粉独自の豊かな色調が得られた。
ついでこれを茶びつに入れて熟成し、高品質カレー粉を完成させた。この完成を待って、それまでの業務用に加えて一般にもカレー粉が普及し始めた。
昭和6年には浦上靖介商店がカレー粉をもっと手軽にということから、メリケン粉、グルタミン酸ソーダ、バター、ミルクなどを加えた現在の即席カレーの原型ともいうべき「ハウス即席カレー」を作り出すことに成功した。
当時はカレー粉の純カレー、それを原料にした即席タイプのカレーと、その間の「南蛮カレー粉」、あるいは「軽便カレー粉」といわれた味付けされていない即席カレーがあり、その需要はもっぱらきそば、うどん用に集中していた。
戦時下、スパイスなど本場インドから原料が途絶える中、かろうじて台湾、フィリピンものでまかなうというひっ迫状態であった。また、英語の使用は敵性語だとして使用中止となり、エスビーカレーは「ひどりカレー」、ナイトカレーは「楠公カレー」という具合に改められた。
カレー粉は国民食というよりも軍の糧抹廠への納入が主流になっていた。イギリス流の海軍は、カレーライスそのままの呼び名であったが、ドイツ流の陸軍ではカレーライスを「辛味入汁掛飯」と呼び、コロッケを「油揚肉饅頭」と呼び名を変えるなど、徹底していたようだ。
昭和20年ごろになると、もはやカレー製造どころではなく、原料の入手は困難を究め、工場は空襲によって消失するなど絶望的状況となった。戦後、製品化に際しては、戦前には目もくれなかった野草を粉末化して混入したりしてしのいだ。
こうした中、21年のガリオア資金による学校給食へのカレー製品供給にカレー業界は積極的に応援、カレー業界の再結集というチャンスに恵まれた。ようやく企業的存続にめどがついたものの、カレーの生命ともいえるターメリック、ナツメッグなどのスパイス原料の不足から、粗悪品のそしりは致し方なかった。
30年代にはいると、カレー調理缶詰が各メーカーからデビュー、カレーの新商品開発には勢いがあり、それとともに消費はうなぎ上りに伸びた。戦時中に輸入をたたれた純カレーのC&Bカレーは36年、ネッスル社(現ネスレ)に吸収された。
40年代にはレトルトカレーが登場する。50年代は安定成長路線で推移して、メーカー間の新製品ラッシュが続く。
このような業界の過渡期を経てカレー業界は、企業間格差による家庭用、業務用ブランドの明確化、製品も純カレー、即席カレー、レトルトカレー、缶詰カレーといったバラエティー化が図られ、それぞれの分野で企業特色を打ち出している。