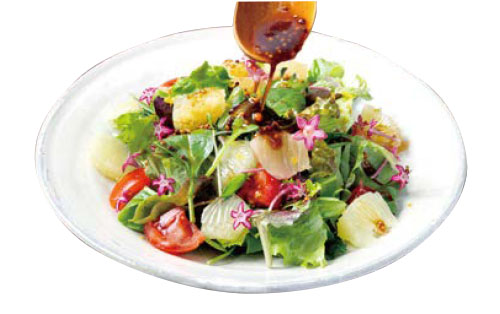外食コンサルタントに聞く’98外食・飲食業の動向 桑原才介氏
(1)-(1)今後のチェーンストア、明暗を分けるポイントは?
(1)-(2)その理由は?
(2)-(1)今後の単独生業店、明暗を分けるポイントは?
(2)-(2)その理由は?
(3)-(1)今後の有望コンセプトは何か?
(3)-(2)その理由は?
お客が自分の店に何を求めているか。知っているようで意外に知らないものだ。多くの場合、ズレが生じている。今まで持ち味だったと思っていたモノやコトの価値が低減してしまったことに気がつかない。そこを発見することから始めなくてはならない。間違ってもディスカウントでもって問題を糊塗してはならない。
持ち味の価値をもう一度再構築していかなければならない。単独生業店では経営者自らが客に接し、客の好みをその場で生産することができるわけだから、価値をしっかりしたものにつくりあげることは比較的容易なはずだ。お客の感動した姿をもう一度追い続けていけば、新しい持ち味は必ずできる。
楽しみを身近なところに求めていく閉塞状態の時代には、消費者は相変わらず味に敏感になる。「チェーン店はうまくない」という“常識”をどこかで打ち破っていかなければならない。
料理の味、という点ではもともと生業店にはかなわない。求められるのは味のある料理だ。味でも価格でも工夫に工夫を重ねた料理、知恵を使った料理が必要なのだ。
人も同じこと。ステロタイプ化したサービスしかできない人も嫌われてしまっているが、消費者は一流レストランのギャルソンのような厚みのあるサービスを求めているわけでもない。
きびきびした動きの中にも心がしっかりつきそい、味のあるサービスのできる味のある人づくりが今求められている。
生活の個人化は今後も続いていく。個食化は弧食につながっていく。そうなると人間性がどんどんそぎ落とされていく。しかし、反動は必ず起こる。人間性を回復しようという欲求は、一方では強烈になっていく。
何らかの契機でバラバラになった家族は再結集しようとする。その最適の場所が食事処だ。共食しながら人間と人間との関係をしっかり取り結ぼうとする。その共食をフランスではコンヴィヴィアリテというが、それは快適に過ごすという意味につながる。
このキーワードをお店のコンセプトにできるかどうか。それは経営者のマーケティングセンスにかかっている。
桑原才介氏((株)桑原経営研究所代表取締役)昭和15年、東京都出身。早稲田大学文学部中退。数多くのホテル、レストランで修業後、コンサルタントとして独立。飲食店の開業プロデュース、商業施設の開発とトータルマネジメント、地域飲食ゾーンの開発など、商業エリアのプロデューサーとして活躍している。