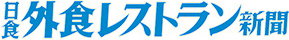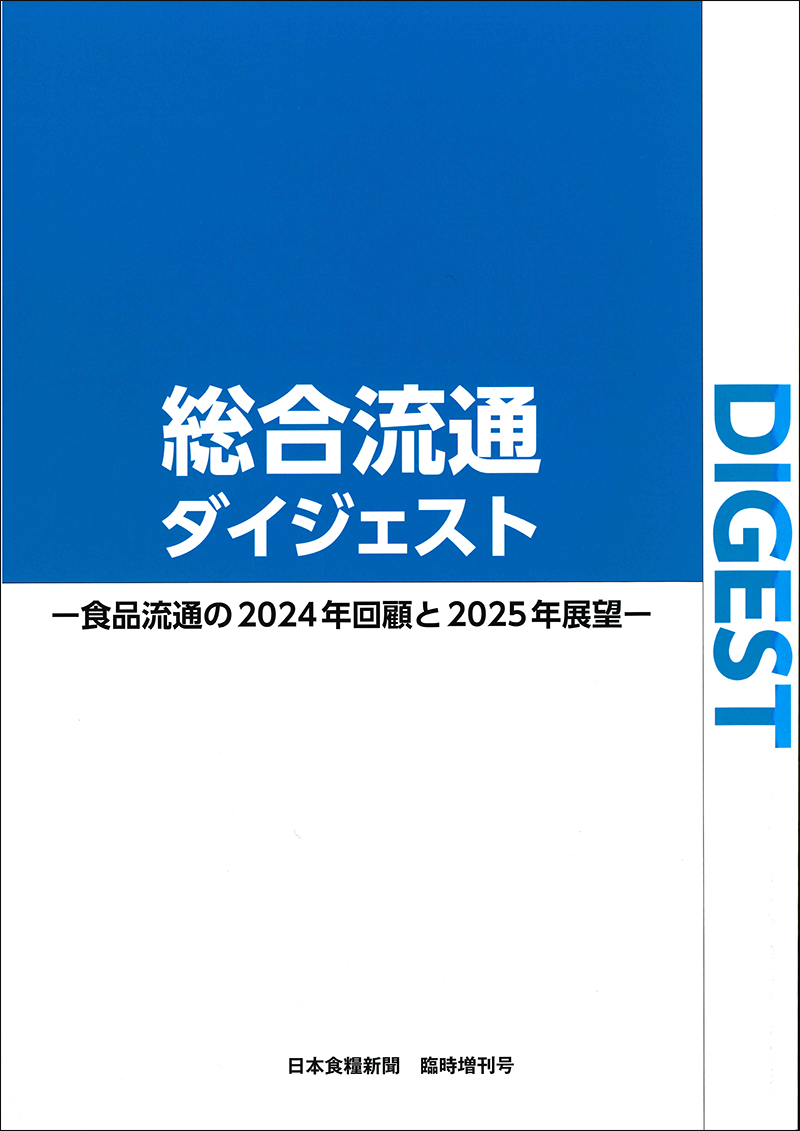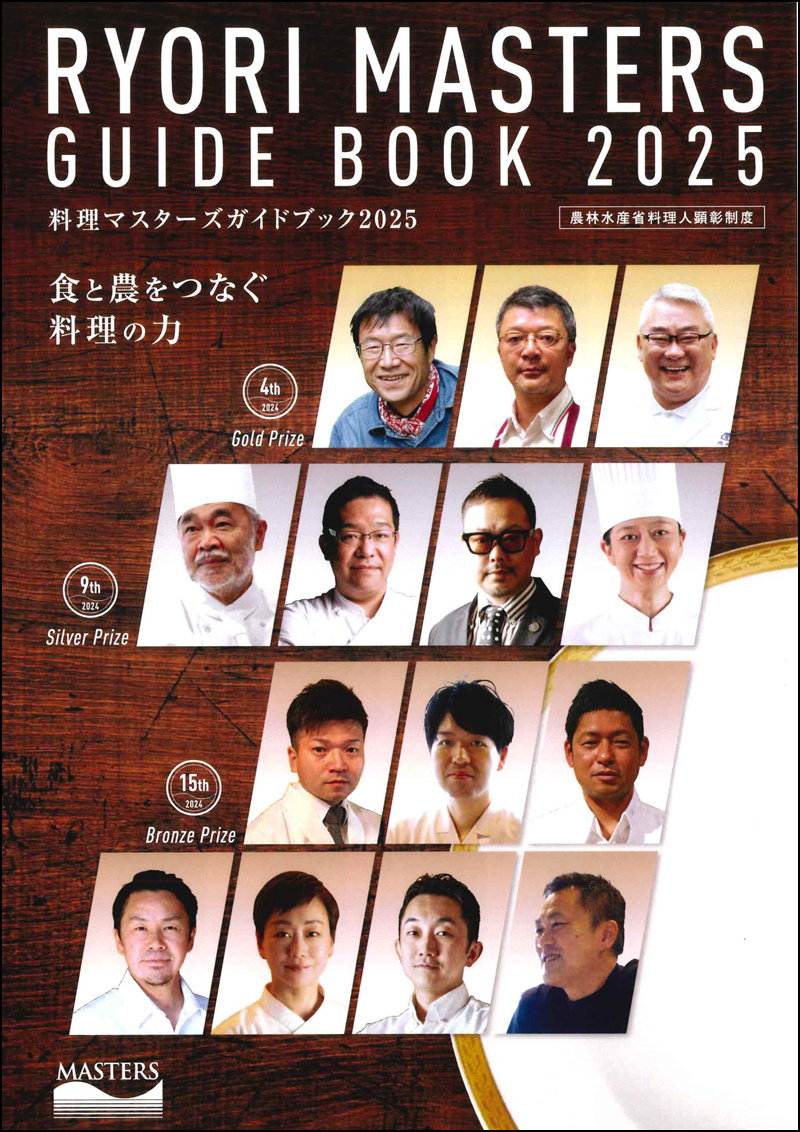シェフと60分:レストランW・市川知志総料理長
ゴージャスな雰囲気の中、適正価格でおいしいものを食べたいというお客は必ずいる。このニーズは近い将来大きなうねりとなることを予想、「あえて世の動きに逆らい、レストランWをオープンさせた」。
一時期、フランスでは三つ星レストランが閉店という暗たんたる時期があった。同時にお金を掛けない店づくり、料理は三つ星と同じ、料金は安い店が主流となり、ビストロブームが起こった。今まで三つ星で食事をしていたお客もドッとそちらに走ったが、最近では、もとに戻り始めているという。
「日本はフランスの二~三年後を追っています。今は苦しくても潜在欲求をいち早く体現させてあげたい」。これが店に掛ける思いの最大エネルギー源のようだ。
一握りに近い客のニーズ。これに応えるための市川流フランス料理はどう展開されているのだろうか。
フランスでも消えつつあるお客の目の前での切り分けサービスを行う。より軽いものがもてはやされ、皿の上のアートがうたわれたヌーベルキュイジーヌ。不可解な料理を食べ、疲れたお客には昔からのホッとするもの、知っているものがいいのではとの考えが根底にあるからだ。
「これがなくてはフランス料理が作れないというフォンドボーやヒューメドポアソンをとれる料理人も少なくなった。振り子もあるところまで行けば必ずもとに戻るんです」
また、かつてきら星のごとくあったシャンパンバー。ワインブーム到来で消えてしまったが、「心がささくれだっている都会で、心のオアシスとして立ち寄ってもらえれば」と店内の一角に置く。
料理人でありながら管理者という立場のシェフが多い。今の時代に求められる料理人像かもしれない。
料理人であるからには当然おいしい料理を作らなければならない。そして結果を上げていかなければならない。
レストランの収入はお客が払う食事代のみ。あとはすべて経費として出ていく。それだけに出ていくものの管理には目を光らせる。食材三〇%、飲料三〇%、人件費一五%、家賃一〇%、諸経費五~一〇%が理想の姿とするが、ままならないのが現実。これにいかに近づかせるかがシェフの腕。
「原価率の動きを知るのは難しいことではない。毎日の習慣にすればいいのです。ただ計数管理に集中しすぎてもいけません。結果としてお客が来なくては意味のないことです」と笑う。
計数管理ができたら調理場にも目を転じてみよう。意外に切り方が厚く、戸惑いながら食べるお客の顔に出くわすかもしれない。
「一瞬にして客の反応を感じとるくらいにならないと、いつまでたっても自分本位の料理しか作れなくなります」
調理場とホールはまったく異なる世界だが、切っても切れない関係で成り立っている。これを認識すればお客への対応も自ずと異なってこよう。
残念ながら現在、フランス料理はイタリア料理に大きく水をあけられている。理由は大きく分けて三つあると分析する。
まず価格が高いこと。日本ではお客は料理にお金を払っているという認識が強い。「環境にお金を払う感覚がない」のか、それ以外のものにお金を取られると結果として高く感じる。
第二が窮屈。正装して行かなくてはいけない、ナイフやフォークをきちんと使わなくてはなど、マナーを重んじたため、カジュアルなイタリアンに行こうとする。
第三が何を食べているのか分からない。
「これらフランス料理が敬遠されている三大要因を取り除くにはどうしたらよいか。それには切り分けサービスが一番」と結論付けた。
これから食べようとするものを目の前で切ってくれる、会話を楽しみながらだ。ただこの提供法には一つの鉄則がある。
「一部のお客のためにはやらない。来た人全員が公平感をもつようにすること」。こうした気持ちを持ったのには一つのきっかけがあった。
子供を連れてディズニーランドに行った時のこと。当然、全員入場料は同じ。松竹梅はない。同じように並び、常に清掃されているためか、むやみにたばこを吸う人もいない。ビールを飲む人もいない。強制されているわけではないが、これだけ我慢をしてもまた行こうという気持ちにさせる。この平等さがうれしかったという。
レストラン内ではどうしても不平等になりがち。常連客にはサービスマンが張り付いて対応するが、一年に一回の客にはじっと注ぐ視線のみ。気楽に話もできない。メニューも松竹梅で真ん中にいくように仕向けられ、ソムリエはワインリストを持ってくると身なりで判断、安い価格の一本をすすめる。これではプライドの傷ついたお客は二度と来ないだろう。
「小野さん、村上さんらは第一世代。行動を起こした井上さん、高橋さんらが第二世代。そして今のわれわれ第三世代が今までのフランス料理を収拾し構築していく役割がある思っています」
各世代は時代背景があって必然的に生まれたこと。今後の新しい流れがどう支持されるか、それは時代が決めることか。
◆ 一九六〇年、東京生まれ。中学時代、偏差値制度に歯向かい勉強を逃避。いつしか祖父と同じ職人の道を目指し、料理業界に入る。先輩にプレゼントされた一冊のフランス料理の本に魅せられ、フランス行きを決意。裸一貫で乗り込んだフランスでは、望んで日本人とは疎遠な田舎で修業。帰国前の二年間はトロワグロでセクションシェフとして在籍。五年間のフランス生活を終え、トロワグロ・ブティック・シェフとして帰国。銀座レザン・ドール、ル・マエストロ、ポール・ボキューズの料理長を経て、九七年、レストランWオープンと同時に現職に至る。
文 上田喜子
カメラ 岡安秀一