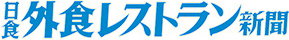シェフと60分:リストランテ・ヒロオーナーシェフ山田宏巳氏
イタリアから帰国後、二五歳で自ら店を持ち、まず取り組んだのが化学調味料を断つこと。塩とオリーブオイルと野菜。「イタリア料理のおいしさはここにあるとわかったから です」
修業時代から長い間、化学調味料の味に慣らされている。おいしすぎる味。これを使わず自然のおいしさを出すにはどうするか。
「がむしゃらにイタリア料理やフランス料理講習に参加し模索した」が、なかなかに納得できず、結果はイタリアへ行くことになる。
自分なりの味をつかんだところで、さらにフランスにも足をのばす。イタリア料理を日本でやっていくにはフランス料理をベースにする必要性を感じたからだ。
帰国後、「むこうで出合ったおいしさを同じレシピでやっても味が足りない」ジレンマに遭遇。
野菜スープひとつをとっても味が足りないと、つい鶏がらを使ってしまう。
「これでは野菜スープならぬチキンスープ、野菜は浮いているだけの存在。鶏のだしを使わず水と野菜でなくてはならない」
トマトソースはどうだろう。レシピどおりに少量のトマトにたっぷりの玉ネギを使ってはオニオンスープになる。玉ネギでおいしくしてはいけない。ここはやっぱり「おいしいトマト」をたっぷり使い、玉ネギは少量使いたいところ。
「飾りのない、味のハッキリした料理。変化球ではなく直球勝負の料理をしたい」
ほとばしる山田流料理信念。二〇年前オーナーとなり、食材が自由に入手できないころから今もこの姿勢は崩さない。
今から二七~二八年になろうか、「初めて熱々のピザを食べたとき、ピザってこんなにうまいものかと感激した」という。
洋食に憧れて入ったイタリアレストランで食べたピザは、作り置きし冷えたものばかり。
スパゲティも同じ。当時のナポリタンは、注文があると、あらかじめゆでておいたスパゲティから一人前二〇〇gを量り取り、ケチャップとトマトソースを混ぜ、チーズをかけてオーブンで焼き上げ、鉄板にのせて出すのが一般的。
「周りでイタリアへ行った人はだれもいなかった。メニューは、本を頼りに見よう見まねで作るのが当たり前」
イタリア料理店も少なく、スパゲティの輸入業者も大量の売れ残り品を埋め立地に埋めたという逸話もある時代背景があった。「確かに厳しいものだったが、毎日、仕事が覚えられ楽しかった」と当時を振り返る「ハングリータイガー」での修業時代。
どん欲に新しいものに立ち向かう若き料理人にとり、初めて味わう熱々のピッツァ、アルデンテのスパゲティなどなど、今に至るまで忘れられない感動として脳裏に刻み込まれている。
「気に入った食材を入手するには、店に張り付いていたのではできない」が持論。常にアンテナを張り巡らし、機会をつくっては店を離れ、良いものがあると友人、知人に分けてくれと頼み込む。
このどん欲さ「逆に、自分が知っていることはどんどん教えていく」心意気が裏打ちされている。
先代から引き継いだ店ではなく、自分自身で切り開いたもの。他人の料理を勉強し、消化し、排せつし、新しいものを取り入れての繰り返し。「人の料理をパクリ続けてきたから、失うものもない」という開き直り。この潔さが意外な出合いを授けてくれている。
静岡でレストランを経営する友人から、「おいしいオリーブオイルが欲しい」との相談を受けた。そこは江戸っ子、すぐさまバイクを飛ばして届ける。着いたのは夜中の1時。感激した友人は、わざわざ届けたお礼にとトマトをごちそうした。
「このトマトがおいしいこと。おいしいオリーブオイルを届けたい一心で持っていった結果、おいしいトマトに出合えた」と手放しで喜ぶ。
どこでどんな出合いがあるか予測はつかない。今では、おいしいトマトを静岡から仕入れていることはいうまでもない。
料理のおいしさを決めるのは野菜と言い切る。
「野菜にこだわるあまり、自ら栽培に手を出す人もいるが、これは自分でやることではない。料理人は料理のプロであるべき」と領分をわきまえる。
畑で作物を作るのに半端な時間ではできない。これに投入する時間があったら、そのエネルギーを料理作りに振り向けろというわけだ。
自らは、ルッコラ、アーティチョークなど、知り合った農家に「使う立場からの要望はどんどんぶつけ」ながら、自らが求めるおいしい野菜を入手している。
「気がついたら仕入業者数は増え、事務的作業が煩雑になる一方」と苦笑する。
イタリア料理は野菜で決まると言い切るだけに、今後もこの格闘は続きそうだ。
◆プロフィル
一九五三年東京・浅草生まれ。父親の事業失敗で新潟に移り住む。生来の食いしん坊根性は地元の豊富な食糧をどんどん吸収、一年でいっきに一五センチメートルも背丈が伸びたことも。また、男子厨房に入るべからずの禁を犯し、台所に入っては子供ながらに料理の腕を振るっていた。高校卒業後、ごく自然に料理人の道へ進み、地元の「イタリア軒」に入る。二年後に上京、「ハングリータイガー」「高野ワールドレストラン」などを経てイタリアで五年間の修業。帰国後、「バスタパスタ」初代料理長を務めた後、「ヴィノッキオ」の主となるが、やむなく閉店。九五年、再度の挑戦で「リストランテ・ヒロ」をオープンさせ、今に至る。
文・カメラ 上田喜子