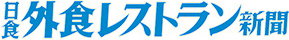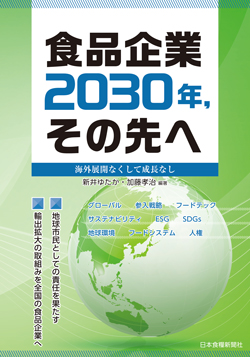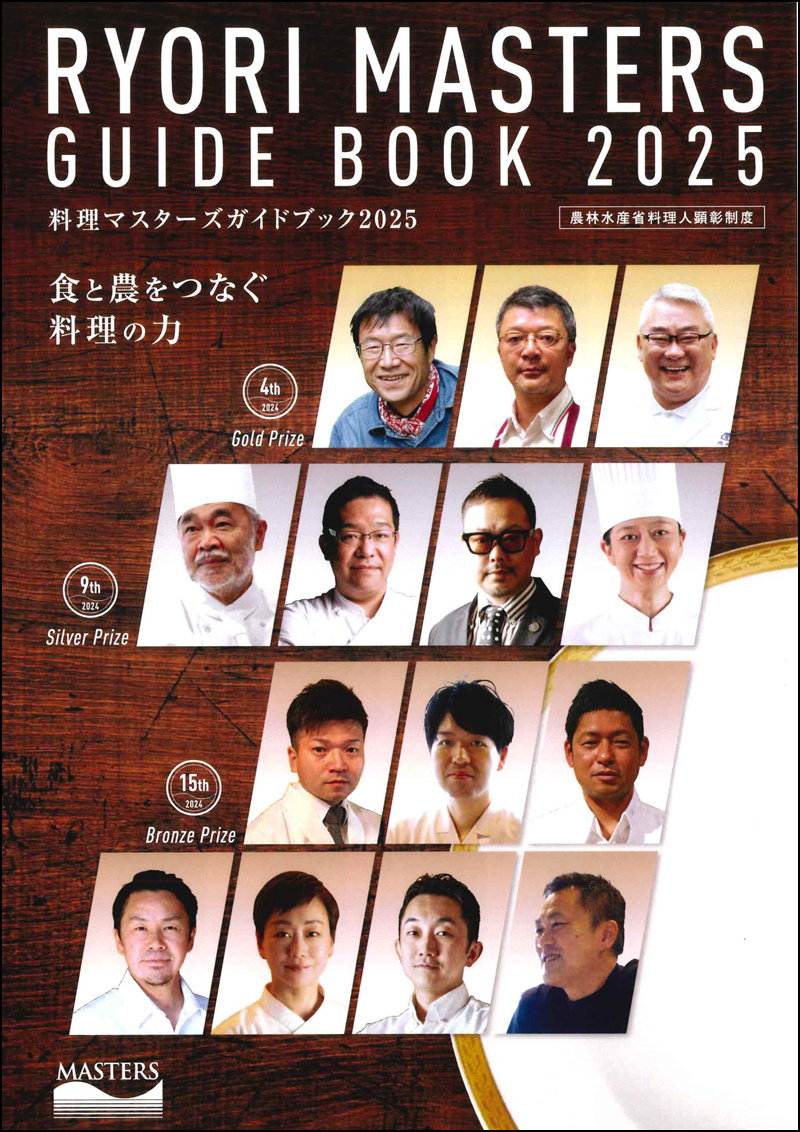シェフと60分:パンパシフィックホテル横浜総料理長・河合隆良氏
日本での修業にあきたらず海外に飛び出し、カナダ、ヨーロッパ、アメリカへと約二〇年の料理人行脚を経て帰国。
「味覚があまりにも変わっているのにビックリ。肉でも、口当たりのいい柔らかいもの志向になってきている」
確かにリンゴひとつとっても、かつては「リンゴをかじると歯茎から血が出ませんか」といったコマーシャルがあったように思う。
こうした変化に「われわれ料理人は、消費者ニーズに応じるだけでなく、教えていく立場にあり、教える義務がある」と語気を強める。
当面、自らが実践していきたいことは、「もっと大胆に野菜を使うこと。野菜が主で、肉が付き合わせの料理があっても良いと思っている」と。
確かに長年、日本の家庭の味として親しまれている肉じゃがは、色とりどりの野菜がゴロゴロ。肉はだしとり的存在である。
フレンチではどう提供するのか。「肉を魚に替え、ソースを工夫するのです。淡泊な魚も、ソースの工夫によって肉のようにこってりとした重量感あるものに変わる。これからはソース料理が注目される」と力説。
日本古来の調味料、醤油の偉大さを知ったのも、海外の料理人と接してのこと。アメリカ滞在中、料理人にもてはやされる醤油を、「日本人だから使いたくなかった。使い方を熟知している醤油を使わず、彼らと同じ味にしたかった」という。
こうした安易な道をとらず、何事にもどん欲に挑戦する姿勢が「カミカゼキュイジーヌ」「爆発する男」の異名をとったのかもしれない。
帰国してみんなが醤油の世界。当然に醤油を使うが、あくまでもフレンチ料理人としての心意気で控えめに使う。
思い起こせば、二二歳で海外脱出を図る。いつ帰るというあてもなく、「とにかく本物を見たい。何が何でもモノにしたい」という一途な気持ちでの出発だった。
初めての上陸地はカナダ。やっと得たホテルでの仕事は、二四時間フル稼働。自らのシフトが終わると、他人のも奪って働けるだけ働いた。
「今ではどこのホテルに行ってもできない半身の牛を掃除したりした。学校で習ったものではない、これこそ求めていた現場での学習だと、死にもの狂いで取り組みました」
ここで働く料理人すべてがヨーロッパ人だったことに触発され、またもや次の新天地、ノルウェーに旅立つことに。
ここでもあきたらず、スイス、そしてヌーベル・キュイジーヌ全盛期のフランスへと料理人放浪が続く。
「料理は基本的にどこへ行っても同じこと。肩書きを取りに行ったが、本当に得たものは生活だったと思う」
その土地でチーズを食べながら、バケットをかじりワインを飲む。また友達のお母さんが作ってくれた料理を食べ、土地の空気をいっぱい吸うという生活。これが一番の収穫だったと、長い料理放浪生活を結論づける。
最も行ってみたかった国、アメリカ。一九八六年、三一歳で念願かない「レストラン・マサズ・サンフランシスコ」のスーシェフとして招かれる。
このレストラン、ソースにしろ魚類にしろ、鮮度が要求されるものはその日に使いきる。使えると思ったものも使わせない。
保管のための冷蔵庫もなく、プロでもすべてを見分ける目がないからと、危険回避のためすべてを捨てるよう指示していたほどの徹底ぶり。
「数々のレストランをみたが、今までにないぜいたくなレストラン」と絶賛する。
アメリカ中から集まってきた料理人と仕事をともにするが、彼らの仕事ぶりは、「東洋のカミカゼ、爆発する男」と異名をとるほどの男から見ても「半端ではなかった」という。
営業は夜だけだが、朝9時半に店に入り、午後11時まで働く。料理人はすべて日給制。時給いくらの世界ではない。何時間働こうが残業手当もつかない。いきおい一二時間かかるところを一一時間にしようと仕事をとばす。
「キッチンの中は仕事でピリピリ。普段は楽しく愉快に話しているが、こと仕事に入ると人が変わったようになるのが常」
こうした仕事環境が厳しければ厳しいほど、チャレンジ大好き人間にとり、「プロとしての誇りをくすぐるのか、クリアしたときの達成感、これは口では言い表せないものがあった」と笑う。
◆プロフィル
一九五五年、静岡県浜松市生まれ。小学生のころ、テレビで見た村上料理長の帽子の気高さに魅せられる。家業は八百屋。地元デパートにも納入していたため、母親は常に新しい野菜を扱い、食べ方の研究に余念がなかった。これを吟味する癖が高じ、将来は料理人と決める。ただ好きなサッカーのプロになるか迷いはあったが、結局、手に職をと料理の道へ。
大阪あべの辻調理師学校では、日本料理は手の冷たい人が合うという先生の一言であっさり断念、西洋料理を専攻。オイルショック後の不況で思う職はなくインド料理店などで働くが、勉強にならないと一念発起、思い切って海外への料理修業に旅立つ。
広大な自然にあこがれ、夢を抱き渡ったカナダ。三年間の修業後、あくなき探求心からノルウェー、フランスへ渡る。再びカナダに戻ったのは二九歳。さらにアメリカに足をのばし、「マサズ・サンフランシスコ」のスーシェフ、「パンパシフィックホテルサンフランシスコ」総料理長を経て、九六年、現ホテル開業とともに現職に就く。