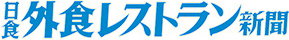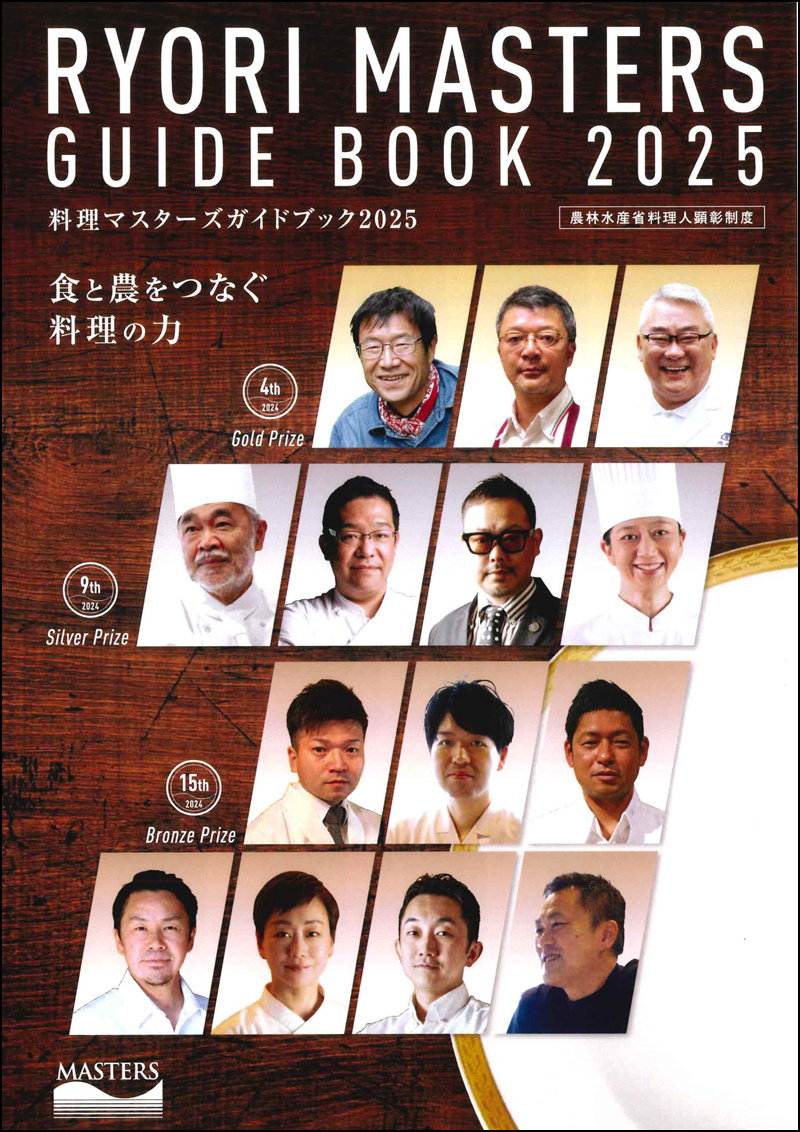カフェブームとは何か!人間味感じられる癒しの時代を象徴
二一世紀最初の年、二〇〇一年の飲食業界を振り返ったとき、「カフェ」は、時代を象徴する、外すことのできないキーワードのひとつとして将来の業界年表に刻まれることだろう。
そもそも、カフェとはフランスで有名な街角の飲食店のことであり、その利用のされ方は日本の喫茶店に近いものだ。一人あるいは少数の人間が、コーヒーを飲みながら会話を楽しんだり、商談を行ったり、本を読んだり、軽い食事をとったりといったために利用する飲食店で、その多くはオープンテラスの形式で、テーブル会計を行うスタイルで営業している。
パリには、サンジェルマン・デ・プレの中心にある「ドゥ・マゴ」など老舗のカフェが数多くあり、文化人たちのたまり場としても知られている。しかし、現在、東京などを中心に流行しているカフェと呼ばれる一連の店舗は、こうした本場フランスのカフェとは少しばかり異なった経緯で生まれた飲食店のグループであるといえるだろう。
わが国の外食トレンドの中で欠かすことのできないカテゴリーのひとつに「喫茶店」がある。今でこそ、喫茶店というのは、どちらかといえば流行遅れの、少数派の飲食店グループになってしまった感があるが、バブル期までは、飲食業界の中心的なカテゴリーのひとつとして日本中に存在していた。
こうした喫茶店は、パリのカフェと同じように、「コーヒーを提供する」というサービスをベースに、人々の休憩や語らい、出会いなどの舞台として、飲酒を中心としたもうひとつのカテゴリー「居酒屋」とともに隆盛を誇っていたが、喫茶店には、決定的な経営上のウイークポイントがあった。
それは「生産性の低さ」である。もともと喫茶店とは「コーヒーなどのドリンク商品を中心に扱うことで、低い原価率を維持し、専門の調理人を必要としないために人件費も抑えられる」というFL費率の低いビジネスとして成立しており、これが店舗面積当たりの売上高が比較的低くても成り立つ飲食店として、素人起業家や異業種企業の参入をも容易にして成長してきたという経緯があった。しかし、こうした特徴がバブル期の不動産価格高騰によって裏目に出ることとなった。
一九八〇年代の後半以降、高騰した地価にともなって日本中の古い建物が取り壊され、家賃相場が大幅に上昇した時期に、それまで細々と営業を続けてきた喫茶店の大多数は、都心部の有力店などを除いて、その姿を消した。代わって、七〇年代からチェーン展開を続けてきたファストフード業態を中心とする生産性の高い外食チェーンが路面店舗に急激に進出し、また首都圏などでは八〇年から展開を始めたドトールコーヒーのような売上坪効率の良い喫茶チェーンがフランチャイズ組織で既存の小規模な喫茶店に取って代わったのである。
やがて、バブル崩壊を迎えた九〇年代初頭、家賃の下落傾向を踏まえて外食チェーンの出店はさらに加速していたが、そうした中で、それまでレストラン経営を主体としてきた「ひらまつ」が九三年、広尾に「カフェ・デュ・プレ」というフランスのカフェそのままのスタイルで営業する店舗を出店、九四年に表参道店(現在は閉店)をオープンしたことで人気に火がつき、連日超満員の繁盛店となった。
さらに九五年には、恵比寿でイタリアン業態の「イル・ボッカローネ」「ラ・ビスボッチャ」と立て続けにヒットを飛ばしていた「オライアン」が、原宿の竹下通りに「オー・バカナル」という「カフェ+ベーカリー+ブラッスリー」の大型店舗を出店、明治通りの路面に面したオープンカフェは話題を呼び、その人気は現在でも続いている。
そして九六年には「スターバックスコーヒー」の銀座一号店が開店した。その後「スタバ」の急激な展開については、説明の必要もないだろう。現在のカフェブームの下地は、この時期につくり上げられたといって間違いないといえる。
しかし、現在のカフェの大流行の直接のきっかけとなったのは、九七年に東京・世田谷の駒沢公園の近くに出現した「バワリー・キッチン」という飲食店である。この小さな店に、いつしか客が行列をつくるようになったときから、現在のカフェブームへと続くトレンドの流れが始まったのだといっても過言ではない。
多くの外食業界人が、そうした現象に気にも留めないうちに、カフェは都市部を中心としてジワジワと広がり、九七年の暮れには東京・青山の表参道近くに「ニューズ・デリ」の一号店が開店、九八年には東京・渋谷に「デザート・カンパニー」が開店して、単なる喫茶店ではなく「カフェごはん」という言葉に象徴される「フードを重視したカフェ」という現在の流れのひとつが出来上がった。
また、九九年、東京・恵比寿のビル九階にオープンした「ヌフ・カフェ」は、店内に中古の家具を配するなど、「癒し系」という時代のキーワードをそのまま体現したかのような、経営者や従業員の生活感覚あふれる飲食店として話題を呼び、その後開業する多くのカフェに影響を与えたといえる。
そしてミレニアムにわいた二〇〇一年には、カフェと呼ばれる飲食店が、首都圏のみならず全国各地に雨後の竹の子のごとく現れ、さすがにこうした現象を無視できなくなった業界メディアによって、カフェの名を冠した業界誌がいくつか創刊されるまでになったことは周知の通りだ。
では、なぜいま、こうしたカフェが圧倒的に顧客の支持を受けているのだろうか。現在、カフェと呼ばれている一連の店の出店立地や商品構成、価格帯、営業時間などを比べてみれば、すべてがバラバラであり、いわゆる「業態」としての共通項は存在しないことに気づく。つまり、カフェとは業態の呼称ではないのである。現在のカフェとは、どこを切っても金太郎アメのような、人間味を感じさせない多くの外食チェーンに暗黙の不満を持つ客たちが望む「好ましい飲食店のイメージ」を総称したものであり、それは決して業態のように機能面から定義されたものではない。
いわば「カフェ現象」とでもいうべきものなのだ。そうして、こうしたカフェにおける唯一の共通項は「その店をつくり上げている人々(=スタッフ、経営者)の顔が見える」店であるという点だ。
こうした多くのカフェに入店すると、どの店のスタッフも、自分の店に自信と誇りを持っていることがありありと感じられる。さらに、先に述べた独立系カフェでは、良くも悪くもオーナー自身の「人となり」すらハッキリと見えている。カフェには、多くの既存チェーンが、店舗の「標準化」を行うという名目のもとに実質的に切り捨ててきた「人間」の存在感に満ちているのである。そして恐らく、その「人間くささ」こそが、閉塞感あふれる現代の日本人に強烈にアピールしているのであろう。
現在のカフェブームの中で、われわれはもう一度、飲食店とはどうあるべきなのか、客と、そこで働く人々に、飲食店は何を提供しなければならないのかを見つめ直す必要があるといえるのかも知れない。
(現在、ちまたでカフェと呼ばれている飲食店とは、大きく分類すると別表のようになる)