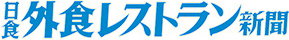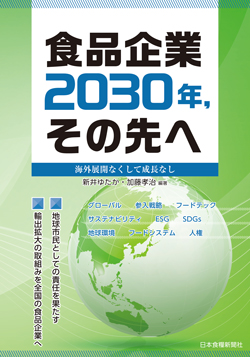外食大国アメリカの当世料理人雇用事情
アメリカでは、就業者の八%、すなわち一二〇〇万人が外食産業で働いており、外食産業は、公職に次ぎ、第二に多い雇用を生んでいる。アメリカ人の三人に一人が人生に一度はレストラン業界で働いたことがあるという。いろいろな側面でアメリカ人の生活に影響を与えている外食産業。アメリカ最大の民間の雇用者の就職の実態はどんなものなのだろうか。(外海君子)
◆労働市場支える巨大成長産業へ
全国レストラン協会によると、一九七〇年から去年にかけ、外食産業の売上げは毎年平均して七・一%ずつ伸びてきており、今年は四七六〇億ドルに達すると予想されている。アメリカ人は、実に食費の四六・四%を外食に費やしているという。
労働統計局は、二〇〇四年から二〇一四年までの一〇年の間に、外食産業の職は総じて一八〇万件増加するとみている。成長産業の一つである外食産業は、有望な労働市場だ。
個人の家に出向き、まとまった分の食事を作るパーソナルシェフや、顧客のために新しいメニューや商品を開発するリサーチシェフなどの新しい形態も生まれている。また、最近は目を引くスーパーシェフの活躍があり、料理業界への関心も深まった。
以前は、料理人になるには、師匠となるべきシェフに奉公し、見習いながら調理技術を学んだが、「今ではおそらく料理人の九割が、専門の教育機関で学んでいるでしょう」とニューヨーク市にあるインスティテュート・オブ・キュリナリー・エデュケーションのモーリーン・ドラムの就職部長が言うように、調理や製菓・製パンなどの基本知識と技術を身につけてから就職するというのが典型的なパターンだ。
ドラム部長によると、卒業生のうち、フードスペシャリストやフードライターなどの志望者は就職先を見つけにくいが、料理人を志望する学生は必ず仕事が見つかると言う。この調理師学校での学費は一年で二万三〇〇〇ドルほど。生徒の多くは転職組だ。
調理師学校は全米に数百校あり、レストラン経営や調理学などは、大学、大学院でも学べる。また、数多くの高校も、フードサービス関連のカリキュラムを整えている。教育環境は整っている。
◆外食団体も奨学金制度
プロの料理人の養成学校の先駆者、アメリカ調理研究所(CIA)ができたのは、一九四六年のこと。アメリカ最高峰とされる調理師学校で、少なからずのスーパーシェフを輩出している。
ロードアイランド州にあるジョンソン&ウエールズ大学は、アメリカで初めて調理学での学士号を授与するようになった大学だ。現在では、全米各地の大学で、一〇〇〇を超えるフードサービス関連の学士、修士プログラムが用意されているという。中でも、ジョンソン&ウエールズ大学は五〇〇〇人以上の学生が学ぶ世界最大のフードサービス分野の学問の殿堂となっている。
各種教育機関は、業界と連携してレストランでの研修プログラムを展開し学生に実地体験をさせている。全国的に組織化されている研修制度も多い。料理人の団体、アメリカ・キュリナリー・フェデレーションは、一九七〇年代にアメリカで最初に組織化された研修制度を始めた。伝統的な見習い制度とは異なり、マニュアル化された研修が行われている。
一方、外食産業自体も、人材育成に腰をすえて取り組み始めている。全国レストラン協会は教育財団を発足させ、医者や弁護士といった専門職のように、外食産業をキャリア志向の若者の選択肢とさせることを目標に掲げて、フードサービス関連分野を専攻する大学生に奨学金を授与したり、高校生向けの研修や教育プログラムを展開したりしている。
◆アメリカンドリームが現実に
アメリカ料理界の父と呼ばれるジェームズ・ビアードがテレビで料理を教え始めたのが、一九四六年。六〇年代には、ジュリア・チャイルドが登場、ブラウン管を通してフランス料理を教え始めた。今では、料理番組に特化したフードチャンネルで、スーパーシェフ陣が講義している。
労働省による一番新しい統計によると、シェフや総料理長の平均年収(二〇〇一年)は三万〇三三〇ドル。ファストフードや社員食堂など、異なる業態の飲食店の料理人の年収を平均すると、二万ドルを少し上回る程度だ。全職業の平均の三万四〇二〇ドルより下回る。全国レストラン協会は、同年の総料理長の基本給の中央値を年四万八〇〇〇ドル、副料理長を三万ドルとみている。
料理人と一口にいっても、格差は激しい。法律で定められた最低賃金以下で働いているとされる不法移民がいれば、その一方で、毎年数億円を稼ぐスーパーシェフがいる。レストラン業界のカリスマ的な存在が、カリフォルニア・ヌーベル・キュイジーヌで一躍有名になったウォルフギャング・パックとケージャン料理のエメリル・ラガッセだ。
パックは、ファインダイニングやエキスプレスダイニングのチェーンを展開するだけでなく、料理用具のビジネスまで手を広げ、収入は二〇〇四年で推定一一〇〇万ドルにのぼる。例年、一〇億円以上を稼ぐレストラン業界のスーパースター的存在だ。
単身アメリカに乗り込んで、俳優からカリフォルニア州知事になったアーノルド・シュワルツネッガーと同じように、オーストリアから渡米して一から始め、レストランエンパイアーを築き上げた世界一高収入のセレブシェフだ。
一方、エメリル・ラガッセはクレオール料理で頭角を現し、パック同様、レストランだけでなく、料理用具や食品のビジネスを展開している。二〇〇四年の年収は、推定九〇〇万ドル。パック、ラガッセとも、フードネットワークで自分のTV番組を受け持っている。
フランス出身のジャン・ジョルジュ・ヴォンゲリヒテンは、フランス料理にアジアンテーストを取り込んだフュージョン料理で腕を鳴らし、二〇〇四年の年収は五〇〇万ドル。
「成功するということは、金銭的に成功することだ」
と言い切るチャーリー・パーマーは、レストランの周辺ビジネスにも投資してブドウ園まで買い取り、実業家としての腕も周知だ。ほかにも、フードチャンネルでアメリカでもおなじみになったイギリス人の若いシェフ、ジェイミー・オリバーや、週刊誌でスター並みの扱いを受けるトッド・イングリッシュなど、多くのセレブシェフがいる。中には、アンソニー・ボーディンのように、小説を書き、ベストセラーのエッセーを著した多才なシェフもいる。
◆起業家精神、不動産・金融知識も不可欠
伝統的なシェフは厨房の奥に隠れていたが、スーパーシェフは富と名声を手にし、メディアの華々しい脚光を浴びている。ジャーナリストのジュリエット・ロッサントは、著書の『スーパーシェフ』の中で、このレベルまでたどり着く料理人は、ほとんどの場合、人から好かれ、勤勉で、非常に楽観的な性格をしていると述べている。
ロッサントによると、スーパーシェフになる基本条件は、まずは料理の才能があること。しかし、それだけではない。同時に、起業家精神があり、不動産の知識があり、資金調達や渉外の能力に長け、メディアのスターになる才覚がなければならないと言っている。
インスティテュート・オブ・キュリナリー・エデュケーションのモーリーン・ドラム就職部長は、ここ数年で全国の調理師学校の在校生数が急増したのは、外食産業の成長、健康や食に関する関心、外食レベルの向上なども背景にあるが、こうした華やかなスーパーシェフの台頭もあると認めている。
外食業界の成長につれ、かつては比較的低賃金の単純労働とも見なされていた料理人の仕事も、有望なキャリアに変貌しつつある。料理人に対する意識は、ここ四半世紀の間に大きく変わっていった。一九七六年には、労働省はシェフを単純労働職から専門職へと公的な見直しをしている。
アメリカ全国の料理人は、あらゆる業態を含めると三〇〇万人を超える。その中でスーパーシェフに躍り出るのはほんの一握りだ。ドラム部長は、料理人の必要条件を「探究心と太い神経」と言っているが、スーパーシェフの道のりはそれだけでは遠い。
◆ジャン・ジョルジュ・ヴォンゲリヒテンさんの場合
フランスのアルザス出身のジャン・ジョルジュ・ヴォンゲリヒテンさんは、フランス料理にアジアンテーストを吹き込んだフュージョン料理で脚光を浴びた。ニューヨークを始め、ラスベガス、シカゴ、バハマ、パリ、ロンドンなど世界各地にレストランを展開している。ジャン・ジョルジュさんのレストラン帝国の売上げは非公開だが、自身の年収は推定五億円。押しも押されぬスーパーシェフだ。二〇〇四年のフォーブスのセレブのトップ一〇〇のリストでは九一位になり、有名人の住む豪華マンションに住み、世界を股に駆ける生活をしている。
ジャン・ジョルジュさんによると、シェフの資質としては、規律、味覚、美的感覚もしくは創造力という三つの要素が必要だと言う。料理人になっていなかったら、建築家になっていたと言うジャン・ジョルジュさんは、インテリアなどレストランのトータルなコンセプト作りにも大きくかかわっている。レストランでの食体験は、舌だけに限らないからだ。
しかし、三つの素質を持っているだけではスーパー・シェフにまで登り詰めることは難しい。ジャン・ジョルジュさんは、自らの成功は幸運だったと認める。
「確かに私はラッキーでした。でも、幸運を呼び込む努力をしなければ、幸運にめぐり合えることはできません。私も最初の一五年間は下積みで、学ぶために費やしたのです」
「ウォルフギャング・パックにしても、オーストリアにとどまっていれば今のような成功はなかったでしょう。アメリカのレストラン業界が大きな転換期を迎えたときに、われわれはアメリカに来ました。彼にしても、私にしても、適切なときに適切な場所にいて適切な行動を取り、起こりつつあった波にうまく乗ったのです」
ジャン・ジョルジュさんは、アメリカの外食産業には巨大な市場があり、大きなチャンスがあると言う。そして、またアメリカは移民の国であり、コスモポリタンで、外国のものを受け入れる土壌があるとも言う。アメリカでのスーパーシェフの多くが、外国出身者だ。「ノブ」の呼称で知られる日本の松久信幸さんも、押しも押されぬスーパーシェフの一人だ。
ジャン・ジョルジュさんの口ぶりからは、自信と楽観主義が感じ取れる。世界各地に数々のレストランを展開させ、厳しい競争と戦っていかねばならないが、「プレッシャーやストレスは感じていません。一〇〇%仕事を満喫しているからです。一日一五時間働いていますが、朝起きたときには、これからいく仕事が楽しみで仕方ありません。実に天職だと思っています」と言う。
去年は、ヒューストンや上海にもレストランをオープンした。将来は、ホテル業にまで足を踏み入れたいと考えている。
「レストランには、客はほんの二、三時間しかいません。とことんまで気配りをして客を満足させ、究極のもてなしをするためには、ホテルを展開するのがベストだと思っています」
これからもまだまだ事業を拡大していく予定だ。それにしても、何がジャン・ジョルジュさんを駆り立てるのだろう?
「三一年間、無我夢中で仕事をしてきました。これだけ長く働くと、消耗して引退する人も出てきますが、私にとって仕事は命です。でも、仕事をするのは、お金のためではありません。料理を通して表現したいんです。表現したいという情熱、それに尽きます」とジャン・ジョルジュさんは言う。