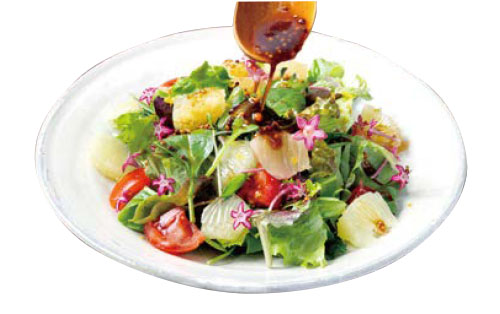給食特集 小規模には「バウチャーシステム」
給食施設を持てない企業で、社員の福利厚生の一環として所得税法上、非課税扱いとなる食券補助制度のバウチャーシステムを導入するケースが増えている。全国展開をしている大手バウチャー会社は、(株)バークレーヴァウチャーズ(BV、03・3234・5311)と(株)ヴァウチャーシダックス(VC、03・5950・7811)。加入会社の社員は月額三六〇〇円を自己負担し、会社から七二〇〇円分の食券を受け取る。バウチャー会社が提携している職場の近辺や外出先、出張先の飲食店で利用できる。つまり、街の飲食店が給食施設を代行できるということ。設備投資しないですむことになる。
BV社は加盟店のメリットとして(1)企業の社員食堂代わりとしてある程度安定した収入が期待できる(2)近隣のビジネスマンを夕食や宴会などの利用も含めた固定客につなげやすい(3)提携飲食店のリストに掲載されることにより、無償で告知効果が得られる(4)加盟料なしでシステムに加入、食券代金請求時に五%までの手数料をBV社に支払うだけ‐‐をあげている。
九四年1月にBVに加盟した洋食屋「ラム」(東京・千代田区)の江崎洋一店長は「お客様からBVが使えるようになって欲しい」という要望があり加盟した。同店は一四坪二四席で昼はイートインとテークアウトの弁当を提供。昼の客単価は八〇〇円、夜は二五〇〇~三〇〇〇円位である。BV利用者は平均すると月約一〇万円は堅い。「以前からバウチャーシステムは知っていましたが、食券はめんどくさいと思ってました。加盟してみたら事務処理はわずらわしくないですし、売上げの五%を販促費と思えば、強力な販促だと思います」と食券のみならず、そこから派生するメリットは大きいと語る。
最近SVにも加盟し、客の間口を大いに広げている。
SLN(SHIDA LUNCH NETWORK)方式は一九七七年、ドイツのハンザ社との技術提携により、日本食に適合した調理済冷凍食品の開発に成功したことから「完全調理済食品」としてスタートした。当初は家庭への宅配として、その後は業務用として厨房設備が狭く限定されていた新宿NSビルや池袋サンシャインビルなどの高層ビルへ提供しながら、メニューの種類、質の向上を図った。湯煎して盛りつけるだけという手軽さと、調理士や栄養士が不要というメリットをもっと広めたいとしていたころ、金融機関の支店に利用してもらった。そこで、小規模給食に力を発揮することが認められ、業界の中にクチコミで広がり、現在はほぼ金融機関で七二〇事業所、一日二八〇〇食を提供、年間四〇億円を売り上げている。
金融機関にこれほどまでに受け入れられた背景についてSL関東第一営業本部舘岡紀久雄本部長は「金融関係のところは職員が昼食を外食でとることを嫌っています。ですからほとんどの支店クラスでも事業所給食を行っています。人数が平均で三五人位となると通常のスタッフを揃えていては採算が取れないし、少ないスタッフになるとメニューのマンネリ化や突発的な休みの問題があり、厚生担当者は苦労が多かったようです」と語る。
SLNは調理済食品をSLN本部のオリジナルレシピで食品メーカーに生産を委託。物流会社により週一回事業所に配送される。事業所側は冷凍庫、湯煎ウオーマー、電子レンジを完備する。規模によって、喫食者が四〇人以下はパート一人、四〇~六〇人は二人、それ以上は三人で対応。エリアマネジャーが二五~二六事業所に一人付き巡回指導や食材の発注などの事務処理をサポートするので、パートは給食の提供のみに専念し、一日五~六時間勤務。喫食者の食事単価は希望にもよるが、平均すると一食三五〇円程度。今から五~六年前にはある銀行から全支店にSLNを導入したことにより、年間一億円の経費削減になったといわれたことがあるという。
このSLNも時代とともに様子を変えつつある。「完全調理」が最大の武器であったが、時代は一手間、二手間かけた手作りを望む。常に改善改良はつきものであるが、最近は特に手作り嗜好が強く、一週間の中で完全調理済給食は二回。カレーやシチュー、酢豚などの手間のかからないものが多い。あとは手づくり風に変わっている。現在の課題としては“食”については良くなったが、サービスの部分で、外食と同じサービスをめざそうと努力している。
同社では現在、このSLNをモデルにして、海外技術オペレーションから調理、流通、事業所の対応も含めたトータルでもっとローコストで提供できるシステムを研究中である。