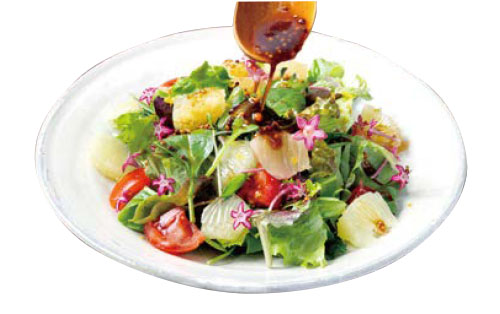淘汰進む居酒屋チェーン データにみる外食マーケット
居酒屋・パブ関係のFC(フランチャイズチェーン)は、一九六六年(昭和41年)4月、養老乃瀧がFC一号店を開設したときに始まる。以後七四年まではこの分野でFCを展開する企業はほとんどなく、七四年末現在でわずか三チェーンにしか過ぎなかった。
この間に養老乃瀧は急成長する。六年半後の七二年12月には早くも一〇〇〇号店(実質は八〇〇店舗)を達成し、七九年9月には二〇〇〇号店(実質一六〇〇店舗)にまで広げた。昭和40年代といえば高度成長時代。「モーレツ社員」という言葉がはやったように、ブルーカラー、ホワイトカラーを問わず、誰もが仕事にいそしんだ時代だった。
そうした時代背景の中で養老乃瀧は、「きょう一日の疲れをいやし、あすの活力を養うための安らぎの場を提供する」というマーケティングスタンスを設定した。つまり、工場労働者や中小企業のサラリーマンをメーンターゲットにし、ポケットの中の小銭で毎日立ち寄れるように徹底的に低価格にし、一人でも二人でも、またグループでも利用できるような店造りをする。
したがって、立地は工場地帯をひかえた駅前や下町が主体であり、店舗は大型、店内は大テーブルを入れ、また宴会場も備えるといった構成だった。これが当時の消費者ニーズにぴったりと合っていたわけである。
その養老乃瀧も、八〇年代に入ると安定成長期を迎えてしまう。オイルショック(七三~七四年)の後、消費者の価値観やライフスタイルが変わったばかりでなく、工場の地方移転など社会構造も変わり、従来のコンセプトが通用しなくなってしまったからである。
七〇年代後半に登場してきた業態で注目すべきチェーンがいくつかある。一つは、炉端焼きである。「戸端焼ごっつあん」は七五年にFC展開を始め、最盛期には四〇〇店以上のチェーンに成長した。しかし八〇年には倒産、わずか五年ほどの命であった。
失敗した要因は、炉端焼きは「焼く」という単純な調理法であり、あまりにも加工度が低く消費者にすぐ飽きられてしまったこと。焼くという調理法だけに食材の良しあしが命だったのだが、均一価格制をとっていたために良い食材の手当が難しかったこと。そして、本部体制を整えなかったのが原因であった。
注目すべき第二の業態は、若者をターゲットにした新しい居酒屋である。七六年に登場した「村さ来」、七七年の「酔虎伝」、七八年の「つぼ八」などがそれである。養老乃瀧を含めた従来の居酒屋がどちらかといえば中高年の男性客を中心としていたのに対し、新しい居酒屋は若者、それもグループ客を中心にし、さらに女性客も視野に入れたところが目新しい。
若者や若い女性客を相手にするということから、安く、雰囲気もよく、料理も充実しているというコンセプトを強調した。客単価は一五〇〇~一八〇〇円、料理のアイテム数は一〇〇品前後。飲むことよりも食べることに重点を置いた。
実際、当時の養老乃瀧では、売上げの六五%がドリンク類、料理の売上げは三五%前後という売上げ構成であった。しかし、村さ来やつぼ八ではそれが逆転し、ドリンク売上げは三五%前後、料理売上げは六五%前後という形になっている。
村さ来もつぼ八も八〇~八五年に爆発的な成長をみせる。養老乃瀧も、八三年には若者相手の新しい業態店(ND方式店)を開発、時代のニーズに合った戦略を採用する。これに刺激されて、若者相手の居酒屋チェーンが続出した。いわゆる“居酒屋ブーム”が出現したわけである。ただし、追随企業はあまり大きなチェーンには育たなかった。
居酒屋ブームが終焉した八〇年代後半から九〇年代前半にかけては、洋風居酒屋、中国風居酒屋、あるいは昼はイタリア料理店、夜は洋風居酒屋などといった二毛作方式店などさまざまな業態が開発された。ただし、九〇年代前半のバブル経済期には、居酒屋は総じて停滞してしまった。
そうした中で登場してきたのが、少投資・高回収率を目指した業態である。一〇坪前後で夫婦二人で運営できる「八剣伝」、焼鳥店の「ダイキチ」などがそれに相当する。昼酒屋分野は“生き残り競争時代”に突入したといわれるが、投資回収率こそこれからの居酒屋経営のキーポイントになるはずである。
なお、居酒屋・パブのFCの過去の推移をみると、九〇年までは店舗数、売上高ともに順調に伸びてきているが、その後は完全に停滞してしまっている。