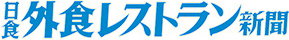シェフと60分:「ラ・コメータ」オーナーシェフ・鮎田淳治氏
イタリア料理は、イタリアからストレートで入ることなく、今でもNYを通して入ってくる。「NYへのあこがれが強いのでしょうか」と笑う鮎田シェフ。
一念発起しイタリアに渡った一九七五年当時、日本ではハワイはパイナップル、イタリアンはハンバーグにチーズ、これにトマトソースだった。またスパゲティといえばナポリタン、ミートソースの時代でもあった。
一方イタリアは、地域性が強く、極端にいえばローマの住民にとってナポリは海外ほどに意識は遠くにあり、おらが国の料理という地方文化が根付いていた。
ところが近年、経済力がつき多くの人が海外に出掛けるようになり、食文化も大きく変化する。ピザ一つとっても土台は薄くなり、分厚いトッピングをのせ、素材を楽しむようになった。
同時に全土的に高まる健康志向から、日本のすし文化が深く浸透してきた。一部プーリア地方などではウニ、カキを食べるが、生魚を食べる習慣はなかったのに、ミラノ、ローマではすしバー、焼き鳥、天ぷらなど日本の食文化がもてはやされている。
「イタリアは日本とよく似た国柄。地方色ある料理は残しながら新たに創作料理も加わり、イタリア料理は大きく変化している」日本でイタリア料理が花開き二十数年。同業店同士お互い食い合ってきたきらいはあるが、「優秀な人も出てきたし、地盤も築いてきた。これからは切磋琢磨していく時代。長い道のりはこれから」とイタリア料理界のさらなる発展に夢をかける。
「イタリアに行った割には食材の目利きができない者が多い」と嘆く。
現在イタリアで三〇〇人もの日本人料理人が働いている。バブル期にはイタリアに行けばハクがつき、待遇がよくなるとだれもかもがイタリアへ向かった。また日本ではイタリア料理店イコールファッションで打ち出す多くの店舗は、これら料理人により支えられてきたきらいがある。
「今は流れが変わってきた。日本でしっかり基本を学び、イタリアの風に当たり帰国し、それなりの料理を出していると思うが、食材についての知識が不十分」と厳しい口調。
名を挙げ名声を得ている料理人でも足繁くイタリアに通う人もいる。
「かれらは今に座っていない。前進するため常に次のものを探している。それは料理の手法ではなく食材です」
自身も年に二~三回はイタリアに足を運ぶ。行くたびに新しい発見があり、そこに身を置くことを楽しんでいる。
かつては禁忌だった組み合わせが堂々と通用していたり、思いもかけない小さな店でその土地だけにある食材を見つけたり。
こうした出合いの成果を持ち帰り、自分なりに消化し料理に出していく。「これが料理人みょうりに尽きるところ」と笑う。
料理人は、「その時代を演出している芸術家。変わり人であってこそ生きていける世界。中途半端では面白くない。向上心、好奇心をもち、料理に自分を出すべし」とキッパリ。
イタリア料理店で、ドーンとチーズがのっていればピザと思い込んでいた時代があった。ところがイタリア人シェフが作るイタリア料理を目の当たりにし、家族の反対を押し切り渡ってのイタリア料理修業。
「まずは下積みをキチンとすれば、技術は後からついてくる」と徹した下積み生活を送る。
当時はガスオーブンとコークス折衷の時代。自ら志願しコークスを担当する。仲間たちが出勤する前に赤々と火を燃やし、オーブンを温めておくのが務め。毎日絶やさない務めをきっかけに料理人と親しくなり、「食材についての目利きを教えられた」と感謝する。
また時間があると地方に出掛け見聞を広め、自ら身を置くホテルレストランばかりでなく、街場のレストラン、菓子屋などにも足を運び、貪欲に疑問を晴らしていく。
「店を構えるようになり、トータルでイタリア料理が提供でき、今までの歩んだ道は間違いではなかった」とする。
徹底した下積み修業を財産にした一人の料理人の言葉は重い。
文・上田喜子
カメラ・冨田怜次
・所在地/東京都港区麻布十番一‐七
・電話/03・3470・5105
●プロフィル
1951年栃木市生まれ。銀行マンだった父親が、海外勤務のおりに体験したヨーロッパ食文化について、間接的ながら接する環境だった。こうしたことが刺激となり、ごく自然に洋食への道を歩むことに。
武蔵野栄養学校卒業後、イタリア料理店で1年修業するが、初めてイタリア人シェフによるイタリア料理を見てカルチャーショックを受け、一念発起し渡伊。ローマENALCホテルスクール卒業後、リストランテ・フェランテッリ、パスティチェリアダヴィデ、ローマ・サテリテパラス、LEGRANDホテルなどのシェフを歴任。7年間の滞在後、1982年に帰国。同年麻布十番にリストランテ「ラ・コメータ」を開店、現在に至る。
かたわら日本イタリア料理協会会員、全世界イタリアレストラン協会日本支部理事などを務める。2000年には、イタリア料理界最高名誉である全イタリア料理人連合最高技術者賞受賞。日本で唯一人の全イタリア料理人連合最高料理人協会会員。
●私の愛用食材 モスタルダ
残念ながら色素の問題で日本には輸入されていない「モスタルダ」。聞き慣れないネーミングだが、未熟の洋ナシ、チェリー、ミカン、レモン、イチジクなどをシロップとマスタードエッセンスに三ヵ月間くらい浸し、煮詰めたもの。鹿肉の煮込みやチーズに合う面白い食材という鮎田シェフ。
イタリアから持ち帰り、イタリア流にチーズと合わせて提供したところ、「みなさん、最初は半信半疑ながらも一口食べて、意外な味わいが気に入られています」
モスタルダは、ベネット州の食べ物。地元産物として他県に売られている保存食である。菓子屋では切り売りされており、レストランでもタレッジオ、スカモンタなどのチーズに合わせて提供される。
「レストランは家庭で食べられないものを食べさせる場。旅行費用二〇万円をかけずに、イタリアのものが食べられると感動してもらえばよい」と年に二~三回はイタリアへ出掛け、新しい食材を仕入れる。モスタルダもその一つ。
ただ、こうしたものは長く引きずると新鮮味が薄れるので、スポット的に出したほうがよいとのことだ。