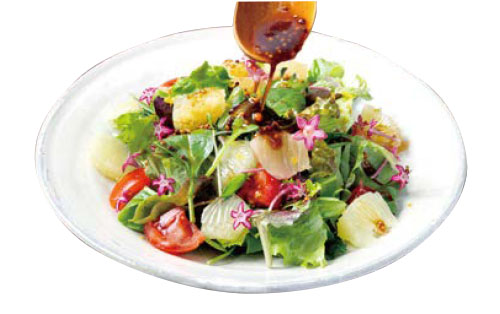御意見番・一人勝ち!スターバックス徹底検証:榊芳生・オージーエム代表取締役
「ドトールコーヒー」と「スターバックスコーヒー」の違いは、オペレーションの違いに表れている。ドトールはファストフード型だ。
食品販売は、(1)オーダーを取る(2)料金を受け取る(3)商品を作る(4)商品を提供する‐‐という四つの行程から成り立っている。ファストフードは、オーダーを取った人が料金を受け取り、商品を提供する。
これに対し、スターバックスは、オーダーを取った人ではない、製造者が商品を直接客に手渡す。もし料金を受け取った人がコーヒーを渡したら、あれほどのグルメ感はなかったと思う。客は出来立てのものを欲しがる。ならば作った人が直接渡せばいいという本音に戻った。
世の中はいまスターバックス的なカフェが急増しているが、ほとんどがファストフード型のオペレーションだ。本来の意味では、セルフ式カフェと呼べるのはスターバックスだけだろう。ただ逆にそれがスターバックスの限界でもある。
ファストフードシステムは大量生産、大量販売にたけていた。製造者が提供すれば生産性は落ちる。しかしスターバックスは、日本での展開でその問題をクリアした。渋谷の駅前店は、いま月商五〇〇〇万円という世界ナンバーワンの売上げを誇っている。
繁華街で最大限の生産性を上げようと思ったら、方法は二つあった。ひとつはドトールスタイルにすることだが、それはせず、(1)オーダーをとる人(2)料金を受け取る人(3)商品を作る人(4)商品を提供する人‐‐をそれぞれを分業することで三店舗分のパワーをつくった。
米国の本部は、当初このオペレーションに首を縦に振らなかった。しかしスターバックスの商品力を犠牲にしないで、一人でも多くの客に利用してもらうためにはこの方法しかないと説得した。
米国でもこれから、テーマパーク内などの店舗にこのオペレーションを導入するだろう。高品質を生む生産性のシステムを、初めて日本から米国に輸出することになるかもしれない。
これから高単価でコーヒーを売ろうとする人たちは、みなスターバックスのシステムに習おうとするだろう。しかし大事なことは製造者がサービス者になるということだ。コーヒーの立ち飲み店を研究してもしかたないという人たちは多いが、ここに商売の原点がある。
スターバックスの店長は、エスプレッソマシーンの前に立っている。シアトルベストなどは、スターバックスとオペレーションはほとんど同じだが、店長はレジの前にいる。店長がレジ前にいるのはチェーンストアの理論であって、繁盛店では厨房に立っている。昔の飲食店はそうだった。ところがいつしか商品よりオペレーションを優先した結果、レジの前でお金を勘定するようになった。
大切なのは商品だということをスターバックスが示している。それにもかかわらず、レジの前に店長を立たせたスターバックスのような店がたくさんある。 ◆榊芳生(さかき・よしお)昭和12年香川県生まれ。中央大学法学部在学中、愛媛県松山市に和食処「へんこつ庵」を開業。以後一九店舗展開するも倒産。コンサルタントとして復活し過去の経験をもとに、地域・生業店志向の飲食店経営を説く。現在、わが国最大の外食コンサルタント企業OGMのトップとして活躍。