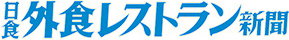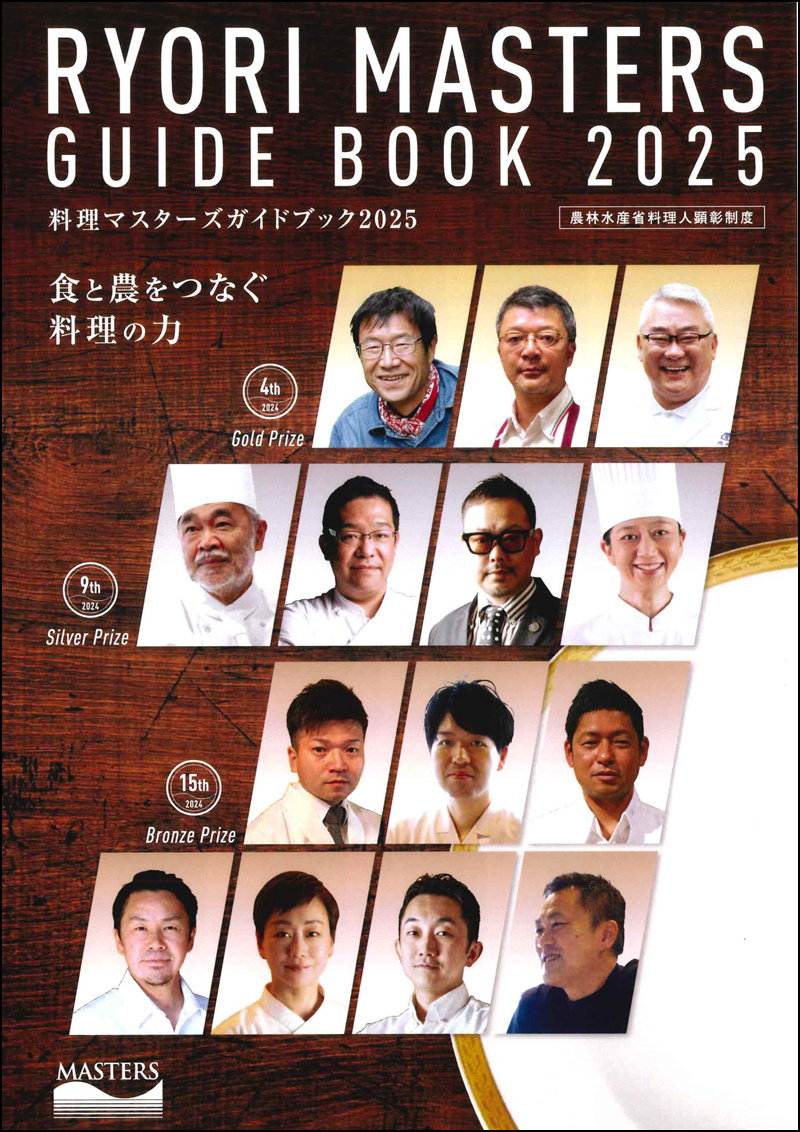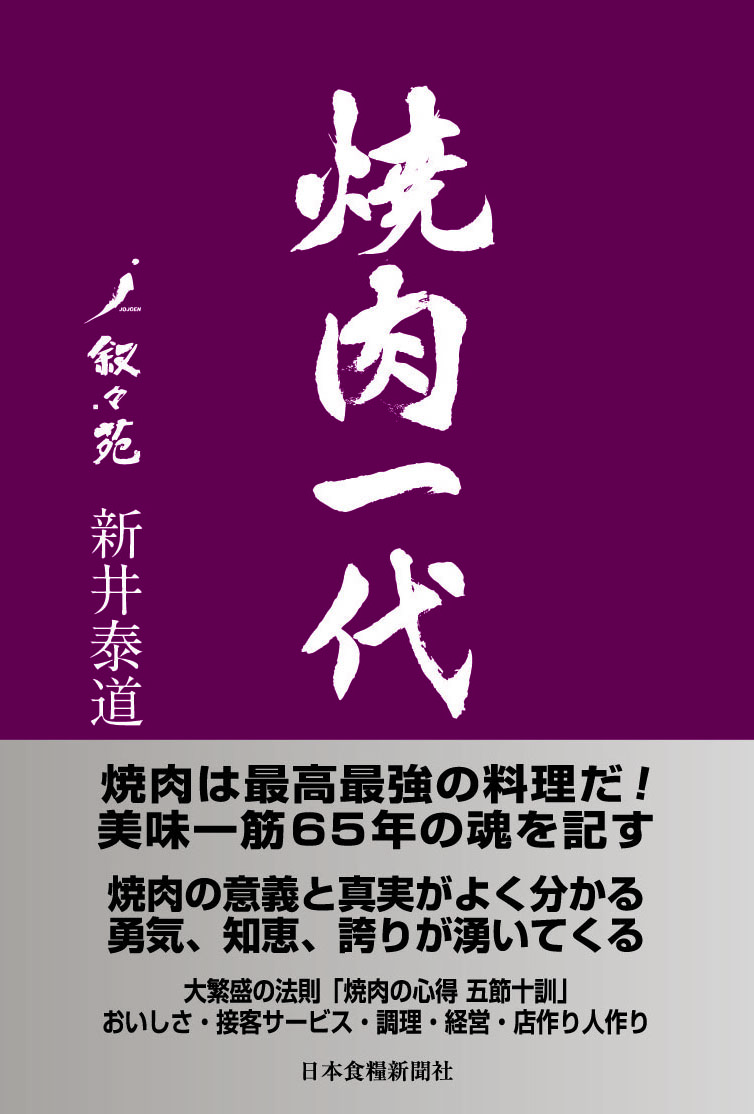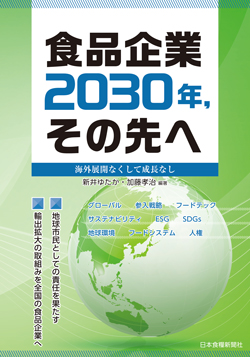インタビュー:ドギーバッグ普及委員会・小林富雄委員長 持ち帰り容器普及で新しい外食文化創出
「食品ロス削減推進法(以下、食ロス法)」施行(2019年10月)を契機に、外食業界では食べ残しの持ち帰りを推奨する動きが活発化している。これまで多くの飲食店では、食べきれなかった料理を消費者が持ち帰ることには否定的な姿勢だった。料理の持ち帰りは法令でこそ禁止されていないが、食中毒のリスクから飲食店では自己規制が働いていた。
しかし、外食業界が食品ロス削減に取り組むのなら、その本丸となるのは「食べ残しによる食品ロス」だ。消費者が食べ残しを持ち帰ることで削減できる食品ロスは、年間80万tとも推定される。
外食における「食べ残し持ち帰り」文化は今後、浸透していくか。飲食店の「食べ残しの持ち帰り」を提唱し、ドギーバッグ(=食べ残しを持ち帰る袋や容器)の定着を目指すドギーバッグ普及委員会の小林富雄委員長に見解を聞いた。
●食べ残しの持ち帰りは国が許可している
–注文した料理の食べ残しを持ち帰ることは、そもそも許可されているのか。
小林 飲食店で食べ残した料理を消費者が持ち帰ることは、法的に何ら禁止されていない。消費者の権利としてはもちろん、店が「持ち帰り」システムを採るのも許可されている。店で提供しているメニューを店頭で売ったり、イートインの提供後に持ち帰りを認めるのは、営業許可を取って営業しているすべての飲食店で可能である。これは、厚生労働省にも確認済みだ。また、飲食店での料理提供は対面販売になる。商品に関する説明は直接行われている前提なので、スーパーの惣菜のような表示義務もない。
–持ち帰りを自己規制している飲食店も少なくない。本来、許可されていることなのに、なぜなのか。
小林 食べ残しの持ち帰りがタブー視されてきたのは、縦割り行政の弊害、といえるかもしれない。「食品ロス削減」の課題を行政は共有しているが、食ロス法はもともと食品事業者を対象に農林水産省主導でスタートし、一般廃棄物の処理は環境省マターになる。また、食品衛生を管轄(飲食店含む)するのは厚生労働省と、省庁をまたがる対策が必要なだけに、動きの鈍いところがあった。
–保健所が「好ましくない」と、誤った指導をする例もあったのではないか。
小林 そうした指導が実際にあったかどうかは分からないが、何といっても保健所の至上命題は「食中毒をなくす」こと。そんな保健所に忖度(そんたく)し、自己規制する飲食店はやはり少なからずあっただろう。
–19年10月の食ロス法施行で、状況は変化したか。
小林 ここ数年、風向きが大きく変わり、「食べ残しを出さない」という意識が広がっている。食ロス法によって、その動きはますます加速している。昨年は、すかいらーくやロイヤルが「店で食べ残した料理は持ち帰りできる」という内容のプレスリリースを出した。大手ファミレスの多くは実は持ち帰り容器を用意しているが、これまではあまり公表していなかった。それをアピールするようになった。また、ワタミも持ち帰り容器を用意し、気軽に持ち帰れるよう、タッチパネルで注文できるシステムを順次導入している。こうした風潮は、今後、外食業界全体に波及するのではないか。
–飲食店で食べ残しをなくすことよる食品ロス削減の効果はどの程度か。
小林 現状、国内の食品ロスは年間約600万tで、外食から出るのは120万t。その内の80万tが食べ残し、というのが大まかな数字。これほどのまとまった量が一つの理由で出る食品ロスは、ほかにない。ここを突き崩せられれば大きい。
–飲食店でドギーバッグを活用するのは、食品ロス削減の大きな効果が見込める、ということか。
小林 さらにいうと、「食べ残しを出さず、持ち帰って食べる」という行動が外食から定着すれば、消費者の意識が高まり、家庭内での食行動にも大きく影響を及ぼす。家庭での食べ残しで発生する食品ロスは年間130万tと推定されるが、外食も含めて食べ残しをなくすだけで、全体として200万tの食品ロス削減がターゲットとなり得る。
●キーワードは「自己責任」
–食べ残しを持ち帰ることで、トラブルが起きる可能性もある。そのリスクを恐れて、ドギーバッグ導入に消極的な飲食店も多いようだが。
小林 その問題は根深い。食中毒のリスクだけではなく、例えば、車で持ち帰った際に中身がこぼれてシートが汚れてしまい、店が法外なクリーニング代を請求された、という例もあった。あるいは、飲食店で出される料理はすぐに食べるという前提で作られているため、時間が経つと味が落ちてしまう。それを食べて「おいしくない」と評価されるリスクもある。
–そうしたリスクに、飲食店はどう向き合うべきか。
小林 「消費者との信頼関係づくり」に尽きると思う。理不尽なクレームは、店と消費者とのコミュニケーション不足によるところもある。消費者が店を応援してくれるように、店も長期的な良好関係をつくる努力や戦略が必要。一方で、あまりに横柄な消費者には、店が「NO」を突きつけてもいい時代になりつつある。個人店でも今は、SNSなどから声を発信できる。「消費者が支援したくなる店づくり」と「消費者との良好な関係性の維持」というのが、今後の外食が目指すべき一つのあり方ではないだろうか。
–これからの時代、「お客様は神様」ではない。
小林 そう。同時に、飲食店を利用する消費者の意識改革も肝要だ。特に「食べ残しの持ち帰り」にあたっては、消費者の倫理的な意識向上が強く求められる。店で衛生的に提供された料理が、持ち帰る途中で汚染され食中毒になった場合は、明らかに消費者の責任だ。料理を持ち帰るのは、あくまでも「自己責任の範疇」と消費者は理解しなくてはいけない。「料理を持ち帰って車のシートが汚れたから、クリーニング費用を店に請求」という話に帰結させては絶対にいけない。
–しかし、飲食店側から「何かあっても消費者の自己責任ですよ」とは直接言いづらい面もある。
小林 そうした声を受けて、ドギーバッグ普及委員会では「自己責任ステッカー」を発行している。ぜひ活用してほしい。食べきれなかった料理を持ち帰るのは、店側、消費者側ともにWin-Winになる話のはず。外食文化をもっと豊かにしていくには、消費者の歩み寄りによる価値共創が不可欠だ。また、「食べ残し持ち帰り」の推進については、国の意向を受け、今後は消費者庁も消費者の意識変容を積極的に啓発していく構え、と聞いている。消費者庁には、大いに期待したい。
●「持ち帰りたくなる料理」を出せる店が生き残る
–「食べ残しをなくす」という視点では、適量を注文して残さない「食べきり運動」といったアプローチもあるが。
小林 もちろん、それも重要だ。ただ、テーブルにたくさんの料理をにぎやかに並べるというのも外食の大きな楽しみ、と個人的には思う。たくさんのおいしい料理を楽しみ、余った物は持ち帰ってありがたく「いただきます」でよいのではないか。
–ドギーバッグを店で用意したことで、「お土産に持ち帰ることができるから」と追加注文が増え、店にとってもメリットにつながった、という事実もある。
小林 単にドギーバッグを用意するだけでなく、これからの飲食店は消費者が持って帰りたくなる料理を追求する必要がある。持ち帰りたい料理というのは、言ってしまえば「おいしい料理」と「高価な料理」。まずい料理、安価な料理は、持って帰りたいとは誰も思わないだろう。持ち帰り文化が成熟することで、外食というチャネルはこれまで以上に多様な社会的役割を担う可能性を秘めている。その中で生き残ることができるのは、冷めてもおいしい「持って帰りたくなる料理」を出す店になっていくはずだ。
●ドギーバッグ普及委員会・小林富雄委員長
サスティナブルフードチェーン協議会代表理事
愛知工業大学経営学部教授
●ドギーバッグ普及委員会
2009年 ドギーバッグ普及委員会設立
2009年 特定非営利活動法人(NPO法人)認定
2020年 一般社団法人サスティナブルフードチェーン協議会内の委員会へ改組
【写真説明】
写真2:飲食店お持ち帰り用ステッカー「自己責任バージョン」
ドギーバッグ普及委員会が発行しているステッカー。食べ残しの持ち帰り容器に貼付し、消費者の「自己責任」意識を促す。同委員会のHPから無料ダウンロードできる。
「ドギーバッグ普及委員会HP」 https://www.doggybag-japan.com/