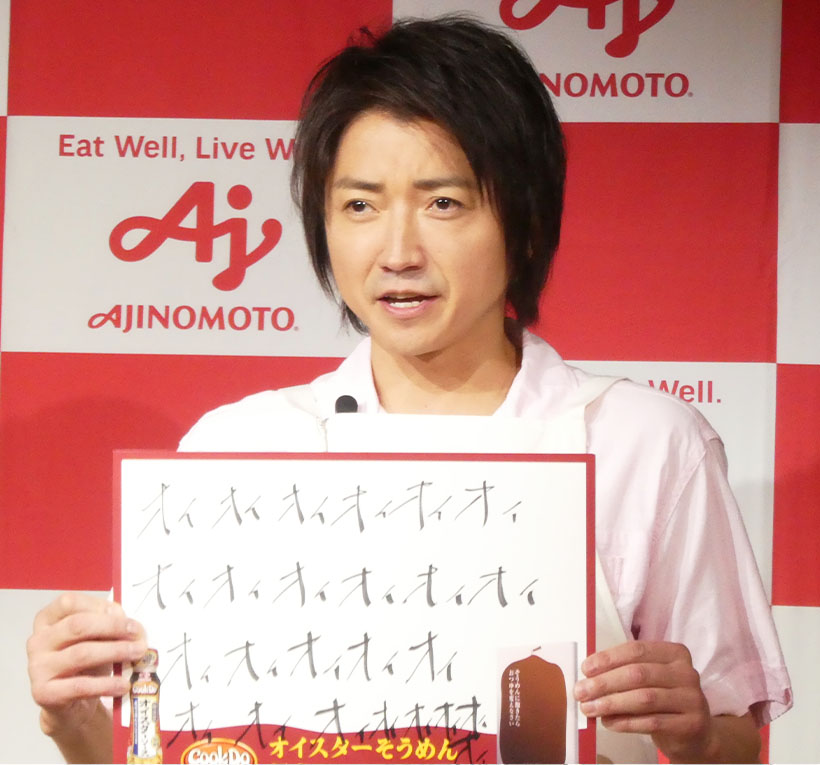納豆用からしの粉末新タイプ「ふりかけからし」登場~芥子屋四郎
納豆に不可欠の調味料といえば練りからし‐‐市販の納豆には小袋入りの練りからしがつきものだが、その粉末タイプが新たに登場した。開発したのは、からし専業メーカーとして知られる(株)芥子屋四郎(埼玉県浦和市、048・852・4842)。「食べるものの味をよくするからしづくりを目指して」(酒井四郎社長)研究を重ね、いきついたのが納豆用の「ふりかけからし」(粉末)だ。従来の発想を転換し「からしの原点はドライ」(同)と、いわば初心に戻って味で勝負する“添付用からし”を世に送り出した。
新製品は「納豆専科ふりかけからし」。粉末のからしを添付用の小袋に詰めたもので、用法は“練りタイプ”と同じく納豆に直接かけてかき混ぜればオーケーと、水で溶く手間は不要。しかも、からし本来の辛さや旨味が乾燥状態で損なわれずに保持され、納豆に混ぜた後にそれらが発生して「食べるもの(納豆)の味そのものをよくする」というわけだ。
添付用小袋入りの練りからしは納豆用がメーンで、「昭和36年に特許をとった」(酒井社長)という同社でも主力商品の一つ。からしは酵素の働きで特有の辛さや風味を生むが、「四五度C超の加熱に過敏に反応し、風味を損なう」という。つまり、練りからしは手間(水で溶く)を省いて、その機能を納豆に付加していたわけだ。
ところが、納豆の製法もその後は変化して最終工程で加熱処理などが加わり、事前に添付されている練りからしに対する影響が心配され、今回の粉末の開発につながったわけだ。ただ、当然ながら粉からしの製法そのものも大きく進化した。欧米のからしは種をそのままつぶすフラワーと称するものが一般的だが、日本のからしは搾油して粉末化、「種から不要(油、皮)なものを除いたもの」といえる。酒井社長によると、搾油時に当初は九五度Cの高温になったが、改良を重ねて「二三年前に六五度Cの機械を開発」。五~六年前に四〇度C以下の低温搾油機にたどりつき、同社一〇〇%子会社のカナダ工場に設置した。
今や粉末からしの製造はすべてカナダで対応している。数年前から日本に輸入を開始し、「二一世紀をリードする」との自負を込め「からし粉21」と命名して販売を開始。今回の「納豆専科ふりかけからし」は、その製品をアレンジして商品化した。「練りタイプの五倍ほどの価格」ながら、からし本来の辛さ、風味を再認識させるべくチャレンジを開始した。