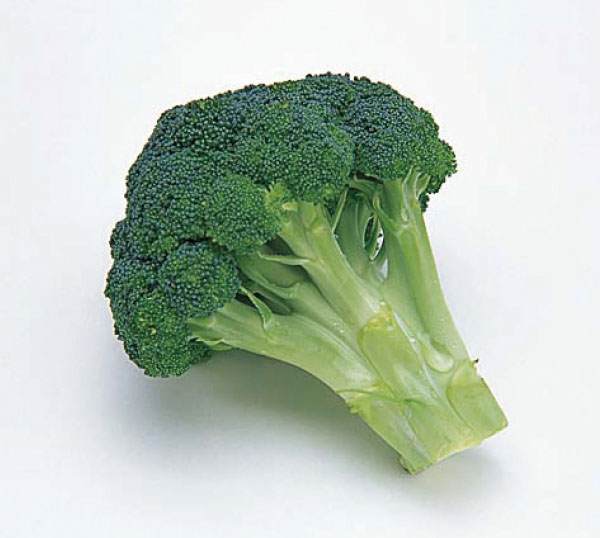百歳への招待「長寿の源」食材を追う:緑豆(リョクトウ)
韓国は薬食思想が強く、食べるものはすべて薬になると考える。薬食・薬飯・薬酒・薬果・薬脯(干し肉)・薬念(調味料)・薬水などと呼び、大切に取り扱う。五味子・緑豆も薬食である。
(食品評論家・太木光一)
緑豆は、「リョクトウ」と読む。豆科の一年生の植物で、原産地はインドと見られ、紀元前二〇〇〇年頃にはすでに栽培されていたと思われる。現在ではインド・ミャンマー・東南アジア諸国・アフリカ・中国・韓国などで広く栽培されている。日本にも縄文時代に伝播したと見られ、貝塚から緑豆が出土している。
成分的にはタンパク質や鉄分・ビタミン類に恵まれ、優れた食品と呼べる。中薬大辞典によると、緑豆は性甘にして涼、清熱解毒・消熱解毒・消暑(暑さ負け)・利水・水腫(はれもの)・丹毒・瀉利(下痢)・解毒などに効く。煎じて服用するとある。
薬膳食として緑豆粥がよく、中国の北方地域では夏の暑さよけに食べられている。町の屋台でもみられる。緑豆をサッと洗い、水に三時間ほど漬けた後、水を捨て、倍量の水で三〇分ほど煮る。金銀花(スイカズラ)を加えるとさらに効果的となる。
緑豆を原料とした緑豆粉は豆麺(ドウミェヌ=豆そうめん)を作るのに用いられる。中国春雨である。粉糸(フェンスー)とも、粉条(フェンティアオ)とも呼ばれている。日本の春雨よりコシがあっておいしい。このほか溶いた緑豆粉を薄く円形に広げてゆでたものを粉皮(フェンピー)と呼び、干粉皮が輸入されている。また中国やミャンマーから輸入された緑豆を原料として、モヤシが作られている。緑豆芽菜と呼び、大豆モヤシと違って軟らかである。サラダや炒め物に多く利用されている。
原価が安く、しかも歯ざわりも良く、ボリューム感も出て利用範囲は広い。そしてヘルシーさがセールスポイントとなろう。
緑豆の収穫期は中国や韓国でもほぼ同じで花期は6~7月、果期は8月となる。立秋を過ぎる頃から一斉に収穫される。このため残暑の厳しいときは解暑・消暑(いずれも暑さしのぎ)の食品(主としてスープ)に利用される。緑豆の性寒にして、除熱効果も期待している。
韓国は緑豆を巧みに利用して、あんや粉状にして利用する。あんのバラエティーは日本より遙かに多い。キヨダンは誕生日の祝い菓子として欠かせない。特に初誕生には三~五色のあんが作られてお祝いする。材料は緑豆・小豆・栗とナツメ・いりゴマやきな粉など。
白玉粉をボール上に丸め、沸騰した湯に入れ、色のあんで包む。特に緑豆は美しい。
また緑豆を粉状にし、お好み焼き(ピンデトオク)を作る。小麦粉よりも軽く腹にたまらずお年寄りに向く。緑豆は日本ではあまり知られていないが重要食材といえよう。