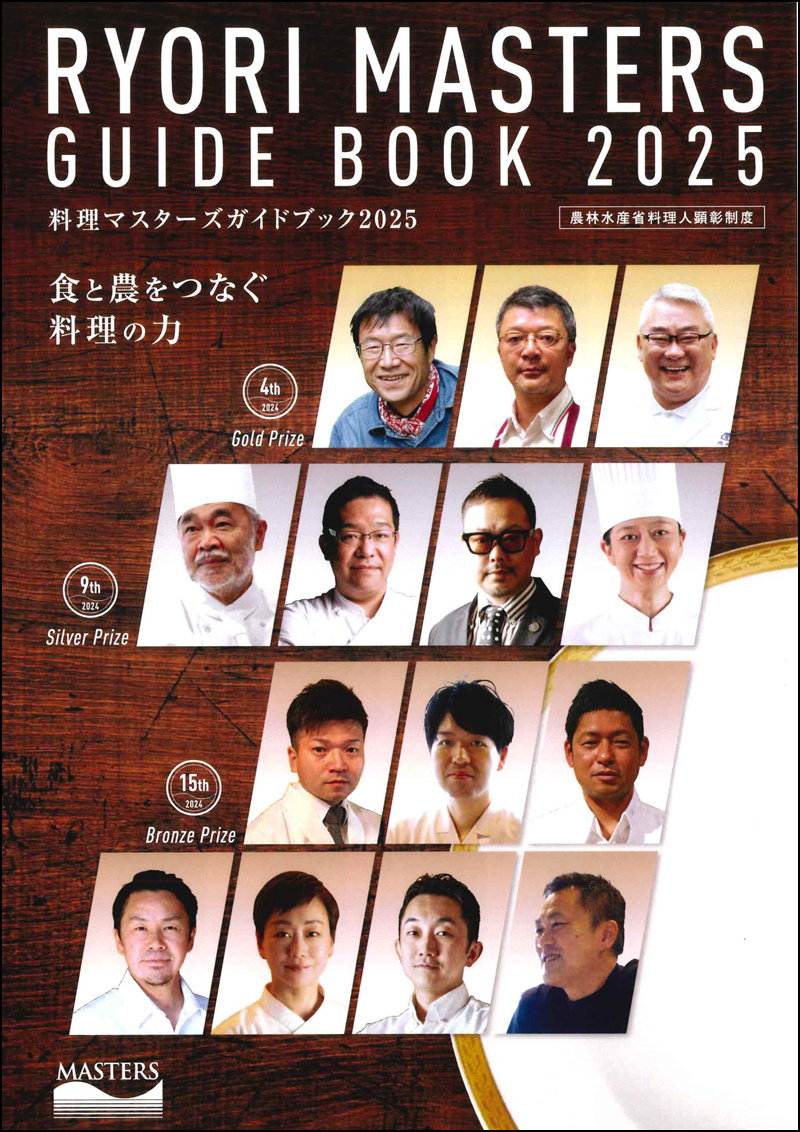忘れられぬ味(59)プリマハム・坂井光男社長「ほろ苦い野いちご」
北陸は加賀の在郷に生まれ、京都の学生時代を経て商社から食品メーカーに勤める今日までに国内海外の各地で喫した食べ物料理は数知れない。その中で舌が味を覚えているものは「私の食べ物誌」と題するノートに記録している。成人してからの料理の味は、その時供された酒の味と結びついているのは私の酒好きの所為であろう。人の話や出版物でおいしそうな食べ物や店を知ると手帳の「いずれコーナー」に書き留めておき、いずれ機会があればと楽しみにしている。
生来食い意地が張っていて変わった食べ物に巡り会うと食欲が出る。不思議と旅先でお腹をこわすことがなく、ソマリアでラクダの乳のヨーグルトを出され、他の日本人は皆すぐに下痢したが、私はおいしくいただいた。一度だけインドの一番辛いカレーでちょっとおかしくなったが、あれは長旅の疲れからだと勝手に解釈している。
忘れられぬ味で思い起こすのはやはり食料不足時代のこと、終戦は五歳の時であった。芋粥が多くドジョウなどの川魚が主なたんぱく源で、炊きたての米粒一つひとつが光沢を放つご飯の時はその香りだけで他に何もなくてもおいしかったように思う。食糧難ではあったが、そこは田舎暮しのありがたさで裏庭にはイチジク、桃、柿の木があり、畑にはスイカ、トマト、マクワウリ、山野には野イチゴ、野ブドウ、桑の実や栗などの自然の恵みが食べ盛りの空腹を満たしてくれた。
小学校六年の夏、近所に住む同級生のK君が腎臓で病床に伏した。毎日のように遊んだ友達だけに私は寂しくてたまらず、度々病床を覗きに行った。そんなある日、K君は意を決したように「河原いちごのあの場へ行きたい」と言う。あの場所とは二人だけの秘密にしていた野イチゴの群生地である。夏に指先ほどの黄色の実をつける。熟したのを手の平一杯に摘みとり頬張ると甘酸っぱい果汁が喉を潤す。ラズベリーとも違うコリコリした歯触りがあった。
他に人のいない家を抜け出したがK君には一人で歩く体力がない。彼を背負って草いきれの中を休み休みしながら、やっとその場所に辿り着いた。草の上に何とか座っていたK君は河原いちごを二粒、三粒口にして、空を見上げながら飲み込んだ。
その夏の終わり、油蝉が終わり、ツクツク法師からひぐらしになる頃にK君はこの世を去った。あの時の無理が病気を悪化させたのかも知れない。誰にも断りなしにK君を連れだしたことを私は少なからず後悔した。私がK君を背負って手取川の堤防に行った事は皆に知られていたが、親からも何も言われなかった。
あの時の河原いちごはどんな味だったのか私は思い出すことが出来ない。あの時私は食べなかったのかも知れない。
(プリマハム(株)社長)

日本食糧新聞の第8874号(2001年7月25日付)の紙面
※法人用電子版ユーザーは1943年以降の新聞を紙面形式でご覧いただけます。
紙面ビューアー – ご利用ガイド「日本食糧新聞電子版」