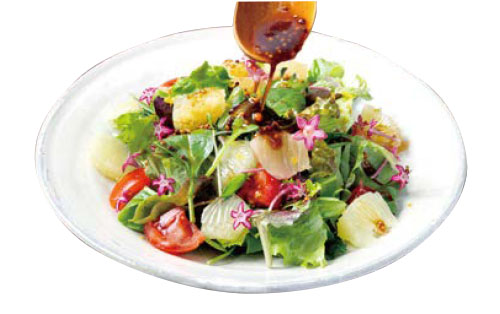榊真一郎のトレンドピックアップ:おにぎりの本質、料理の本質
大衆的でとてもB級な店を見たくなると足を向ける場所がある。東京・大塚の「ぼんご」。おにぎり屋さんである。
カウンターの中に、お姉さんとおばさんの中間の人が立っていて、注文に応じておにぎりを作ってくれる。カウンターの上には寿司屋にあるようなネタケースがあって、その中に筋子、昆布の佃煮、梅干など、おにぎりの具材が収められている。
好きな具を選んで、それで握ってくれるところは寿司屋のようで、でも作ってくれるのが女性であって、作ってもらえるのがおにぎりだから家庭的だ。
で、このおにぎりがとても美味しい。まずアツアツ、それにフワッとしている。不用意に手で持ち上げるとボロッと崩れてしまいそうなほどに柔らかく握り上げられている。
かつて、「おにぎり」という料理は、家でお母さんが作ってくれるか、あるいは居酒屋や定食屋とかの隠れたメニューでしかなかった。でなければお弁当。前者は熱々でふんわりとしていて、それが本来の主流だった。
だが、いま日本で作られるおにぎりの大半がコンビニで売られている。コンビニのおにぎりと言えば、冷たくてミッチリ固い。機械は固く握ることしかできないし、固くないおにぎりを物流にのせるのは難しい。だから、アツアツでフックラのおにぎりは少数派になったし、何よりそれを食べる場所を見つけるのが難しくなった。
コンビニのおにぎりを食べると、「ご飯とおにぎりは別の食品だ」と思うが、同店のおにぎりは「ご飯を握ったモノだ」ということを実感できる。
ご飯を握りつぶすのがおにぎりを作ることではなくて、ご飯を優しく握るのがおにぎりの正しい握り方なのだ。
優しく握るから、ご飯粒は握られたことを気づかないうちにくっつきあって、おにぎりの形を成すけれど、口の中に入った途端にもう一度、自分たちは炊き立ての一粒一粒のご飯粒なのだ、ということを思い出す。口に含んだ途端にハラハラ、おにぎりが普通のご飯に戻って行く。
しかもそのご飯粒一つ一つが微妙に味をまとって口の中に広がって行く。「よし、今度おいしいおにぎりを作ってみよう」という気になる。
ところで、最近のセブンイレブンは、なんだか変だ。
先日、久しぶりに弁当売場を見たら、「焼き鯖寿司」というのがあって、五五〇円という目を剥く値段で棚の中段に王様のような顔をして鎮座している。「買え!」と人に命令するような顔をしてにらんでいるので、買ってみた。そして食べると、そのままの味。鯖を焼いた切り身を寿司飯にのっけただけだった。
鯖と飯の間にガリが入っているのが風味づけとか食感づけだとかの工夫なのだろうけど、そのために本来、一体じゃなくちゃならない魚とシャリが一つにならずバラバラになる。
口に運ぶ前にバラバラになってしまった鯖寿司を別々に口に入れると、それこそ冷えた焼き鯖と味のぼけた酢飯を食べているような気になる。しかもこれで五五〇円だ。
空弁。空港で売っている弁当に実は「焼き鯖寿司」というのがあり、かなりヒットしている。それを臆面もなくパクって売る。飛行場で一〇〇〇円以上で売っているから、町中のコンビニではその半額程度で売る。
一〇〇〇円もする価格に見合ったクオリティーだから買いたいと思う。飛行場という、空に一番近い場所で売っているから買いたいと思う。
いろんな特殊事情を一切合切無視して、料理だけがごろんと目の前に剥き出しになる。つまらなく感じてしまう。
そう言えば冒頭の「ぼんご」。いろいろな人がそれを見て、システム化を図り新コンセプトとして発表をした。
例えば「ony’s」。レインズが手掛けるおにぎり専門店だが、作る人から直接売ってもらえる、というオリジナルの良さを無視して、目先、かっこいいだけのファストフードスタイルにしてしまった。
わかってないよな、と思う。何がわかってないのか? 飲食店の一番大切な部分、ヒューマンビジネスという部分をわかってない、と言うことでしょう。
◆「ぼんご」(豊島区北大塚二‐二六‐三、電話03・3910・5617)
((株)OGMコンサルティング常務取締役)