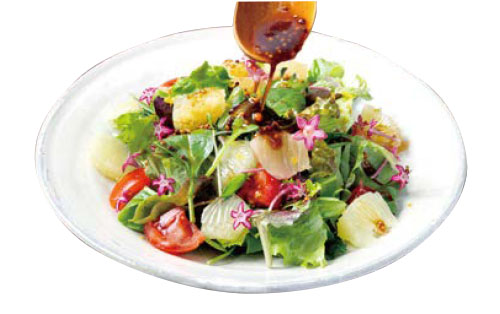絶対失敗しないための立地戦略(21) マーケティングマップの作成
《大分類し、 色別に区分》 周辺商店の全店チェック調査が終了したら、次の作業は、これを分類した商店別に集計、一覧表として作成する。
さらに、この集計表とは別に、でき得れば、全店調査時に使用したのと同じ地図をもう二部作成し、これを、見やすくかつ作業しやすいようにパネル(ハレパネなど)に貼り、このパネル地図の上に、カラーピンやカラー鉛筆などで、もう一度調査した全商店を落とし込んでいく。
この場合、カラー分けにも限度があり、また、より理解しやすくするために、分類した商店をさらに集約して、せいぜい一〇~一二種類程度にまとめることが作業のたいせつなポイント(この場合は、飲食店は一分類として作業する)。
飲食店については、もう一つ用意した地図の上に独自に飲食店調査マップとして作成したい。さもなければ、地図の大きさとマッチした大きな透明シートを用意してこの透明シートの上に、飲食店のみの分布マップをカラー別にして落とし込み、全店調査マップと重ね合わせながら使用しても効果的で良い。
これも全店調査同様かなりめんどうな作業ではあるが、やはり一日もあればできるもの。
このようにしてできあがった全店調査マーケティングマップは、出来上がりを見ていただければ、その効果のほどは一目僚然だ。どの道、どのエリアに、どのような店舗が集中、分散しているか一目で判断でき、その中で、自社、自店のロケーションが、どのような相関関係にあるのか‐‐すぐ判断できる。
これはすでに先述したことであるが、飲食店というのは、サバーバンタイプの特殊店は別として、通常、一般の商店と密接な関係にあり、その商店と一体となり、一般商店の周辺に貼り付いている‐‐それが飲食店の実態であるはず。したがって、自店またはその出店予定地が、この調査した全店調査マップのなかでどのような位置に置かれているかは、実に重要なポイントであるわけだ。
自店の予定地を「最寄品店」(日常の生活をする上で必要とされる生活に密着した商店)が取り囲んでいたならば、そこに出店する飲食店は、すくなくともこの最寄品店のランクに沿った、客単価の比較的安い庶民的な大衆店か、せいぜいふんばっても中級店‐‐のランクで出店しなければ、周辺のカラーに馴染まないものとなり、成功の確率は極めて低いものとなる。
逆に、周辺が、ブティックや高級な専門店群の、いわゆる「買回り品店」で成り立っているゾーンであれば、そこに出店する飲食店もこれに見合った、中級店以上の専門店か、それに準じた店舗であるべきである。
極端な話、豆腐屋や肉屋、雑貨店などの最寄品店の並ぶゾーンに、高級なステーキ屋を出店するか、輸入高級品店、カバン店、画廊ブティックなどの高級な専門店の並ぶ買回り品店エリアに、まっ赤な看板とチョウチンのラーメン店を出店する‐‐と思っていただければ、その奇異さ、不自然さがご理解いただけよう。
(これは後述する、これも極めて重要な要素となるゾーニング(ゾーン分析)とも関連してくることでもあるので、ぜひ行ないたい項目である。)
そんなことはいわれなくとも普段からやっているし、見れば一目で分かるわい‐‐という人は、認識不足である。繁華街というものは微妙に入り組んでおり、複雑にからみあって生きている。これを一目見ただけで分かるなら、失敗する人はあまりいないはずである。メンドウではあるが、この全店調査を行ない、これを地図の上に整理して落として、改めて眺めてみると、実に自店の置かれたロケーションが、ハッキリと鮮明に見えてくるものである。
特に微妙な位置にあるロケーションでは、これほど役立つ資料はない。騙されたと思って一度やってみていただきたいもの。得てして、自己物件、または出店予定地は、頭に血がのぼって判断しているケースが大半で、良い点ばかり頭の中に残り、不利な項目は忘れてしまうものである。
女性(失礼!)でも車でも、家でも同様、一度気に入ってしまうと欠点はまったく見えなくなり、すべて好意的に解釈してしまい、後々ホゾを噛んだ経験をお持ちの方も多いはず。この作業は、それを一度距離を置き、鳥瞰図的に、冷静に、適確な判断を下し、自己の置かれている立場を高所から判断するための作業なのである。
マーケティングコンサルタント
戸田 光雄