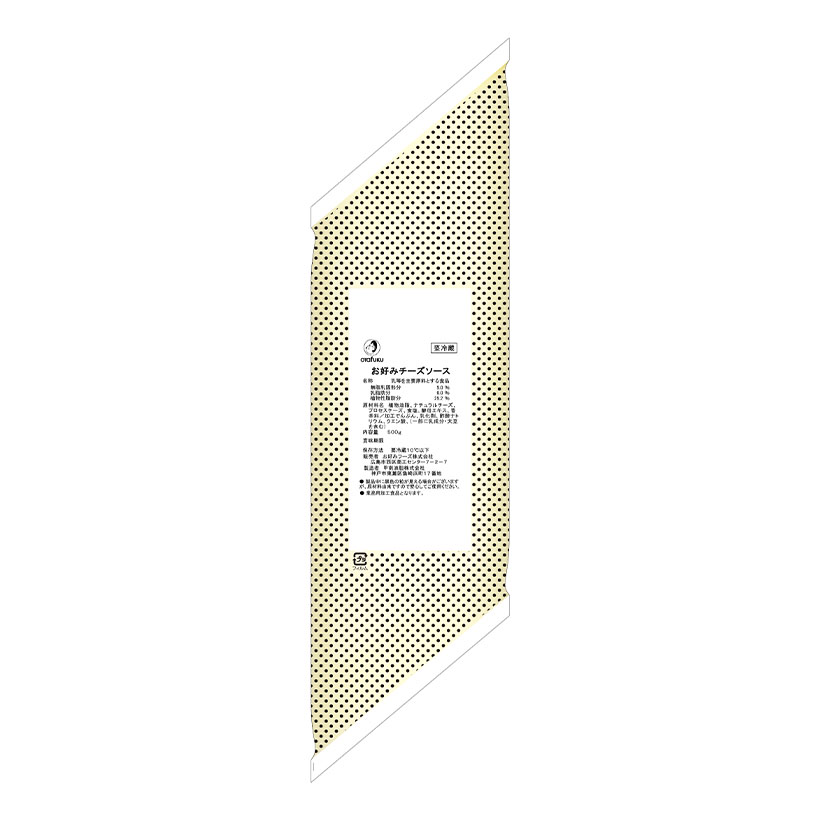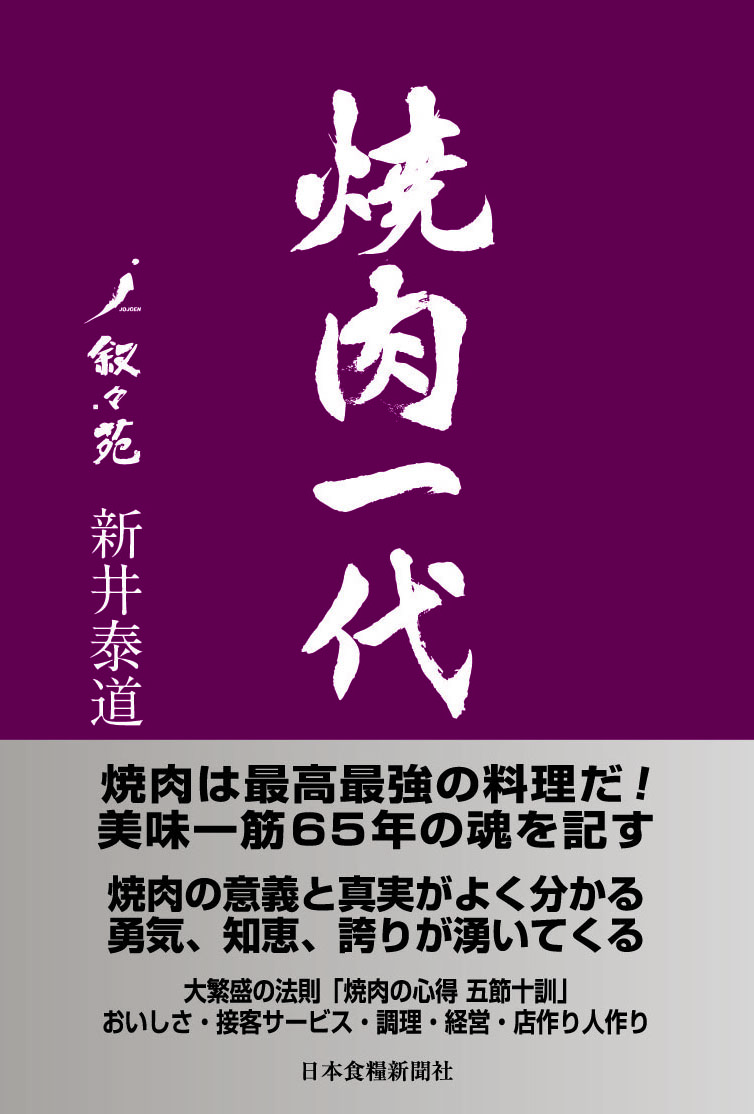食品企業におけるパーパス経営の先進事例:味の素・藤江太郎社長に聞く
◇味の素株式会社 取締役代表執行役社長 最高経営責任者 藤江太郎氏
インタビュアー:新井ゆたか/加藤孝治
インタビュー日時:令和5年12月12日
インタビュー場所:味の素株式会社本社(東京都中央区)
※社名・役職はインタビュー当時のものです。
* * *
新井:御社において中期経営計画を廃止して「2030ロードマップ」を作成しようとしたきっかけと、それを切り替えたことの社内・社外の反応、特に社外では株式市場の反応が知りたいです。また、取締役の位置づけも見直していらっしゃいますが、その影響も教えてください。
藤江社長(以下、敬称略):自分が社長になることを内示されて以降、前社長(西井孝明)と味の素グループの良い面と課題について、意見交換を繰り返しました。社長交代にあたり、まず、2014年に表明したASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)経営を良い点として受け継ぐこととしました。この考えは、社会課題を解決しながら経済価値を生み出すということです。もう一つは、志(パーパス)への熱意、そして一人ひとりもチームも実力を磨き込むという「志×熱×磨」。これも、良い点として受け継ごうと考えました。
一方、大きな課題の一つが「挑戦する企業風土」が以前と比べ弱くなってきているのではないか、ということでした。例えば、長い間策定してきた3ヵ年中期計画。変化の激しい時代に3年先のどうなるかわからないことに対し、非常に精緻に計画や数字を作り込みすぎることで、計画ができた時にはメンバーが疲れきって実行する気力や体力が不十分になり、挑戦する力が弱まっていったという課題がありました。その課題に対して、経営会議でも議論を重ね、計画中心の経営から、2050年の「Picture of the Future」に基づき2030年の「ありたい姿」を創って、それに向けて機敏に打ち手を講じながら実行力を磨き込む経営に変えていこうと考えたのです。取締役会でも議論し2030ロードマップを磨き込みました。
当初は社内でも「大丈夫だろうか?」といった反応もありましたが、経営会議メンバー・執行役・リーダーも各職場で対話を重ね、理解が進みました。かなり多くのメンバーが3ヵ年中期計画に対する課題を感じていたのだと思います。
社外の受け止めも、驚きの声が多かったと思います。3ヵ年中期計画の課題を感じていらっしゃる会社も一定数あるようで、「どのように対応しているのか?」といったお問い合わせを数多く頂いています。
投資家のみなさんには、当年度の業績見通しは継続して対外公表しており、また2025年・2030年の主要KPIについても公表済みですので、概ねご理解は頂けていると捉えており、実行力の磨き込みと「スピードアップ&スケールアップ」が期待されていると思います。
また、一般に、企業集団は縦型組織をとる会社が多く、サイロ化(注:組織の中でシステムや部門が分断され、独立している状態を指す)しやすいと思います。これは悪いことばかりではないのですが、組織が硬直化しがちです。各部門の部分最適が優先され、全体最適視点に問題がでたり、過度な忖度が生まれたり、その結果、挑戦する力が弱まったりすることも多いでしょう。私が心がけているのは、サイロの良さは活かしながら、それを打破する横串を刺して一人ひとりがチャレンジングに自発的にいろいろな仕事ができるようにすることです。
全体最適を考えて判断する
新井:ローテーションが少なくなってきたジョブ型の組織では、サイロがより強くなりますね。
藤江:縦型組織がサイロ化する弊害を乗り越えるために、西井前社長の時代に横串の切り口として、CDO(チーフ・デジタル・オフィサー)を作り、DXで横串を刺そうと考えました。さらに私が務めたCXO(チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー)と、今の副社長の白神が務めたCIO(チーフ・イノベーション・オフィサー)の3つで横串を刺す形にしました。各事業部門の縦軸の良さは活かしながら、機能で横軸を刺そうという試みです。
ただ、この試みは、縦型組織の責任と権限の意識が強かったため、最初は混乱しました。縦型組織の事業部門長にとってみれば、横串を刺すリーダーと考えが食い違うことがよくあります。その解決のために、リーダー同士がしっかりコミュニケーションをとる、そして、それでも決まらない場合は経営会議で議論し決める、ということにしました。さらに西井は、横軸をやっていた人間を縦軸に変えるという人事異動を行いました。私に関して言えば、CXOという横串をやっていたところから、縦の食品事業本部長へと異動しました。逆に、縦軸をやっていた人間が横軸を担当するという人事異動も行いました。
また、縦同士でも、アミノ酸に強い正井(現専務)を食品事業本部長にし、食品に強い前田(現常務)をアミノサイエンス事業本部長に変えています。トップを変えることで縦型組織の良さと横串を刺すことの良さを実現しようと考えた取組みです。その結果、お客様の変化のスピードが速いので、どんどんチャレンジしないと事業が成長していかないことが当たり前になっていたアミノサイエンス事業の感覚が、食品事業の方に活きることになりました。逆に、地域ごとに異なる食文化に応えるように、それぞれのお客さんに深く入り込んで可視化・数値化するという食品事業の特徴を活かしたマネジメントが、アミノサイエンス事業に活かされるようになりました。
私は2017年に経営会議メンバーになったのですが、当時の担当部門は人事と調達と情報の3つでした。その時の経営会議メンバーは私も含めて8割方、自分の担当部門の代表として発言していました。なるべく自分の部門の従業員たちが考えてきたこと、あるいは自分の考えていることを認めてもらいたいということになり、その結果、担当部門の案件に関する発言が多かったと思います。そうなると、各役員は自分がいろいろなことを言われたくないので、自分も相手のことをあまり言わなくなってしまいます。人間にはそのような防衛本能があると思います。これが結局、実はお客様や社会に受け入れられないような予定調和型の意思決定が多くなることにつながってしまう。
こういう弊害を見てきたので、新しいメンバーでの経営会議がスタートしたときに、経営会議メンバーの行動指針というものをみんなでつくって、全体最適を目指すこととしました。例えば、食品事業本部長の専務執行役の正井は経営会議メンバーであり、食品事業の代表であるけれども、全体最適ということで考えて判断していく、というのが一番大事ですよ、という風に考えてもらっています。今は、経営会議の場に10個の行動指針をいつも掲げています。そこには個別最適ではなくて全体最適の経営判断をしようということも書かれています。
新井:経営会議のメンバー構成を教えてください。
藤江:今は11名で構成されており、日本人以外のメンバーが1名、女性が1名おります。また、2022年度までValue Creation Advisory Boardメンバーだった斉藤剛に取締役執行役常務として入社してもらいましたのでキャリア採用のプロ人財も1名おります。今後、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの観点で、こういった人財の割合を、もっと増やしていかなねばならないと考えています。
併せて、経営会議には、社内のメンバーだけではなく、Value Creation Advisory Boardとして3名の社外の方に参加してもらっています。1名は株式会社インターブランドジャパン代表取締役社長兼CEOである並木将仁氏です。彼はブランディングの専門家です。次に、見えない資産を可視化して企業価値につなげることが得意な株式会社バリュークリエイト社長の佐藤明氏。もう1人がパナソニック株式会社の前執行役員、サステナビリティやイノベーションに長けた馬場渉氏です。今まで経営会議は、味の素社のメンバーのみでしたが、これらの方に入ってもらい、外部の意見を取り入れることにしました。また、経営会議に審議をかける従業員もオブザーバーでの参加を可とし、Webを通じていろいろな人が聞いてもいいようにしています。そうすることで、経営会議でどんな議論をしているのか、従業員もよくわかるようになります。また、意識的に経営会議メンバー以外の方からも意見を聞くようにしています。
新井:経営会議をオープンにしているのですね。
手挙げ型・自発型で挑戦する
加藤:新たな取組みを2019年から2023年の時期に進められたということですが、内容をお聞きするともっと以前から取り組んでもよかったように思います。この時期に取り組んだ背景を教えてください。
藤江:企業価値を継続的飛躍的に上げ続けることが、当然従業員の幸せにつながりますし、マルチステイクホルダーの期待に応えることにもなります。しかし、2019年頃までの数年間は業績も低迷し、企業価値が上がらず、時価総額が1兆円を下回ることもあり、社外、特に投資家からの強い批判にさらされました。これはある意味健全なことなのですが、批判はトップに集中的にやって来ます。それで、リーダー層や従業員にも疲弊感がただよってしまっていたのです。
新井:外部から批判されていると、その雰囲気が社内を覆うわけですね。
藤江:この苦境を大きく変えることができたのは、西井の2019年の覚悟が起点だったと思います。
新井:この時期に比べて、今は時価総額が本当に3倍になりましたよね。
藤江:例えば、投資家とのコミュニケーション(IR)の方針を大きく変更しました。当社では、電子材料事業にも取り組んでおり、味の素ビルドアップフィルム(ABF)という、層間絶縁体を取り扱っています。この製品は、パソコン・携帯電話・サーバー向けの半導体の層間絶縁体として、95%を超える圧倒的なシェアを有しています。以前は、そのことをIRではあまり触れておりませんでした。対外公表することで競争が激化することを恐れたからです。しかし、それをうまく社会に理解していただきながら、競争力を向上させ続けることが重要であると考え、IR方針を変える覚悟を決めました。
根底には、もともと強かった挑戦する企業風土を再生したかった、そのためにもやらされではなく、手挙げ型・自発型で新しい事業や製品・サービス開発にどんどん挑戦してほしいという想いがありました。そして、それが企業発展の原動力になると考えたのです。
加藤:今、御社の取組みの中で、従業員たちのマインドを変えたことが、大きく会社の価値を変えていったということでしょうか。
藤江:はい、その通りです。当社では、企業発展の原動力は、無形資産の一つ、人財資産だと考えています。資産には有形資産と無形資産がありますが、有形資産である設備や在庫についてはできる限りアセットライトにしていこうとしています。一方で、より大事なのは無形資産の方です。当社では無形資産を、人財資産、技術資産、顧客資産、組織資産の4つに分類しています。そして、とりわけ人財資産が企業発展の原動力であり、これをより豊かに、元気にする取組みを、いろいろな形で行っています。
人財資産を豊かにする取組みの一つは、AGES(Ajinomoto Group Executive Seminar)と称している役員研修の進化です。以前は役員だけでやっていたのですが、2021年からは、参加希望者を手挙げ型で募集し、一般職のメンバーや、マネージャーにも入ってもらって一緒に我々の将来を考えるようにしました。
加藤:無形資産を増やすことが会社にとって大事なことであり、その無形資産を増やすために、社内のいろいろな考え方や制度を変えていったということですね。会社の目的を、利益を追うということから、無形資産を貯めて潜在的な力を蓄積させることが大事だという風に見直したということでしょうか。
藤江:当社はASV経営を進めており、社会課題解決と経済価値の共創を大切にしています。その意味では利益を追うことも大切です。一方、利益を生むための原動力は無形資産、とりわけ人財資産が重要だという考え方です。果実を例にとると、土壌をしっかり作って、種をしっかりまいて、水やりとか手入れをしっかりやって初めて、おいしい実ができますよね。その考え方と一緒だと思います。一時期、目先の利益を追いがちになって、果実をどう刈り取るかといったようなところにかなり集中してしまいました。やはり人間、そうなりがちだと思います。経営者として短期業績にも責任はありますが、中長期のための土壌作りや種まきや手入れが非常に重要だと思います。
新井:それぞれの従業員の方が挑戦する機会をいろいろ提供したことで従業員の方々は変わりましたか?
藤江:まだ十分とは言えませんが少しずつ進化してきていて、企業文化が自発型でどんどん挑戦していくような風土になる胎動を感じています。意識が変わってきている人たちの割合は、肌感覚ですがまだ1割くらいでしょう。
どんどん挑戦していく取組みや改革は、ある一定の割合までは「何やっているんだ」と後ろ指を指されることもよくあると思います。これが、意識が変わった人が2割ぐらいになれば、意識が変わった人、無意識の人、絶対変えようとしない人の割合が、2対6対2の水準に達し、会社全体の自発型でチャレンジングな風土が一気に加速していくと思います。当社では、エンゲージメントサーベイを毎年行っていますが、その中でも今申し上げたような取組みが発展途上にあるという結果が出ています。もう少し進むと、「後ろ指を指されることを恐れる人が一定数いる」という状態から「この指止まれ」みたいに自発型でチャレンジングな企業文化になってくるのではないでしょうか。こんな風に進めるのが面白いと考え、変わっていく人が出てきていますのでとても楽しみです。
新井:一般的に組織の中で変革をしようとする人が3割いると無視できなくなるので、そのために組織を変えていかないといけないということになる。社長が交代されてからの期間で1割になっているということですので、今後、相当に上がってくるのではないでしょうか。
藤江:こうした変革の取組みを私だけでやっていると独り相撲になるので、経営会議メンバーがワンチームでどういう風にやるのか、それぞれの組織長がどうするのか、ということも大事です。例えば、手挙げ型の施策である公募での異動や、プロジェクトへの参加の募集、自発的に挑戦してイキイキ仕事をしている従業員にもっともっと光を当てていくといった具体策に取り組んでいくことも大事だと思います。
加藤:新たな取組みへの変化は部署によって違いがありますか。
藤江:まだあると思います。今、味の素社というと食品会社というイメージがあると思います。以前は売上げも利益も9割程度は食品事業部門が生み出していました。これが2021年段階では、3分の1がアミノサイエンス事業部門で、電子材料やバイオファーマサービスなどが担うようになっています。もちろん、食品事業部門も安定的にオーガニック成長で一桁後半ではずっと伸びていくと思いますが、アミノサイエンス事業部門は2桁以上でかなり伸びていくのが見えてきています。このまま進めば、2030年には食品事業部門とアミノサイエンス事業部門が利益ベースで1対1ぐらいになります。
そうなると、単なる食品だけの会社でもないし、単なるアミノ酸メーカーだけでもないというユニークな会社になります。そのベースが創業以来のアミノサイエンス®です。この言葉は造語なのですが、アミノ酸の働きに徹底的にこだわった研究プロセスや実装化プロセスから得られる多様な素材・機能・技術・サービスの総称です。1909年に当社がうま味調味料「味の素®」の発売を始めましたが、これは、グルタミン酸ナトリウムというアミノ酸でして、創業以来、アミノ酸の働きを徹底的に探求し続けています。私もアミノ酸ファンなのですけれども、アミノ酸フェチみたいな従業員が社内にはいっぱいいます。アミノ酸のことを語り出したら止まらない。それが技術分野の人だけではなくて、マーケティングとか営業の人でも好きな人が多いのです。このアミノサイエンス®を大切な基盤にしながらいろいろな取組みをやっていると、ユニークな会社になれるのではないかと考えています。
一人ひとりに光を当てる
新井:創業のところがすごい最先端産業だったのですね。そういう意味ではもとからユニークな会社だったのでしょうが、時が経つとなかなか続かないですよね。創業の事業が衰退したりする例もあります。御社の場合は、不思議な会社と言えると思います。そして、その不思議さが今活きている。
藤江:「人を大切にする」という味の素グループWayのおかげかもしれません。その一部でもありますが、対話好きの企業文化というものがあります。私も当然やりますし、経営会議メンバーもやります。リーダーのみならずメンバーも、対話を大事にしています。時には、車座になって対話することもあります。また、今はデジタルがかなり進んでいるので、対話好き文化が更に進化してきているとも感じています。社内版SNSのWorkplace上には「私が語るASV」というコーナーがあり、「今、こんな取組みやっています」とか、「ASVに対して、こんなやりがいを感じながら、こういう形で自分は取り組んで、こんな成果が出ました」といった事を自分から語ってもらっています。また、そういった投稿に、世界中の仲間たちが共感や応援のメッセージをレスポンスしてくれています。一人ひとりになるべく光を当てていこうというのも企業文化の中にあり、いい取組みにスポットライトを当てようよ、みんなで横展開しようよ、という意識も従業員にあると思います。
こういった組織文化は、最近生まれたのではなく、企業文化として以前からあると思います。それを言葉にしたのが、味の素グループWayです。「新しい価値の創造」「開拓者精神」「社会への貢献」「人を大切にする」。この4つは、やはりすごく大事にしている会社だと思います。ただ、以前に比べると「新しい価値の創造」と「開拓者精神」が弱くなっているように感じます。日本における世の中の流れということもありますが、当社についてもそれが弱くなっている可能性があります。これをどういう風に強くしていくのかということにもぜひチャレンジしていきたいと考えています。
新井:味の素グループWayを従業員の皆さんに共有したのは、いつ頃ですか?
藤江:味の素グループWayができたのは2009年です。ASVを発表したのは2014年なので、その前から、ということになります。
細かな話となりますが、このASVの指標は経済価値と社会価値を同列にしています。どっちが上とか下とかではなく、経済価値と社会価値を共創する、ということです。より大きな経済価値を創出できれば、それを更に大きく、更に多くの社会課題解決に活用できますね。その循環をもっと「スピードアップ&スケールアップ」したいと考えています。
ASVについての議論は2005年にスタートしました。もともと、当社には、社会課題を解決しながら経済価値を共創しようという社風はあったのですが、こういった価値をCSV(Creating Shared Value)と呼びはじめました。これは、マイケル・ポーター博士が提唱するCSVに相当するもので、経済価値を生み出すことによって、より多くのより大きな社会課題も解決できるという考え方です。このCSVの味の素グループ版をASVとしたのです。これを取り上げた当初は、多くの従業員が社会課題の解決の方に重点を置いていました。その結果、いいことをやっているけど、この取組みは本当に経済価値が出るのだろうか、という疑問が生まれてくる。
例えば、2016年まで味の素社がガーナで展開していた「KOKO Plus®」(ココプラス)という非常に素晴らしい製品があります。その地域には低栄養の方が多いので、アミノ酸を補助して子供の頃から栄養価の高い食事をすることで発育が良くなるという母子健康栄養改善の事業です。これは社会貢献としては素晴らしいものでしたが、事業としては市場規模が小さく、黒字化することが困難で、ASVを体現している事業とは言えませんでした。社会貢献の高い事業も経済価値を共創できるようになってASVに進化できればいいなと思います。
なお、現在「KOKO Plus®」は、公益性の高い社会貢献事業として、2017年に設立された公益財団法人味の素ファンデーションに移管され、同財団が独自の戦略構築を行い、公益を目的として事業活動を継続しています。
加藤:CSVについて考えたときに自分たちの儲けよりも、まず社会的課題をどう解決するかという方向に進んだのですね。
藤江:そうですね。社会課題解決の中に多くの経済価値創出の機会があると思います。
新井:御社は社会課題解決のもう一歩先を行っていて、その中でも選別してファンデーション(注:社会課題を解決する事業に特化し、公益のために事業運営を行っていくこと)で取り組むものと本業で取り組むものを分けている。本体で集中するものとファンデーションに移すものとを明らかに区分されていたのはとても驚きました。
社会価値と経済価値を同列に考えている人が、まったく違うところに軸を置いて、社会価値の追求ということだけを、CSRの発展型みたいに行っている会社が多いのが現状です。収益性ということを考えずに行っていて、御社の10数年前の段階にいる会社が多いということでしょう。そこを峻別して事業としてやるべきものは何かというところに到達してる会社はまだ少ないと思います。
加藤:形から入る会社に対し、御社はもうそんなことを言ってる場合じゃないよという水準にいるということなのでしょうね。
藤江:社内的な取組みとしては、毎年実施しているASVアワードというのがあります。この中で、評価対象の案件に対し、経済価値はどれだけ出ているのか、ということを厳しく見ています。最初は経済価値があまり出ていないような取組みもASVアワードの対象になっていたと思いますが、最近は、会社全体でのASVへの理解も深まり、一定の経済価値が出ていない取組みは表彰対象にならないようになってきました。
My Purposeと会社の「志」の重なりを見つける
新井:一般的に従業員の方々が新たな試みに取り組もうというチャレンジ意識について、会社としてバランスを取ろうとルールを作ったりします。例えば3年経って赤字だったら、取組みを見直すなど一定のラインを作るといったものです。御社においてはチャレンジのバランスをどのように考えていますか。
藤江:人間はどのようなときにチャレンジするかと考えると、本能的な部分にもなりますが、自分を振り返ってみても、ライフワークや生きがいといった自分の「志」に重なるような部分については寝食を忘れて取り組むと思います。味の素グループの新たな「志」を「アミノサイエンス®で人・社会・地球のWell-beingに貢献する」としています。Well-beingとは健康で幸せな状態という定義です。味の素グループの「志」は割と広い概念なので、従業員に対しても、「みなさん自身の人生の「志」と味の素グループの「志」の重なりを見つけてみませんか」と話をしています。重なりが見つかると、そこがやりがいにつながると思います。やりがいや生きがいにつながるような仕事だったら、自然に「挑戦しようぜ」という感じになるんだと思います。
最初から「挑戦しよう」といった感じの挑戦というのはやらされ感もあるのであまり長続きしない。内面から自発的に出てきて湧き上がっていくようなものがあり、それをどういうふうにして、みんなで自然に引き出されていくのかというのが大事だと思うのです。今年の役員研修でも、経営企画部が良い企画を考えて実行してくれました。それは、My Purposeを紡ぎ出すことを目的としたワークショップです。執行役25名全員が一人ひとりのMy Purposeを明文化して、みんなの前で発表する。
そうすると、「あなた、そんなこと考えてたの?」とか、「あなた、そんな趣味あったの?」とか「あなたは修羅場に追い込まれながらも、本当に人生を苦労して乗り越えてきたんだね?」というような日頃の業務からだけではわかりづらい、その人が大切にすることが理解でき、共感が湧いてきます。もう聞くも涙、話すも涙といった発表もありました。そのような機会を通じ、その人の「志」の熱意に打たれて、自分自身の熱意も紡ぎ出されていくようになるのです。私ももちろんMy Purposeを創りましたけど、よかったですよ。
加藤:社長のMy Purposeがあって、他の役員のMy Purposeがあって、それぞれが「あの人はこういうこと考えているんだ」と思い、自分のMy Purposeと他の人間のMy Purposeが組み合わさって、Our Purposeになってくるという紡ぎ出しができてくるということですね。
新井:「Purpose」を標榜すると、従業員はみんなそれに合わせなくてはいけないと考えてしまい、すごく苦しい会社になってしまうように思います。「自分の思いは違うんだけど」と思うと、逆に会社の中に閉塞感を作ってしまう恐れもあります。特に日本人は、はみ出していいということにはならないですから。自分のやりたいことを表明できることで、これから楽しいということになるのですね。そして、この取組みを少しずつ従業員に広げていくということになるのでしょうか?
藤江:まずは執行役25名からはじめて、これから広げていこうと考えています。先日も人事業務に関わる国内外のメンバーが集まる会議の場でMy Purposeを明文化するワークショップをやってみました。日本人だけではなく、海外の人たちも多く参加したワークショップだったのですが、大変好評でした。今後、ある程度の期間粘り強く続けていこうと考えています。ASVを始めた時も、やはり息の長い取組みとして始めました。最初は「ASVって何?」ということを、ワークショップ的に全員が議論する会合を実施しました。1回あたり30から50名程度参加するもので、これを繰り返しやり続けました。ある意味しつこいところがあると思いますが、今回の「志」を共有する取組みも、息長く継続していきたいと思います。
会社から言われたのでMy Purposeを創るというのではなく、自発的にMy Purposeと味の素グループの「志」の重なりを見出していってもらいたいと考えています。というのも、会社というのはどうしても「Yes, sir!文化」があると思うのです。私は「前向いて後ずさり」と表現しているのですが、やらされだと、表面的には「Yes, sir!、いいですね!『志』、いいですよ」とは言ってくれますが気持ちとしてはもう後ずさりする人が多いのだと思います。私はそういうのが人間の本能なのだと思います。防衛本能ですね。
当社では、やらされではなくて、自発的に重なりを見つけて「志」に火がついて頑張っている人たちが生まれてきています。今の時点ではまだ1割くらいだと思います。その人たちにスポットライトをいろいろなやり方であてています。2割を超えてくると会社が大きく進化していくのではないかと思います。
加藤:そのような意識変化は、どのようなセクションにおいて早く変わっていますか。中心ではなく、外部・周辺部から変わっていくという感じでしょうか。
藤江:やはり海外が早いですね。先日訪問したベトナムでは、私も「すごい!!!」と思うくらい進化していました。多分、海外の方が変わりやすいですし、それらにも刺激を受けて日本の中も変わってきていると思います。
新井:海外のほうが、仕事に対するMy Purposeがよりはっきりしているかもしれませんね。やはりジョブ型の方が、自分の業務がはっきりしていて、自分がこの会社で何をできるかなどの意識をきちんと言葉で表すことができるのだろうな、という感じで捉えています。
藤江:どの会社でもよくあることだと思いますが、日本の本社で働いている人たちは、多層階の意思決定や社内調整で疲れてしまいがちなではないかと思います。仕事はしんどいし、複雑だけど、本社の仕事もやりがいがあるね、どんどん挑戦できて、こういうところが楽しいね、と思えるような従業員をもっともっと増やしていきたいですね。エンゲージメントサーベイでも課題が浮き彫りになっている「意思決定が複雑」といった項目も改善していくことで、実現できるのではないかと考えています。
加藤:会社組織の中心で、保守本流みたいな感じで考えている人の方が変わりにくいということですね。上は危機感がある、と周りがそういう文化を持っていて、変わりにくい保守本流の人が変わらなきゃ、というふうに見えると、パタパタと変わっていくということなのですかね。
藤江:そういう辺境から変わっていくという部分があると思うので、辺境をどう意識的に変えるかということも意識しています。
また、取締役会も西井の時に指名委員会等設置会社にして、社外取締役の方に議長をやってもらい、指名委員会、報酬委員会、監査委員会なども社外取締役の方が多数になるということで、キャスティングボードを社外に委ねることにしました。これは、ものすごい覚悟だったと思います。執行役の任期も変更し、一年にしました。こうすることで、一年一年が勝負になるし、社外の方々に背中を押してもらうことで変革がより進むと判断しました。
更に、2022年の指名委員会の中で私がCEOに指名された時、CEOのサクセッションプランを作りました。候補者一人ひとりのCDPプラン(Career Development Program(キャリア・デベロップメント・プログラム))を作っていますが、なるべくしんどいところや辺境に意図的に送り込もうとしています。私も赤字の中国やフィリピンでの仕事を通じて様々なことを経験し学ばせて頂きました。
CEOだけではないですが、辺境でいろいろな変革を行ったり、あるいは辺境で頑張っている人たちがいろいろな影響を受けたりすることで、さらに成長してもらう。そういうところから本体の方に変革が及んでくることを期待する。そういう流れは確かにあると思います。
新井:海外はある意味で辺境の業務ですよね。従業員以外の人との関係を考える必要があり、海外市場と交渉することなど、日本国内のホームの考え以外のアウェイの考えを取り入れていかなくてはいけないですよね。逆にそうしないと会社は変わらないような気がします。
なお、思い出話になりますが、自分が就職した最初のころに、上司に「仕事は趣味のようにやれ」と言われました。仕事を仕事のように思うと楽しくなくなるから、趣味のように捉えられれば、ずっと楽しくなるということです。仕事の中に趣味の要素を残すということは大事だと思います。
ステージゲートを設ける
新井:さきほど社長がサイロ化のお話をされたことと、今の横軸を動かしていくという話は根っこが同じだと思うのですが、御社は結構大胆にポートフォリオの変更をされていますよね。ポートフォリオの変換はやはりサイロ化と横軸のバランスの中で自ずと出てきたものですか。
藤江:そうですね。縦型組織がサイロ化すると自組織だけではポートフォリオの大胆な進化は行いづらい面があると思います。当社は資産効率の低い有形資産のアセットライト化というのが上手くない会社だったと思います。西井前社長の時代の2016年から2018年の頃、アセットライトの取組みが1歩から3歩遅れ、企業価値が落ち、投資家からの信頼も低下してしまいました。それをふまえて西井が覚悟を決めて変革へのリーダーシップを発揮しました。そして、資産効率が著しく低下した分野でアセットライトを進めました。またこの取組みは1回やったら終わりではなく、永遠にやり続けないといけませんよね。だから、私が着任し新しい体制になってからも、事業ポートフォリオの考え方を再度議論したのです。
以前は縦軸が成長性、横軸が効率性だったのですが、これだけだとやはりいかんという反省がありました。そこで、縦軸を2030年から2050年位の時間軸で見た、中長期の成長性に変えることにしました。横軸は効率性ではなく、競争優位性で考えることにしました。特に当社の特徴であるアミノサイエンス®が活きる分野を考え、その強みをどういう風に活用したら競争優位性を確立できるのか、できる限り中長期視点で競争優位性の高まる分野に事業ポートフォリオを進化させていこうと考えたわけです。まだ競争優位性が足りないものについては、ステージゲート管理をしていくことも決めました。企業経営としては、非効率な事業や法人を素早く判断し、すぐに売却や撤退するというのが合理的という意見もありますが、ステージゲートの真の目的は、いつまでにどのくらいまで進化させようという目標や期限を定めて努力することで実力が磨き込まれて事業や法人の価値が「スピードアップ&スケールアップ」することだと考えています。
また、事業に思い入れのある人たちの人財資産を引き出すことも重要です。その際には、感情に流されるのではなく冷静に判断をすることも重要です。例えば、日本のある事業の場合はステージゲートを設けて、「2年の猶予期間を与えるから、来年の3月までにここまで到達しよう、再来年の3月までにここまで到達しよう」などと決めるのです。そのうえで、その基準に到達しなかったら、それはもうベストオーナーは我々じゃないからやめるよ、と判断するほうが良いと考えています。これは欧米の会社からすると、特にアメリカ型の会社からするとスピードが遅いということでダメ出しを食らうかもしれません。しかし、私はステージゲートを設けるのが日本企業の地力を引き出すにはいいかなと思っています。実際、日本のある事業は、「数年後にここまで到達しない場合は撤退する」ということも視野に入れていたのですが、今では大きく業績が向上したという例も出てきています。
ただし、一旦窮地に追い込まれた事業というのは、期待するステージゲートの水準にはなかなか行きづらいこともあります。その時には、その事業のリーダーには、悲観的に準備し、楽観的に取り組む重要性を伝えています。例えば、アメリカの冷凍食品の事業がコロナの時にものすごく苦しんで赤字になり、いくつかの工場を閉めているのですが、その時には、責任者も自主的に工場数の削減に取り組んでくれました。その結果、現在では大きく業績が改善しています。
加藤:その事業から撤退しなくてはいけなくなった部門のリーダーには、その方針が伝えられるわけですよね。リーダーは認識しながら、部下たちには頑張れと言い、最終的にはやはり無理だな、と、部門全体の人たちが自分を納得させるような時間を作っていく感じですね。
藤江:私にも経験がありますが、事業責任者や法人長にとって、現場の一人ひとりの顔が見えますから撤退はしづらいことなのです。ただ、いくら頑張っても改善しづらいとか、その事業のベストオーナーは当社ではない、といったことはあります。
ですから、現状の困難さを「見える化」し、ステージゲートを設けて人財の力を結集して乗り越えられるかどうかに挑戦してみることが重要ですね。たとえ撤退になったとしてもその努力と取組みはメンバー一人ひとりの実力向上につながると思います。そして次の方針決定の選択肢を増やすことにもつながると考えています。事業ポートフォリオの進化は経営トップが全体最適で冷静に決定し実行していくことが重要だと思います。
加藤:大胆なアセット圧縮に向けた取組みや、会社全体の方針をアセットライトに向けていく意識変化などを考えると、今は大きく変えていくことと、その変化を浸透させていく意味で、苦心されていると思います。こういう時に、社内での意識変化が1割ぐらいかなとおっしゃっていました。また、パーパスの浸透や見直しということも必要ですが、この状況は社長としてどう評価されますか。
藤江:現状は滑り出しとしてはまずまずの状況だと思います。まだ1割程度だと思いますがもう少ししたら、3割に至って、自発型で挑戦をし続ける企業風土に向けて、全体が変わっていくという時が来ると思います。
2023年2月に「志」を「アミノサイエンス®で人・社会・地球のWell-beingに貢献する」に進化しましたが、その「志」の浸透もまだまだこれからだと考えています。会社の「志」が腹に入ってくるというのは、「志」の重なりが見つかり、自分の「志」と合致していることをやって、これってやはりWell-beingだなと感じるということですよね。
Well-beingに関しては、面白いデータがあります。当社が米国の調査会社Gallup, Inc.と連携して行った調査で、週に4回以上共食している人(誰かと一緒にランチやディナーを取っている人)は全然取らない人に比べてWell-being度が60%高いという結果が出てきたのです。また、料理を楽しむ人はそうでない人に比べて2割Well-being度が高いという結果もあります。こういった知見は、味の素グループで食を通じたWell-beingに貢献したいと考えている多くの従業員の取組みの確からしさを、データによって後押ししてくれるものでもあります。
また、グリーン(フード)ビジネスに従事している従業員は人や社会のWell-beingに、グリーン(アグリビジネス)ビジネスに従事している従業員は、地球のWell-beingに関わっています。先日、タイにある味の素FDグリーン(タイランド)社を訪問したのですが、そこではアミノ酸を製造した後の副生物を肥料にし、キャッサバ農家への技術支援なども通じて、収穫量向上や収入増に貢献しています。そして、そこで働いている人はものすごく目をキラキラさせながらエンゲージメント高く働いています。まさに、人・社会・地球のWell-beingに貢献しているんだという意識で働いています。また、社内にインフルエンサーが自発的にたくさん出てきています。
新井:対話とか議論を通じて進められるのは、実行するだけの余力があるということだろうと思います。この部分に意識を割いてくれる豊富な人材を有していることが大事ですよね。余裕がない状況で人的資源の開発に取り組むといってもなかなか実現しない。御社はその時間と人的資源を持っているということも、各社から見ると羨ましい状況だと思います。
藤江:人財資産に関しては、「人を大切にする」という観点からもこれまで磨き続けてきました。味の素グループWayは100周年でスタートしました。節目の年にあたる2009年ですね。しかし、この後も事業的には調子の良い時期もあれば良くない時期もありました。良くない時期はどうしてもエンゲージメントが落ちてしまうことがありました。それらも反省点にしながら、味の素グループの発展の原動力は無形資産、とりわけ人財資産であるとし、自発型でチャレンジングな企業風土への進化に向け、取組みを終わりなき旅で継続していきたいと考えています。
新井:本文に現れないものを、インタビューを通じて皆さんにお伝えできたのではないかと思っております。ありがとうございました。