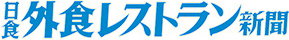シェフと60分:日本料理「田村」調理長・佐藤正夫氏
「建築では、昔は書院造りや校倉造りといった特徴的な建築方法があったけど、今はみんなビルになっちゃってどれも一緒に見える。料理も今様の食べ物は、手抜きをすることが多くて何の料理かわからないこともあるよね。それはそれで、その店としてはいいと思うんだけど、私にはできないんですね。どっかで線を引きたい。日本の食文化をきちんと守っていきたいというか。お惣菜や冷凍食品なんかを使うときもひと手間かけて、仕事をしてから出したいですね」
これだ、という伝統の味があるわけではないが、食文化としての日本料理を歪んで変えたくない気持ちを持ち続けている。
「中学の時からコックになりたかったんです。それも豪華客船に乗ったコックに。だって、世界中を旅できるじゃない」と料理への原点を語る。
高校を卒業して海上自衛隊の料食班を希望するが、航空自衛隊の方へ配属された。二年間働くがその間、日本食の道を進めてくれた知人の話を聞いて、虎の門の日本料理屋へ修業に入る。
「そしたらもう、コロッと考えが変わっちゃった。給料は自衛隊の半分だったけれど、船の上のフランス料理よりも、日本食だ、と思いました。奥が深いというか、日本文化に触れたんですね。そこで一年ほどお世話になって、その後は調理師会に紹介してもらって日本橋の畔居に入って修業しました」
胡丁を経て、二八歳で料理長になる。二一歳で入って七年というスピード昇進。
「人より努力した、ということはなかったと思うんだ。ただ、運がよかっただけで。でも、親方になってからの方が大変でしたね。教わったことじゃなくて、自分で考えてつくることが多くなったからね。例えば、昔の日本料理って旬のものしか使わなかった。水菓子だって旬のフルーツというように。でも、今はゼリーやシャーベットのように新しいものをどんどん取り入れているでしょう日本食も。そういうのは教わっていなかったから、苦労しましたよ」
料理長になってからは新しいものを受け入れると同時に茶道、華道といった、文化も習った。
「あの世界は変わらないところがいいんですよね。一〇年やったけど、礼儀、あいさつ、言葉づかいを学べました。がさつにならないっていうのは、料理にも生きたと思います」
お茶をいれる人、食事をする器をつくる人、食事をつくる人、お花を生ける人、茶事は生活そのものを結びつける。そうした一連のことを簡素にめでることが、日本料理のなかにもあり、奥深いといわれるゆえんとなっている。
厨房には現在一一人の弟子たちが働く。
「僕自身は洗い場から始めました。半年くらいで見習いを卒業したけど、なんでかっていうと、先輩の望むことをよくこなしたからだと思います。だから、用事が多くて大変でしたね。一日三時間、四時間の睡眠時間でしたから」
「でも、やっぱり二〇代の独身のうちに仕事は覚えるといいね。年をとってくると、どん欲に求めなくなるからね。家族をもったりすると特にね。比重がどうしてもそっちにいっちゃうからね。鉄は熱いうちに打て、っていってね。その時期にのれなければやっぱりだめだろうね」
新人に必要なことは「あいさつと返事」とシンプル。
「今の子はあいさつと返事ができないんだね。だから、会話ができない。コミュニケーションがとれない。それができていれば器用さなんてあまり関係ないと思いますよ。そんなものはあとからついてきます。あいさつができて、掃除ができれば徐々にできてきますよ」
巣鴨という土地柄もあるが、年配のニーズにこたえる店づくりを心がける。
「年寄りでもステーキの好きな人います。でも、突き詰めていけば煮物なんかの火の通ったものを好みますね。それとご飯。茶事でも先に出てくるように、やはりご飯が原点なんだと思います」
「何か食べたり飲んだりした後でも、ちょっと食べられるのはお茶漬けやおすしだったりするし、一日一食は食べたいとだれでも思っているんじゃないですかね。日本文化の基本を変えずにいたいというか、お造りがあって、味噌汁があって、ご飯がでてくる。それから煮物や揚げ物という昔から続く日本食文化の基本をこれからもつくっていきたいですね」
目まぐるしく変わっていく中で、変わらないものを求めている。
◆ 昭和26年12月生まれ。出身は山形県。豪華客船でコックになりたいと中学生のときから志し、二一歳で和食の世界へ。日本料理店を二、三軒経験し、二八歳で料理長になる。新しい料理と、茶道・華道といった古い文化を同時に学び、自分の料理を確立する。
家族は、妻と三人の子ども。二二歳の長男と一八歳の次男は、二人とも日本料理への道を選んだ。
「やめろっていったんですけどね。苦労がわかるから。それでも選んだんだから、頑張ってほしいとは思っていますよ。将来三人で店を構えることは絶対にないだろうけど、会話があうのは楽しいですね」
文 石原尚美
カメラ 岡安秀一