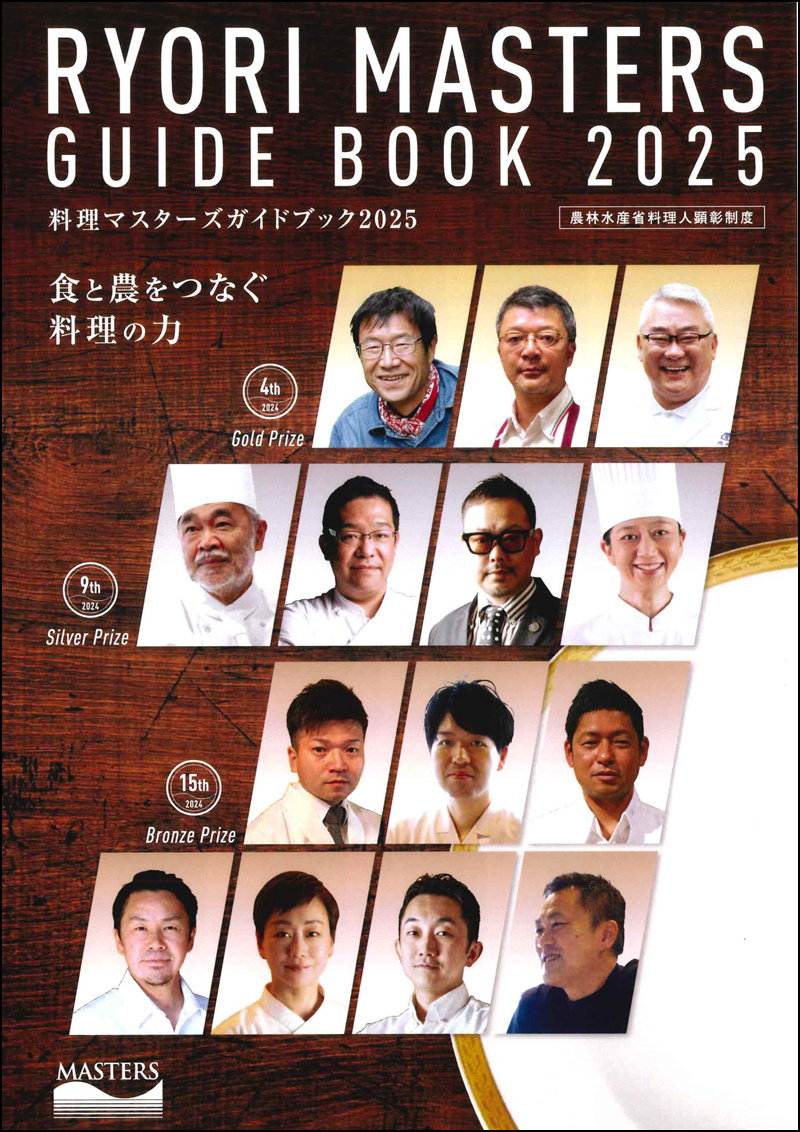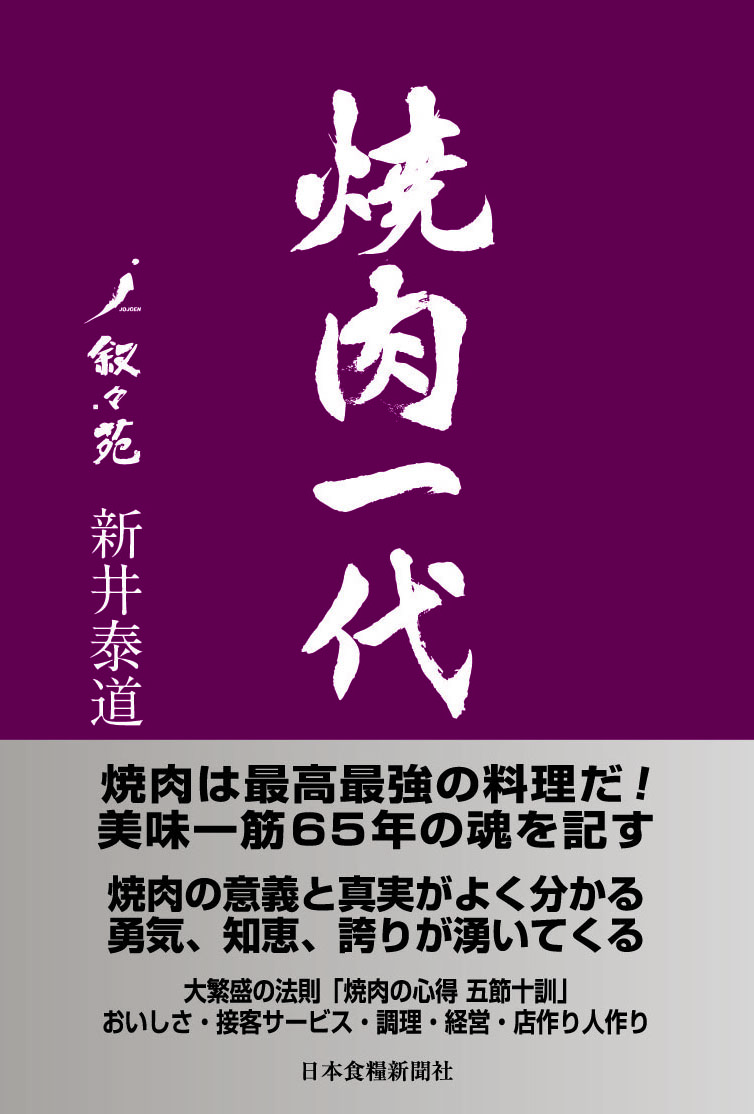忘れられぬ味(11) キユーピー相談役・藤田近男 新宿更科と万盛庵
私が学校を卒業して社会人になったのは昭和24年であり、なんとか食糧事情も改善され戦後の最悪期を脱した時代であったが、会社の仕事の方は戦後再開したばかりであり、連日夜遅くまで頑張らざるを得ないような状態であったのである。従って仕事が終わり会社からの帰りの道すがら、キユーピーの創業者の中島董一郎が、現在はJRの新宿駅の一角になっている、いわゆる新宿西口商店街の狭い路地に面した「新宿更科」という蕎麦屋に私達を連れて行き、遅い夕食のごちそうをしてくれるのが一つの慣行になったのである。
「新宿更科」というお店は木造で間口が狭く、とてもたくさんの客が入れるようなたたずまいではなかった。そこで私は細長い筆箱状の蒸篭に盛ってあるさらした蕎麦と天麩羅蕎麦と二人前をいただき、若い胃袋を満たしたのである。さらしてあるからうどんと見まがうほどの白い蕎麦そのものの旨さ、そしてコクのあるタレとのバランスが絶妙であり、戦後の食物の不自由な時代というハンディキャップを加味しても、私には忘れ得ない味の一つである。それから数年後、家内との婚約時代(昭和32年)に「新宿更科」の味が忘れられず、わざわざ食べに行き、私の舌の確かさを二人で確認した。
現在「新宿更科」は駅周辺の再開発によって廃業したのか、どこかへ移転してしまったのか不明であるが、今でもどこかで営業しているのであれば、たとえ遠方でも今一度食べに行ってみたい味であったと家内と話し合っている。
もう一軒も私の自宅(京王線千歳烏山)の近所にある蕎麦屋である。「万盛庵」といい、この主人は一家言を持ったひとで、早くから出前をやらずに店に来てくれる客のみで商売をしていた。この店での推薦品は天麩羅蕎麦である。天麩羅の材料そのものも新鮮で、良い油での揚げたてであり、おつゆを残すことに罪悪感を持たされるくらいおいしくて、全部飲み干してしまうのが常であった。
ある時主人にその旨さの秘訣を尋ねたところ、地下倉庫にかめを何十本か準備して、ジックリと熟成させた原液を薄めて使っており、その原液作りがノウハウであるというお話であった。この「万盛庵」も今は駅前の再開発と、主人の高齢化のため廃業して無くなってしまった。
蕎麦というものは蕎麦そのものの旨さはもちろんのこと、つけ蕎麦ならば残ったつゆを蕎麦湯で薄め天麩羅蕎麦なら前述のように思わず汁を一滴も残さずに飲んでしまいたくなるという旨いだしのとり方が生命ではないだろうか。
先代の中島からは食べ物を商売にする人は旨いものを食べなければいけないと常に言われ、いろいろ旨いと言われるお店に連れて行かれたが、その第一番目が「新宿更科」であった。その更科が無くなり、「万盛庵」も無くなった。キユーピーの仕事を含め大量生産志向の現在、何とかして手づくりの忘れられぬ味を残したいと痛感している今日この頃である。
(キユーピー(株)相談役)

日本食糧新聞の第8286号(1997年11月5日付)の紙面
※法人用電子版ユーザーは1943年以降の新聞を紙面形式でご覧いただけます。