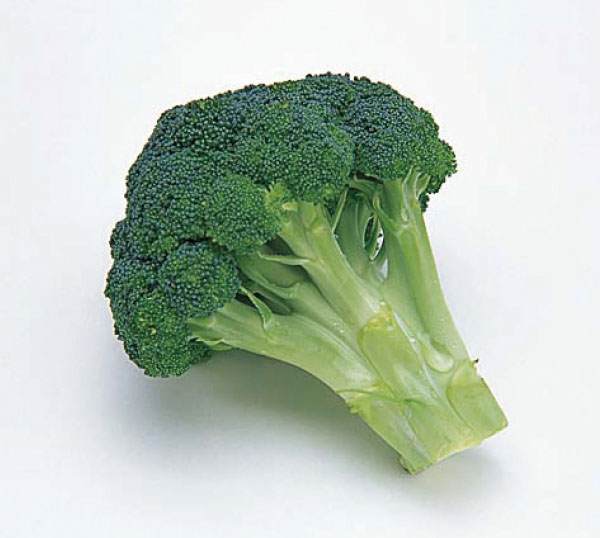おはしで防ぐ現代病:完熟みそが大腸がんへの病変を抑える
みその原料の大豆に含まれるフラボノイドの一種が肝がんを抑えること、みその発酵を促す麹菌や酵母菌が胃がんを抑えることなど、ここ数年、みそのがん予防効果が次々と明らかになっている。このほど、大腸がんの前がん病変(ACF)が、みその摂取で抑えられることを発表した広島大学原爆放射能医学研究所の渡邊敦光教授に聞いた。
大腸がんは日本人に増加傾向が著しく、現在の死亡率を部位別にみると、男性では肺がん・胃がん・肝がんに次いで四番目、女性では肺がんに次いで二番目に多いがんである。
大腸の内壁は粘膜の層で覆われ、腺窩から粘液が分泌されている。正常な腺窩は開口部が一個だが、発がん物質に侵されると、その開口部が大型化し二個、三個と増えてくる。このような状態が大腸がんの前がん病変と考えられている。
そこで私たちは、みそを混ぜたエサをラットに与えながら、発がん物質を投与し、ACF発生への影響を検討した。
実験では、乾燥赤みそ(米辛口みそ)を五%・一〇%・二〇%の三種類混ぜたエサを用意。それを一週間与えたラットに、大腸がん誘発物質を週一回・計三回投与し、その二週間後に大腸内の変異を測定した。結果は、普通のエサを与えた群ではラット一匹当たり一三六個のACFの発生が確認されたのに対し、一〇%みそ群では八六個、二〇%では六六個にまで抑えられた。与えたみその濃度が高いほど抑制効果は高かった(表1)。
さらに、同じ実験方法で、みその熟成度による差を検討したところ、完熟みそにのみ抑制傾向が認められた(表2)。
みその大腸の前がん病変抑制効果はひとつには、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルの作用によるものと考えられるが、さらに完熟みそだけに含まれる「+α」が作用していることが、この実験ではっきりした。この「α」が何であるかは今後の研究を待つしかないが、私たちは目下、みその熟成度による胃がんの発生率の差を調べる実験を続けている。
昔の日本人に大腸がんが少なかった理由の一つは、海水を塩田にひいて乾燥させた粗塩などからミネラルを豊富に摂取していたためではないかと考えられている。では、がん予防のために海水塩を食卓に取り入れることが勧められるかといえば、そうとはいえない。
海水塩に含まれる硝酸塩は、口の中で雑菌の作用により亜硝酸に変わる。この亜硝酸が魚の干物などに含まれる二級アミンと反応すると、胃の中で強力な発がん物質であるニトロソアミンを生成する。また、食塩はそれ自体、胃がんの発がん促進物質として作用するため、日本人に昔から胃がんが多かったのは、海水塩を過剰に摂取していたためとも考えられるのだ。
一方を抑えると他方のリスクが高まるというように、食生活において胃がんと大腸がんを同時に予防することは難しい。
これに反して、昨今、その発酵を促す麹菌や酵母菌・乳酸菌などの作用により胃がんの発生を抑える作用も確認されている今回の実験結果と合わせると、みそは大腸がんと胃がんのリスクを同時に下げてくれる理想の食品と考えられる。