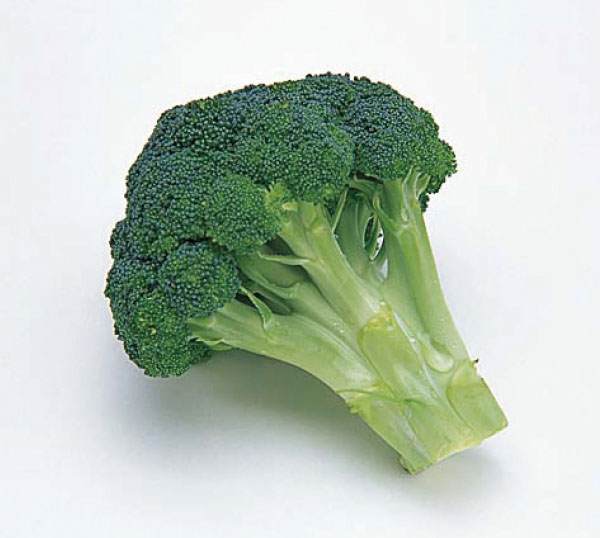だから素敵! あの人のヘルシートーク:フードデザイナー・七沢なおみさん
8面『月刊漢方美人』中の「シノアカフェ」レシピでもお馴染みの七沢なおみさんは、雑誌の料理スタイリストを経て、「食」を中心に素敵な暮らしを提案するフードデザイナー。薬膳から日常のテーブルコーディネート、毎日をちょっと気をつけてヘルシーに楽しく過ごすヒントを聞いた。
『お部屋で「薬膳カフェ」』では、日常の中で普通に食べるご飯で自分の身体を良くしていくレシピをまとめています。
薬膳の基本は養生。自分の体質を正しく知って、その身体を養ってあげる。ごく普通の食材の効能が一通り頭に入っていると、毎日が変わります。
私は冷え性なのに、キュウリやナスなど身体を冷やす食べ物が好きでした。だからどんどん冷えてしまった時期があったのだけど、唐辛子やショウガなど温める食べ物を積極的にとるようにしたら身体が変わりましたよ。ちょっと風邪っぽいかなと思ったら、夜、寝る時にショウガ湯にはちみつをたらしてホットで飲む。身体が温まって、ポカポカしてきます。結局、自分の好みが身体を作るので、食材の効能を特に知らなかったら偏った方向に行きがちです。温帯の人はやはり熱がこもりやすいものが好き。お肉に唐辛子をプラスしたものをたくさんとっていたりね。身体は中間がいい。「中庸」というのですが、そこに持っていくのが薬膳ですね。
講習でよくこう話します。「テーブルはあなたたちの舞台ですよ」。家ではテーブルの上には基本的に何も置きません。お話を聞いていると、皆さん、いろんな物を置いてるんですね。舞台は演出する場だから、まずはまっさらにして。テーブル用のお醤油は、使う時に冷蔵庫から出してくればいいわけです。
自分なりにその時のテーマを持つといいと思います。テーマが決まると中心ができてくる。毎日いろんな実験ができますよ。例えば明日のお茶の時間は「白」でやってみようとか。春が来たら「ピンク」もいい。それでうまくいったら、おもてなしの時、やってみる。
基本的なカラーバリエーションの全く逆をやるのも面白い。和食なんだけど洋皿でやってみるとか、洋食なんだけど和でセッティングする…というのも。洋食といっても、「ちょっとプロバンス風」とか、「いま流行の北欧風」などの切り口で。「あれがないからできない」ということはありません。テーマですから、北欧風の器でなくて、手持ちの物でいいんです。それに近づけてやることでどんどんテーブルが広がっていくのです。
テーブルクロス1枚でも随分変わります。とはいっても何枚も持つ必要はないですよ。ランチョンマットでもいいし。それもないなら、A4のカラーコピーでランチョンを作ってもいい。雑誌や英字新聞、絵本も使えます。小さな子供のお客さまは、絵本のコピー、とても喜びますね。「絵を塗っていい?」とかね。お子さんの描いた絵も使えます。
縛りがあるから、何もできないではなくて、多分縛っているのは自分自身なんですね。手持ちのもので工夫してみて。自分の家の物って、その人の好みで集めてるから、案外合うんですよ。みんな、好きな色や好きな形があるから。
自分の家って究極のセレクトショップだと思います。自分が気がついていないだけで、その人なりの空気がある。それを大切にして下さいね。
◆プロフィル
ななさわ・なおみ 『LEE』『MORE』などの雑誌や料理単行本でスタイリストとして活躍後、自身が提案する料理の本を手がける。著書は『お部屋でカフェ 私だけの手作りレシピ63』『想いが伝わる30+18 お菓子&ラッピング』(ともに祥伝社)など多数
■はちみつ&ジンジャーソーダ■
あわただしい朝でも、1杯のドリンクを飲むだけで身体がシャキッと目覚める。はじける炭酸が、朝のだるさを消す。「クロスはフィンランドでボートに乗ったときのチケットを、カラーコピーしました」。
〈材料(2人分)〉
ショウガの絞り汁……………少々
はちみつ…………………大さじ1
氷・炭酸水(無糖)…………各適宜
〈作り方〉
(1)グラスにショウガの絞り汁、はちみつ、氷を入れる。
(2)(1)に炭酸水を一気に注ぐ。
■緑豆のおかゆ■
「女性特有のむくみをとる美人がゆ。身体の中の毒を取る、デトックスですね」。
〈材料(2人分)〉
コメ………………カップ1/2
水………………カップ3・1/2
緑豆(乾燥)‥……………20g
〈作り方〉
(1)コメは洗って分量の水とともに鍋に入れて、30分以上つけておく。緑豆はさっと洗う。
(2)(1)鍋に緑豆を入れて強火にかけ、煮たったら弱火にして30~40分炊く。