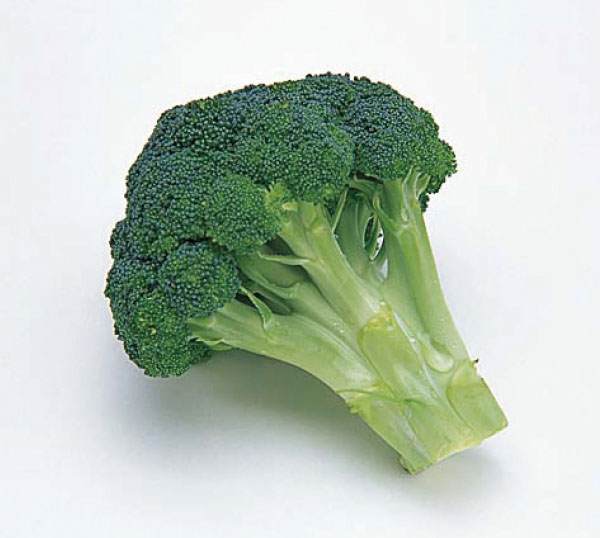らいらっく人生学:当世隠居の心得
東京で生まれ、大阪に職をえて四〇年、ほぼこちらに土着した。高校の同期生一五人が関西で生活しており、そういう年齢に達したのであろう、三月に一度ぐらいの割りで同窓会が開かれている。
秀才だったり、きかん坊だったりしたのが、経営者、サラリーマン、大学教授、ジャーナリスト、主婦…、と人生の垢(あか)にまみれながらも、それぞれが昔の風貌を残しており、第二、第三の職場に移るなどして、多くはなお、辛うじて“現役”にとどまっている。
「六〇歳を過ぎて、仕事にしがみついているのは罪悪だよ。若い人のチャンスを奪っているのだ」というのが持論のM君が、その言葉通り昨年春、自適の生活に入った。
関西系の福祉重視の大企業の部長職までいったからできる選択だが、前回の会合で『退職後の生活』についてスピーチしたのが面白かった。以下に要約したい。
◇ ◇ ◇
例えばこんな具合である。
◆雇用保険受給申請 期間は退職後一年間で、申請日ではない。もっとも来年度から厚生年金との並給は制限される。
◆保険の切り替え 妻はだいたい年下であろうから、六〇歳までは国民年金に再度、加入しなければならない。団体扱いの保険を、自分で払う手続きもする。
◆税金 住民税は前年度所得が基準だから、たいていの退職者はあわてる。所得税も年末調整が不十分だと追徴される。
◆保険料 団体加入していると、退職後一括払いとなるから、資金計画に組み込んでおくこと。社内共済なども同様。
その他、キャッシュカード、同窓会・社外団体への通知と、きちょうめんな性格を反映して微に入り、細にわたっている。そこらの入門書にもある内容かもしれないが、彼の実生活と併わせて聞くと、別の興味がある。
続いて、彼の生活信条である。
◆奥さんが主人 なるべく妻をボランティアなどで外へ出す。家事は手伝いではなく自分のメーンの仕事とする。
◆小遣いの確保 定額、自分の通帳を作って毎月、入れさせる。彼の場合、在職中のへそくりが二~三〇〇万円、子・孫への小遣い、海外旅行などの原資に。
◆物で残すな、記念・記憶で 苦心して集めた収集品を息子に進呈しようとして断られた。これからは水泳、社交ダンス、太極拳などの趣味に力を入れる。
◇ ◇ ◇
若いころから、『隠居』にあこがれていたが、いかに邪魔にならず、粗大ゴミ、濡れ落ち葉にならないように暮らすのが精いっぱいで、長屋のご隠居さんなどは、進歩の早い現代、存在を許されない。
藤沢周平氏の『三屋清左衛門残日録』に「隠居をすることを、清左衛門は世の中から一歩しりぞくだけだと軽く考えていた節がある。ところが実際には、隠居はそれまでの清左衛門の生き方、ひらたくいえば暮らしと習慣のすべてを変えることだったのである」とある。
まことに、その通りなのだ、清左衛門は結構、藩やその役人に頼りにされ、活躍する。だれもがかくありたいと思って、かえって周囲に迷惑をかける。
M君の場合はまことに潔く、拍手をおくりたい。