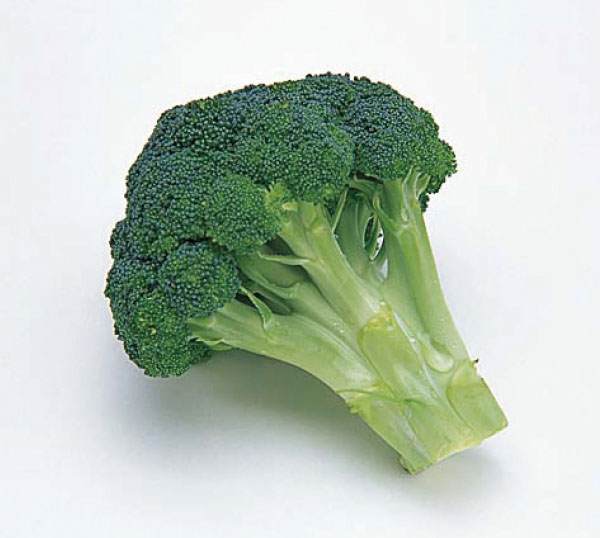5月5日は「わかめの日」 びっくり! 海藻再発見
三重県といえば、お伊勢さん(伊勢神宮)や鈴鹿サーキット、それに志摩半島の海が有名だ。日本列島の真ん中辺に位置し、南北に細長くて、古代から歴史上の重要な土地として遺跡や文化財も多い。南北に細長い三重県は、いわば片側がすべて海に面していることになり、それだけに海と密接に関係した漁業や水産加工が盛んだ。鳥羽市にある「海の博物館」は、海を知り海を愛する心を育てることを目的に、財団法人東海水産科学協会が設立している「海と志摩の文化を紹介した日本最大の文化財を収蔵する博物館」。今回初めての試みとして海藻をテーマにした、ロングラン展示会が開かれている。
海藻テーマに特別展
海の博物館の今春の特別展のテーマは「海藻」。海藻を現代の目で、新しい優れた海の資源として活用しようというもの。「びっくり!海藻再発見」と題した特別展は、3月20日から6月25日までの三カ月間開かれている。
三重県沿岸部には数多くの海藻類が成育・分布しており、古くからワカメ、アラメ、ヒジキ、フノリなどが食用として利用されてきた。最近は食用だけでなく、海藻から抽出した成分が食品、化粧品、肥料、医薬品などにも活用され、さらに高度な海藻繊維の開発、美容への利用、医学関係の新薬開発など新たな分野の活用も期待されている。
ワカメ料理試食会や講演会、映画会
特別展は期間中、二万人の入場者を予定しているが、海藻が生育する海の役割と海藻の幅広い活用について問いかける。
展示会場は▽海藻を育む海「藻場」のビデオコーナー(海藻の種類、海藻の生態、海藻の役割)▽食用としての海藻コーナー(そのまま食べる海藻、加工して食べる海藻、成分を抽出して食べるもの、抽出成分を利用している食べ物)▽海藻が利用されている品物(寒天、アルギン酸、カナギナン、フノリ、肥料、美容、化粧品、医学、海藻パルプ)▽二十一世紀の海藻利用(水産資源、健康食品、抽出物資、医学、エネルギー資源、環境問題)などがテーマごとに展示され、海藻の基本的な組成から、先端をゆく活用方法まで分かりやすく示してある。
会期中は講演会や体験学習会、海藻料理の試食会、映画会など盛りだくさんのイベントが組み込まれている。5月5日の「わかめの日」に合わせた、ワカメ料理の試食会や学識経験者を招いて海藻にかかわる講演会も行われる。
3月23日には、「海藻と健康」と題して野田宏行三重大学名誉教授の講演が行われ、およそ一○○人が参加した。