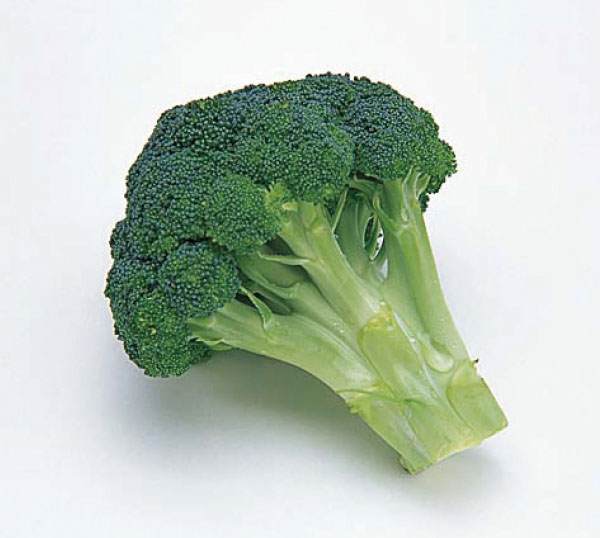クチーナ通信 カタツムリ、生きたままは胃潰瘍に効果
値段が少々張るはしりの夏野菜やフルーツに混じって若葉の芽吹くころになるとやってくるのが、『ルマーケ(カタツムリ)』の大袋だ。生きているのを処理しなければならないので気はとがめるが、いわゆるニンニクバターのブルゴーニュ風をはじめ、スープや煮込みなどにすると、とてもおいしい。
網袋から出したばかりのカタツムリを洗っているとカメリエーレ(ウエーター)の一人がやって来た。
カタツムリを見るとニッコリ笑って、オレに一個くれと言う。え、何でまた…まあ、いいよと深く考えず手渡しすると、彼はツマようじを取り出し、カタツムリの殻に差し込むと、中身をほじくりだし、そして、ゴックリと飲み込んでしまったのであった。
胃を悪くしているので胃潰瘍には生きカタツムリがとても効くのだと言う。日本にもナメクジ健康法なるものがあるとは聞くけれど…?
イタリアにはこうした色々な民間の健康法や俗信がまだ残っているが、中にはブーイングしたくなるようなものも数多い。
いわく、コショウは身体に毒なので病人には厳禁!(そのかわりトウガラシはOKというから、辛いからダメという訳ではないらしい。漢方ではコショウも立派な健胃薬なのだが…)。
いわく、卵を朝に食べると消化不良をおこす(朝食に菓子パンくらいしか食べない彼らには、卵は重い食べ物と信じられているようだ)。もちろんハーブを使った消化薬などは、ハーブの効能が科学的に解明される以前からの伝統で、感心してしまうものもあるのだが…。
たとえ胃に穴が開いたとしても、できれば生きカタツムリの世話になりたくないものであるが、健康法というのは怪しげであればあるほど御利益があるように思えるものなのかもしれない。
(イタリア・トリノで料理修業中 合田達子)
(生のカタツムリは入手しにくいこともあるので、缶詰を使用とした。フレッシュなものがあれば、モアベター)
<材料>(4人分)
カタツムリ(缶詰)大2缶、玉ネギ薄切り小1個分、セロリ薄切り玉ネギと同量、白ワイン(酸味の少ないもの)約1本、塩、コショウ、バター、オリーブ油適宜、クルミのみじん切り約10個分、あればグラッパ少々
<作り方>
(1)カタツムリは缶から出し、内臓などの不要物をていねいに取り除く。水から鍋で軽くゆがき、ザルにあげておく。
(2)フライパンにオリーブ油とバターを溶かす。玉ネギ、次いでセロリを加え、薄く色づくまで炒める。
(3)(2)に(1)を加え、余分な水分を飛ばすように炒めたらワインをひたひたに注ぐ。下味の塩を加え約2時間ほど、アクを取って弱火で煮込む。
(4)グラッパで仕上げに香りをつける。塩、コショウで整え、クルミのみじん切りを散らして供する。
(カタツムリをメーンにした軽い食事のプリモピアットに)
〈材料〉(4人分)
完熟プチトマト20~30個、ニンニク1/2片、タカの爪1本(種を取る)、アンチョビー約2切れ、スパゲティ適宜(1人前は80~90g)、オリーブ油、塩、パセリみじん切り適宜
〈作り方〉
(1)プチトマトは洗ってへたを取り、すべて縦半分に切る。
(2)フライパンにオリーブ油を熱し、熱くならないうちにニンニク、タカの爪を加え、ごく弱火でじっくりとエキスを出す。十分出たら、両方とも取り出す。アンチョビーを加え、熱しながら溶かし混ぜる。(1)を加えて弱火でざっと炒める。塩で調味する。
(3)スパゲティをアルデンテの直前までゆでたら(2)のフライパンにゆで汁少々とともにあけ、弱火で混ぜながら麺とソースをからめる。
(4)皿に盛り、パセリのみじん切りを散らす。
☆仕上げに、パン粉(固くなった田舎パンなどをすりおろしたもの)を色づくまで炒めたものを加えてもおいしい。