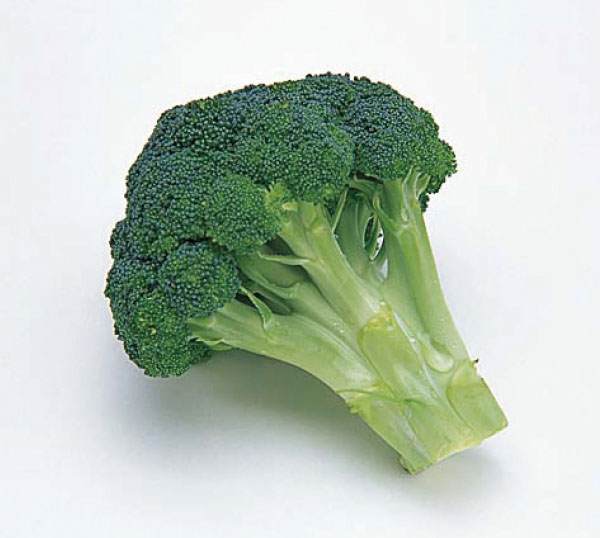だから素敵! あの人のヘルシートーク:食生活ジャーナリスト・岸朝子さん
「料理記者歴48年」の岸朝子さんといえば、料理対決番組の上品なコメントを誰もが思い出す。最近は、サントリー提供の深夜ドラマにも出演するなど、傘寿を迎えられて、ますます活動のステージを広げている。社会に出たのが32歳、それからこれだけ豊かで長い職業人人生を繰り広げた人の、プライベートの夕ご飯の話、食についての一番大切なポリシーを聞かせていただいた。
‐深夜のドラマ、驚きました。
周囲から「七〇歳で芸能界にデビューして、八〇歳で女優になったなんてあなただけ」と言われました(笑)。キッカケは『料理の鉄人』の放送作家の小山薫堂さん、「私の記憶が正しければ……」というのを創った人ね、あの方からお話があったので、それならばと。前日に厚いシナリオが届いて、「一晩で覚えられないわ、どうしましょう」と思いながら行ってみたら、「おいしゅうございます」を五回言うだけなの(笑)。おそばを食べて「おいしゅうございます」、ピッツアを食べて「おいしゅうございます」。
この前は、ジャニーズジュニアとしてこれからグループを組む男の子たちと、食べ歩きの番組に出ました。
私の推奨するお店に、その子たちと行くという趣向で、一日五軒。天どん、カレーライス、沖縄料理、パスタ、最後にあんみつ。楽しかったですよ。そうですね、胃袋は丈夫です。
正式な肩書は「食生活ジャーナリスト」と名乗ります。一五年くらい前にそういう会を作ったのね。でも「料理記者四八年」の方で皆さん、覚えていただいてますね。『料理の鉄人』の初出演の時、「岸さん、肩書を何にしよう」と現場で言われて、とっさに「料理記者歴四〇年でどうかしら」と言ったのが、定着しまして。分かりやすいのでずっと使っていたら、新聞の投書で「岸さんはずっと料理記者歴四〇年だけど、歳はとらないのでしょうか」と掲載されてね(笑)。それから毎年数えて、ちゃんと加えていくことにしたんです。
‐「料理記者歴四八年」の岸さんは、いつもどのような食事をしているのでしょうか。昨日のことを教えてください。
夜は友だちとオペラを見に行ったので、その帰りに焼き肉屋へ。取材を兼ねていろいろなお店へ行くので、夕ご飯はけっこう外食が多いです。「居酒屋栄養学」って私は言ってるのだけれど、その日に不足した野菜を食べるの。昨日は韓国風の千切りサラダ、ナムルにキムチ。お野菜は「一日に三五〇グラム食べましょう」という目標があるでしょう。昼、持参したお弁当でトマト一個三〇〇グラムをいただいたから、もう二日分の緑黄色野菜を食べちゃったと思ったけれど、夜もまたたくさんいただきました。お肉はレバー・ハラミ・骨付きカルビで、三〇〇キロカロリーくらい。糖尿病の本を三〇冊くらい、それに食品成分表を肌身離さず利用しているから、食材のカロリーはそらんじています。
ご飯はご一緒した若い人が注文した丼物の新製品を、お味見程度に。その分、お酒をいただきました。ええ、大好きでございましてねぇ。女性で初めての東京国税局酒類審議会常任委員に就任して、一二年やってたくらいだから(笑)。多い時は三〇〇種類くらい試飲したこともありました。昨日は焼酎とマッコリ。おいしゅうございましたよ。
ビールを飲んだのさえも三二歳で編集者なんてやくざな商売を始めてからなので、飲酒歴も四八年でございます。でもおかげさまで、肝臓の数値は何ともないの。どうしてかって、それでは居酒屋栄養学のポイントをまとめましょうね。
まず空腹で飲んではいけません。アルコールは腸でなく胃の粘膜でも吸収されるから、空っぽのままだと傷めます。飲む時は、牛乳一杯とか冷蔵庫にあるチーズを一つとか、そうしてから出かけましょうね。二つ目は、良質なつまみを食べて肝臓を保護しながら飲むこと。お野菜やレバーとかね。いまの時代はどうしても良くないものも身体の中に入ってしまう。肝臓は食べたものを分解して必要なものが取捨選択されるところ。肝臓が元気に仕事ができる、つまり余計なものが排出され、正しくタンパク質を作り替えられるように、食事で助けてあげたいものです。
「酒知る、味知る、人を知る」と、私よくサインに書きます。お酒は料理をおいしく食べるためのもので、酔うためのものじゃない。確かに栄養素のない“エンプティカロリー”だけど、それだけじゃないのよ。お酒は心の栄養になるの(笑)。
‐両親とも沖縄のご出身。お父さまは特に長寿村として有名な大宜見村の生まれですね。
沖縄がどうして長寿か。暖かい気候、食生活、年寄りを大切にする社会環境などからでしょうね。
食生活は、中国の影響が大きいです。昔から肉食、豚肉を食べる習慣がありました。韓国は牛肉、あれはジンギスカンの支配下にあったから、つまり蒙古文化の影響です。漢民族の影響下は豚肉なの、ノロノロしてるから遊牧の蒙古民族には向かないものね。どちらにしてもヤマト(本土)の肉食は明治維新以後でしょう。沖縄は肉食に伝統があるから、「鳴き声以外は全部食べる」というくらい、料理法が上手です。市場からブロックで買ってきてゆでこぼして使う。もちもちしたところのコラーゲンも活用して。お豆腐は中国と製法が同じ沖縄豆腐。木綿豆腐のタンパク質は六・六グラムなのに対して、こちらは九・一グラム。ビタミンB1は木綿豆腐〇・〇七ミリグラムに対して〇・一〇ミリグラム。栄養価が高いんです。
豊かではなかったので、あるものは何でも利用する、これも良かった。四方が海だから魚介やモズク・アオサなどの海藻をよく食べる。昆布は取れないけれど消費量はとても多い。北海道から回ってきた北前船が那覇に入り、薩摩藩の昆布座で琉球との貿易の品物になったのだけれど、その頃には下の方はメタメタになってしまうのね。その部分を捨てないで煮て食べた。だから沖縄の昆布は柔らかいの。海藻は塩分やコレステロールを排出してくれます。
田んぼが少ないので主食はおコメでなくサツマイモ、食物繊維が多いですね。大きな鍋でふかして、下の方のくちゃくちゃした部分は一家に一頭はいた豚の餌に。緑黄色野菜はヨモギ・フーチバ・ウイキョウなど、これを豚から取ったラードで炒めて食べる。ヤマトでは油の摂取量が少なかった時代からです。緑黄色野菜は油があるとカロテンがビタミンAになって吸収率が高くなるし、塩分の摂取も少なくて済む。塩分摂取が一〇グラム以下なのは都道府県の中で沖縄だけです。
‐素晴らしい伝統食の知恵ですね。けれど最近は異変が起きていると聞きます。どういう風に維持したらいいか、目安はないのでしょうか。
そうなんですよ! そんな優秀な食生活と健康寿命の長さを誇っていた沖縄がいま、危ないんです。男性の平均寿命はいまや全国二六位に落っこちてしまいました。女性と総合ではまだ日本一だけど、男性は特に四五~五五歳の成績が悪くてこうなってしまった。数年前、一位から四位に落ちたと聞いて、私は「なんてこと!」と怒り狂ったんだけれど。アメリカの占領下に二七年あったでしょ、戦後生まれの人たちは、その食文化の悪い部分の影響をもろに受けているんです。牛肉はいまでも関税が安くて、野菜を合わせてゆでこぼして食べるという方法ではなくて、そのままステーキで食べてしまう。野菜やイモ、海藻などの伝統料理は食べない。ただしこれは都市の話で、地方ではいまでも昔ながらの食生活で、そうした人たちは健康そのものです。
しかし私は沖縄だけの問題ではないと思います。沖縄は食の欧米化がヤマトよりも早かっただけで、あと一〇年もしたら日本列島の都市部全体が同じ状況になってしまうのでは、と警鐘を鳴らしているんです。いま一五~二九歳の若い世代は動物性脂肪の摂取が理想が二五%のところ、三〇%近くになっています。アメリカは四〇%近く、目標を三五%にするのがやっとです。もちろん、良質のタンパク質の摂取は大切で、足りなくなると血管が弱くなり脳卒中も起きやすい。摂取エネルギーの比率が、タンパク質一五%、脂肪二五%、残り六〇%が炭水化物という昭和60年くらいの食生活が理想とされています。
こうした栄養に関する基本的な知識は意識して、できることを実践しながら、あとはおいしく食べて健康長寿。そんな風にいきたいですね。
●プロフィル きし・あさこ
1923年東京都生まれ。42年女子栄養学園(現・女子栄養大学)卒業。55年、32歳の時、「食」に関する職業をと主婦の友社に入社、料理記者としてのスタートを切る。68年から『栄養と料理』の編集長を10年間務める。79年から編集プロダクション「エディターズ」主宰。93年から6年間フジテレビ系『料理の鉄人』の審査員として活躍。97年、(財)日本食生活文化財団から食生活文化金賞を受賞。著書『岸朝子のおいしゅうございますね』(ベストセラーズ)など多数。