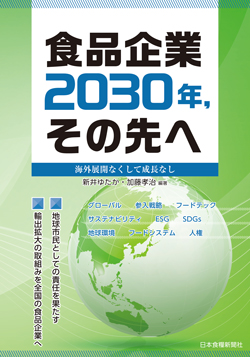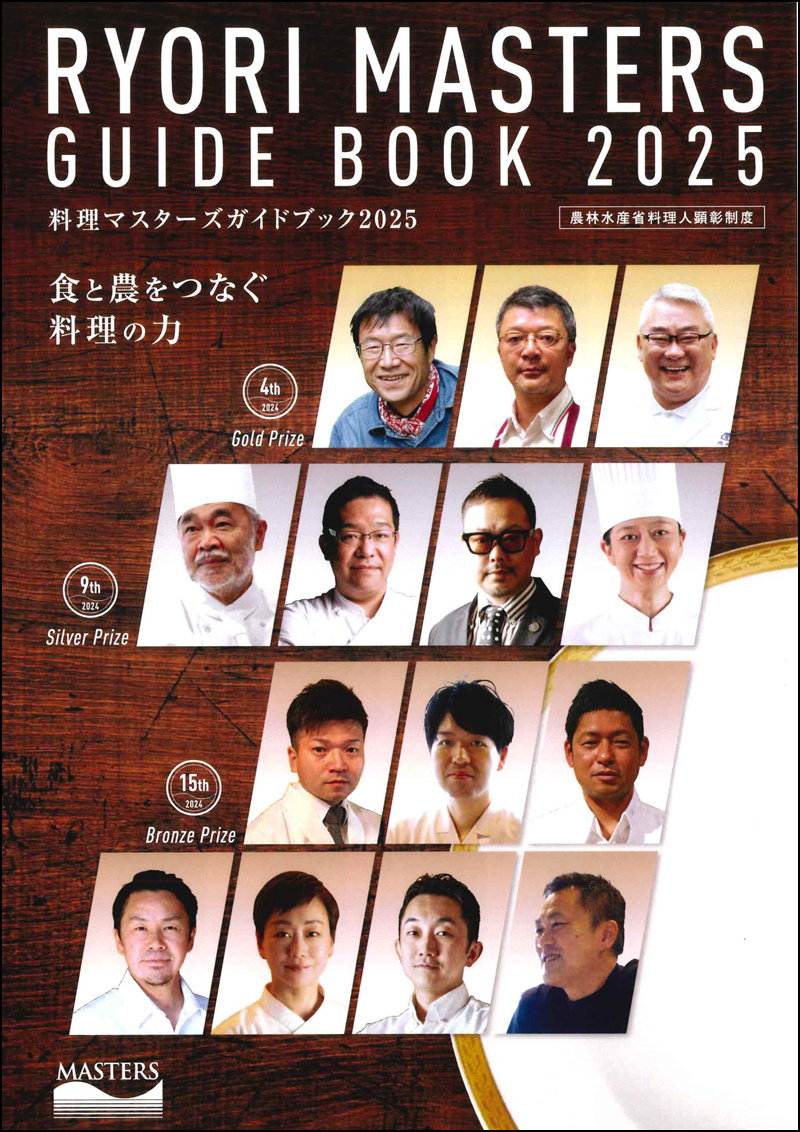忘れられぬ味(77)ニチレイ・浦野光人社長「とろろ汁と家族」
私の実家は寿司屋であったが、宴会のできる座敷を設け、小料理も出していた。私が小学校高学年の頃には商売も相当にうまくいっていたようで、それなりのご馳走を食べられる環境であった。そんな実家で一番のご馳走は、豪華なお造りでも、こだわりの小料理でもなかった。それはとろろ汁であった。とろろ汁を食べる時は、とろろ汁とご飯の他は何も食卓に並ばない。必要がないのである。両親と五人の子供の家族全員が一番のご馳走と感じるのが、とろろ汁であった。ご馳走とは心が決めるものだと思う。
まずは素材である。両親の生家があった三河の山間で自然薯を探し、大変な苦労をして掘り出す。長いものは六尺にも及ぶ。とろろ汁は自生の自然薯でなければならないというのが父のこだわりであった。栽培した自然薯では納得しない。滋養丸や仏掌芋や大和芋はなおさらである。
次に作り方である。自然薯をすり鉢ですりおろし、すりこぎですり込む。粘りが出て、ふっくらと容積が増えるまですり込むのである。この力仕事は男三人の役割であった。最後にカツオと椎茸の出し汁で少しずつ、ていねいに伸ばしていく。すりおろしからたっぷり二時間はかかる。腕が鉛のごとく重く感じる頃、とろろ汁のでき上がりである。これをあつあつのご飯にかけて食べる。ご飯はほんの一口をよそい、たっぷりとろろ汁をかけ、飲み込むようにして食べるのが実家の流儀である。
本当においしいのである。自然薯を掘り出すところから、ご馳走の序曲が始まる。そしてすりおろしからでき上がりまで、すべて男三人の仕事である。こんな料理は他にない。母以下四人の女性軍は待っていればよい。もしかしたら、このあたりがご馳走のご馳走たる所以であったかもしれない。
三〇年前の婚約時代、実家に来た妻に出されたご馳走は、豪華絢爛のお造りであった。そして、新婚旅行の帰りに寄った実家で出されたご馳走は、このとろろ汁であった。「今日はご馳走よ」と母にいわれ、大好きなお造りを想像した妻はとろろ汁だけの食卓に絶句したそうである。その妻も今ではとろろ汁が大ご馳走と感じる仲間になってしまった。
((株)ニチレイ代表取締役社長)

日本食糧新聞の第8935号(2001年12月3日付)の紙面
※法人用電子版ユーザーは1943年以降の新聞を紙面形式でご覧いただけます。
紙面ビューアー – ご利用ガイド「日本食糧新聞電子版」