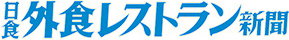シェフと60分:中国料理「一閣」料理長・国分静夫氏
一八歳のとき、山形県の中華料理店から先輩のつてをたどって、横浜の老舗と呼ばれる味雅(みが)という北京料理の店に入店、上京した。
「ショックでしたね。田舎の料理と全然違うんですよ。当時、田舎では中華といえば八宝菜とか、唐揚げなんかだったんですが、横浜ではコースメニューでオードブルなんかがあったりして……。そこでがく然としました」
幼いころからおじさんの経営する手作りギョウザの店の手伝いをしていた。家でも見よう見まねで焼きそばを作ったり、パンを焼いてみたりという料理好きな子どもだった。中学を卒業と同時に、おじさんの店に住込みでびっちり四年間働いてからの上京。大丈夫だろうと多少の自信はもっていた。もちろん十分経験は積んでいたが、「一からやり直そう」と目が覚め、見習いとして再スタートをきった。
「チーフがとにかく、中華のノウハウの基礎をしっかりと教えてくれました。仕事以外ではとにかく『よく勉強しなさい』と言われていました。おかげで漢字のメニューや中国のこと、料理に関すること、何でも勉強しました。今ももちろん勉強中です。習字も独学ですがやっています」
二四歳になったときチーフに「もっと欲をもちなさい。もっとよそを見なさい」と勧められ、知り合いの紹介で上海料理「目黒楓林」へ。
「郭さんという台湾出身のシェフがチーフだったんですが、とにかくこれが厳しい人で、いつもガンガン怒っているんですよ。給料も下げられちゃって『嫌なら来なくていいよ』って言うんですよ。今までのチーフが優しい方だったんで、頭にきちゃって、チーフに認めてもらおうと努力しました」
強烈な出会いだが、チーフの煮込み料理の鍋の使い方、技の一つ一つにほれ込んでしまった。「光る料理」をつくるチーフを、今でも師匠と呼んでいる。
「勉強熱心」なチーフと、「見せる技を持つ」チーフの二人に育てられたことを新人教育に生かす。
「体と頭、二人の両極端な教えをちょっとずつ取り入れています。メニューの読み方から道具の手入れ、使い方、繰り返しの実践をみっちりとやらせています。あと私が言っているのは『食べることを好きになること』。ギャンブルするくらいなら食べ歩きをしなさいとよく言いますね。それと、わからないことはそのままにしないで必ず聞くこと。聞かないで過ごしてしまうのは、大変危険なことですからね。私だっていまだに、わからないことは師匠に電話しますし、若い人に聞くことだってありますから」
チームワークづくりにも余念はない。
「一人ひとりが違う環境にいて、その人たちが、一つのチームとしてやっていくのがこの厨房です。ですから、一人だけがズレていても味がぶれてしまいます。隠しごとはしない、何を考えるにしてもみんなで、が基本でしょう。そのチームワークづくりとしては、よくみんなで遊びに行きますよ。私は山形出身ですから、冬にスキーに行こうって誘ったりします。先日若いスタッフから『今年はスノーボードをやりましょう』と誘われて迷いましたが、何事もチャンレンジですからやりましたよ。もー転んで転んで大変でしたけど。上から言うだけじゃなくて、若い人からも吸収できることは吸収する。自ら何にでもチャレンジして、新しい努力をしていかなければ、と思っています」
女性が八割を占めるため、味ではこってりしたもの、見た目はグロテスクなものを避け、骨付きもメニューにはない。上海料理がベースだが、広東も取り入れ、毎月旬のもののメニューを組んでいる。特に四季折々の野菜と、主材料の組み合わせはいつも考えている。
「基本はしっかり、仕上げは国分風。客を飽きさせない料理がモットーなんです。最近は、修業時代に学んだ伝統料理、豚スネの煮込みや塩漬けして干した豚肉の料理をもう一度再現することに凝っています。見た目がグロテスクなところもあるので、それはオーダーのときや、料理を運んだときに積極的に説明して勧めています」
リピーターのウケを見ながら、じっくりと伝統料理を広げている。今の人気メニューは、飲茶の流行も手伝って、はちみつづけのベーコンを蒸しパンに挟んだもの。ベーコンはもちろん自家製。
「高くても安くてもおいしくなければリピーターはつかない」と言う。一〇〇%地元の客への難しさと、厳しさを知っているが、それが励みになることも知っている。
◆プロフィル
昭和29年山形県生まれ。親戚のおじが一代でギョウザの店を五店舗もったことにあこがれをもち、また、料理好きも高じて中学卒業後、料理界へ入る。横浜の味雅、目黒楓林を経て、昭和59年一閣にオープンの手伝いに入るが、チーフシェフが病気のため辞めてしまい、そのまま任せられることになる。目黒楓林の郭宗欽師匠(現在高知楓林経営)の弟子として、上海料理を基本とした料理を提供している。
小学校二年生と、六年生の二児の父。月に一度くらい自転車に乗って公園へ行って子どもたちとの時間をもつ。公園で拾った枝やドングリを持ち帰り、店の飾りとしてリースをつくることもある。店の装飾はほとんどが、国分シェフのオリジナル作品。
文 石原尚美
カメラ 上田喜子