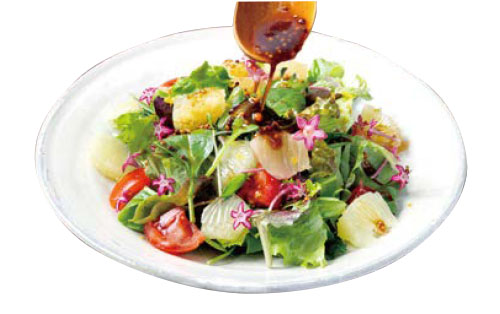岐路に立つFC:FCビジネスモデルの過ち
市場に余裕がありGDPが高い伸びを示していた時代では、規模が優先された。大きいとそれだけ売上げ・利益が望める。したがって、短期間ですさまじい成長が可能なFCは、時代の申し子として高い成長率を誇っていた。しかし、市場が飽和した大競争時代において規模は必ずしも利益を産み出さない。「価値」が大切になり規模よりも品質が優先される。マイナスを多く産み出す規模は必要ない。
しかし、FC業界の苦悩がここにある。FC業界においては規模と成長を前提としてビジネスモデルを育んできた。なぜならば、売上高から得られるキャッシュフローを加盟店とFC本部が分け合うので、レギュラーチェーンよりも大きな規模による大きな売上げ・利益が必要となる。
大きな規模にするためには加盟店を増加させねばならないため、加盟店増加を主体として組まれたビジネスモデルがFCの基本スタイルといえる。したがって、加盟希望者が殺到しやすい加盟パンフレットや見栄えのよいマニュアル、低いロイヤルティなどが長年にわたって構築されてきた。しかし、問題なのは低いロイヤルティである。
一般的にロイヤルティは売上高の二~三%がFC業界の平均とされている。近年はやや上昇傾向にあるが、それでも売上高の五%となると高いという印象が持たれる。低いロイヤルティの方が加盟店にとって良いような気がするが、FCは所詮、本部と加盟店の運命共同体である。本部の収益力が弱まると加盟店に対する支援・指導も弱まる。FC本部が加盟店へ適切に支援・指導を行うためには最低限ロイヤルティは売上高の七%は必要である。SV人件費、広告キャンペーン費、研究開発費、商品センター・セントラルキッチン費用など、これらは加盟店が増加すればするほど多く必要になってくる。
したがって、ロイヤルティによる収入だけでは不足となる分は、IT機器活用による情報提供料、広告宣伝協賛金、高い仕入原価から発生する食材や包材の本部指定業者からのリベート、売掛金金利などのオープンアカウントなどというさまざまな名目や制度でロイヤルティとは別に加盟店から徴収している。
しかし、そんなことをするくらいであれば、堂々とロイヤルティを高くすればよいと思われるが。
また、加盟希望者はこれらの仕組みに加盟後初めて気づくことになるが、もう遅い。かえって気づかないほうが幸せかもしれない。