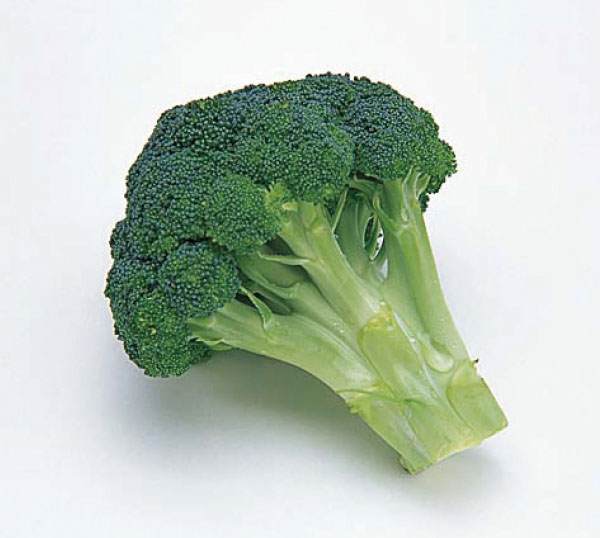百歳への招待「長寿の源」食材を追う「ビワの葉」
ビワは中国原産のバラ科の常緑高木で日本には一〇〇〇年以上前に移入された。初夏の味覚としてこの実を楽しむが、葉・種・根などはすべて漢方薬剤として貴重で、また堅い材は装飾用としても有用である。
実は成分としてビタミンAが多く、旬に食べると夏カゼをひかないといわれる。薬効面では潤肺・止渇・治肺咳血・吐血などに良く、小児の発熱を冷ますのにも良いとしている。
ビワの葉を薬用とする場合、果実用の栽培品種ではなく庭木として植えられている原種に近いものの方が効果は大きい。ビワの木は救人医学の重要薬剤として用いられる。寺院などに多くみられるのはこの理由による。
葉の採取はいつでもよく、新葉に限らず古葉でも良い。随時とれるのも強味である。採取した葉は水洗し裏面の細かい毛を落とし、これを天日で乾燥させる。夏なら三日ぐらいでパリパリに乾く。この葉をもみ、細かく砕いてビニール袋などに入れて保存する。
ビワの葉茶は江戸時代から庶民の健康茶として販売されていた。夏バテ防止によく、金魚売り同様、江戸の夏をにぎやかにした。
成分をみると、葉には揮発性油が含まれ、ぶとう糖・しょ糖・果糖・酒石酸・クエン酸・リンゴ酸などが含まれている。そのほかアミグダリン・タンニン・ウルソール酸・サポニン・微量のヒ素など。アミグダリンがビワの薬効の決め手となる。
アミグダリンの作用で昔から暑気あたりや疲労回復に卓効がみられた。江戸時代東海道の宿場町ではビワの葉茶を旅人にサービスしたと伝えられている。最近ではアミグダリンが、がんに対して効果があるといわれてきた。その大きな成果が期待される日も近い。
中国ではビワ茶が感冒・清肺・和胃・咳止め・脚気・暑気あたりなどに良いとして愛飲が勧められている。
上手なビワ葉茶の入れ方は大さじ二杯(約一五グラム)の乾燥葉を四〇〇㏄の水で煮出し一日二~三回に分けて飲む。日常飲むビワ茶は夏バテや食欲不振を改善する健康茶といえよう。
ビワの葉を茶としてでなく濃く煮つめコンクジュースのようにしたものをビワ葉露と呼ぶ。これを小量飲むと止咳・化痰・利尿に良く、健胃整腸効果大である。
薬膳としてビワ粥は手軽で食べやすく人気が高い。ビワ葉一五グラム、うるち米一二〇グラム、砂糖小量。粥として食べると、前述のビワ葉露と同様の効果が期待される。薬粥の効果大。
健康入浴剤としてビワ葉風呂は疲労回復が主力であるが、神経痛やリウマチによる痛みを和らげる効果もある。冬の入浴剤として利用すると価値は一段と高まる。この場合生葉を一〇枚ほど布袋に詰めて浴槽に入れるだけ。湯はややぬるめにしてゆっくりと入ること。
その他ビワ酒は疲労回復に、ビワの花は煎用すると止咳・頭痛に良く、ビワの根は関節痛・咳止めに。極めて有用な薬剤といえよう。