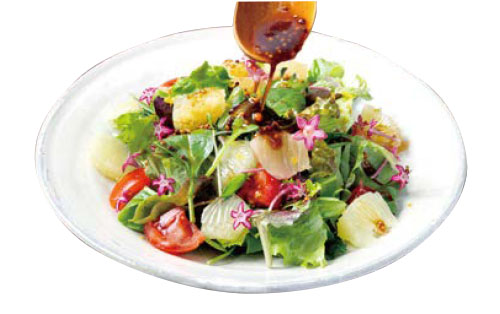激震下の外食・飲食業 1店舗1工場vsセントラルキッチン
(株)神戸屋レストランは関西は芦屋、西宮などの阪神山手地区、関東は世田谷周辺エリアにドミナントで出店している。いずれも主要幹線道路と生活道路が交差した角地で背後に成熟した住宅地を控える。エリアを広げないのは「目の届く範囲」で確実な店舗運営をするためである。
「神戸屋レストラン芦花公園店」は世田谷区の環状八号線に面した角地にあり、ベーカリーレストランの旗艦店としての機能を持つ。一八四坪のうち、ベーカリー部門が約二〇坪、レストラン部門は一二六席。通りからはガラス越しにパンを焼く工程が見え、香ばしいにおいが鼻をくすぐる。入り口に立つと正面に広いオープンキッチン、左手がレストラン、右手がベーカリー部門。白いユニホーム姿のコックがたくさん目に入るのが印象的だ。
従業員は正社員一五人、アルバイトが八五人登録している。正社員の配置は店長一人、ベーカリー五人、キッチン七人、ホール二人。
レストランのメニューはパンにあうフランスの田舎の家庭料理というコンセプトでオーブン料理、シチュー、煮込み料理を柱にステーキ、ハンバーグ、サンドイッチを組み合わせて約四〇アイテム。地域ごとに若干の違いはある。基本的に多店舗での手づくりで、たとえばハンバーグはミンチから手ごね、ソースも手づくりしているため、アイテム数は必然的に絞り込まれている。
ベーカリー類はヨーロッパのバケットに代表される食事パン「HEARTH(ハース)ブレッド」を粉から練っている。ハースとは炉床の意で、型にはめ込んで焼く食パンと異なり、生地をじかに鉄板に密着して焼くパンのこと。レストランとベーカリー部門の売上げ比率は約七対三で平均客単価は一六〇〇円。来店客数は祝祭日が平日の二倍となり平均すると一日一〇〇〇人、平均月商は四二〇〇~四三〇〇万円、客層は平日は三〇代を中心とするファミリーや主婦、ビジネスマンで祝祭日は老若男女となる。
効率第一主義のFRとは袂を分かち、「ベーカリーのスペシャリティーレストラン」をめざす。実際、「経営戦略で問題にするのは客数増が最重要課題」(関東レストラン事業部岡課長)という。特に昨年6月からはサービスをホテルレストラン並みにフルサービスオペレーションをめざそうと同店で実験を開始し、現在六店舗で行われている。
テーブルに布の青いテーブルセンターを敷き、一人の接客員が席の案内から見送りまでを行い、注文を聞いたら「〇〇はどなたですか?」と客席で確かめることなくお客の前にスーッと注文のメニューを出せるなどサービスシステムを強化した。
原価率は売上げの四二%、人件費は二五%。客数は九四年度も前年比一〇〇%をクリアし、今年に入ってからも約二%増で推移している。
(株)神戸屋レストラン(東京都調布市、03・3484・1313)はパンの中でも食事パンにこだわり、一店舗一工場主義を貫き、大量生産主義のセントラルキッチン(SK)を否定した経営方針で「ベーカリーレストラン」「神戸屋キッチン」「サンドッグイン神戸屋」のいずれもベーカリーを柱にした三業態をすべて直営で四五店展開している。
一方、(株)サト(大阪府、06・309・6301)は職人との訣別を図り、専門店に負けない味へのこだわりと低価格を追求するため、大阪・関東の二拠点にSKと配送センターを置き、一一〇種の食材を製造、コストダウンを実現して和食の「さと」と洋の「エブリディーズ」「ステーキ&ステーキ」の三業態を二一一店すべて直営で展開する。
相対する方法であるが、それぞれが客の高い満足を得て、多くの固定客をつかんでいる。(株)奥住マネジメント研究所所長の奥住正道氏は「要は企業(店)は何を持って客にアピールしていくのか、その方針を特化させることが大事である」と、これからは企業規模の拡大ではなく満足度の追求であると示唆する。
九四年度農林水産省のニューフードサービス推進優良事業者表彰で新規サービス形態部門「(株)神戸屋レストラン」、フードシステム部門「(株)サト」で大臣賞を受賞した二つの事例から価値の創造を探ってみる。
(株)サトは昭和43年、すしと鍋の店からスタートし、若い働く人達のために「専門店に負けない味へのこだわりと低価格」を追求しようとしたが、店舗が四~五店舗の頃、安く売ろうとする方針を現場の職人が受け入れてくれないため「思いきってクビにした」という経緯がある。SKでの日配システムの確立と共に、物流面でもアルコール類を除く全品を大阪・関東の二拠点で一括仕入れして自社便で日配するなど、食材費、人件費、配送費をはじめ経営全般にわたってコストダウンを実現している。
一方では「ポン酢」「うどん」「夫婦善哉」「ふぐ」などの和食の基本となる商品を低価格高品質で開発し、同社の伝統の味を築いている。
鍋にかかせないポン酢は二〇年前から徳島など数ヵ所の産地と提携し、一つの工場を借りきってシーズンの内に二五~三〇万本分を作る。一八~一九年間変えていなかった味を二年前から少しマイルドにした。うどんは「老舗なみのうどんすきをうどん鍋として半額で」を実現した。うどんは讃岐の本場でオリジナルレシピで作っている。鍋用のうどんのみは生で日配。他は冷凍麺で、二〇年来の伝統を築いており、常に売れ筋A商品群のトップを走っている。
夫婦善哉は昭和39年に法善寺の権利を買い、京都丹波の大納言小豆を使って堺の工場で生産している。ふぐも特定のものを市価の三分の一の価格で提供している。
また、昨年10月のメニュー改定では価格ゾーンを挟め、品数も絞り、価格ラインを下げており、客単価約一五〇〇円位が一二五〇~一三〇〇円位になっている。特に和食はお膳の定食概念があるが、お客に選んでもらいたいということから、価格を下げることによって単品をチョイスしてもらい、一アイテム増の注文ができるように配慮している。てんぷらと刺身のさと和定食のように同じ内容で一八八〇円を一三八〇円と五〇〇円下げた商品もある。
和食さと墨田堤通店(東京・墨田区)は墨田堤通りに面した郊外型のロードサイド店である。昨年の10月にオープンした関東では初めての複合店で、同じ施設内にはデニーズやモスバーガーなどが入り、集客力を高めている。
価格を見直したことにより、「さとは“ハレ”の日の利用頻度が高かったが、少しずつ日常化してきている。現場ではフロアのサービス、調理の品質のキープが第一」と同店甲斐店長は店を引きしめている。
同店は一〇〇坪一〇二席。従業員数は正社員四人、パート三八人。客単価は一三〇〇円で、一日来店客数は平日三〇〇人で日・祭日は七〇〇人。平均月商は一四〇〇万円前後。客層は昼はサラリーマン、OLで週末はファミリーが圧倒的に多い。人気メニューは刺身とてんぷらのさと和定食一三八〇円、すしとうどんのちらし丼と釜揚うどん定食一三八〇円、天丼五八〇円。