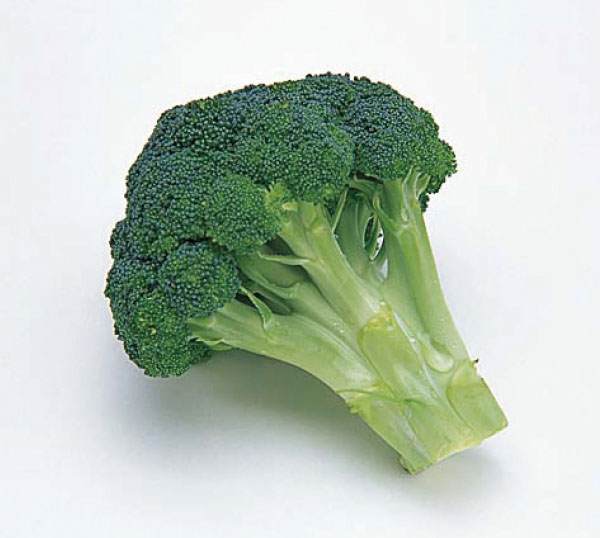百歳への招待「長寿の源」食材を追う:「モロヘイヤ」エジプト王の超高栄養野菜
緑黄色野菜が身体にいいことは常識だが、できることならその中でも足りない栄養素補給に最大限有効な物をセレクトしたい。お正月の雑煮に欠かせない小松菜と夏の青菜の王様、モロヘイヤ。成分の実力をみていきたい。
(食品評論家 太木光一)
モロヘイヤはエジプトを中心とする東地中海地方が原産。古代エジプト時代から食べられていたといわれ、その歴史は古い。名前はアラビア語で王様の食べる野菜の意味を持つ。エジプト王が病気で苦しんでいる時に、モロヘイヤスープを飲んで全快したという言い伝えもあるほど、高栄養食品である。
日本にモロヘイヤが導入されたのは戦後間もなくであるが、生野菜として公的市場に出荷されたのは八○年代に入ってからで、比較的新しい野菜といえよう。
栽培期間は7月から10月まで、夏場が中心となる。播種は種子の粒子が小さいので特に注意を要する。覆土は種子が見えない程度にして水分を十分に与えることがポイント。施肥は他の野菜より生育期間が長いため、有効。かつ適切なタイミングが大切となる。育成には土壌と水分が密接な関係を持つ。
草丈が二㍍以上になるまで成長する。通常五○~七○㌢ぐらいに成長したら、葉の部分を摘みとり食用とする。この葉の部分は柔らかく崩れやすく、生野菜として出荷される時はパックに詰められる。一般に収量は九九㌃当り一㌧程度といわれるが、気温・期間・栽培法などの違いで六○○㌔㌘から二㌧程度と差が大きい。
クセやアクがなく生で食べられる。葉はシソに似ており、刻むとオクラのようなヌメリが出てくる。このためトロロナの別名を持つ。また若干の甘味もみられる。
一○○㌘当りの成分をみると、カルシウム四一○、鉄二・七、B1○・七二、B2四・九五、C六二、いずれも㍉㌘。A六○一五国際単位となる。カルシウムでは人参の一○倍、ほうれん草の七・五倍、鉄では人参の三・三倍、南瓜の四・五倍、ビタミンAでは人参の一・四倍、ほうれん草の三・五倍、代表的な緑黄野菜と比較しても非常に多い。超高栄養野菜で夏バテ防止に最適だ。
葉を刻むと独特の粘りが出る。刻んでかき回せば一層粘ってくるので納豆やトロロの代用としても食べられる。刻んで味噌汁に入れればナメコの代用となる。
生の葉は刻んでサラダにしてもよいが、エビなどを巻いて衣をつけて天ぷらにしてもよい。そのほか野菜炒め・おひたし・酢の物などに向く。中華料理として餃子や野菜スープに入れてもおいしい。洋風ではサラダのほかスープ・パン・ケーキなどに入れると緑色が美しく映える。
また地方によってモロヘイヤの粉末を入れたそばやコンニャク・豆腐なども売られている。加工適性が広く、特に粉末品はあらゆる加工食品に利用されよう。
原産地のエジプトではモロヘイヤスープが最高の人気で、次いでサラダが喜ばれている。モロヘイヤが日本に流通し始めて十数年たつが、まだ知名度が非常に低いのは残念。クセがなく、食べやすいので高齢者の長寿食として一段の愛用をおすすめする。